
春の京都の名物になりつつある国際写真フェスティバル「キョウトグラフィー(KYOTOGRAPHIE)」が開催中だ。2013年にスタートした同フェスティバルは、毎年異なる社会的・文化的テーマのもと、世界から集まった写真作品を町屋や蔵などの京都ならではの建築で展示する。会期は桜の開花やゴールデンウィークに重なるため、日本のみならず、世界各国から多くの来場者が訪れる。京都という土地の魅力と、写真芸術の力を組み合わせたユニークな文化イベントだ。
そんな「キョウトグラフィー」の今年のテーマは「HUMANITY(人間性)」。同フェスティバルのルシール・レイボーズ共同ディレクターらが「日本と西洋という異なる文化的視点を通じて人間の営みの複雑さを浮かび上がらせる」と語るように、各作品は単なる人間讃歌にとどまるわけではない。環境やジェンダー、多様性、人権などの社会的トピックスに目を向け、人間性が抱える矛盾や負の側面をも浮き彫りにし、鑑賞者に問いを投げかける。集めた作品はどれも、アーティストたちのパーソナルな主題や問題意識から始まったプロジェクトだが、それらを語る中で見えてくる「人間性」にまつわるユニバーサルな問題を提示する。
全展示を見て回った「WWDJAPAN」記者が、読者にぜひ見てほしい5つの展示を厳選して紹介する。なお全ての展示が素晴らしかったので時間のある方はぜひ全てをチェックしてほしい。
JR(ジェイ・アール)「クロニクル京都 2024」
展示会場:JR京都駅ビルの北側通路壁面、京都新聞ビル
1 / 3
市民のポートレートで作り上げる壮大な写真物語
京都の玄関口、JR京都駅ビルの北側通路壁面に巨大な写真イメージを展示するのは、フランス人アーティストのJR(ジェイ・アール)。今回出展した「クロニクル(Chronicles)」シリーズは、地域社会の多様性と物語を巨大な写真壁画として表現する参加型アートプロジェクトだ。
「クロニクル」は、その土地に住む人々のポートレートを多数撮影し、コラージュして記念碑のようなパブリック・アートを作り上げる。JRは、今回の「キョウトグラフィー」のために昨年秋に京都に滞在。市内各所に設えた撮影スタジオで総勢505人の地元民を撮影し、それらを一つ一つパズルのように組み合わせていった。この気の遠くなるようなプロセスを経て、京都市長から舞妓や芸妓、さらにはドラァグクイーンまでの多種多様な京都人が織りなす「壮大な物語(=クロニクル)」を完成させた。
この作品が単なる合成写真ではなく(それだけでも甚大な労力だが)、奥行きある参加型アートプロジェクトとして成立するのは、街の人を撮影するだけでなく、全員に聞き取りを行い、彼らのライフストーリーも収集しているから。集めた各自の音声は、専用のウェブページで確認できるほか、作品に専用のアプリをかざすことで聴くこともできる。
別会場の京都新聞ビルの展示では、その膨大なライフストーリーや「クロニクル」の制作プロセスに光を当てる。特に同ビル地下の高さ10m、広さ1000平方メートルに及ぶ印刷工場跡地での展示は圧巻だ。提灯の手法で巨大な立体彫刻として再構築した数人のポートレートが、自らのストーリーを来場者に語りかける。空間の広さや作品の大きさも手伝い、そこで語られるパーソナルな物語は私たちの心を静かに揺さぶる。JRは「このプロジェクトの趣旨は、全ての人に平等に光を当てること。それだけに立体彫刻として再構築すべき人を選定するのは難しかったが、特異なストーリーを持っている10人を選んだ」と語った。あらためて、街という「クロニクル」はさまざまな個人のストーリーが折り重なって成り立っていることを思い出させてくれる作品だ。
レティシア・キイ
「ラブ&ジャスティス」「キョウト・ヘア・イメージ」
展示会場:アスフォデル、出町桝形商店街
アフリカ女性としての自分を受け入れ表現する毛髪アート
「キョウトグラフィー」は20年、アフリカ出身の若手作家を対象にしたアーティスト・イン・レジデンス(滞在制作)プログラムを開始した。今回、同プログラムに参加したのがコートジボワール出身のレティシア・キイ(Laetitia Ky)だ。
フランスの旧植民地国で生まれ育ったキイにとって、欧米を中心に形成された美の基準に当てはまらない自分の「白くない」肌や「まっすぐではない」毛髪を受け入れることは容易ではなかったという。自己受容のための模索のなかで出合ったのが、植民地期以前のアフリカの女性たちが編み出した自由で創造的な髪型の数々。それらに強い興味を持ったキイはリサーチを進め、当時の女性にとって髪は単なる「美」の道具でなく、アイデンティティを物語るための表現であり「対話」の形だったことを知る。それをきっかけに自分の髪の毛をメディアとして、造形物を作る活動を始めた。やがてキイの作品は、現代の女性を取り巻く規範やスティグマ、人種的な抑圧や不公正に対して、ブラック・フェミニストとして表明する詩的なメッセージとなっていった。
1 / 2
キイが展示を行ったのは、古くから舞妓やお茶屋の女将が活躍し、歴史的に女性の街とされてきた祇園。会場の「アスフォデル(ASHODEL)」には、女性の生理や体毛、妊娠など、社会的にはまだまだセンシティブな内容に触れる作品が並ぶ。しかし、キイが毛髪で作るポップな写真イメージは、身構える鑑賞者の緊張を解き、作品のメッセージをさりげなく心に届けてくれる。何より葛藤を乗り越えて自分を受け入れ、生き生きと写真に写るキイの姿そのものが、自分の境遇やアイデンティティを肯定することの意義を率直に伝えている。なおキイは、滞在制作の拠点だった出町桝形商店街にも作品を展示している。こちらには、シリアスなトピックスに触れる祇園の展示とは対照的に、アフリカ出身の若者が、京都の文化に触れて得たインスピレーションを形にしたユーモラスでコミカルな写真イメージが、バナーとして商店街を彩る。
リー・シュルマン&オマー・ヴィクター・ディオプ「ビーイング ゼア」
展示会場:嶋䑓ギャラリー
1 / 2
ノスタルジックな空間と写真が多様性を考える装置に
同じく写真イメージを通して、人種的なパワーバランスの不均衡というトピックに触れるのが、イギリス人アーティスト、リー・シュルマン(Lee Shulman)とセネガル出身の写真家、オマー・ヴィクター・ディオプ(Omar Victor Diop)の共作「ビーイング ゼア(Being There)」だ。
2人は、町屋を改装した「嶋䑓ギャラリー」に、ミッドセンチュリースタイルの家具とポップな色味の壁紙を配置。「古き良きアメリカ」を思わせる心地良い空間を設えた。展示するのは、家具と同時代のものと思われるノスタルジックな写真や映像。だがよく見ると、全てのイメージに同じ黒人男性が写り込んでいる。アーティストのヴィクター・ディオプ本人だ。実はこれらのイメージは、1950〜60年代の北米で撮られたスナップ写真に、ディオプのイメージを合成して作り上げたフィクション写真。しかし「そもそも、家族のアルバムは巧妙に作られたフィクションだ。調和のとれた世界を演出し、厄介な真実はフレームの外側に追いやる」とシュルマンは言う。
シュルマンは、匿名の家族写真や日常のスナップショットを収集・保存するプロジェクト「アノニマス・プロジェクト(The Anonymous Project)」を主宰する。現在、1950年代から2000年代までに撮られた100万点以上の画像を所蔵するシュルマンは、20世紀半ばに北米で撮られたスナップ写真を多数見るうち、牧歌的な魅力に引かれつつ、人口の多数を占めていたはずのアフリカ系アメリカ人の「不在」に気付く。それらを批判的に考察し、再構築するためにセルフポートレートを中心に活動する黒人アーティスト、ヴィクター・ディオプを写り込ませるアイデアを着想した。当時のアメリカは第二次世界大戦後の経済繁栄を謳歌していたが、平等とは程遠い状況にあった。人種隔離政策が敷かれ、多くの人が肌の色を理由に、基本的人権の制限を受けていた。その事実に向き合った時、先ほど使った「古き良きアメリカ」という言い回しの残酷さに気付かされ、快適だった「おしゃれ」な展示空間は、当時の白人中産階級的ライフスタイルの外側に追いやられた人種的マイノリティーたちへの想像を喚起する装置となる。
2人の作品は、そうした歴史を批判しつつも、どこか軽妙でユーモアすら感じさせる。しかし同時に、私たちにフレームの内側と外側に作用するポリティクスへの思考をうながし、複雑な歴史に滑らかなコーティングをほどこす「ノスタルジア」の危険な魅力を浮き彫りにさせる。
マーティン・パー「スモール・ワールド」
展示会場:タイムズ
1 / 2
観光がパッケージ化してしまう文化 写真で切り取るオーバーツーリズム
安藤忠雄の設計により1984年に建てられた高瀬川沿いの「タイムズ(TIME’S)」では二つの展示を見ることができる。一つはマーティン・パー(Martin Parr)の「スモール・ワールド(Small World)」。マグナムフォトのレジェンドの作品を、街中の会場で気軽に見ることができるのも「キョウトグラフィー」の魅力の一つだ。
今回展示している「スモール・ワールド」はパーの代表作のひとつ。国際的な観光の拡大とその表層性、均質化を鋭く、かつユーモラスに批評した写真シリーズだ。1980年代から90年代初頭にかけて、パーは世界各国の観光地(ヨーロッパ、アメリカ、日本など)をめぐり、観光客たちの行動、ポーズ、消費行動を写真で記録。「観光」という営みがもたらす画一的な光景──人々が同じ場所で同じポーズを取り、同じようにお土産を買う姿──を、鮮やかなカラー写真で捉えている。クスッと笑ってしまう作品群だが、グローバル化や消費社会に対する辛辣な風刺が込められている。
今回の「キョウトグラフィー」に合わせ、パーは一足早く来日。桜の開花でにぎわう京都の観光客にレンズを向け「スモール・ワールド」の京都バージョンを撮り下ろした。皮肉を感じさせる独特な距離感で切り取った京都のオーバーツーリズム。パーの冷静な態度は、京都観光で浮かれる観光客の「滑稽さ」を少し意地悪に浮き彫りにしてしまう。それに拍車をかけるように写真はコミカルなBGMにのせてスライドショー形式で展示される。インスタグラムの登場により、文化を「映えるか映えないか」という基準でジャッジする風潮が高まったが、パーが80年代から続けてきた「スモール・ワールド」は、それを予見してきた作品とも言え、今の時代にますます強いメッセージを放っている。
アダム・ルハナ「ロジック・オブ・トゥルース」
展示会場:「八竹庵」
1 / 2
パレスチナの日常の写真を通して問う「真実」
「八竹庵」で展示するアダム・ルハナ(Adam Rouhana)の作品「ロジック・オブ・トゥルース(真実の論理)」は、パレスチナの人々の日常生活を切り取った写真を通じて、歴史の操作や真実の歪曲に意義を唱え、観客に新たな視点を提供する。
パレスチナ系アメリカ人のルハナは、アメリカで育ち、現在はエルサレムとロンドンを拠点に活動する写真家だ。写真を通して、西洋を中心に構築されてきた「東洋」への偏ったまなざしを再構築することをテーマにかかげる。ルハナは、パレスチナの家庭や日常の美しい風景を撮影する。日本家屋の中にインスタレーションとして展示されるこれらの写真は、メディアによって描かれるステレオタイプなイメージとは異なる、現地の人々の生きた日常を伝えている。
ニュース番組を通して放映される戦地の映像は、私たちの日常とあまりにもかけ離れているからこそ、時に現実感に乏しく、戦禍の影響を受ける人々への想像力を奪ってしまう。繰り返し流される凄惨で「非現実的」な映像は、戦争被害者にもおだやかな日常や家族とのささやかな幸せがあったことを忘れさせてしまう。またその戦禍の「真実」は「誰が報じるか」によって見え方はまるで違ってしまうことも事実だ。「ロジック・オブ・トゥルース」は、そんな忘却や印象の操作に抗う作品だ。パレスチナの人々の生活を記録した写真を通して、私たちの想像力に働きかけ、植民地主義や帝国主義を起因とする混迷の歴史を見直し、真実とは何かを問いかける。
The post 「キョウトグラフィー」2025リポート 写真を通して「人間性」を問う国際フェスティバル appeared first on WWDJAPAN.




















































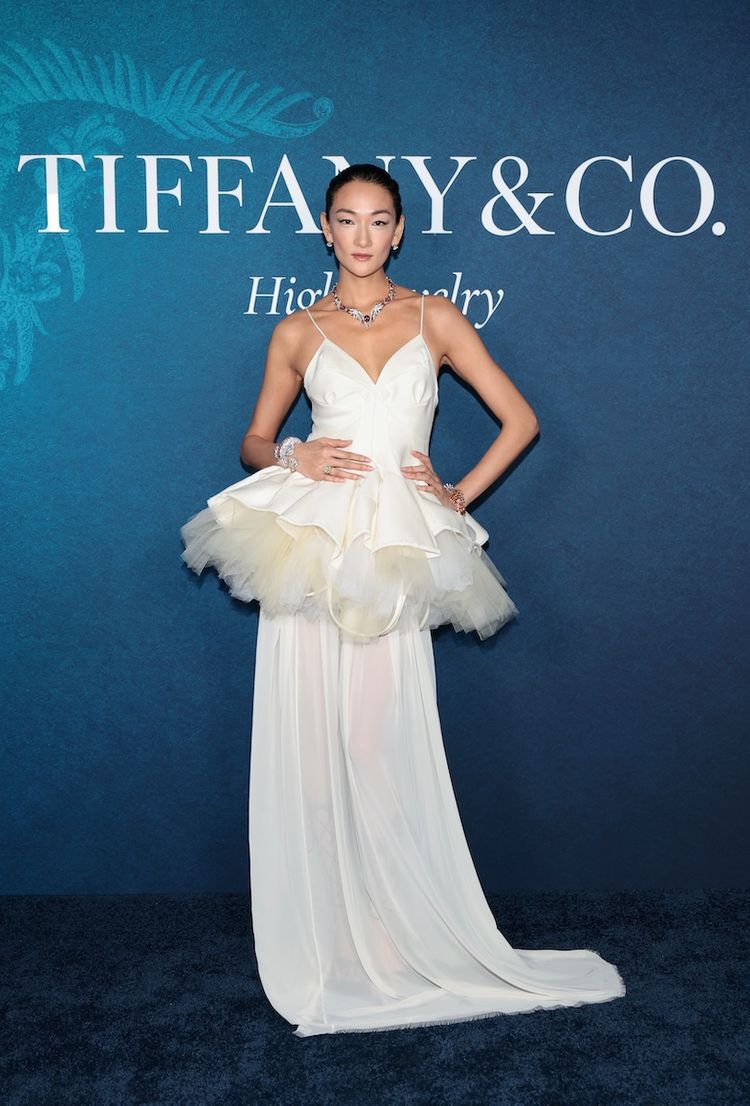



































 ロマンチックやフェミニンなムードが一気に広がった2025年春夏のファッション。その潮流に合わせ、ヘアスタイルにも軽やかさや優しさ、柔らかさを求める動きが表れ始めている。ここでは4人の人気美容師に、高発色がかなうナプラのヘアカラー「N.(エヌドット)ルフレカラー」を使い、その変化を表現した最旬ヘアを披露してもらった。
ロマンチックやフェミニンなムードが一気に広がった2025年春夏のファッション。その潮流に合わせ、ヘアスタイルにも軽やかさや優しさ、柔らかさを求める動きが表れ始めている。ここでは4人の人気美容師に、高発色がかなうナプラのヘアカラー「N.(エヌドット)ルフレカラー」を使い、その変化を表現した最旬ヘアを披露してもらった。






















































