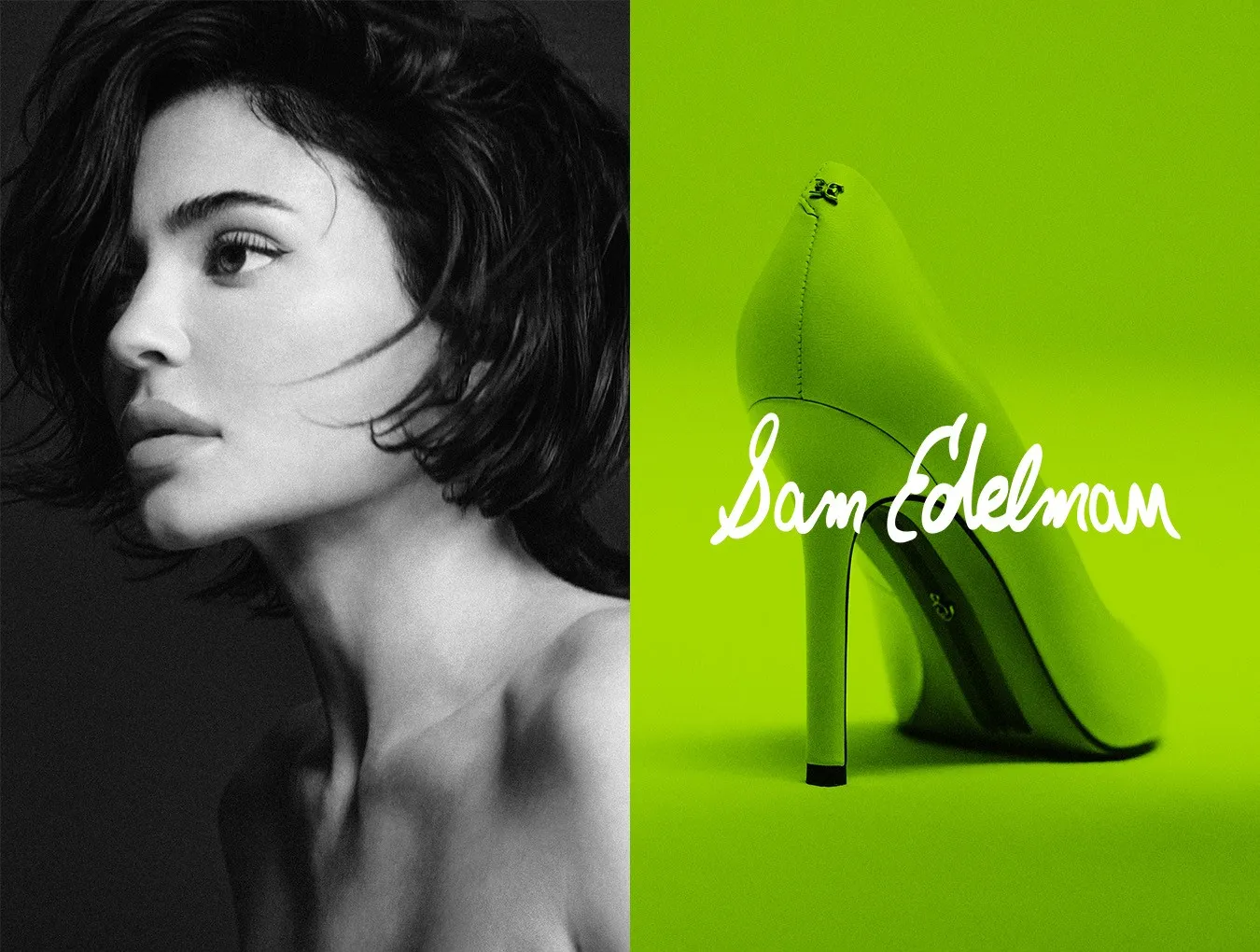ケイト・マレヴィ(Kate Mulleavy)とローラ・マレヴィ(Laura Mulleavy)姉妹によるブランド「ロダルテ(RODARTE)」は、来年ブランド設立20周年を迎える。地元ロサンゼルスを拠点に、ニューヨーク・ファッション・ウイークに参加し、コレクションを発表してきた。近年では、アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞などの授賞式に参加するセレブリティーのカスタムドレスを手掛けたり、映画やオペラの衣装を制作したりと、活動の場を広げている。こうして実力を発揮し、キャリアを積んできているものの、2人は「(ファッション業界において)デザイナーとして正当に評価されていない」と感じるという。
ケイトは1979年、ローラは80年に、カリフォルニア州パサデナで生まれた。姉妹である2人は幼い頃からデザイナーになる夢を持ち、カリフォルニア大学バークレー校(University of California, Berkeley)を卒業後、故郷のパサデナに戻り、05年に母親の旧姓を冠した「ロダルテ」を設立した。06年春夏シーズンにニューヨークでデビューコレクションを発表し、08年には、Tシャツやカジュアルウエアのコレクション「ラダルテ(RADARTE)」をスタート。09年、アメリカファッション協議会(COUNCIL OF FASHION DESIGNERS OF AMERICA以下、CFDA)による「CFDAアワード(CFDA Awards)」の新人賞にあたるスワロフスキー・アワードのウィメンズ部門を受賞。その後もコレクションの発表をする傍ら、映画「ブラック・スワン(BLACK SWAN)」やオペラ「ドン・ジョヴァンニ(Don Giovanni)」で衣装をデザインするなど、新たな道を切り開いてきた。映画制作にも取り組み、17年には姉妹が脚本と監督を手掛け、キルスティン・ダンスト(Kirsten Dunst)が主演を務めた映画「WOODSHOCK」が、第74回ベネチア国際映画祭で公開された。
同世代のアメリカブランドには、02年設立の「プロエンザ スクーラー(PROENZA SCHOULER)」や今年20周年を迎える「トリー バーチ(TORY BURCH)」がある。またロサンゼルスのつながりで言えば、「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」前メンズ・アーティスティック・デザイナーで「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー(OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH)」の創業者ヴァージル・アブロー(Virgil Abloh)や、「モスキーノ(MOSCHINO)」のクリエイティブ・ディレクターだったジェレミー・スコット(Jeremy Scott)といった、ビッグメゾンに抜擢された男性デザイナーがいる。
女性デザイナーが活躍する難しさを痛感
メトロポリタン美術館(METROPOLITAN MUSEUM OF ART)のコスチューム・インスティチュート(COSTUME INSTITUTE)は12月、ファッション業界における女性のデザイナーの仕事にフォーカスした展覧会「ウィメン・ドレッシング・ウィメン(Women Dressing Women)」を開催。「ロダルテ」の作品も展示されているこの展覧会や、23年9月に退任した「アレキサンダー・マックイーン(ALEXANDER McQUEEN)」のクリエイティブ・ディレクター、サラ・バートン(Sarah Burton)の後任に男性デザイナーのショーン・マクギアー(Sean McGirr)が起用されたことをきっかけに、ファッション業界における性差別や欧州のラグジュアリーブランドを率いる女性デザイナーの少なさに関する対話が増えているが、マレヴィ姉妹はこれを痛感しているという。その一例として、キャリア20年にして一度だけ、大手メゾンからクリエイティブ・ディレクター候補として声を掛けられたときのことを挙げた。
「たった一回の会話でそぐわないと判断され、とてもショックだった。私たちは最高の女優たちにドレスを提供し、すばらしい衣装を作り、世界中の美術館に展示され、ショーも開催し、アーティストとも協業している。これらすべてを独立した企業として行ってきたし、人々は『ロダルテ』がどういうブランドであるかも知っている。自惚れるわけではないが、ほかに何が必要だというのか」。
最近では、映画祭などのレッドカーペットでその名を広めている。今年に入ってからは、1月に行われた第35回パームスプリングス国際映画祭で、第81回ゴールデングローブ賞で主演女優賞(ドラマ部門)を受賞したリリー・グラッドストーン(Lily Gladstone)にドレスを提供。その後の第96回アカデミー賞では、最多受賞となった「オッペンハイマー(Oppenheimer)」のプロデューサー、エマ・トーマス(Emma Thomas)や映画監督マーティン・スコセッシ(Martin Scorsese)の娘で俳優兼監督であるフランチェスカ・スコセッシ(Francesca Scorsese)ら、過去最多12人のドレスをデザイン。制作には、8人のチームで数カ月におよぶ集中的な作業を要した。
その間には、「ロダルテ」の24-25年秋冬コレクションのルックブックとポートレートシリーズにも取り掛かっていたため、多忙を極めたという。ローラは、「すごく疲れたわ。12ルックはそれぞれ4〜5回ものフィッティングが必要だった」と、俳優らのスケジュールに合わせながらドレスを制作したことを明かした。

トーマスには、シースルーの袖に、フロントをクロスさせた黒のドレスを提供。長年映画業界に携わり、今回「ロダルテ」にドレスを依頼したスタイリストのクリスティーナ・エールリッヒ(Cristina Ehrlich)は、「ケイトとローラには、レッドカーペットという晴れの舞台で詩的に語りかけるような、ユニークで時代を超越したスーパーフェミニンなドレスを生み出す目と知性がある」と高く評価した。
ケイトは、トーマスにドレスを着せたことは意義深いことだったと振り返る。「男性中心で女性の活躍が容易ではない映画業界で、多くのことを成し遂げてきた彼女に、とてもインスパイアされた。多くの扉を開いてきた彼女の活躍の重みを感じたし、彼女が10年後を振り返って、まだこのドレスを好きでいてくれることを願っている」。
大手ブランドは、レッドカーペットなどの重要なイベントでトップクラスのセレブに衣装を着用してもらうため、報酬を支払うことも多い。そうした予算がないブランドは、デザインを無料で行うことしかできないが、ケイトは「それでも『ロダルテ』を選んでくれたとき、これまで誠実に積み上げてきた実績を誇らしく思う」と話した。
「何十億ドル規模の巨大企業と同じレベルで活動することは、持続可能ではない」
「ロダルテ」は売上高などの数字を公開していないが、独自の戦略を掲げて事業を拡大してきた。コロナ禍の間、年2回のコレクション発表を4回に切り替え、イヴニングウエアを中心に発表することにし、D2Cのオンライン販売を強化。また、米高級百貨店バーグドルフ・グッドマン(Bergdorf Goodman)やサックス・フィフス・アベニュー(SAKS FIFTH AVENUE)、ECのモーダ・オペランディ(MODA OPERANDI)、ネッタポルテ(NET-A-PORTER)、マイテレサ(MYTHERESA)、ショップボップ(SHOPBOP)、アマゾン・ラグジュアリー(Amazon Luxury)でも販売している。主な価格帯は、プレタポルテとイヴニングウエアが966〜4000ドル(約14万〜60万円)、セミクチュールは4000〜1万ドル(約60万〜151万円)、オーダーメードのクチュールは1万〜4万ドル(約151万〜604万円)。さらにブライダルを加え、ネッタポルテでカプセルコレクションを発売する予定だ。
同ブランドは23年9月に発表した24年春夏コレクション以来、ランウエイショーを行っていないが、今年9月のニューヨーク・ファッション・ウイークに参加するかどうかは未定だという。「何十億ドル規模の巨大企業と同じレベルで活動することは持続可能ではない。映画制作も手掛けているので、シーズンにとらわれず、クリエイティビティーを大切にデザインし、必要に応じてショーを開催する。こうした“賢い”決断の積み重ねが、ビジネスを続けられてきた理由だと思う。私たちはアーティストであり、夢を与えるコレクションを作っている」とマレヴィ姉妹。また、彼女たちのように女性主導のビジネスが成功するためには、より均等な機会の創出など業界のシステム改革が必要だと説いた。
The post アカデミー賞のドレスで再注目の「ロダルテ」 デザイナー姉妹が「正当に評価されていない」と感じる理由 appeared first on WWDJAPAN.