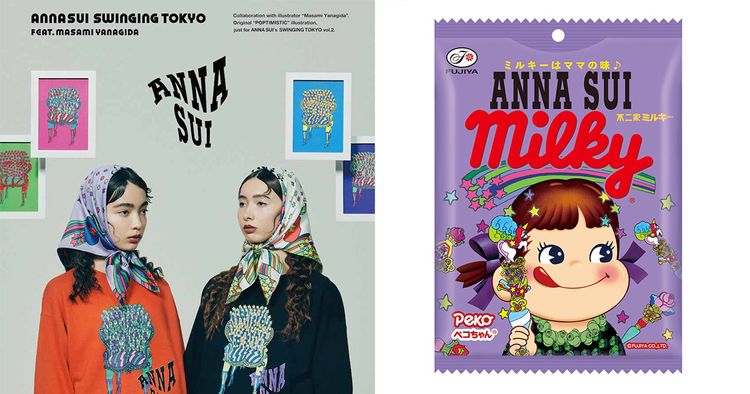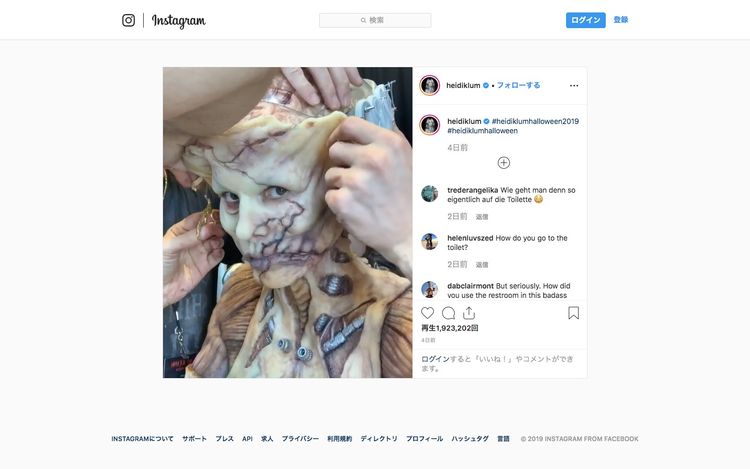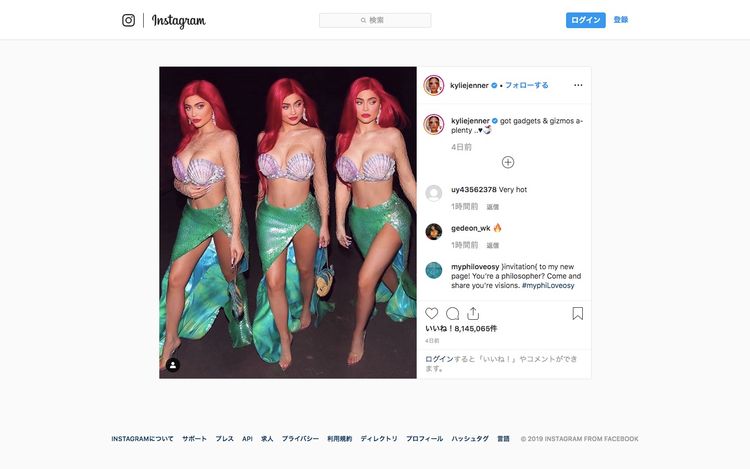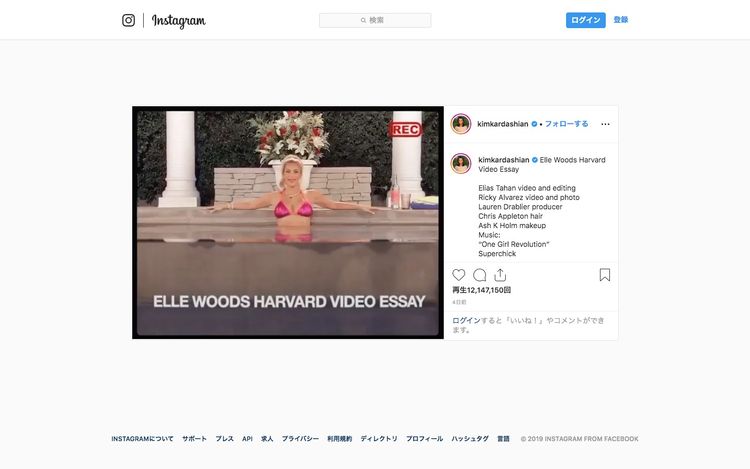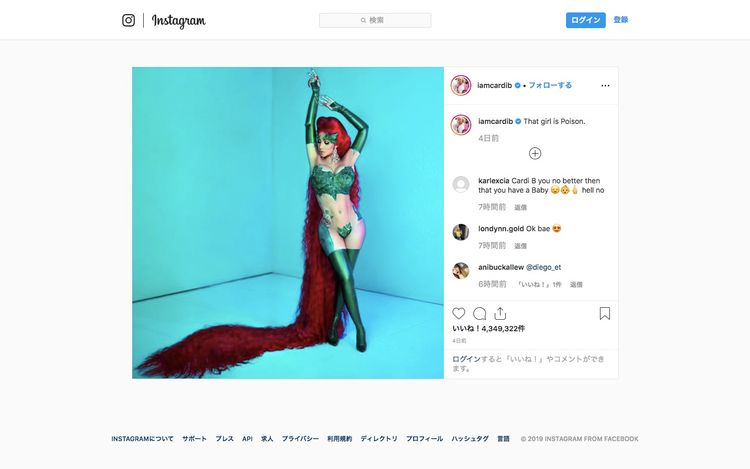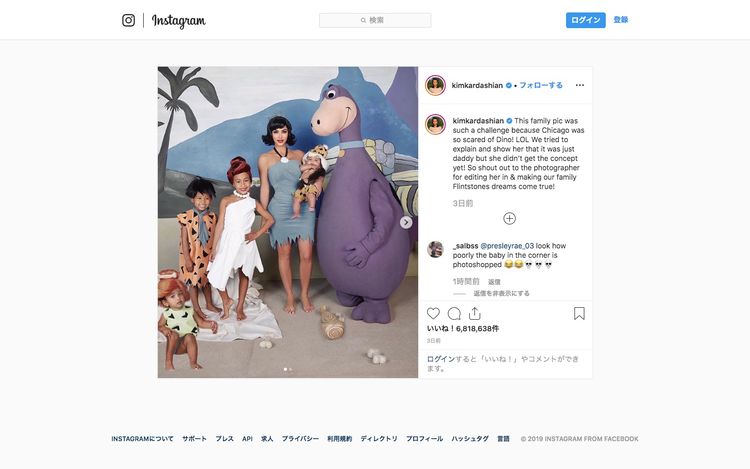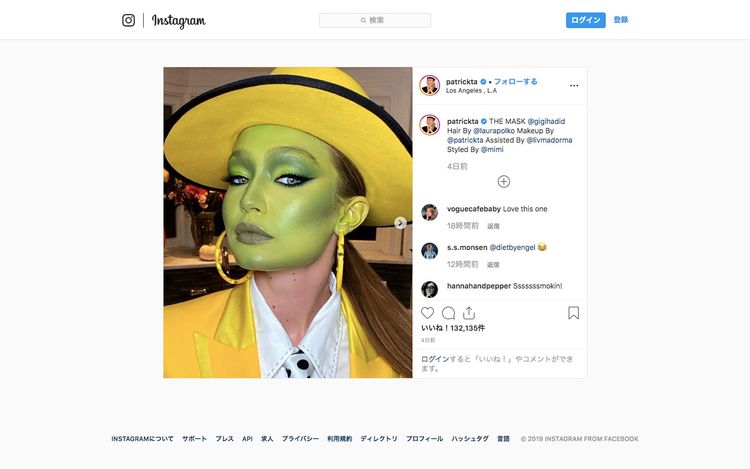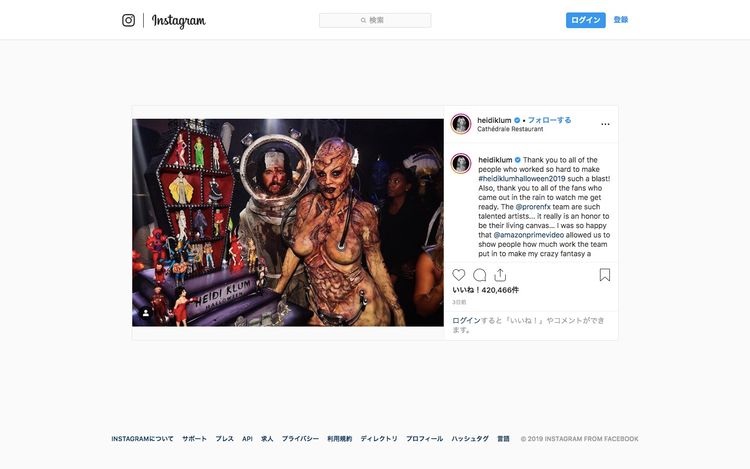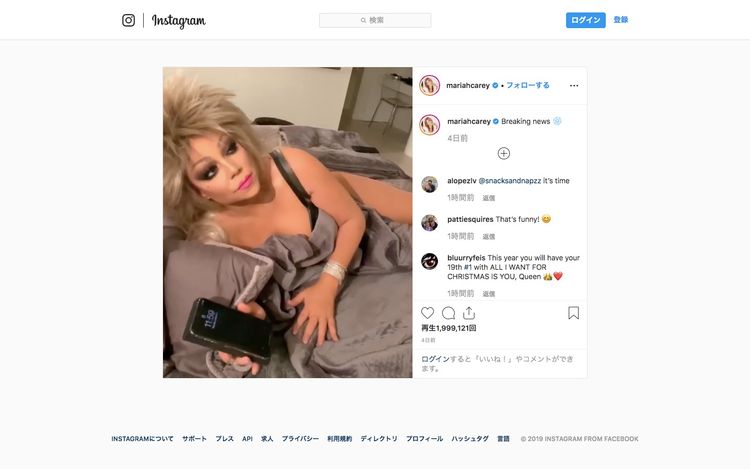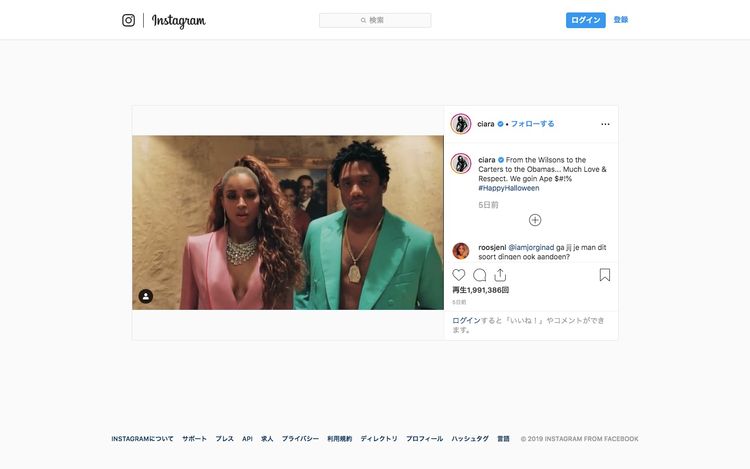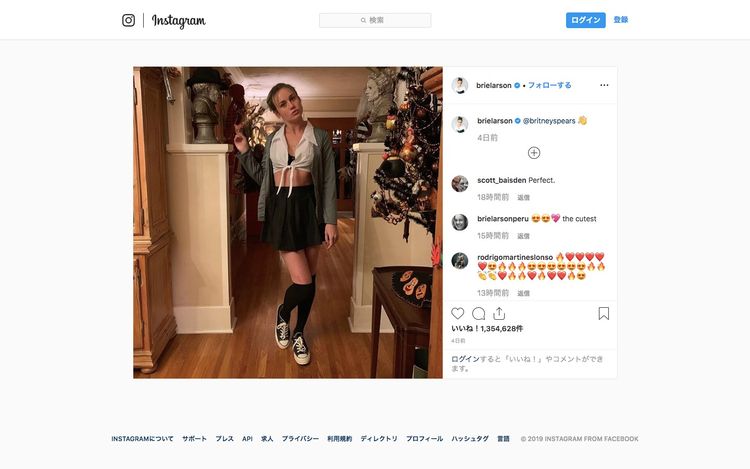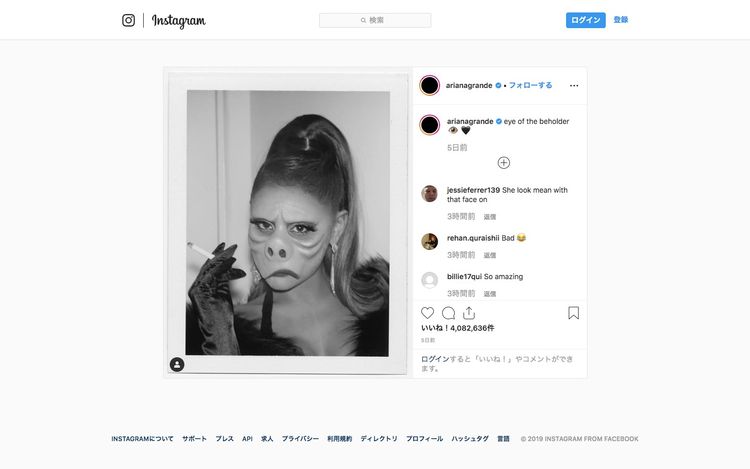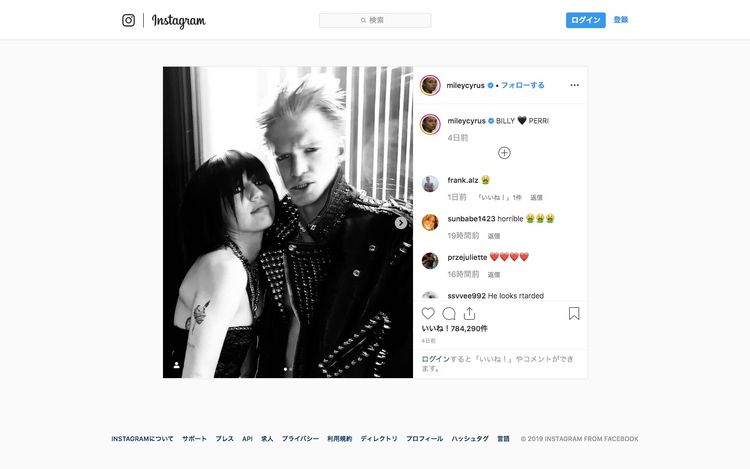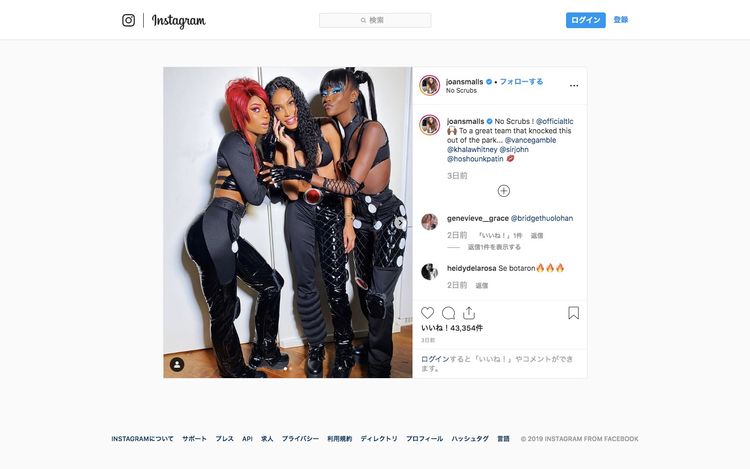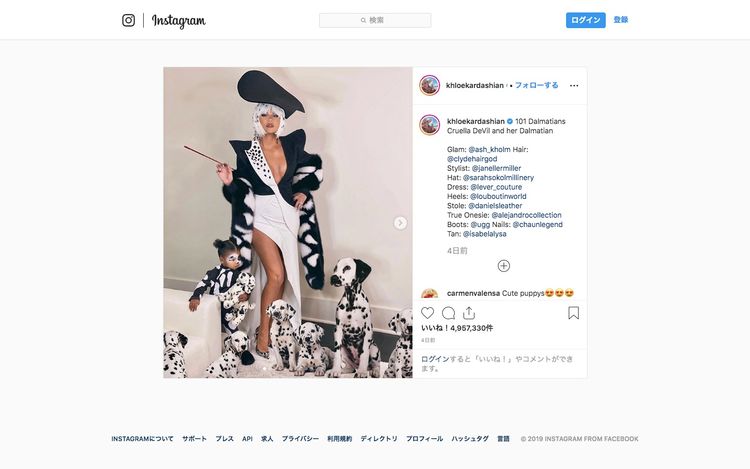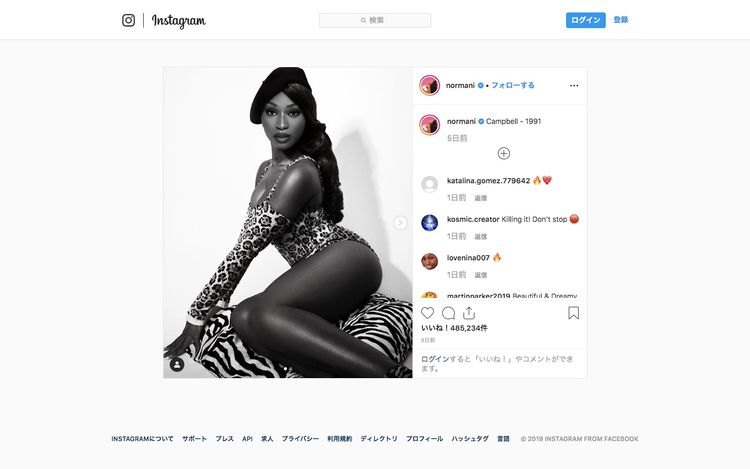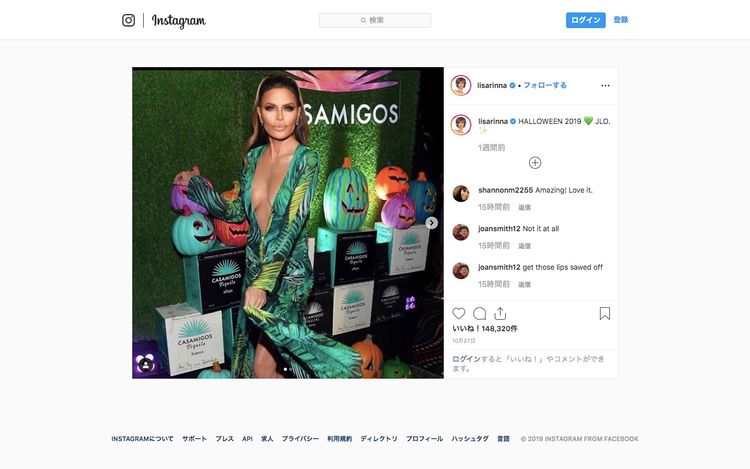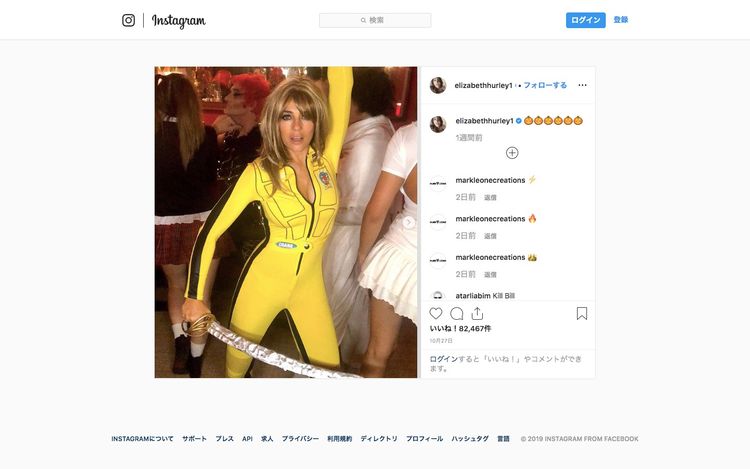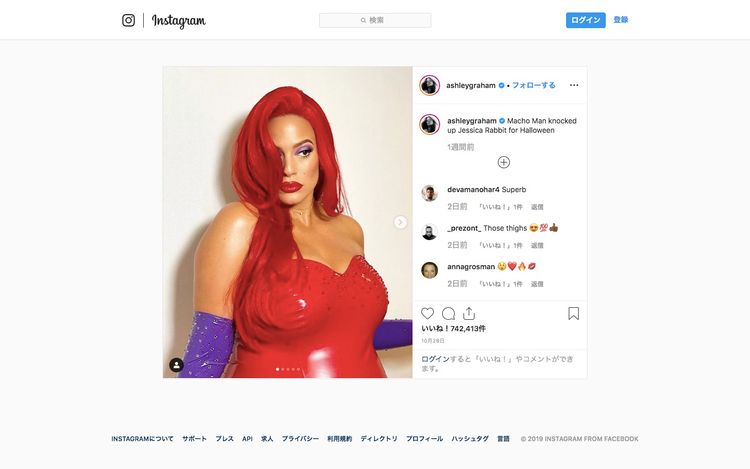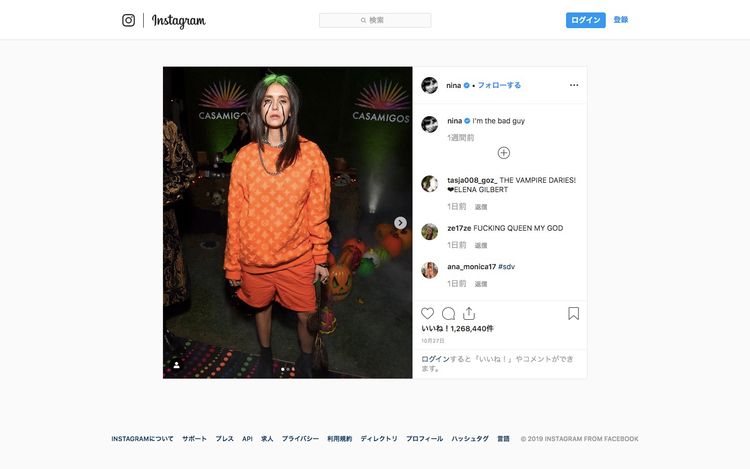サステナビリティに取り組まない企業は存続できない――といわれる一方で、具体的に何をどうしたらいいのか分からないという声も聞く。そこで「WWDジャパン」11月25日号では、特集「サステナビリティ推進か、ビジネスを失うか」を企画し、経営者やデザイナー、学者に話を聞きその解決策を探る。今回は名門セント・マーチン美術大学(Central Saint Martins)マテリアル・フューチャーズ学科のキーラン・ジョーンズ(KIERAN JONES)=主任教授に“未来の素材”を問う。
「重視しているのは、最新技術を
どう産業に組み込むか」
WWD:修了生の就職先はナイキ(NIKE)のような人気企業から、バイオテクノロジーの有力スタートアップ、モダンメドウ(MODERN MEDOW)まで幅広いが、いずれも分野のトップ企業ばかりだ。企業ですぐに活躍できる学生を送り出しているが、マテリアル・フューチャーズ学科の強みは?
キーラン・ジョーンズ=マテリアル・フューチャーズ学科主任教授(以下、ジョーンズ):学生は自らセルロースなどを培養していて、そうした最新技術を身に付けながら、その素材をどう生産工程に組み込んでいくか、どうスケールアップしていくかを重視している。サンプルを意味あるモノに変えていくことが重要だからね。この9月から学内にバイオラボを開設して専門家2人が常駐することになったのも、そうした考えからだ。
10年前は、私たちがやっていることはクレイジーだと不思議がられた。けれど今は真逆で、さまざまな分野の人たちが訪ねてくる。専門知識を求めてね。例えば「ステラ マッカートニー(STELLA McCARTNEY)」やLVMHもそう。
WWD:学生はほかにどういうところに就職するのか。
ジョーンズ:例えば、菌やバクテリアなど微生物のセルロースでスニーカーを編み上げるバイオ編機を開発したジェン・キーン(Jen keane)は、ちょっとした競争入札になって、ナイキ、アディダス(ADIDAS)、プーマ(PUMA)が争っていた。パイナップルの葉の繊維から織物を作る技術を開発したナタリー・スペンサー(Nathalie Spencer)はパイナップルの葉の繊維からレザー風の素材を作るアナナス・アナム(ANANAS ANAM)に行った。
「学生たちは自然を操れる力があると信じている。想像もできなかったことが起きているから」
WWD:学生が就職したいと思う企業も変わっている?
ジョーンズ:ファッション学科全体では、現在のメインはクチュールハウスだろう。しかし、これから大学に入る若い世代は企業に変化を求めているし、彼らは全く新しい道を選ぶだろう。
だから、変化できない企業は大きなリスクを背負うことになる。5年先は大丈夫かもしれないが、その後は絶望的なトラブルに見舞われるだろう。
われわれが教える学生たちは産業に合わせるのではなく、積極的に改善し、産業を破壊するのではなくリードして新しい方向に導く人物だ。
WWD:今学生たちが一番面白いと感じていることは?
ジョーンズ:間違いなくバイオデザインだ。特にラボで育てる菌糸体、バクテリア、キノコ類、粘菌などがそう。新しい分野であり、錬金術のような魔法みたいなところがあるから。プラスチックを食べる酵素が開発されたりと、遠い未来に起こると思われたことが今起こっている。そして今の学生たちは、自然を操れる力があると信じている。2年前に想像できなかったことが目の前で起こっているから。
「デザインは強いツールだが、今までとは異なるアプローチが求められる」
WWD:なぜ今、サステナビリティがかつてないほど大きなトピックになっているのか。
ジョーンズ:人類の歴史上、今ほど変わらなければいけないという証拠がそろっていることはないから。エクスティンクション・リベリオン(Extinction Rebellion:英国を中心に起きている気候変動に抗議する非暴力行動)やグレタ・トゥンベリ(Greta Thunberg:スウェーデン出身の環境活動家)を見ていたらそれが分かる。けれど、(抗議活動ばかりが報道されていて)それらは問題の本質から目をそらせてしまっているのも事実。国連のSDGs(持続可能な開発目標)やどの信頼できるレポートを見てもどれも同じことを言っている。これから10年、20年、30年後、具体的な数字は定かではないが、今までのようにはやっていけないということは明らかだ。
私たちはこれまで、モノを作ることを学んできた。特に売れるモノをね。だけどこれからの学生たちは、“デザインとは何か”を考え直さなければならない。デザインは本当に強いツールであり、私たちが持っている最も魅力的でパワフルな道具だけど、今までとは異なるアプローチが求められる。
WWD:デザインを根本的に変えなければいけないのはなぜ?
ジョーンズ:ファッション、デザイン、アート、建築は実はとても破壊的なんだ。特にファッションは廃棄物が多い産業トップ3に入る。英国におけるファッション産業の環境への負荷は輸送産業よりもひどいと言われている。そう考えるとショックだよね。
素材でいうと、1950~60年代は合成繊維の開発に突っ走っていたけど、それ以降、技術的進歩はあまり見られなかった。それよりもトレンドやデザインといった見た目を重視していたから。でも今はまた素材に関心が戻ってきていて、面白いことができるようになっている。
「問題は山積み。
状況に合うパズルを見つけて
はめ込むイメージで取り組むこと」
WWD:ファッション産業の問題点は?
ジョーンズ:全て。何かに限定できない。一つ一つの問題に関して深く考えていくことが必要だ。例えば、循環型の仕組みにはまらない合成繊維を使うべきではないのは明らかだけれど、天然繊維だったとしても、コットンの栽培には水が大量に必要だし、農地も必要でしょう。ほとんどが農薬も肥料も使う。モノによっては合成繊維よりも環境に悪い可能性もある。仕組みや状況に合うパズルを見つけてうまくはめていくイメージで取り組むことが必要だね。
WWD:今、循環型の考え方が重視されている。
ジョーンズ:循環型の考え方は絶対に必要だ。素材や仕組みから考えなければいけないけれど、今ある仕組みに適応できなかったら意味がない。今のベストは、すでにある合成繊維や山ほど捨てられているものを再利用して新しい服を作ること。そのプロセスも最低限のエネルギー使用にとどめて、染料の使用も控えて永遠にリサイクルすること。そして、素材をミックスするのをやめて単一素材に替え、解体できるデザインにする。素材の構成はもちろん、どう回収するかまで考えなければならない。
WWD:単一素材だと面白味がなくなるかも。
ジョーンズ:単一素材か、もしくは簡単に分解できる構成素材ならばよし。循環型の生産をするには、法律を変える必要があるかもしれない。各企業が分解できるもののみの生産を許されるなどね。
WWD:今後ファッション業界はどうなると思う?
ジョーンズ:ファッションのぜいたくなところはなくならないと思う。ファッションは退廃的で、だからこそ好きだし遊び心があると感じる。それはたぶん誰も失いたくない点だろう。一番変わるのは消費者が服とどうつながるかだと思う。
私たちは今、目に見えるデザインが気に入ったから購入するという習慣だけど、これからはブランドが取り組むサステナビリティのここが好き、と選ぶことになると思う。一つの会社が全部をカバーするのは無理だからね。例えば、循環型、バイオマテリアル、生分解性、山林破壊をしていない、節水、汚水を出さないなど、全ての要素をカバーできるわけがない。だから企業はよく考えて、サステナビリティの何にフォーカスするのかを決めなければいけない。
The post サステナビリティって何? 専門家が答えます。連載Vol.7 ファッションの名門セント・マーチンの教授に聞く“未来の素材” appeared first on WWD JAPAN.com.

 CKR Kondo : 大手通信会社に入社後、暗号技術/ICカードを活用した認証決済システムの開発に従事。その後、欧州/中東外資系企業向けITソリューションの提供、シンガポール外資系企業での事業開発を経験。企業とその先の利用者が必要とするもの、快適になるものを見極める経験を積み、ウェアラブルデバイスやFree WiFiを活用したサービスインキュベーションを推進。現在は、米国、欧州、アジア太平洋地域にまたがる、新たなサイバーセキュリティサービスの開発を推進中
CKR Kondo : 大手通信会社に入社後、暗号技術/ICカードを活用した認証決済システムの開発に従事。その後、欧州/中東外資系企業向けITソリューションの提供、シンガポール外資系企業での事業開発を経験。企業とその先の利用者が必要とするもの、快適になるものを見極める経験を積み、ウェアラブルデバイスやFree WiFiを活用したサービスインキュベーションを推進。現在は、米国、欧州、アジア太平洋地域にまたがる、新たなサイバーセキュリティサービスの開発を推進中
 FROM OUR INDUSTRY:ファッションとビューティ、関連する業界の注目トピックスをお届けする総合・包括的ニュースレターを週3回配信するメールマガジン。「WWD JAPAN.com」が配信する1日平均30本程度の記事から、特にプロが読むべき、最新ニュースや示唆に富むコラムなどをご紹介します。
FROM OUR INDUSTRY:ファッションとビューティ、関連する業界の注目トピックスをお届けする総合・包括的ニュースレターを週3回配信するメールマガジン。「WWD JAPAN.com」が配信する1日平均30本程度の記事から、特にプロが読むべき、最新ニュースや示唆に富むコラムなどをご紹介します。

 Azu Satoh : 1992年生まれ。早稲田大学在学中に渡仏し、たまたま見たパリコレに衝撃を受けファッション業界を志す。セレクトショップで販売職を経験した後、2015年からファッションベンチャー企業スタイラーに参画。現在はデジタルマーケティング担当としてSNS運用などを行う。越境レディのためのSNSメディア「ROBE」(@robetokyo)を主催。趣味は、東京の可愛い若手ブランドを勝手に広めること。ご意見等はSNSまでお願いします。Twitter : @azunne
Azu Satoh : 1992年生まれ。早稲田大学在学中に渡仏し、たまたま見たパリコレに衝撃を受けファッション業界を志す。セレクトショップで販売職を経験した後、2015年からファッションベンチャー企業スタイラーに参画。現在はデジタルマーケティング担当としてSNS運用などを行う。越境レディのためのSNSメディア「ROBE」(@robetokyo)を主催。趣味は、東京の可愛い若手ブランドを勝手に広めること。ご意見等はSNSまでお願いします。Twitter : @azunne




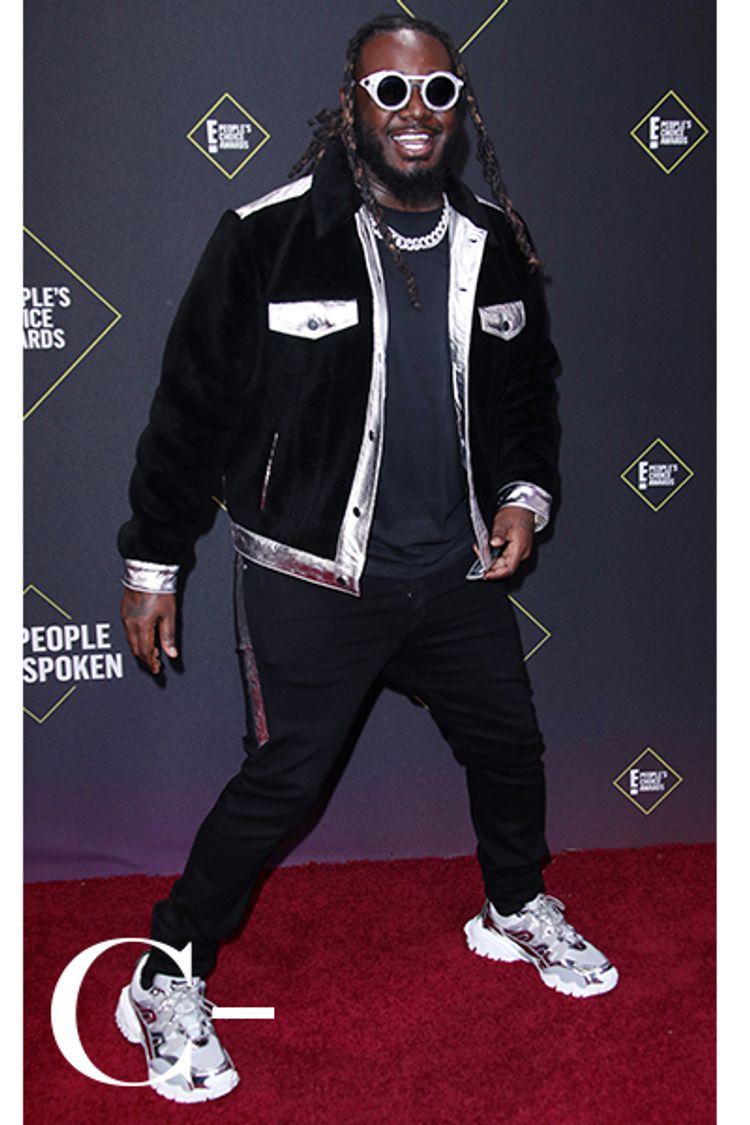




 ファッションジャーナリスト・ファッションディレクター 宮田理江:
ファッションジャーナリスト・ファッションディレクター 宮田理江:












 宇野ナミコ:美容ライター。1972年静岡生まれ。日本大学芸術学部卒業後、女性誌の美容班アシスタントを経て独立。雑誌、広告、ウェブなどで美容の記事を執筆。スキンケアを中心に、メイクアップ、ヘアケア、フレグランス、美容医療まで担当分野は幅広く、美容のトレンドを発信する一方で丹念な取材をもとにしたインタビュー記事も手掛ける
宇野ナミコ:美容ライター。1972年静岡生まれ。日本大学芸術学部卒業後、女性誌の美容班アシスタントを経て独立。雑誌、広告、ウェブなどで美容の記事を執筆。スキンケアを中心に、メイクアップ、ヘアケア、フレグランス、美容医療まで担当分野は幅広く、美容のトレンドを発信する一方で丹念な取材をもとにしたインタビュー記事も手掛ける










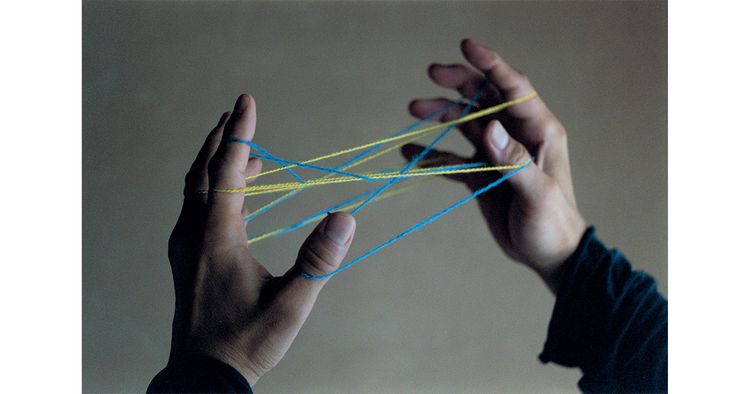








 鈴木敏仁(すずき・としひと):東京都北区生まれ、早大法学部卒、西武百貨店を経て渡米、在米年数は30年以上。業界メディアへの執筆、流通企業やメーカーによる米国視察の企画、セミナー講演が主要業務。年間のべ店舗訪問数は600店舗超、製配販にわたる幅広い業界知識と現場の事実に基づいた分析による情報提供がモットー
鈴木敏仁(すずき・としひと):東京都北区生まれ、早大法学部卒、西武百貨店を経て渡米、在米年数は30年以上。業界メディアへの執筆、流通企業やメーカーによる米国視察の企画、セミナー講演が主要業務。年間のべ店舗訪問数は600店舗超、製配販にわたる幅広い業界知識と現場の事実に基づいた分析による情報提供がモットー






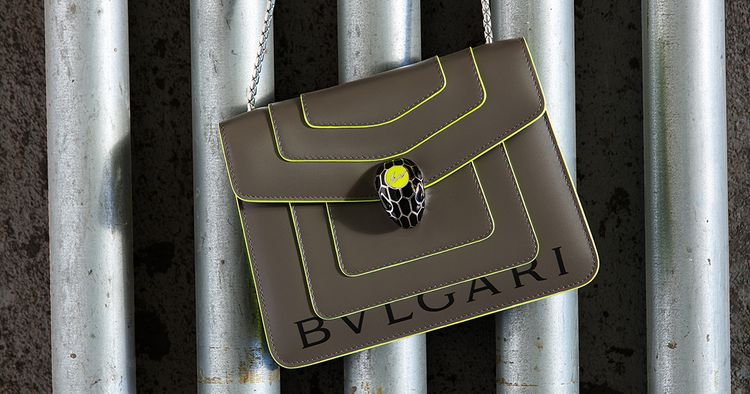
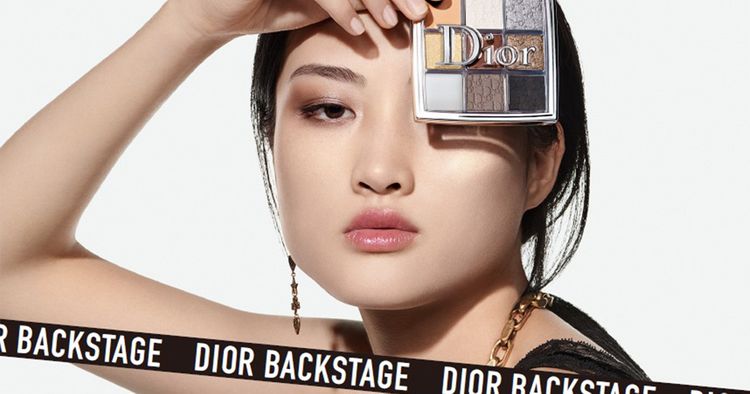





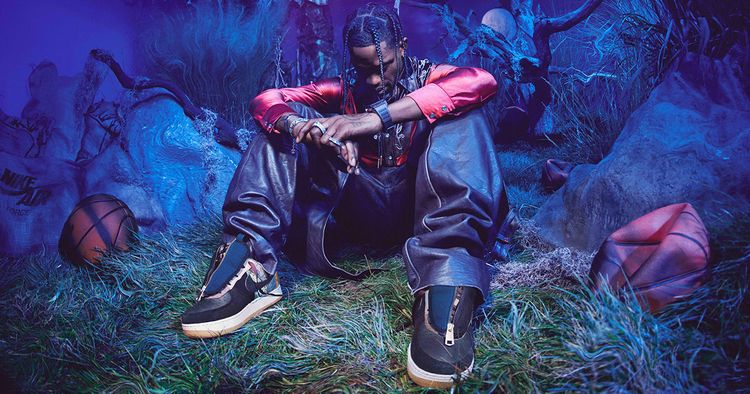



 ELIE INOUE:パリ在住ジャーナリスト。大学卒業後、ニューヨークに渡りファッションジャーナリスト、コーディネーターとして経験を積む。2016年からパリに拠点を移し、各都市のコレクション取材やデザイナーのインタビュー、ファッションやライフスタイルの取材、執筆を手掛ける
ELIE INOUE:パリ在住ジャーナリスト。大学卒業後、ニューヨークに渡りファッションジャーナリスト、コーディネーターとして経験を積む。2016年からパリに拠点を移し、各都市のコレクション取材やデザイナーのインタビュー、ファッションやライフスタイルの取材、執筆を手掛ける





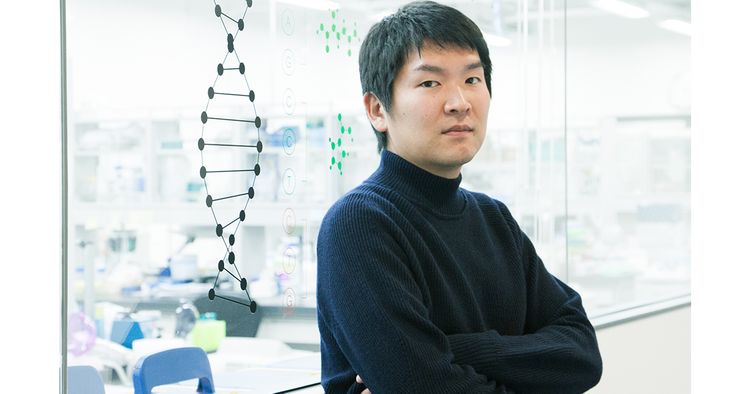

























 井上智和:1981年生まれ。東京生まれ東京育ちのCITY BOY。中央大学商学部を卒業後、三陽商会に入社し、店頭研修後に「バーバリー・ブラックレーベル」で販売トレーナー及びVMDを担当。3年目の終わりに「ラブレス」に異動しバイヤーに。国内外ブランドの開拓・買い付けをしながらセレクトショップの運営を学び、直近はバイヤーの他にプレス・販促・販売の長を兼務しながらリテール事業を経験。15年在籍の後に退社し、現在は「1H basix(ワンエイチ ベイシックス)」の名を冠して独立。ファッション・ライフスタイル領域のセレクトにて、アドバイジングやディレクション、買い付けを行なう傍ら、大人の本気遊びを体現し記事執筆を行う
井上智和:1981年生まれ。東京生まれ東京育ちのCITY BOY。中央大学商学部を卒業後、三陽商会に入社し、店頭研修後に「バーバリー・ブラックレーベル」で販売トレーナー及びVMDを担当。3年目の終わりに「ラブレス」に異動しバイヤーに。国内外ブランドの開拓・買い付けをしながらセレクトショップの運営を学び、直近はバイヤーの他にプレス・販促・販売の長を兼務しながらリテール事業を経験。15年在籍の後に退社し、現在は「1H basix(ワンエイチ ベイシックス)」の名を冠して独立。ファッション・ライフスタイル領域のセレクトにて、アドバイジングやディレクション、買い付けを行なう傍ら、大人の本気遊びを体現し記事執筆を行う




















 ホリデーコレクションのイメージ動画に起用された双子モデル・歌手のAMIAYAが「ホリデーカラーズ ミニリップブーケ」を唇に施した印象などを語った。「すごい色が綺麗ですよね。テクスチャーも軽くて長時間つけてても、つけているのを忘れるくらい。だけど色はちゃんとビビッドに出るのですごくよい!お気に入りはピンク(518)とレッド(591)。ピンクベージュ(590)っぽいのもいつもと違う大人の雰囲気になれそう」(AMI)。「5色それぞれの色の個性があって、全部使いやすそうな色ですね。色味も計算されて作られているのが分かるし、肌なじみも抜群。パーティーのときとか、朱赤(509)とかはすごい映えそう。洋服によって変えるのも楽しいかも」(AYA)。
ホリデーコレクションのイメージ動画に起用された双子モデル・歌手のAMIAYAが「ホリデーカラーズ ミニリップブーケ」を唇に施した印象などを語った。「すごい色が綺麗ですよね。テクスチャーも軽くて長時間つけてても、つけているのを忘れるくらい。だけど色はちゃんとビビッドに出るのですごくよい!お気に入りはピンク(518)とレッド(591)。ピンクベージュ(590)っぽいのもいつもと違う大人の雰囲気になれそう」(AMI)。「5色それぞれの色の個性があって、全部使いやすそうな色ですね。色味も計算されて作られているのが分かるし、肌なじみも抜群。パーティーのときとか、朱赤(509)とかはすごい映えそう。洋服によって変えるのも楽しいかも」(AYA)。