日頃大変お世話になり誠にありがとうございます。
下記の催事出展予定となります。
・1月4-6日 JR名古屋高島屋
・1月15-21日 鹿児島山形屋
・1月29-2月4日 東武宇都宮
・2月19-25日 富山大和
・3月4-10日 宮崎山形屋
・3月26-4月1日 横浜高島屋
・4月9-15日 新潟伊勢丹
・4月23-29日 新宿高島屋
・5月22-27日 吉祥寺東急

今後の催事・Pop Up等の催行につきましては
確定次第に随時掲載させて頂きます。
宜しくお願い申し上げます。
様々な分野にトレンドがあります。
日頃大変お世話になり誠にありがとうございます。
下記の催事出展予定となります。
・1月4-6日 JR名古屋高島屋
・1月15-21日 鹿児島山形屋
・1月29-2月4日 東武宇都宮
・2月19-25日 富山大和
・3月4-10日 宮崎山形屋
・3月26-4月1日 横浜高島屋
・4月9-15日 新潟伊勢丹
・4月23-29日 新宿高島屋
・5月22-27日 吉祥寺東急

今後の催事・Pop Up等の催行につきましては
確定次第に随時掲載させて頂きます。
宜しくお願い申し上げます。
2025年もテクノロジーの最前線を知る絶好の機会として、世界中のテクノロジー企業が一堂に会する「CES(Consumer Electronics Show)」がラスベガスで開催される。
毎年、次々と発表される革新的な製品やサービスが注目を集め、未来のテクノロジーを垣間見ることができる。CES 2025では、どんな画期的な技術や製品が登場するのだろうか。
本記事では、CES 2025で期待されるトップ10の技術とトレンドを紹介し、どのようなイノベーションが私たちの生活を変えるのかを予測する。
現場での発表や展示エリアが東京ドーム4個分と膨大すぎて何から見て良いかわからくなりがち。

CESはとにかく会場がデカすぎる!
開催時期: 2025年1月7-10日 (Media Dayは5, 6日)
開催場所: ラスベガスコンベンションセンター、Venetian Expo. Venetian, Aria, Mandaley Bay等
出店社数: 3,500以上 (見込)
来場者数: 13万人以上 (見込)
公式サイト: https://www.ces.tech/
イベント・展示エリア
CESでは、LVCCだけではなく、ストリップと呼ばれるラスベガスの中心エリアに複数のイベント・展示エリアを設置する。それらは大きく分けて3のエリアに分布し、それぞれのエリアの複数の建物の中で開催される。

CES 2025の開催場所のフロアマップ: 参照元 Floor Plan – CES 2025
これだけ膨大なエリアを回らなければならないので、時間がいくらあっても足りない。なので本題に入る前に時間を節約するためのコツ3つほど紹介する。
まずはどこに行ってどの展示やセッションを見るかを事前に決めておくのが良い。というのも、現地に到着してからだとあまりにもバタバタしすぎてて、それどころでは無いから。
ここで問題になるのが、同じ時間に複数のセッション・展示が同時に行われていおり、それも前後の予定の場所とかなり離れている可能性もあるということ。
一つずつのセッションをWebで確認して、カレンダーに入れていくのは気が遠くなるレベルの作業になる。
ここで便利なのが、公式アプリ CES App。こちらをダウンロードしてログインすれば、日時に合わせたスケジュールが表示され、”Add to Agenda” をタップしておくだけで、 事前に、そして自動的にスケジュールが生成される。

かなり便利なCES 公式アプリ
イベント会場に到着してまず最初の難関は入場バッジの引き換えプロセスだろう。事前にメールやアプリ経由で受け取ったQRコードを紙の入場バッジに変えるのだが、かなりの列になっていることが多い。
そこで便利になるのが、空港に設置された引換所だ。
飛行機を降りて荷物を受け取るエリアの駐車用に近い側、エスカレーター横に設置されており、フライトごとに到着時間が異なるので、大きな混雑になることが少ない。
また、開催日の前日や、結構夜遅くまで開いているので、かなり便利で時間の短縮につながる。

空港のバッジピックアップ所はあまり混んでいない
イベントの会場が複数の建物に点在しているため、建物間の移動だけでもかなりの時間を要する。また、タクシーやUberなどのライドシェアを捕まえようとも、なかなか時間がかかってしまう。
加えて、交通渋滞も予想されるので、予定していたセッションに間に合わないケースが多発する。
それを解決してくれるのが、通称 Teslaタクシーと呼ばれるVegas LOOPだ。これは3つあるLVCC間をトンネルを通じてつないだルートをスムーズに移動してくれる便利な乗り物。それも完全無料!事前予約も要らないし、待ち時間もほぼ無い、かなり画期的な移動手段である。

コンベンションセンター間の移動向けに次から次へとTesla車が提供される (無料)
では、CESの基本をカバーしたところで、本題の見どころをいくつか紹介する。
CESで、テクノロジーのさまざまな分野を議論する幅広いセッション複数ある。 ざっと考えても、デジタルヘルス、AI、サステナビリティ、ゲーム、自動車テクノロジー、サイバーセキュリティ、フィンテック、さらには宇宙テクノロジーなどが含まれる。
そんな中でも、今回特に注目したいセッションはこちら。
CES 2025の注目セッションの一部をご紹介:
人工知能(AI)は消費者向け電子機器にますます統合されており、CES 2025では個人アシスタントからゲーム用ハードウェアに至るまで、さまざまな分野でAIの可能性が示されるだろう。
注目すべきポイントは、効率性を高め、ユーザー体験を向上させるために特別に設計されたチップを搭載したAI搭載ノートパソコンである。
例えば、AIは使用パターンに基づいてバッテリー寿命を最適化したり、写真やビデオ編集をAI支援で改善することが考えられる。
具体例:
複合現実(MR)はCES 2025で大きな進展が期待されており、Microsoft、SONY、Metaなどの企業がリーダーとして登場する
次世代のヘッドセットが発表され、より快適で軽量なデザイン、解像度の向上、視野角の拡大、さらにAI技術を駆使したインタラクションが可能になる
また、ビジネスでのリモートコラボレーションやエンターテイメントで新しいMRアプリケーションが登場する
具体例:
CES 2025では、ウェアラブル技術の進化が大きな注目を集めるだろう。
新しいセンサーを搭載したフィットネストラッカーや、心臓問題やストレスレベルを予測して管理するAI搭載のスマートウォッチが登場するかもしれない。
ウェアラブルデバイスは、健康監視やフィットネストレーニング、ゲーム体験の領域にも広がりを見せ、さらに高度な機能を提供する可能性がある。
具体例:
コスメや美容のフィールドは長い間テクノロジーをあまり活用していないと思われていた。
しかしここ数年で、CESで発表・展示されるプロダクトの中にもいくつか興味深いビューティーテック系のものが増えてきている。
特に注目したいのは、CES 2023で昨年はコンピュータ化されたメイクアップアプリケーターと自宅用電子眉毛アプリケーターを発表したロレアルと、スマートミラーやメイクアップ支援ロボットなどを提供する韓国の複数のスタートアップ。
具体例:
CES 2025では、スマートホーム市場がさらに成熟し、便利さ、セキュリティ、エネルギー効率を高める製品が登場するだろう。
新しいスマートサーモスタットやAI駆動のセキュリティカメラ、キッチン家電が発表され、Google Assistant、Alexa、Apple HomeKitなどのスマートホームエコシステムとシームレスに統合されることが予想される。
スマートホーム技術は、日常的なタスクの自動化、持続可能性の向上、音声やジェスチャーコントロールを通じて、ユーザーのインタラクションを向上させることに焦点を当てるだろう。
具体例:
ヘルステクノロジーはCESで急成長している分野であり、2025年にはAIとデータ分析を統合した新しい個人向けヘルスケアデバイスが登場するだろう。
リアルタイムで健康状態を監視し、病気の早期兆候を察知できるウェアラブル健康モニターが発表されることが予想される。
AIを活用したヘルスケアアプリは、ユーザーに対して睡眠パターンやフィットネス、食事のアドバイスを提供する可能性がある。
具体例:
環境意識が高まる中、CES 2025はエコフレンドリーな技術の発表の場となるだろう。
太陽光発電の家電、エネルギー効率の高い家庭システム、電気自動車(EV)などの革新が注目されることが予想される。
企業はエネルギー消費の削減、廃棄物の最小化、カーボンフットプリントの低減を目指した製品を発表するだろう。
太陽光発電のスマートホームやカーボンニュートラルな技術ソリューションなどが登場する可能性がある。
具体例:
EV業界が進化を続ける中、CES 2025ではモビリティ技術の最新情報が発表されるだろう。
長距離走行、迅速な充電、先進的な自動運転機能を備えた新しいEVモデルが予想される。
また、新しいバッテリー技術がEVの性能と手頃な価格を向上させ、車内のインテリアも革新されるだろう。
AIを活用したナビゲーションシステムやカスタマイズ可能な車内エンターテインメントも注目されるだろう
具体例:
量子コンピュータはまだ初期段階にあるが、CES 2025ではこの分野の重要な進展が見られるだろう。
IBMやGoogleなどの企業が量子コンピュータハードウェアやソフトウェアの進歩を披露し、暗号学、機械学習、医薬品開発などの分野で実用化が進んでいく可能性がある。
量子コンピュータの性能向上により、企業や開発者向けの新しいサービスやデバイスが登場するかもしれない。
具体例:
ロボティクスはCES 2025の重要な注目分野であり、消費者向けおよび産業向けの革新が登場するだろう。
家庭内での日常的なタスクをサポートする自律型ロボット、例えば掃除ロボットやパーソナルアシスタント、食品配達ロボットなどが発表されることが予想される。
また、物流や製造業向けの自律型システムも進化し、複雑な環境をナビゲートして広範囲なタスクをこなすロボットが登場するだろう。
AIと機械学習は、ロボットの能力向上に欠かせない要素となる。
具体例:

CES 2024で発表されたHD Hyndaiの自動運転重機
CES 2025は、これからのテクノロジーがどのように進化し、私たちの生活にどんな影響を与えるのかを示す重要なイベントである。
AI、MR(複合現実)、ウェアラブルデバイス、そして持続可能な技術など、今後数年間にわたり私たちが体験するであろう技術革新の数々が一堂に会することは、まさに未来を先取りする瞬間と言えるだろう。これらの技術がどのように現実のものとなり、私たちの日常生活にどのように組み込まれていくのかを楽しみにしながら、CES 2025を注目していきたい。

徳島県南部の豊かな自然環境・文化・歴史・伝統産業等の観光資源を活かしたアドベンチャーツーリズムによる観光振興の可能性について、特別講座を実施します。
とくしま観光アカデミーにお申込みの方も、別途お申込みが必要です。特別講座のみのお申込みも可能です。
令和6年11月25日(月)13:30~15:00
徳島県南部総合県民局美波庁舎 2階大会議室(美波町奥河内字弁才天17-1)
演題:徳島県南部のアドベンチャーツーリズムの可能性について
講師:一般社団法人 日本アドベンチャーツーリズム協議会 理事 山下真輝 氏
50名程度
無料(事前申込必要)
徳島県電子申請サービス(登録不要)または、「受講申込書」をFAX・Eメール等でお送りください。
令和6年11月20日(水)
徳島県南部総合県民局<美波>地域創生防災部 地域創生担当
【電話】0884-74-7354 【FAX】0884-74-7337
【E-mail】nanbu_c_m@pref.tokushima.lg.jp
2024年10月12, 13日に開催された「Designship 2024」。
このイベントは東京で毎年開催され、約5,000人ほどの数々のクリエイターたちがデザインの最前線を探る場となっています。今年のコンセプトは「広がりすぎたデザインを、接続する」でした。

グラフィックデザイン、モーションデザイン、サービスデザインなどデザインの幅が広がっている(Designship 公式ページより参照)
Designship 2024には、ビートラックスからはCEO ブランドンが登壇したのに加え、デザイナー3名もDesignshipに参加しました。このイベントは弊社にとっても、テクノロジーやビジネス、アートまで多岐にわたる分野でのデザインの役割と影響力を再考する素晴らしい機会となりました。
参加したビートラックスのデザイナーは以下の3名です。
そこで今回は、以上の3名がイベントに参加して感じたそれぞれの「① 現地で1番興味深かったセッション」「② Designship 2024全体を通して得た学び」「③今後の意気込み」についてご紹介します。
Mari:
引地さんの「人間中心から生命中心の未来へ」というテーマのトークセッションが特に印象的でした。大阪万博のデザインシステムがどのように作られたのかに興味があったので、非常に興味深く感じました。「いのちの循環」という広く抽象的な万博のテーマを具体的なビジュアルに落とし込むプロセスと考え方が面白かったです。
「いのちの循環」をもう少し具体的に説明する言葉として引地さんは「全てのいのちが融け合い、響き合う 共に進化する生態系へ」としていましたが、それを具現化したビジュアルに落とし込んでいました。

引地 耕太さん、テーマ『人間中心から、生命中心の未来へ〜大阪・関西万博デザインシステムを通じて〜』
個々のいのちがそれぞれLive, Growth, Evolutionと変化をとげ、またその個が他の個を交わって生態系ができていくことをJoin, Sync, Actという言葉で表現し、それらのビジュアルを融合させたものが現在のキービジュアルです。
引地さんのトークは聞きやすく、プレゼンスライドの見せ方も綺麗で、赤と青の目玉がついたビジュアルがどういう意図で作られたのかを図解してくれたことで、セッションを聞く前と後ではキービジュアルの見え方が変わり、納得感が増しました。

引地 耕太さんの登壇風景
Suzy:
引地さんによる万博のデザインシステムについてのセッションが個人的にはとても印象的でした。デザインプロセスの全体像、どのような意図でシステムやデザイン要素が生み出され、それらがどの様に様々なアセットに展開・適用されているのか、その過程を詳細に知ることができたのがとても面白かったです。
デザインプロセス自体も興味深く聴いていたのですが、それ以上に、その工程が第三者の私にも理解しやすい、引地さんのプレゼンテーションの仕方が大変勉強になりました。
特に最近はブランディングやマーケティング戦略の提案などの上流工程のお仕事に関わらせていただくことが多いので、頭にスッと入ってくる話し方とピッチ構成、スピード感、スライドの作り方などの重要性を改めて感じました。
このセッションを通して得た気づきや学びは、今後のプロジェクトに早速応用していければと思っています。

菅野 薫さんの登壇風景
Hiro:
菅野さんの仕事や考え方に関するセッションが印象的でした。森ビルやサントリー、リオの閉会式など心踊るような広告やブランディングを手がける方が何を考えているのかを知りたいと思い参加しました。エンジニア出身と聞いて驚きましたが、『新しいアイデアとは何かに』ついての考え方が非常に参考になりました。
以前、井口尊仁さんの「アイデアは実装されて初めて価値を持つ」という発言を聞きましたが、菅野さんはまさにそれを体現している方だと感じました。特に電話に関する話が興味深かったです。電話というアイデアは歴史的に古くから存在し、実装した人も多くいました。
最終的にAT&Tの創業につながった技術者が特許を取得しましたが、他のエンジニアたちも同じ時期に特許を目指していたそうです。この事例は、アイデアが単なるアイデアのままだと価値がなく、実装されて初めて価値を持つことを示していると強く感じました。
エンジニアのバックグラウンドがあることから、映像やブランディングのクリエイティブも技術ベースでありつつ、伝えたいメッセージは非常にわかりやすかったです。また、やった仕事のサマリー動画を持つことは自分でもぜひやりたいと思いました。
Mari:
「デザインとは?」を考えさせられるイベントでした。Designshipはデザイン系のイベントの中でも特に広義にデザインを捉えており、様々なジャンルのデザイナーが集まっていました。btraxでの仕事ではプロジェクトによって異なる領域のデザインをしているため、自分は何のデザイナーなのかと考えることが多く、コアを見つけて強化できると良いと感じたイベントでした。

Goodpatchの本棚の前でbtrax CEO Brandon(左)とGoodpatch CEO 土屋さん(右)のツーショット
Goodpatchの大きめの本棚を設置したブースが印象的で、多くのブースがある中で目を惹く存在でした。最近、展示系のプロジェクトも増えているので参考になりました。
Suzy:
Brandonさんと引地さんのメインステージのセッションの他にも、ブランディングデザインや共創デザインアプローチのパネルセッションにも参加しましたが、Designshipのテーマでもある「デザインの定義が広がっている」ことを強く感じました。
デザインがメインストリーム化していることは嬉しい一方で、どこまでをデザインとし、デザイナーの仕事とするかが曖昧になっている現状で、自分のデザイナーとしてのスキルセットを見直す良い機会になりました。

ビートラックス(btrax) CEO ブランドンも登壇しました
Hiro:
広がり続けるデザインの領域を実感するイベントでした。だからこそ、「デザインでどんな目標を達成したいのか?」を冷静に考える力を養うことがデザイナーには必要だと感じました。また、デザインシップ自体の参加者の年齢層が若く、学生と企業のデザイナーが気軽に交流できる場は素晴らしいと思いました。
Mari:
トークセッションを通じて改めて感じたのは、自信あるトーク力が聴き手への説得力を増すということです。デザイナーとして良いものを作るだけでなく、それを伝える力は非常に重要だと感じました。今後の仕事に役立てたいと思います。
Suzy:
私は「手を動かすデザイン」より「どう良いデザインを効率よくデリバーするか」の部分に興味があり、PMや上流過程の管理が得意です。共創デザインアプローチやデザインシステムの設計と展開についてのセッション内容は非常に参考になりました。プレゼンテーション能力も今の私の課題なので、これからしっかり伸ばしていきたいと思います。
Hiro:
広がるデザインの領域の中で、自分の考え方の軸となる専門性が大切だと感じました。常にデザインの目的や狙いを考え続ける姿勢を持ち続けたいと思います。

Designship 2024に参加し、体験記を寄せてくれたbtraxデザインメンバー3名(左からSuzy, Mari, Hiro)
Designship 2024は、btraxメンバーに多くの気づきと学びをもたらしてくれました。デザインの定義が広がる中で、それぞれが自分の位置づけを見直し、次のステップへの準備を整える場所となりました。このイベントを通じて得た知識や共感を今後の仕事に活かしていきたいと思います。
ぜひ読者の皆さまもデザインの可能性を再考し、新しい挑戦に向けて期待を膨らませていただければと思います。

徳島県は2025年の「大阪・関西万博」の開催など、国内外から誘客を図る絶好の機会を迎えます。
一方では、ニューノーマルな「旅行スタイル」や「観光トレンド」への対応などアフターコロナの「新たな観光」を作り上げていく必要もあり、こうした観光産業を取り巻く「変化」に柔軟に対応できる人材の育成を行うため、開講するものです。
令和6年11月12日(火)~令和7年1月25日(土) ※週1~2回開催
オンライン(ZOOM利用)
※インターネット接続環境とPC・タブレット・スマホ等の媒体が必要です。
※共通講座は徳島大学の教室での受講も可能です。
※演習講座は現地開催です。
講義は共通講座+専門講座(ビジネスコース・チャレンジコース)+演習講座となります。
講義内容について詳しくは下記をご覧ください。

お申し込みは「申込フォーム」もしくは、「受講申込書」をFAX・Eメールでお送りください。
令和6年9月24日(火)~ 11月5日(火)
一般財団法人徳島県観光協会「とくしま観光アカデミー係」
【電話】088-624-5140(平日8:30~17:15)【FAX】088-625-8469
【E-mail】tokushimakankouacademy@gmail.com

阿佐海岸鉄道では、DMV 運行開始2周年企画としてDMV 沿線に関するクイズラリーを開催します。
DMV沿線施設に設置されたパンフレットの7つのクイズに挑戦しよう!
応募用紙にクイズの答えを書き込み応募箱にいれると、全問正解の方から抽選で素敵な賞品が当たるチャンス!
また、1問でも回答すると先着500名様に「仕事猫」コラボステッカーがもらえます!!
是非DMVの乗車と共にイベントをお楽しみください。

2024年1月10日(水)~2月29日(木)
クイズラリー参加施設にあるパンフレット裏面のクイズに答えて、応募箱に回答用紙を投函しよう。
イベント期間終了後、全問正解の方から抽選で豪華商品をプレゼント。
※当選者の発表は商品の発送を持ってかえさせていただきます。
応募箱設置施設にてクイズの回答を1問以上記入している応募用紙を投函前にみせると、ステッカーがもらえます。
応募用紙に受取済みのスタンプを押してもらい、ステッカーをお受け取りください。
※数に限りのある特典となりますので、みなさまにお楽しみいただけるよう、おひとり様1枚までの交換とさせていただきます。
※クイズ応募箱・ステッカー配布施設は10ヶ所、ステッカーは各施設で先着50枚です。
※施設によってはステッカーの在庫が早めに無くなる恐れがありますのでご了承ください。
阿波海南文化村(三幸館)、阿波海南駅(かいふ菓子ロマン きもとや)、海部駅(宝来堂ピア海部店)、宍喰駅(宍喰駅改札口)、甲浦駅(駅待合所内 売店)、海の駅東洋町(海の駅東洋町内 事務所)、道の駅宍喰温泉(海陽町観光協会)、ホテルリビエラししくい

阿波海南文化村、阿波海南駅交流館、海部駅待合所、応募箱・ステッカー配布場所の各施設10ヶ所
阿佐海岸鉄道クイズラリー事務局
TEL:0884-76-3701(平日9:00~17:00)
HP:阿波海岸鉄道ホームページ

徳島県では「とくしま観光アカデミー」の特別講座として、長崎県波佐見町のクラフトツーリズムなどを手がけるイデアパートナーズ(株)井手 修身 氏と、鳴門市大麻町の大谷焼窯元 大西陶器の大西 義治 氏を講師に迎えて開催いたします。
どなたでも無料でご参加いただけますので、ご興味のある方はぜひお申し込みください。
・持続可能な地域マーケティング
・波佐見町(長崎県)のクラフトツーリズムの取組
・鳴門市大谷地区の観光まちづくりを考察する。
イデアパートナーズ株式会社 代表取締役 井手 修身 氏
大谷焼窯元 大西陶器 大西 義浩 氏
令和6年2月6日(火) 14:00~16:00
鳴門市堀江公民館(鳴門市大麻町大谷字椢原18)
お申し込みは「申込フォーム」もしくは、「受講申込書」をFAX・Eメールでお送りください。
令和6年1月26日(金)まで
とくしま観光アカデミー特別講座 受講申込書[PDFファイル]
一般財団法人徳島県観光協会「とくしま観光アカデミー係」
【電話】088-624-5140(平日8:30~17:15)【FAX】088-625-8469
【E-mail】tokushimakankouacademy@gmail.com
2023年12月6日、東京・渋谷にて開催された「Btrax Design Day」は、デザイン業界における次世代のトレンドと革新を探求する一大イベントであった。
中でも特に注目されたセッションの一つが、「マイノリティ視点がイノベーションを起こす:インクルーシブデザインの力」だ。このセッションでは、Audio Metaverse, Inc.の創業者である井口尊仁氏と、株式会社圓窓の代表取締役、澤円氏が、「インクルーシブデザイン」の概念を深く掘り下げた。
井口氏は、自身の豊富な起業経験を基に、マイノリティ視点がイノベーションに不可欠であることを強調した。井口氏の見解では、現代のビジネスにおいては、中庸的な課題に対する解決策はすでに提供されており、新たなイノベーションは特異なニーズを持つマイノリティから生まれる可能性が高いとのこと。
井口氏:「課題っていうのは今見つける時代じゃなくて開発する時代で、発明する時代なのです。これが何を意味しているのかというと、私たちが普段問題視をするような真ん中ら辺にある程よいサイズの課題はおおよそ既に解決済みであるという見方もできます」
新たな価値創造には俯瞰した、そして、マイノリティの視点が不可欠であるのだ。

また、澤円氏も、マイノリティの視点が新たな価値を生むことを強調。「ダイバーシティ&インクルージョン」というテーマにおいて、多様なバックグラウンドを持つ人々を巻き込むことが、革新的な製品やサービスの開発に不可欠であると指摘した。
また、澤氏は、マイノリティからの視点を製品設計の初期段階から取り入れることで、従来の思考の枠組みを打破し、新しい市場を開拓することが可能であると説いた。セッションの中で澤氏は特にアクセシビリティを重視した製品設計の重要性を説明した。
澤氏: 「身体的、知的障害を持つ人々に対する配慮は、製品のユーザビリティを向上させ、より広い顧客層に訴求することにつながるのです」
さらに、澤氏は、文化的背景や経済的地位の多様性を考慮したデザインの重要性について言及。
澤氏: 「グローバル化が進む市場において、異なる文化的背景を持つユーザーへの配慮は、より幅広い層へのアピールにつながります」
マイノリティの視点をビジネスとデザインの中心に据えることが、新たな価値創造の源泉となりうるようだ。

井口氏は、自身が開発、リリースの中心となったプロジェクト、「Dabel」を通じて、インクルーシブデザインの具体的な応用例を提供した。このプロジェクトは、音声アプリケーションを活用して、目の不自由な人々に新たな体験を提供した。
井口氏:「このプロジェクトを通して、目の不自由な方たちが、音声アプリケーションを使って世界を変える体験を提供出来たのではないでしょうか」
このプロジェクトは、テクノロジーを用いて、視覚障害者に新しい情報アクセスの方法を提供し、彼らの日常生活に革新をもたらした重要な例となりうるだろう。
一方、澤氏は、インクルーシブデザインが組織やビジネスに新たな価値をもたらす方法について、自身の経験を基に語った。澤氏は、「全ての人の生活を快適にしようというスピリットが重要」と述べ、多様性を重視することの必要性を強調した。
澤氏がセッション中に紹介したIKEAによる「ThisAbles」プロジェクトは、「汎用性」(全ての人の生活を快適にしようというスピリット)が製品に反映された好例である。
多様なニーズに対応するためには、デザイン思考の枠組を超え、異なる文化的、社会的背景を持つユーザーの視点を積極的に取り入れる必要があるようだ。澤氏による解説は、このアプローチが新たな市場の機会を生み出し、ビジネスの成長を促進することを示唆している。

このセッションを通して、デザインが単に形や機能を決めるだけでなく、社会全体に影響を与える重要な役割を果たしていることが浮き彫りにされた。特に、インクルーシブデザインがビジネス成長や新市場の開拓に直接結びつく可能性が示された。
参加者にとって、このセッションは、デザイン思考の新たな局面を見る機会となり、多様性と革新性の結びつきに関する深い洞察を提供した。このセッションは、デザインの可能性を再考し、新たな視点でアプローチするための触媒となったことは間違いない。

徳島県は2025年の「大阪・関西万博」の開催など、国内外から誘客を図る絶好の機会を迎えます。
一方では、ニューノーマルな「旅行スタイル」や「観光トレンド」への対応などアフターコロナの「新たな観光」を作り上げていく必要もあり、こうした観光産業を取り巻く「変化」に柔軟に対応できる人材の育成を行うため、開講するものです。
令和5年11月14日(火)~令和6年2月6日(火) ※週1~2回開催
オンライン(ZOOM利用)
※インターネット接続環境とPC・タブレット・スマホ等の媒体が必要です。
※演習講座は現地開催です。
講義は共通講座+専門講座(ビジネスコース・チャレンジコース・地域で活躍コース)+演習講座となります。
各コースの講義内容は下記をご覧ください。



お申し込みは「申込フォーム」もしくは、「受講申込書」をFAX・Eメールでお送りください。
令和5年9月26日(火)~ 11月7日(火)
一般財団法人徳島県観光協会「とくしま観光アカデミー係」
【電話】088-624-5140(平日8:30~17:15)【FAX】088-625-8469
【E-mail】tokushimakankouacademy@gmail.com

令和 5 年 8 月7日(月)に開催を予定しておりました鳴門市納涼花火大会は、台風6号の影響により 8 月17日(木)に順延いたします。
※開催時間・開催場所に変更はございません。有料観覧席のチケットは順延日において、そのまま有効となりますので大切に保管してください。
※17日についても荒天により開催が困難な場合は、18日に順延し、18日も開催が困難な場合は中止といたします。
県下最大級7000発の花火が夜空を彩る鳴門の花火。今年はBOAT RACE鳴門開設70周年記念開催。
開催日時 令和 5 年 8 月17日(木)19:45~20:50
打上場所 鳴門市撫養川沿い親水公園
観覧場所 徳島県合同庁舎前市道(立岩区画1号線)
有料観覧席では場所取りの心配なく最高の場所からご覧いただけます。
※ご好評につき有料観覧席は完売いたしました。(7/13追記)
販売開始 2023年7月1日(土)10:00
席数 1,350席 (全席自由)
料金 小学生以上1,000円、3歳以上~小学生未満500円、2歳以下無料
販売窓口 鳴門市うずしお観光協会 TEL:088-684-1731 FAX:088-684-1732 E-mail:info@naruto-kankou.jp
【注意事項】
荒天の場合は8月17日(木)・18日(金)に順延となります。
入場は18時からとなります。観覧席内での必要以上の場所取りはご遠慮ください。
ペットの同伴は禁止します。
観覧席内は禁煙です。ゴミは各自お持ち帰りください。
専用出入口から再入場可能ですが、必ずチケットをご掲示ください。
観覧席券は払い戻しや再発行はいたしません。
【交通規制・臨時駐車場】
周辺交通規制時間 18:30~22:00
臨時駐車場 BOAT RACE鳴門駐車場17:00より開放(駐車1台につき500円)
臨時シャトルバス BOAT RACE鳴門 ⇔ 鳴門郵便局を運行
※駐車場には限りがあります。公共交通機関等をご利用いただき渋滞緩和にご協力ください。
立入禁止区域 文化会館周辺は立入禁止区域となります。
【JR鳴門線運転ダイヤ】
花火大会に合わせて臨時列車も増便されます。
徳島駅発→鳴門駅着
15:00→15:40/16:20→16:56/17:00→17:41/18:03→18:46/19:03→19:49
鳴門駅発→徳島駅着
20:10→20:50/21:10→21:49/21:30→22:17/22:14→23:00
令和 5年8月9日(水)10:00から開催予定の「初おどり」や同日19:00開催予定の「鳴門市阿波おどり」においても、台風の進路状況や被害状況等により、中止する可能性があります。
今後の気象状況を注視しながら、中止等となる場合は追って追記いたします。
 県下トップを切って盛大に繰り広げられる【鳴門市阿波おどり】
県下トップを切って盛大に繰り広げられる【鳴門市阿波おどり】
長さ約80mの桟敷で大迫力の阿波おどりを体感できる「BOAT RACE 鳴門 東演舞場」での百花繚乱の演舞は必見です。
初日9日は鳴門市阿波おどりPR大使 石田靖さんと徳島県応援芸人の中山女子短期大学さんも参加。
最終日11日は21:30より「鳴門市阿波踊振興協会」所属連総出演によるフィナーレが開催されます。
開催日時 令和 5 年 8 月 9日(水)~11日(金・祝)19:00~22:00
開催場所 JR鳴門駅周辺特設演舞場
前売チケット 7月1日(土)10:00より販売開始
料金 小学生以上700円(当日1000円)
販売場所 鳴門市うずしお観光協会・ローソン・セブン-イレブン・ミニストップ・チケットぴあwebサイト
誰もが参加できる「にわか連」も連日実施されます。参加希望者は東演舞場「踊り連入場口」付近に集合。服装はそのままでOKです。
※20時スタート予定。練習を行うので15分前にお集まりください。

【各チケット販売に関するお問合せ】
鳴門市うずしお観光協会 TEL:088-684-1731
【阿波おどり・花火に関するお問合せ】
鳴門市観光振興課 TEL:088-684-1157
鳴門市商工会議所 TEL:088-685-3748
鳴門市納涼花火大会・鳴門市阿波おどり公式サイト

11月3日(金・祝)・4日(土)の2日間、入場無料で阿波おどりを楽しむことができます。
有名連による豪華共演や、学生連の演舞、海外連も参加予定の世界阿波おどりコンテストと盛り沢山の内容です♪
阿波おどりだけでなく、豪華ゲストにより「音楽ステージ」や「お笑いステージ」も予定しております!
また、会場には徳島グルメを楽しめる「キッチンカーマルシェ」や藍染などを体験できる「体験コーナー」など
徳島の魅力がたくさん詰まったお祭りです♪
今後、詳細が決まり次第お知らせしますので、お楽しみに!!

有名連による迫力のある演舞「阿波おどり大絵巻」

総勢100名を超える優雅な演舞「阿波おどり大絵巻」

第6回全国阿波おどりコンテスト表彰式
2023年11月3日(金・祝)・4日(土)10:00~16:00
徳島市山城町東浜傍示1-1 アスティとくしま
アスティとくしま Tel:088-624-5111

本場・徳島の阿波おどり、開催決定!!おなじ阿呆なら今夏も、踊らなそんそん♪
日時 令和 5 年 8 月 11 日(金・祝) 12:00、15:30、19:00 の 3 回公演
場所 アスティとくしま(徳島市山城町東浜傍示1-1)
出演者及び内容 阿波おどり振興協会及び徳島県阿波踊り協会による協会ごとの合同演舞
日時 令和 5 年 8 月 12 日(土)~15 日(火) 11:00、13:30、16:00 の 3 回公演
場所 あわぎんホール(徳島市藍場町2-14)
出演者及び内容 阿波おどり振興協会及び徳島県阿波踊り協会の選抜連による連ごとの演舞
開幕式 日時 令和 5 年 8 月 12 日(土) 17:30~ 場所 藍場浜演舞場
開催時間 令和 5 年8 月 12 日(土)~15 日(火) 二部入替制
【1 部】18:00~19:40 【2 部】20:20~22:00
場所 藍場浜演舞場、南内町演舞場
開催時間 令和 5 年8 月 12 日(土)~15 日(火) 18:00~22:00
場所 両国本町演舞場、新町橋演舞場
 新町橋東おどり広場及び両国橋南おどり広場
新町橋東おどり広場及び両国橋南おどり広場
開催時間 令和 5 年8 月 12 日(土)~15 日(火) 18:00~22:00
 アミコドーム
アミコドーム
開催時間 令和 5 年8 月 12 日(土)~15 日(火) 14:00~22:00
 シビックセンターさくらホール
シビックセンターさくらホール
開催時間 令和 5 年8 月 12 日(土)~15 日(火) 13:00~17:00

2023阿波おどりポスターのコンセプトは踊る『阿呆』と観る『阿呆』。
世界中の皆が恋をするように待ち焦がれ、たくさんの愛が溢れる4日間。
『阿波おどり』を世界中の人たちに知っていただきたい、ということを表現したポスターです。
ポスターの踊り手は「扇連」の円道聖奈さんです。
TEL:088-678-5181/088-678-5182
https://www.awaodorimirai.com/
今年も世界最大のテクノロジーカンファレンス、CESがラスベガスで開催された。
かなり遅いタイミングとなってしまったが、現地に参加したレポートをお届けする。
主要メディアを中心に多くの方々がかなり包括的な記事を書かれているので、僕自身は自分が感じたバイアス満載のぶっちゃけな「裏CES」という文脈でこの記事をお届けする。
そう。多くのメディアはどれだけ「凄い」テクノロジーやプロダクトが発表されたかに焦点を絞り、やや “盛った” 感じのレポートに終始している。
そうするのがメディアの役割であるためだからだが、場合によっては参加したレポーターの正直な感想が書きにくくなっているのではないだろうか。
実際に参加したメディア系の方々に聞いても「ぶっちゃけはこうなんだけど、建前上はこのように書いておかないと…。」という意見も実際にあった。
今回、この記事では、実際に参加して感じた、あくまで率直で個人的な感想をお伝えする。

今年のCESもメディア枠でMedia Dayから参加
今年の最終来場者数は11万人ちょっとで、去年の1.5倍から2倍ぐらいの規模らしい。
とはいうものの、コロナ前の状況から比べるとこれでも少し少ない印象を受けた。
実際に2019年まで利用されていたラスベガスコンベンションセンターのSouthとWestgateホテルは利用されておらず、フルスケール開催は来年かなー、という感じだ。
勿論、とはいえそれでもかなりの規模のイベントであることは間違いない。

コロナ明けを感じさせる大盛況のCES 2023
今回も一般展示が始まる2日前より始まるメディアセッションから参加させていただいた。
これらのセッションでは、プレスカンファレンスを通じて複数の企業がそのビジョンや新規プロダクトの「初お披露目」を行う。
セッションの直前キャンセルが相次いだ去年と比べて、今年は多くの企業がしっかりとメディア発表を行った。
参加したのは、Bosh, LG, Samsung, Panasonic, Canon, Hisense, TCL, Valeo, HD Hyundai, Omron Healthcare, SONY, AMD, BMW, そしてCES主催者がプレゼンする2023 Trends to Watch。
上記のセッションに共通しているのが 「サステイナブルへの取り組み」だ。
自然豊かな緑や地球の映像を投影しながら、我々はどれだけ環境に良いことをしているのかの説明が相次いだ。本当にそればかりで、後半は感覚が麻痺してくるレベル。
特にイベント主催者のCTAによるサステナ押しはすごかった。
というか、そもそも環境保護が重要なのであれば、ラスベガスで大量のエネルギーを消費し、世界中から飛行機に乗って10万人以上の来場者を集めるCESというイベントを開催すること自体がかなり非環境的な気もするが…。
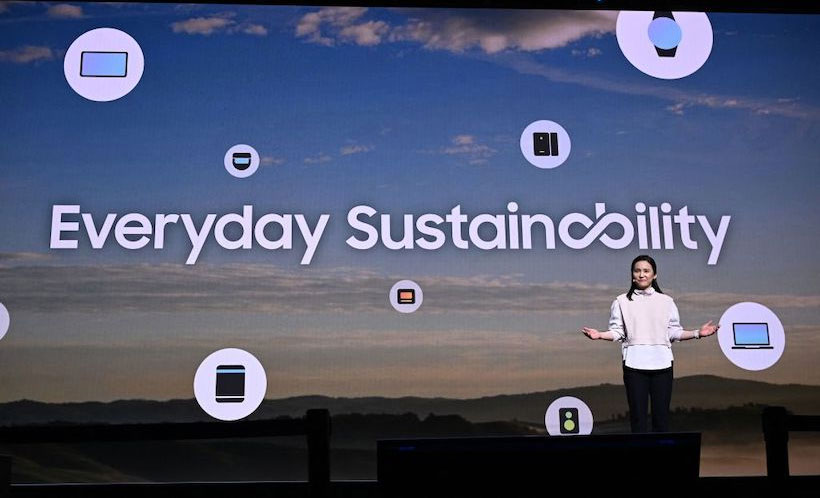
多くの企業が謳うサステイナブルへの取り組み
では、具体的にサステナは何に対しての姿勢なのか?SDGsと同じく、あまりにぼんやり&ざっくりとしたコンセプトな上に、皆が語っているので、いまいちピンとこない。
でも今回はSamsung社がそれをわかりやすく説明してくれた。
サステナブル = 優しさであり、その対象は3つ。人、社会、環境である。
なるほど、会社の存在目的とビジョンをプロダクトを通じて表現していく。その対象は人であり、社会であり、環境であると。

サステイナブルの軸は「人、社会、環境」
展示ブースを周っていてひときわ多かったのが、デジタルツインをコンセプトにしたもの。
自動車の車体や都市だけではなく、人間の体や脳の中身まで、あらゆるもののデジタルコピーを作成し、クラウド上に保管する。そして、その状況や内容を逐一管理できるという仕組みだ。
実際、どのような役割を果たすかはまだまだ未知数であるが、これからはリアルに存在すると同時にデジタル空間でも同じような存在が保持されていく時代になるかもしれない。

自身のヴァーチャルコピーが作成可能なDassault Systèmesの技術
数年前より注目されているメタバースであるが、CES 2023ではもう新しいコンセプトのMoT (Metaverse of Things) が発表されていた。
これは、メタバースをより身近にするために、専用のVRゴーグル等のデバイスがなくても、家庭やオフィス、車の中でメタバースを体験できる仕組み。
一瞬何のこっちゃと思ったが、おそらく言いたかったのは、まだまだメタバースどっぷりの生活にはならないが、日々の中でメタバース的な体験に触れる瞬間は増えてくるよ、ということだろう。しかし、だからと言って完全に腑に落ちたかと言われると、まだやはり「何のこっちゃ感」は残った。

イベント主催会社のCTAによるMoTの説明
今回のCESのキーノートでは、CTAによる世界のイノベーション先進国の発表が行われた。そのなもグローバルイノベーションチャンピオン。
さて日本は何位だっただろう?
正解は、25位。ランキングに入ったのは良いが、微妙な位置だ。経済規模や技術力を考えると少し低いのではと感じた。
日本が採点で特に低かったのは実に「ダイバーシティー」の項目だったそう。
AからEのグレードの中でなんと 「Dマイナス」の評価で、 これはかなり低い。
男女の格差や多様性に関しての課題が大きかったとのことだ。

イノベーションチャンピオンの受賞国: 日本は25位
プレスカンファレンスや展示場を周って、気づいたことがある。
それは、「どの企業も近い領域で勝負している」ということ。言葉を変えると、カバーしている領域がどんどん被ってきている。
例えば、もともと家電をやっていたメーカーは自動車やヘルスケアの領域まで進出していたり、自動車ブランドが家電領域でサービスを提供し始めたり、といったものだ。
最もそれを象徴的に表現してたのがSONYのプレスカンファレンスにて発表された 、SONY Honda Mobility の自動車ブランドAFEELAだろう。
家電のSONYと自動車のHONDAがタッグを組んで作り出したハイブリッドモビリティーな感じのブランドである。

SONYとHONDAが始めるモビリティーブランドのAFEELA
そんな感じで、みんな同じ領域に進出してる中で何が差別化要因になってくるのか?
その一つが「コンテンツ」だろうと思う。
例えばFacebookは社運をかけてメタバース事業に乗り出し、社名もMetaに変更した。
しかし苦戦している。これは恐らく彼らがもともとコンテンツをほとんど持っていなかったからだろう。
デバイスやシステムがあっても、そこにキラーコンテンツが存在しなければ、ユーザーに利用する価値をあまり感じてもらえない。
その一方で、例えばSONYのような会社は、新しいデバイスをリリースしても、ゲームや映画といったコンテンツがあるので、一気に人気を集めやすい。
もしかしたら車の中でコンテンツをガンガン提供すれば上記のAFEELAも人気ブランドになっていくかもしれない。(運転していない時にグランツーリスモ用のレーシングシュミレーターとして利用できるとか…。)
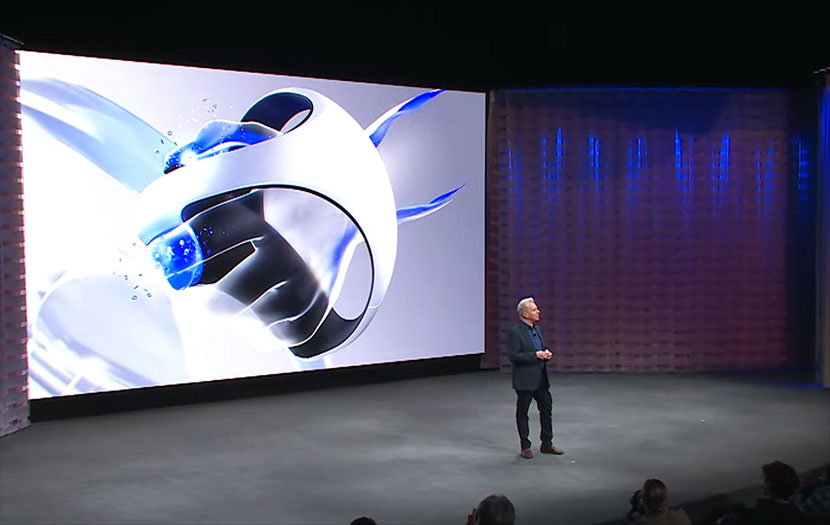
豊富なコンテンツが武器になるSONYのPlaystation VR2
そしてもう一つの差別化要因はブランド力。
これだけ多くのテクノロジーが発達し、デバイスやパーツがコモディティー化していく中では、多くの企業が類似したプロダクトをリリースしていくことは避けられない。
例えばSamsungなんかは、日常家電からキッチン周り、ベッドルーム、バスルーム、ワークスペース、ベビーケア、シニアケア、ヘルスケア、スマート家電、モビリティーまで、本当に全部乗せである。
では消費者はどのような基準で興味を持ち、購入を検討するのだろうか?それは恐らくブランド力に違いない。
「何を作っているのか」よりも、「誰がなぜ作っているのか」が重要な差別化要素になってくると思われる。

ボストンダイナミクスのロボットとそっくりな製品を1/10以下のコストで製造した中国の企業 (名称は忘れてしまった)
去年まではあまり目立たなかったが、今年複数見られたのが「水」を作り出すデバイス。
これもやはりサステナビリティ文脈からくる環境保護への取り組みの一つだと思われる。
それらは空気中の水分を集め、飲料水を生み出す仕組み。軽く見ただけでもフランス、アメリカ、韓国の企業が同じようなデバイスを製造・販売している。

複数の会社から空気から水を作り出すデバイスが展示されていた
数年前まではCESといえば中国企業満載のイベントだった。
しかし3年ほど前の華為をきっかけにアメリカと中国の関係性が微妙になっていくにつれ、一気に中国企業の展示数も減った。
それに代わって激増したのが韓国企業。
もちろん以前よりSamsung, LG, Hyundaiのような大企業は展示していたが、それ以外のスタートアップや中堅企業、そしてそれぞれの地域や産業を代表する団体まで、至る所で韓国企業発の展示が見られた。
これには米国市場に対して、国としての強い覚悟と勢いを感じた。

相変わらず凄い勢いの韓国勢
それに対して、日本企業で展示しているところは多くなかった。
もちろん、SONY, Panasonic, Canon, Nikon, Suntory, Omron Healthcare, ENEOSなどはあったが、その他のテクノロジー会社や自動車メーカーの展示がかなり少なかった。
その一方で、日本から来場客としてきてる方はかなり多く、至る所で日本語が聞こえてきた。
視察を通じて学んだりインプットするのも良いが、ビジネスは展示して、発表して、世の中に知られてもらう動きも重要で、外に出してなんぼじゃないかな、と思う。

そんな中で素晴らしい展示をしていた Japan Pavilion (写真はNEW PEOPLEの吉田さんより拝借)
これまでのCESでド派手な展示とキーノートを開催していたとある企業が今年は見当たらない。Intelである。
彼らは2018、2019年連続でラスベガスの空にドローンを飛ばしたり、巨大なアリーナでAIを使った楽器の演奏を披露したりなど、半導体メーカーからテクノロジー会社としての変革を表現していた。
それが今年はどこにもIntel入ってない!見当たらない。
詳しい事情は知らないが、シリコンバレーを代表する会社の一つがいないのは少し寂しくも感じた。

CES 2018でド派手なドローンイルミネーションを見せたIntelが今年はいない
さてこんな感じで裏CESをお届けしたが、そもそもCESってどんなイベントなのか?
現在では世界最大のテクノロジーイベントであるが、もともとは家電市だった…はず。
確かに10年ほど前まではマニアックなハードウェア系プロダクトの展示が多かったのを覚えている。
そして数年前ごろからIoTや5G, ドローンなどのコアテクノロジーに関するコンセプト展示が増えてきた。
そして今年はそれらを全て統合し、ユーザーにもわかりやすいサービスとして提供し始めた企業がどんどん増えてきた印象を受けた。
その一方で、冒頭でも触れた通り、イベント自体が環境的には全くサステイナブルではないため、今後の存在意義が問われてくる気もする。
どちらにせよめっちゃ楽しいイベントであることは間違いないので、実際に会場に足を運んで参加されることを強くオススメする。

会場にいた謎の鳥集団
先日btraxは、「日本企業はなぜブランディングが弱いのか? – btrax Event Series 01 Brand Design」というオンラインイベントを実施した。
ブランディングに関するよくある誤解を解消し、経営におけるブランディングの重要性をより深く理解していただくことを目指して開催した本イベントは、多くの方にご参加いただき、大盛況のうちに終了した。
しかし、イベント内にて参加者のみなさまからはご質問やコメントを非常に多くいただき、その数は、時間内では回答しきれないほどだった。
そこで、イベント当日、時間の都合上あまり十分な回答をすることができなかった、もしくは、回答をすることができなかったご質問に対して、登壇したbtrax CEO, Brandonより改めて回答をもらい、記事にまとめる運びとなった。

A. おそらく日本のブランディングプロセスの多くが、20世紀から行われていたCIデザインと、広告中心の手法が踏襲されていると考えられます。
一方でアメリカの場合は、多くの企業がデジタルチャンネルの活用を10年ほど前から積極的に行なっているため、それらを活用したよりスピーディーで柔軟な形のブランディングが行われていると思います。
A. これに関しては、まさに上記の質問にも関連する「リーンブランディング」ですね。
今までのようにじっくりと作り込むのではなくて、素早くリリースして、改善していく手法です。以前に弊社のブログにて詳しく紹介してあるので、そちらをご参照ください。
A. とても素晴らしいブランドキャンペーンだったと思います。
特にテレビCMやビルボード広告で全く商品を紹介せずに、世界を変えた偉人の写真と共に自分達の信念を語ったというのが、模範的なブランドメッセージの発信方法だと思います。
A. 営業をする際にもブランド力がある企業の方が圧倒的に成果が出しやすいと思います。
飛び込み営業や、メールでの営業をした場合でも、無名のブランドよりもブランド力が高い企業の方が返事をもらえる可能性が格段に高くなると思います。また、マーケティングをする際にも同様で、その効果が高まると考えています。
A. ブランド力が直接企業の売上、利益、時価総額に影響することをデータと一緒にプレゼンすると良いかと思います。
A. 現代のブランディングにおいては、企業の掲げるパーパスはとても重要な役割を果たします。
自分達の存在意義と、世の中に対してどのような役割を果たしたいかをより明確にすることで、ブランドメッセージもより伝わりやすくなると思います。
A. おそらく最低でも半年、理想的には1年はかかると思います。例えばAppleが倒産寸前の状態からJobsが復帰し、ブランド力が高まるまで最低でも3年はかかったと考えられます。
したがって、企業がブランディングの効果をあまりにも急ぎすぎてしまうと、長期的には逆効果になります。

A. 多くの中小企業は、大企業に比べて小回りが利きやすく、失うものも少ない、トップの一存で物事を決めやすいなどのメリットがあると思います。
ブランディングにおいても速いスピードでどんどん世の中に発信していけるのではないかと思います。
立ち上げの初期はあまり名前やロゴにこだわりすぎなくても良いと思います。それよりも優れたプロダクトとユーザー獲得に注力するべきだと思います。
A. 企業のブランド価値は常に流動的であるため、非常に難しい質問ですが、一般的には下記のような手法が活用されています。
A. ブランド力とプロダクト力は企業の成功においては両輪の関係です。ですので、プロダクトのUXとブランドメッセージの統一が重要になってきます。
特にデジタルサービスはプロダクト自体がブランド力を牽引する役割を果たすので、プロダクトのUXもしっかりと作りたいところです。
A. 業界にもよりますが、プロダクトがある程度完成し、ユーザーがつき始めた頃がよいと思います。
例えばTwitterは、これまでに5回ほどロゴをアップデートし、その度にブランド力を高めています。

Twitter社のロゴの変遷
また、Airbnbも軌道に乗り始めた頃にブランドを大幅に改善しています。

Airbnb社のロゴの変遷
両者とも知名度が高まり、勢いに乗ったところで一気にブランディングに力を入れたようです。
A. これは世の中的にはUXデザインとかユーザー体験デザインと呼ばれているものです。商品やサービスを利用した際に、その利用者が受け取る体験の良し悪しを決めるデザインです。
また、UXデザイナーの仕事は利用者と提供者の両方が満足する体験をデザインすることになります。
A. 現在我々が行なっているプロジェクトのいくつかは、まさにDXとブランディングを掛け合わせたものです。
例えば、本業がアナログのものづくりの会社が、そのブランドメッセージをモバイルアプリ等のデジタルサービスを通じてユーザーに体感してもらうタイプのプロジェクトをいくつか進めています。
A. そうですね。現代では世代に関係なく、デジタルでのブランドコミュニケーションは必須だと感じます。
特に欧米の国々では高齢者でもパソコンやスマホを使いこなしているので、グローバル規模で考えるのであれば、サービスもデジタルメインで考えるべきだと思います。
A. そうですね。最近はGAFAM に代表される、いわゆる「ビッグテック」があまりにもユーザーのデータを所有して力を持ちすぎていることから、一部のユーザーからの不安と不満が挙がっているのは確かです。
一部の企業が独占するより、民主主義的に、Web3の概念に期待をしている人たちも増えてきていると思います。
A. かなりレベルの高い質問ですね。ユーザーがブランド力を高めているのは間違いないですが、タダで行なっていることが必ずしも悪いとは思わないです。
また、Web3は今後どのような役割になるのかが未知数なので、ブランディングへの影響力に関しても楽しみに思っています。
A. 既存の国内ブランドが海外展開する際には、特に社名やプロダクト名には要注意です。
例えば、カルピスが海外に展開する際にブランド名をカルピコに変更しました。これは、カルピスのままだと、英語圏では違う意味に捉えられるのが原因です。
また、ポカリスウェットも “汗”という単語が入っているので、英語の感覚だと少し違和感があります。
A. これは以前にブログにまとめて、かなり色々な議論を生んだトピックですね (笑)。
僕としてはおそらく、日本の企業の場合、母国語ではないアルファベットを並べただけでも、記号としてのロゴとして認識がしやすいからや、アメリカの企業はなるべくスマホのホーム画面でも認知されやすいようなアイコン型のロゴに舵を切ってるからなどが理由だと思っています。
A. 現代においてはどこの国のブランドであっても、”非国籍感” のあるブランドが強いと思います。これはもともと、どこの国のブランドかに関係なく、支持者が多いブランドです。
例えばTikTokは、元々中国のサービスですが、アメリカではそれを知らない人も多いほどに、浸透しています。同じ意味で “スーパーマリオ” も良いブランドを確立していると思います。
A.「誠実さ」「正確さ」「安全さ」ですかね。世界を見ても、これほどこの3つを追求できている国はないと思っています。
A. 組織のメンバーに自分達のブランドの意味が自然と感じられるように、定期的にミーティングでその話をするとか、目につきやすい場所にブランドを表現したビジュアルや言語を掲示しておくなどがあります。
我々のサンフランシスコのオフィスには、自社のポスターを掲げていたりします。

btraxのサンフランシスコオフィスに飾られているカルチャーを表現したポスター
A. これはおそらく日米や組織によって肩書きの名前や定義が異なるため、僕には正確に答える自信がありません。ただ、ブランディングに関わる人たちはできるだけ経営に近いポジションにいる方が良いと思っています。
A. 我々自身のブランディングを行う際には、できるだけ世の中に対して有益な情報を発信していくことで、ファンの方々を増やすことに注力しています。
顧客獲得の前に、応援してくれるファンを醸成することが我々のブランディング戦略のコアとなっています。
ブランディングに関する内容から日本とアメリカを中心とする海外との違いのほか、非常に多岐にわたるご質問を頂戴し、改めて感謝申し上げます。。
イベント本編のBrandonに「日本企業はなぜブランディングが弱いのか?」をテーマに掲げたセミナーは下記の動画よりご覧ください。
今後もbtraxはイベントを開催してまいりますので、引き続きぜひチェックをお願いいたします!
毎年サンフランシスコで開催されている恒例のスタートアップイベントであるTechCrunch DISRUPTが開催された。
このイベントは2011年からスタートし今年で10周年。その名前の通り、主催は大手テックメディアのTechCrunchによるもの。これまでにも数多くの著名人やスタートアップ起業家が出演している大規模イベントだ。最新のスタートアップトレンドを理解するのには最適な機会となる。
通年であれば、巨大な会場を借り、メインステージ、サブステージ、出典エリア、スタートアップピッチバトルエリアなど、大々的に行われる。しかし、今年と去年はコロナの影響もあり、完全オンラインイベントとなった。でもこれは逆にどこからでも誰でも視聴することができるし、メリットも少なくはない。開催期間は9月21-23日の三日間。
内容は大物スピーカーとのトークセッションが行われるメインステージ、カジュアルなトピックが多いExtra Crunch、世界のスタートアップたちがしのぎを削るStartup Battle Field, オンラインで参加者と繋がれるCruch Match、バーチャル出典スペースのExpo。

9月21-23日に開催されたTC DISRUPT
今年のイベントはかなり印象に残った。通常オンラインイベントの場合は、感覚的に得られる情報量が圧倒的に少ないため、リアルと比べて記憶に残りにくい。
でも、今年のTC DISRUPTはそんなハンデを覆すほどに素晴らしい内容だった。印象に残った10つのポイントを紹介する。
これはオンラインイベントならではのメリットであるが、ゲストスピーカーやピッチに登壇するスタートアップが、サンフランシスコ・シリコンバレーエリアだけではなく、むしろ他の地域からの参加だった。スピーカーセッションでは、オーストラリア在住のCanvaのCEOであるMelanie Perkinsなど、アメリカ国外在住の著名人の出演も実現した。
また、ピッチバトルに参加したスタートアップのほとんどがシリコンバレーエリアではないし、予選を通過した20社のうち過半数の11社が非アメリカ企業で、シリコンバレーのスタートアップは実に1社だった。
応募総数990の中からStartup Battlefieldの出演にスタートアップは下記の通り:
一昔前であれば、スタートアップのメンバーといえば大学を中退したならず者たち、っていうイメージが強かった。彼らは、学校では教えてくれないストリートスマートな賢さを武器に、世界を変えるようなサービスを生み出した。
しかし、今回のスピーカーやピッチしているスタートアップのファウンダーたちの経歴を見てみると、めっちゃエリート。LinkedInの経歴を見てみると、ハーバード、スタンフォード、MIT卒が目白押しだった。
それだけスタートアップがビジネスとしてメインストリームになってきているサインだろう。

情報ソース: Crunchbase
エリートが増えていることに加え、女性の出演者が多かったことも印象深かった。
これまでスタートアップやテクノロジー系のイベント・カンファレンスは、男性中心であることが多く、スタートアップ投資全体の実に96%がトップが男性の企業に行われているという統計もある。
しかし、今回のイベントにおけるゲストスピーカー、ファウンダー、審査員に女性が目立った。スピーカーセッションに出演した193人のうち76名、約39%が女性。

スタートアップピッチでのシーン (左: 起業家 右: 審査員)
イベントのメインMCも女性。ピッチバトルに優勝したCellino、準優勝のNth Cycleのトップも両者ともに女性だったし、フェムテック系のサービス2社もファイナリストに残っていた。
逆に「女性起業家」セッションは無い。この変化は素晴らしく、スタートアップでも男女差がなくなってきた事で、時代の変化を嬉しく感じた。
オンラインイベントの隠れたメリットが、目の前で出演している人たちに直接繋がりやすいという点。
方法としては、ライブで話したりピッチしているのを見た直後にLinkedInで個別に「セッションました!めっちゃよかったです!」的なメッセージを送ると、かなりの確率で繋がれる。
普段は無視されそうな著名人でも、本人がアドレナリンが出ているセッション直後に連絡することで、高い確率で繋がれる裏ワザ。また、テンションが高い状態で会話が盛り上がる事も多い。
実際に、今回も出演者ほとんどと繋がることができた。

イベントにはネットワーキングができるプラットフォームも利用可能 (でもあんま使ってない)
多くのセッショントピックや、スタートアップサービスの内容が人々の実際の生活の課題を解決することに関連していた。それもSaaSのような、オンラインで完結するものではなくて、オフラインのテクノロジーも連動させたタイプ。
例えば、ピッチバトル優勝のCellinoはロボットによって器官移植目的に細胞を培養しするシステムを開発している。次世代のヘルスケアに関するセッションも複数見られた。
それ以外にも、環境や貧困の問題など、まさにSDGsで叫ばれている世界課題をスタートアップサービスで解決することへの意欲が高まっている。
世界規模の課題の中でも、環境問題に関するトピックやスタートアップピッチが目立った。
ピッチに参加したのNth Cycleは、EV向けバッテリー製造における環境への負荷を下げるプロセスを開発しているし、ANIMAL ALTERNATIVE TECHNOLOGIESは、食料問題を解決する培養肉のソリューションを、Verdiはより良い農業プロセスへの仕組みを、Fliteは環境に優しい重機コーティングテクノロジーを開発している。

次世代のコーティングテクノロジーを提供するFlite
今回のイベントがオンライン・フルリモートで行われたこともあり、通常であればなかなか参加しにくい国のスタートアップもピッチを行っていた。
その中でもアフリカを代表に代表される発展途上国向けのサービスがかなり興味深い。例えば、Koaは、アフリカに住む多くの銀行口座を持たない人々のためのフィンテックサービスを提供し、より良い生活の実現を目指している。
クレジットカードを飛び越してフィンテックサービスを展開するような、一足飛びのサービスは「リープフロッグ」サービスと呼ばれ、特に発展途上国では高いニーズがある。
これもオンラインイベントの醍醐味 & アメリカのスタートアップイベントっぽい部分であるが、ゲストスピーカーがさまざまな場所からの参加、及び個性的なスタイルで出演していた。
テクノロジストとして有名なTom Chi氏なんかは、ベッドに横たわりながらの参加で、まるでジャルジャルのコントのようになってしまっていた。
TechCrunch DISRUPTのトークセッション見てたらスピーカーの一人がベッドにもたれての参加で、ジャルジャルのコントみたいになってる! pic.twitter.com/LYYi7xjUym
— Brandon K. Hill | CEO of btrax (@BrandonKHill) September 23, 2021
イベント内でいくつか紹介されいたテクノロジーの中でも特に衝撃的だったのが、Deepfake系。
モバイルアプリ人気No.1にもなったMyheritageを提供するD-ID社による写真をもとにユーザーの動きに合わせて動きと声を生成するテクノロジーは、何が本当かわからない時代がすぐそこにきていると感じさせた。
右下の少年は左の男性の子供の頃の写真をDeepfakeテクノロジーで動かしている。
TC DISRUPT 2021では、スポンサー枠として、国ごとにスタートアップを紹介するセッションも設けられていた。参加していたのは、ベルギー、韓国、台湾、そして日本のスタートアップ。こういう場所に日本のスタートアップが出演しているのは非常に嬉しい限り。
国別スタートアップの中で、台湾と韓国はかなり何度も告知したり、凝った動画を作成していたり、ピッチのクオリティーが高かった印象。
一方で日本のスタートアップグループはかなり地味な印象を受けざるを得なかった。JETROがコーディネートしているとのことだったが、MCのやり方などを含め、もうちょい工夫をこらしても良いのかな?と感じてしまった。また、Startup Battlefieldに一社も選ばれてないのも残念。
今回のイベントに参加してみて、スタートアップにおける様々な状況や環境が変化しているのを強く感じた。場所的にシリコンバレーだけではないし、参加する方々の、性別や人種も多種多様に。
これまではドロップアウトたちが多かった起業家だったのが、最近ではエリートが増え、パソコンやスマホの画面で終わらない、より大きな社会問題を解決するサービスを提供。
そして何より、スタートアップのサービスはこれから本当の意味で世界を革命的に変化させるという実感を得ることができたのは大きい。
スタートアップの定番といえばピッチだろう。イベントや投資家の前で数分間のプレゼンで自分たちのビジョンを説明し、賛同者を集める。シリコンバレーから始まったこの手法は、今では世界中に広がり、スタートアップの運命を左右する重要なスキルになってきている。
そのやり方やテクニックはいくつかのバリエーションがあるが、基本的な部分は共通している。世の中における既存の課題を説明し、それを解決するためのアイディア、チーム構成、目指す結果などがそれである。
すでにご存知の方も多いかもしれないが、これからスタートアップを始める方や、ピッチの内容を改善したいと思われている方々のために、いま一度ピッチの基本をおさらいしておこう。ちなみに、今回紹介するのはシリコンバレーを中心に活躍するVCであり、友人のEdith Yeungによる内容をベースにしている。
目次:
戦いの基本はまず敵を知ることから。スタートアップピッチの場合、その多くは投資を受けるために行う。であれば、投資をしてくれる人 = 投資家 はどのような会社に投資をしたいと思っているかを理解するのが重要である。
これは意外と見落としがちなポイントであるが、多くの投資家は起業家が気に入ったからと言って投資するわけではない。特にVCの人たちは、預かったお金から何倍ものリターンを出すことを生業としているので、起業家の人柄や事業のビジョンに共感した“だけ”では投資をしてくれない。
では、どのような スタートアップに投資したいと考えているのか?
GAFAの次に来る企業
や
iPhoneの次に来るプロダクト
である。
そう。小さな成功ではなくて、世界のトップ企業にもなれそうな成功からのビッグリターンを望んでいる。この大きな成功は俗にムーンショットと呼ばれる。
では、逆に起業家側は投資家へのピッチを通じて何を実現しようとしているのだろうか?
まずは、
投資してくれること
そして、
事業の成長を手助けしてくれること
だろう。そう、百戦錬磨のビジネスの先輩からお金をもらい、助けもしてもらう。なかなかの要求なのだ。
もう一つピッチに関してとても重要なことがあるので、紹介するそれは。
投資家は最初のピッチだけで投資することは100%ない
ということ。
最初のピッチだけで投資を決めるのは、初対面の人と結婚するようなものだ。投資家と起業家がカップルだとすれば、最低でも数回はデートをしないとその相性はわからない。
ピッチをしたからといっていきなり投資をしてくれないのであれば、最初のピッチではどのように行えば良いのだろうか?
例: Airbnb
例: Facebook
thefacebook.comは、大学でのソーシャルネットワークを介して学生、卒業生、教職員、スタッフを接続する拡大しているオンラインディレクトリです。このオンラインディレクトリは、友達同士の繋がりを可能にし、コースやイントラと学校間のネットワークを含む社会的ネットワーク、および組み込みのメッセージングシステムを持っています。
簡単なダイアグラムやイラストでプロダクトがどのように動くかを説明する。
例: Castle

トラクションとは主にユーザー獲得数などを基準とした成長率。もしすでにユーザーを獲得している場合は、これまでの成長率をグラフで表現することが多い。プロダクトがユーザーに受け入れらえている一つの証明になる。
例: Instagram

もしすでに売上の獲得方法がわかっている場合は、その方法をわかりやすく説明する。
例: Airbnb

投資をする際に、課題に注目する投資家もいれば、ソリューションを重視する人もいる。しかし、“人”に投資するという考えの投資家も少なくない。ファウンダーをはじめ、どのようなチーム構成なのか、それぞれの実績も含めてピッチに盛り込むと良い。
例: Mapme

ユーザーから見て近いサービスを提供している他の企業の名前とそれぞれのポジショニングを提示し、自分たちのユニークさを強調する。
例: Slack

自分たちにしかできない特別な優位性。特許をとっていたり、特別なコネがあったり、すでに広い認知度があるなど、他の会社が参入しにくい要素を提示する。
これら以外に、もし時間の余裕があるのであれば、下記の情報も盛り込むのも良い
ピッチを行う際の起業家はどのような雰囲気であるべきなのか?投資家が好感を抱くのは下記の3つのポイント
これはプレゼンの神様、スティーブ・ジョブスの雰囲気にも通じる。
ハッタリでも良いが、自分たちがやっている事柄に対しての能力が高そうに見せる。
長々と話すよりも短いフレーズでクリアに伝えるのが良い
では逆にピッチで減点されてしまう内容も見ていこう。
通常はピッチが終わると投資家から質問を受けることが多い。実は起業家から投資家に質問をするのも全然アリだし、むしろ積極的に質問をした方が印象に残りやすい。
でも、どんな質問をして良いのかがわかりにくかったりする。投資家目線でこんな質問をしてもらっても良いよ、というのは
ピッチは起業家と投資家の出会いの場である。最初のデートに近い。であれば、それが終わった後に何をするかがその後の関係に重要な影響がある。
話を続けたいのであれば、ピッチの12時間以内に下記の内容を含むメールを投資家に送るのが良い。
btraxは、福岡市のグローバル起業家育成プログラム『Global Challenge! STARTUP TEAM FUKUOKA』の運営を行う。全編オンライン開催を予定しており、受講料無料で参加できる。
スタートアップ起業家や投資家など、各分野の第一線で活躍される方々に講師としてご登壇いただく。応募期間は残り2日、このチャンスを逃さず、ぜひチャレンジしていただきたい。Webサイトはこちら。
多くの日本企業が、日本国内市場の頭打ち、GAFA (Google、 Apple、 Facebook、 Amazon) の参入、技術トレンドの変遷により、危機感を持つようになって久しい。そしてその多くは、危機脱出のため、イノベーション創出のため、技術調査やスタートアップおよびGAFAとのコネクションを求めて、ここ、サンフランシスコ/シリコンバレーに出張者や駐在員を送る。
技術調査やコネクションは、直接的に新規事業の開発に活用できるものではあるが、会社の危機を救うイノベーティブな新規事業に繋げるのはなかなか難しい。なぜなら技術調査を行っても、それを活用する方法を見いだすのが難しく、スタートアップとコネクションができても、上手く協業していくのが難しいからだ。
ゆえにイノベーション創出を目指すなら、技術調査やコネクション以上に重要なアセットがサンフランシスコにあると筆者は確信している。それが「マインドセット」だ。
筆者はサンフランシスコに住んで5年、btraxで日本企業のイノベーション創出を支援してきた。その支援というのは、日本の大手企業からサンフランシスコへ送り出されたエースに対して、短期集中でデザイン思考、リーンスタートアップ、UXデザインの考え方・手法を活用し、新規サービス開発を行うイノベーショントレーニングを実施するというものだ。
筆者はそのトレーニングのファシリテーターとして、短いものでは1週間、長いものでは2ヶ月半の間、毎日参加者と顔を付き合わし、濃密な議論をし、新規サービスを作り上げてきた。トレーニング参加者の数は累計200にも登る。そして、このトレーニングを通して参加者の多くが大企業のオペレーション人材から、イノベーションを起こすイントレプレナーへと、目の色を変えて卒業していく姿を目にしてきた。
これらの経験から、日本企業がサンフランシスコ/シリコンバレーから得られる、で実は最も価値があるものは、「マインドセットの変革」であると確信している。マインドセットは一見、新規事業には間接的な影響と思うかもしれないが、日本企業のイノベーション創出に必要なのはまずはマインドセット変革であり、それを行うのにサンフランシスコは最適な場所なのだ。
そこで今回はこの経験を通じて、なぜサンフランシスコという地が日本企業の社員のマインドセットを変えるのか、サンフランシスコならではの特徴と事例を交えて紹介したい。
関連記事:現代における大企業の平均寿命は15年 – 生き残り戦略としてのイノベーション
サンフランシスコでのイノベーショントレーニングによってマインドセットが変化する理由
Uber、 Twitter、 Facebook、 Airbnbなど、サンフランシスコからは多くの人気サービスが誕生しているが、多くの起業家は人気のサービスを生む前に失敗を経験している。
例えばLinkedInのファウンダーであるReid Hoffmanは、LinkedInの前にSocialNetというソーシャルメディアを立ち上げて失敗しているし、GoProのファウンダーであるNick Woodmanは、GoProの前にFunBugというゲームおよびマーケティングのプラットフォームを立ち上げて、失敗している。現在の成功者でも、必ずと言って良いほど過去に「しくじった」経験があるのだ。
UberやAirbnbのように、人々の「体験」に対する価値観を大きく変えるようなイノベーティブなサービスを生み出すことは当たり前だが、実際に行うとなると非常に難しい。
メディアでは成功したスタートアップが取りざたされるので、スタートアップというと華やかなイメージがあるが、実際には90%のスタートアップが失敗に終わっている。しかし、前述のしくじり先生方のように、成功するものはそこから学ぶことで成功に繋げているのである。
実際にサンフランシスコでは彼らの失敗ぶりを垣間見ることができる。例えば、サンフランシスコで定期的に開催されているFuck up nightsというイベント。ここでは、多くの人が自分のFuck up(失敗した)経験をさらけだしあい、そこからの学びを共有する。
また、先日筆者が訪れたイベントでは、GoogleのプロダクトマネージャーがGmailの自動返信作成機能を作るに当たっての「ボツ案」を公開し、そこからの学びを会場に共有していた。日本だと大手の企業がカジュアルにイベントで商品のボツネタを公開することはあまり見ないのではないだろうか?

Gmail自動返信機能のUX改善においてボツとなったアイデアも多く公開していた。
このように、サンフランシスコでは「失敗から学ぶ」ことが当たり前のように捉え捕らえられているため、失敗を公開して、みんなで学び合うことをする。
間違いなくサンフランシスコの大きな価値であるのは、「失敗から学ぶ」サービス開発の文化がサービスを作る側だけではなく、サービスを使う側にも根付いていることだ。
サンフランシスコのユーザーは多少バグのあるようなサービスでも、自分の問題を解決してくれそうなサービスであればまずは使ってみる。そしてそのサービスをよくするために積極的にフィードバックを与える。
実際にサンフランシスコでは、起業家たちが自分たちのサービスアイデアをプレゼンする「ピッチ」と呼ばれる形式のイベントが多く開催される。そこで発表されるアイデアは、まだビジネスモデルがきちんと煮詰まっていないもの、プロトタイプもまだバグだらけのものもある。
それでもアイデアを聞いたオーディエンスは積極的にフィードバックを共有してくれる。彼らは新しいサービスを試すことに抵抗が少ないのと、失敗でも改善をすれば良いと思っているからこそ与えてくれるフィードバックなのだと思う。
btraxのイノベーショントレーニングでも、トレーニングの終盤に参加者のアイデアをサンフランシスコのオーディエンスに向けてピッチしてもらうことがある。毎回オーディエンスが彼らのアイデアを自分ごとにして考え、質の良いフィードバックをたくさんくれることに驚く人が多い。新規サービスやスタートアップを行う人にとって非常に協力的な環境があると言える。

このようなサンフランシスコの「失敗から学ぶ」ことに対する価値観は日本企業の若手のマインドセットを大きく変える。その大きな理由は、日本での価値観とのギャップである。日本は事業にしても、キャリアにしても、一度失敗するとそれを覆すのが難しく、「失敗から学ぶ」というマインドセットを構築するのが非常に難しい地である。
特に「優秀」と呼ばれる人ほど失敗への抵抗感が大きく、企業側、起業家、ユーザーといった社会全体として「いかに失敗しないか」が評価の基準とすることが多い。
しかし、新しいものを作り出すのに失敗はしない方がおかしい。失敗を失敗と捉えず、「改善のためのアイディア」と捉えるマインドが必要だ。そのマインドがサンフランシスコには根付いている。だからこそ、短期間でこのマインドが身につき、帰国後のイノベーション創出に繋がるのである。
関連記事:なぜ日本ではオープンイノベーションが生まれにくいのか
イノベーティブと呼ばれる多くの企業やサービスが開発において取り入れているデザイン思考はWhyを考えることを重視している。ユーザーの潜在的な問題に迫ることを重要視する上で、ユーザーの行動や発言に対して、Whyを知ることが重要になるためだ。
例えば「人はなぜ無駄が嫌なのか?」「どうでもいい選択ほどできないのはなぜか?」など、従来のマーケティング手法で行うニーズ調査よりもかなり深掘りしてニーズより深い「価値」の追求をする。
サンフランシスコには、デザイン思考の考え方が根付いており、多くのサービスがこのようなWhyの深掘りから生まれている。
日本の大企業は、既存事業の維持や拡大が重視されることが多いため、効率的なオペレーションが重要視されることが多く、そもそも落ち着いてWhyを考えることが少ない。それを突き詰めて考えることは、普段のHowやWhatを考える脳と全く違う脳の使い方であるため、このような考え方をすること自体が、大きなマインドセット変革に繋がるのである。
btraxのイノベーショントレーニングでは、参加者が夜遅くまでこのような哲学に近い議論を行う。時差ボケも残る中、連日内容の濃いディスカッションが続き、参加者はさぞ疲弊しているだろうと思いきや「普段の機械的な会議とは全く違って楽しい!」と言う人が多い。
このようにマインドを変えた人は、帰国後も「言われたことをやる」のではなく、「Why?を理解することで価値を出す」ことができるようになる人材となるのだ。


サンフランシスコには成功したスタートアップが多くいるが、その成功する理由の一つに、ユーザー視点で作られていることが挙げられる。
「AIを使ってサービスを作ろう」と技術起点で考えられたのではなく、日常のちょっとした不満、イライラするシーンなどを目の当たりにし、それを解決できないか?とユーザーを深掘りすることで、多くのイノベーティブなサービスが生まれているのだ。
例えば「カンファレンスや大きなイベントが開催されるとホテルが足りなくなる」という問題を解決したAirbnbや、「忙しい人ほど良質なコーヒーが必要なのに、良質なコーヒーを飲むには並ばないといけない」という問題を解決したCAFE Xなど。
サンフランシスコでは、これらのサービスを日常的に体感し、真にユーザー視点で作られたサービスの価値をユーザー側として実感することができる。ユーザー視点で作られたサービスの「お手本」を見ることができるのだ。
関連記事:イノベーションが生まれ続けるサンフランシスコの生活とは
また、ユーザーとして新しいサービスを体験できるだけでなく、実際に作り手側としてユーザー視点のサービスを考えることのハードルもむちゃくちゃ低い。
日常のちょっとした不満を解決するサービスが生まれる様子を人々が間近で見ているため、自らも日常の問題に注目し、こんなアプリ作ったらどうか?を考えている。
誰もがサービスを使う側でもあるのだから、ユーザー視点でサービスを考えることは難しいわけではないよくデザイン思考を「専門家が使うメソッド」と捉える人がいるが、そうではない。
デザイン思考は考え方であり、視点をユーザー側に持ってくることで共感をし、サービス開発を行うというマインドセットである。自分は作り手でありながらユーザーに視点を置くマインドセットだからこそ実践が難しいのだ。
しかしながらイノベーティブと呼ばれるサービスやスタートアップはこのユーザー視点に立つということをうまく行っている。
では、なぜサンフランシスコにあるこの要素が日本企業の若手のマインドセットを変えるのか?
1つは「お客様至上主義」と「ユーザー視点」の違いにある。日本企業はそのおもてなし精神とヒエラルキー文化により、「お客様の言うことは絶対」と言うマインドが染み付いている。「ユーザーが欲しいと言ったことを何としてでも実現するのが良いサービス提供者である」と言う考え方が強い。
一方、ユーザー視点の考え方は、「ユーザーのことを徹底的に考え抜くため、ユーザーよりもユーザーのことを理解している」と言う立場をとる。そのため、ユーザーの欲しい(want)と言ったものをそのまま作るのではなく、ユーザーに必要なもの(need)を作るのだ。結果として、ユーザーが「使わざるを得ない」ほど価値のあるサービスを生むことができるのである。
この大きな違いを学ぶことは視点の違いでもあるが、実に「視座」の違いでもある。だからこそ、日本企業の社員のマインドを大きく変える要素なのである。
もう1つ重要な点として、サービス開発は専門家やMBAホルダーのみがやることではないという気づきだ。日本の大企業では「サービス開発は専門家がするもの」と言う考え方がある。
また、新規事業を生み出すにあたって、従来のビジネスの考え方であれば、短期的な収益性が重要視されるため、確実に利益を生み出すビジネスモデルが必要とされる。
そのため、MBAなどビジネスを体系的に勉強した人ではないと、新規事業のアイディアは生み出せないと考える人が多い。しかし、サンフランシスコでは、新しいビジネスアイディアを考えるのにその分野の専門家やMBAは必須ではないのだ。
関連記事:イノベーション=技術革新はもう古い!新たな価値を創造した9事例
このように、サンフランシスコには、日本企業のエース社員の根本的なマインドセットから変える力がある。だからこそ、btraxのイノベーショントレーニングの参加者はこのトレーニングで目の色を変えて帰国し、日本企業のイノベーションに貢献しているのである。参加者の多くは、帰国後に「別人のようだ」と周囲から言われることが多いのものその証拠だ。
イノベーションを起こしたい日本企業は、まずはこのような考え方をできる人材を育ててほしい。そして、それを達成するために、ぜひサンフランシスコにエースを送って欲しい。
その際にはぜひ、サンフランシスコに根ざしたbtraxによるイノベーショントレーニングをご検討いただきたい。btraxにはそのノウハウと実績がある。マインド変革・イノベーション創出をぜひ一緒に起こしましょう。お問い合わせはこちらから。
先日アメリカ・ラスベガスでは、世界最大級の家電見本市として知られるCES(Consumer Electronics Show)が行われた。メディアはイベントで発表された商品やテクノロジーを取り上げ、CESの話題で持ちきりだった。
特にXRと呼ばれる、VR、AR、MR(複合現実)を総称した分野は近年注目度が上がっており、フットコントローラー付きのPlayStation VRのようなエンターテインメント製品をはじめ、8K高画質のVR/AR用ヘッドセットなどの最新技術を用いた製品も多数発表された。
ゴールドマンサックスの調査によると、XR業界は2025年までに80兆円規模の市場価値を生み出すと予測されており、様々な投資家からの注目が集まっている。
そんな中、より積極的な投資を行っている業界の1つが金融だ。Citibankをはじめ、各国の大手銀行たちがXR技術を業界に取り入れていこうとしている。そこで今回は、金融業界で導入され始めているXR技術活用のトレンドを実例と共に紹介していく。
関連記事:【金融革命】最新フィンテック (Fintech) 系サービスまとめ
Citibankで有名なCitiグループは、Microsoftが提供しているMR用ヘッドセットのHoloLensを利用した株式取引システムを発表している。ユーザーはヘッドセットを装着することで、そこに浮かび上がる最新の株価情報や取引データなどを閲覧することができる。さらに声やジェスチャーで株式取引も可能だ。
株式取引にMR技術を利用する利点としてまず挙げられるのが、タブレットやPCなどのスクリーンの範囲に限定せず大量のデータを一度に表示することが可能な点だ。また、画面覗き見による金融取引の内容を第三者に見られる心配がないということも重要な利点の1つとなっているようだ。
アメリカ・ボストンに拠点を置き、金融分野でのイノベーションを牽引する製品開発に取り組むFidelity Labsは、株式バーチャルエージェントのCoraを開発している。CoraはVR/AR/3D開発用のAmazonAWSの新サービスAmazon Sumerianを利用して開発されている。
ユーザーはVRで表示されるバーチャルエージェントのCoraに対して、投資に関する質問や相談を音声で行うことができる。現状、この製品はコンセプト検証中のプロトタイプ段階にあるそうだが、実用化されればトレーダーが投資判断する際の強力なサポーターとなり、株式データのオーバーロードを回避できるようなメリットもあると言われている。
Commonwealth bank of Australiaはアメリカ、アジア、イギリスでも金融サービスを提供するオーストラリアの銀行だ。同社は不動産購入を検討していたり、不動産投資を行う層向けにARを用いた不動産投資サポートアプリケーションを提供している。
このアプリ起動し、街で見かけた住宅に携帯をかざすと、住宅の価格変動や購買履歴などの情報が画面を通して見られるようになる。資本成長傾向やその他の金融メトリックスを確認することも可能になるため、ユーザーの不動産売買の判断を手軽な形でサポートしている。
決済までのオンラインショッピング体験を提供できるVRシステムの開発が進められていることが、MastercardやAlibaba、Payscoutなど各社から発表され始めている。
Alibabaは、ヘッドセットを装着して仮想現実の店舗へ入り込み、気に入った商品をピックアップしてそのまま購入することができるVRシステムの開発を、2016年後半に発表した。あまり詳細は明らかにされていないが、Amazonも同様のサービスを開発し始めていると報告されている。
VRと決済技術の分野においては、ゲーム業界が大きな注目を集めている。ユーザーがVRの世界でゲームを楽しんでいる際に、現実世界に戻らずシームレスにゲーム内課金を促せるためだ。GoogleCardboardヘッドセットを装着して遊ぶVRゲームのPayscoutは、まさにその1つで、VR内での支払い機能をすでに実装させている。
VRを用いた支払いはオンラインに限らず、実店舗に向けたものも開発され始めている。ペイメントテクノロジー企業のWorldpayは、店舗でのクレジットカード支払いのためのPIN入力をVRで行うことができるAirPinの技術を開発している。
AirPinのVRによる決済は、ユーザーがVRヘッドセットを装着して決済処理に必要なPINの入力を行う。VR空間で、使用するカード情報を選択しランダムに並んだ数字から視線を使ってPINを入力する仕組みだ。ヘッドセットを使った操作なので、他人からカード情報やPIN入力を覗かれてしまう心配がなく、防犯性に優れている。
あらゆる業界におけるARの利用実現に取り組むインドのスタートアップYepperでは、クレジットカードの情報管理をARで行える仕組みを開発中だ。クレジットカードをスマートフォンカメラでスキャンすると、そのクレジットカードの使用履歴や利用可能残高などがARとして表示されるというものだ。クレジットカードの利用管理を手軽にできるようなることが期待される。
National Bank Of OmanやRoyal Bank of Canadaといった銀行では、自社ATMの所在地をARで表示することができるというサービスを展開している。
National Bank Of Omanのアプリでは、NBOの口座を持たないユーザーもアプリを利用できる仕組みになっており、ATM所在地の表示以外に、ショッピングモール等でのお買い得情報もARを介してユーザーに知らせてくれる機能も持ち合わせている。これによって新たなユーザーの取り込みも期待されている。
以上のように、投資、日常の買い物にまつわる決済、銀行利用など様々なシーンでXR利用が始まっている。金融業界でのXR利用はアメリカに限らず、インドやオーストラリア、オマーンなど世界各地で活発に進められており、その投資もどんどん加速している。
また、XR導入により金融業界がこれから急速に変化していくと言われてる。身近なところでは、銀行実店舗が2009年の不況以降減り続けているが(2017年6月までの1年間で1700の銀行店舗が閉鎖)、今後銀行がVRを用いたバーチャル店舗体験に注力し、新たな価値を提供していくだろうと期待されている。ますます金融xXRの動向から目が離せなくなりそうだ。
参考記事
・Worldpay Demonstrates The Future Of Virtual Reality Payments
・Future of the brunch
※こちらの記事はNissho Electronics USA様のブログより転載いたしました。
2019年が始まり早くも1ヶ月が過ぎようとしている。例年、ビジネスやテクノロジーに関するカンファレンスイベントが世界各地で開催されるが、参加するイベントの計画を年始のこの時期に立てる読者も多いのではないだろうか。
各種イベントに参加することは、最新テクノロジーや各業界の動向に関する情報を得られるだけではなく、新たなネットワーク構築のきっかけ作りとしても非常に有効だ。
昨今、アメリカを中心に、ヨーロッパ、アジアでも見逃せないテック系の大型カンファレンスが数多く開催されることが決まっているので、今回はbtrax一押しのイベントをご紹介したい。(上から日付順に紹介)
日程: 2/5-7
ロケーション San Jose, California (Silicon Valley)
最も直近に開催が予定されているのが、SaaS (Software-as-a-Service) に焦点を当てたカンファレンスのSaaStrだ。このカンファレンスは例年1万人以上が参加し、今年はStripeやDropbox、Invisionなどの世界的に有名なSaaS企業のリーダー達が登壇を予定。SaaSの分野に限らずソフトウェア開発や組織経営に関わる人であれば、有益な情報、ネットワークを得られる機会なので、ぜひ参加をお勧めしたいカンファレンスだ。
日程: 2/12-13
ロケーション: Redwood City, California (Silicon Valley)
比較的見落とされがちだが見逃してほしくないのが世界の起業家コミュニティ形成を目的に開催されているStartup Grind Global Conferenceだ。2日間に亘り、投資家やテックコミュニティのリーダーと呼ばれる人々によるトークセッションやネットワーキングパーティが行われる。シリコンバレーや世界で成功するスタートアップやVC、投資家達との関係構築が期待できる場だ。
日程: 2/19-23
ロケーション: Nashville, Tennessee
オンラインマーケティングへの注目は年々高まっているが、より良いファネルを持つことは効果的なEコマース戦略を行う上で極めて重要だ。Funnel Hacking Live はその名の通り、良いファネルの作り方とその効果的な活用方法について焦点を当てたカンファレンス。オンラインマーケティングのエキスパート達による実践的なセミナーセッションが行われる。最新のオンラインマーケティング事情をグローバルな視点で学びたいマーケッターにとってはかなり有益なイベントとなるだろう。
日程: 2/25-28
ロケーション: Barcelona, Spain
スペイン・バルセロナで毎年開催されるMobile World Congressは、モバイルテクノロジーを中心に破壊的イノベーション、AI、コネクティビティ、デジタルウェルネス、デジタルトラストなどのテーマで各種トークセッションや製品体験会などが行われる。例年Cレベルの参加者が多く、昨年は7700人以上のCEOがイベントに参加した。今年はMicrosoftやVimeoのCEOをはじめ、世界でイノベーション創出に挑むリーダー達が登壇を予定。スペイン語圏での開催のため、参加企業やスピーカーも北米とは少し異なる傾向にある。これまで北米のカンファレンスにばかり参加してきた人にとっては新たな気づきを期待できるだろう。
日程: 3/1-3
ロケーション: San Francisco, California
Wisdom 2.0はここまで紹介してきたような一般的なテック系カンファレンスでは忘れられがちな、人々の繋がりやウェルネスの分野に着目している。ビジネスにおける利益や成功を追求することに伴い、“人々の精神的な充足感や生活の質をどのように向上していくか”をテーマに置く。マインドフルネス講師やTwitterとMediumの創設者Ev WilliamsやGoogleのバイスプレシデントKaren Mayといったビジネス界のリーダーたちが一緒に議論する、世界的にもユニークなカンファレンスだ。
日程: 3/8-17
ロケーション Texas
以前【SXSW2017レポート】キーワードは「社会問題解決型」注目の最新テクノロジー5選でも紹介しているが、SXSW (South by Southwest)は、例年アメリカのテキサス州オースティンで行われるテクノロジー、音楽、映像、ヒューマニティをテーマにした大規模イベントだ。80年代に音楽の祭典として始まった同イベントだが、VR/AR、ブロックチェーン、フードテック、医療テック、AIといったテクノロジーによるあらゆる分野での未来のあり方を探索するような内容になっている。
ビジネスやテクノロジー業界のみならず、政治やエンターテインメントなど各界の著名人たちもスピーカーとして参加するSXSWは新たなインスピレーションの習得やネットワークの構築に最適な場となるだろう。
日程: 3/20-22
ロケーション: San Diego, California
Social Media Marketing Worldは、ソーシャルメディア戦略を実際に行う担当者にとってはまたとないネットワーキングと学びの場だ。Instagram、Youtube、Facebookなど、各プラットフォームに特化したエキスパートが詳細な活用方法を語るトークセッションや彼らと1対1で対話できる機会も用意されている。数あるマーケティング施策の中で特にソーシャルメディアに注力したいと考えている人にとっては見逃せないカンファレンスだ。
日程: 4/9-10
ロケーション: Los Angeles, California
Crypto Invest Summitは、ブロックチェーンや仮想通貨への投資がテーマのカンファレンス。昨年は2000人以上の投資家が集い、分散型チャットアプリSENSEのCEO Crystal Roseなどブロックチェーン界隈で有名な起業家や投資家が登壇した。フィンテック業界への投資を検討しているビジネスマンにはぜひ逃さずチェックしていただきたい。
日程: 5/13-15
ロケーション: New York City, New York
Coindeskが主催するConsensusもまた、ブロックチェーンやクリプトに関する大規模なカンファレンス。昨年は8500人程度が参加し、250人以上の業界リーダーたちによるスピーチが行われた。注目のスタートアップやメディアとのネットワークの機会を期待できる場だ。ブロックチェーンやクリプトといったフィンテック業界の人であれば、絶対に見逃したくないイベントだ。
日程: 5/20-23
ロケーション: Toronto, Canada
Collisionは、テクノロジーと起業がテーマのカンファレンスイベント。これまでニューオリンズで開催されてきたが、今年度からはトロントでの開催が決まっている。今年はY Combinator CEOのMichael SeibelやShopify CEOのTobias Lutke、MastercardのCMO Raja Rajamannarなど100名が登壇予定だ。スタートアップ界隈でのネットワーク構築やテクノロジーの最新動向をチェックしたい方にお勧めのイベントだ。
日程: 6/7-9
ロケーション: New York City, New York
今年で5年目を迎えたNext Gen Summitは、世界の優秀な起業家たちが招待制で集るイベントだ。メンターや投資家と1対1でセッションを行う機会もあるため、起業家たちにとって世界でも最も良質なネットワークの場の1つと言われており、今年は1000人が参加予定だ。本イベントは招待制なので事前にオンライン上で参加申し込みが必要となる。
日程: 7/8-11
ロケーション:Hong Kong, Hong Kong
RISEはアジア最大のテックカンファレンスで世界各国から毎年15000人以上が参加している。世界中からスタートアップや大企業、投資家、メディアが集うので、グローバル規模でのネットワーク構築ができるのが最大の特徴。
会場では各界のリーダーらによるトークセッションからスタートアップピッチ、デモブース出展など、幅広く催しが行われている。アジアでのスタートアップ、テック界隈でのネットワークの機会を探っているのであれば、このカンファレンスは絶対に見逃せない。
なお、2017年には弊社のCEO Brandon K. HillがMazda、Honda、Yamahaのイノベーター達とともに自動運転の未来についてセッションを行った。セッションの様子はYoutubeページから観ることが可能なので、RISEの様子を見たい方は是非ご覧頂きたい。(セッションは1:56:00から開始)
日程: 10/2-4
ロケーション: San Francisco, California
TechCrunch Disruptは、スタートアップコミュニティに関連のある人なら誰もが参加したいと思うイベントの1つだろう。スタートアップやテック業界での著名人たち(過去の登壇者はSalesforceの創業者Marc BenioffやAndreessen groupのMarc Andreesseなど)によるトークセッションに並行して、アーリーステージのスタートアップたちがステージ上で自分たちのサービスを競い合ったり、ハッカソンが行われたりする。
起業家、投資家、テクノロジスト、メディアからの参加者が集う巨大なネットワークパーティも注目だ。最新のスタートアップ情報をいち早く手に入れたい方は特に見逃せないイベントとなっている。
日程: 10/5-12
ロケーション: San Francisco, California
SF Blockchain Weekは、消費者・開発側両者に向けたブロックチェーン技術に関する教育を通してブロックチェーンコミュニティ界隈の活性化を目的にした9日間のカンファレンスイベントだ。業界を牽引するリーダーたちが最新のブロックチェーン動向を語るセッションや基本的な学びを得るためのワークショップ、ネットワーキングのためのミートアップイベントのなどが行われる。
ブロックチェーン業界に深いネットワーク構築を求める場合やこれからブロックチェーン業界に乗り出すことを模索している場合に最善の機会と言えそうだ。
日程: 11/4-7
ロケーション: Lisbon, Portugal
Web Summitは、Forbesに「世界最高のテックカンファレンス」と称賛されるほどクオリティーの高いカンファレンスだ。世界のテック企業の創業者やCEO、スタートアップ、政治家たちが一堂に会し、「これからの未来」をテーマに議論する。著名人らによるトークセッションのみならず、最新テックプロダクトやサービスのショーケース、その他のイベントが目白押しだ。参加者は70000人を超え、開催地のリスボンが街全体としてカンファレンスモードになる。
なお、世界最大のテクノロジーカンファレンスに登壇して思ったことでも紹介しているが、2017年にBrandonが登壇しており、その時の様子を記事にしている。イベントの詳細が良く分かる内容となっているので、是非お読み頂きたい。
日程: 11/8-11
ロケーション: Downtown Los Angeles, California
Summit LAは「アイデアの祭典」とも呼ばれ、聴講スタイルが中心の従来的なカンファレンスとは異なり、参加者同士の距離が近く感じられるコミュニティの醸成や参加者の参加体験に重きを置いている。
このイベントでは、ビジネスやテック業界のみならず、社会起業家や活動家、クリエイターらまでもが各方面から集い、より良い未来を目指した新たな繋がりを見出していくことが目的とされている。会場では、従来的なトークセッションの他に、ウェルネスのクラスやアートインスタレーションなどが行われている。これまでにないような新たな切り口でのビジネスを模索しているのであれば、Summit LAはとても良い機会となりそうだ。
日程: 11/19-22
ロケーション: San Francisco, California
Dreamforceは、Salesforceが主催するビジネスカンファレンス。2003年から開催され、今年で16年目を迎える。Salesforceをビジネスに活用するためのワークショップやソフトウェア業界のリーダーらによるトークセッションがメインだが、セレブリティや政界の有名人などがキーノートスピーカーとして登壇したり、有名バンドがネットワーキングパーティでコンサートを行うなど、華やかさも併せ持つカンファレンスだ。
大企業からの参加者が多く、イベントとしても業界間のネットワークを促進することに力を入れているため、他企業との交流を希望する場合には良い機会だろう。
1年を通し、世界各地で大型のテック系カンファレンスで開催されているが、フィンテック系やオンラインマーケティング系、スタートアップ系など、それぞれに特徴や開催目的が異なる。自分のミッションや広げたいネットワークに合わせて、カンファレンスに参加することがキーになりそうだ。
btraxは年に1度東京でデザインとビジネスをテーマにしたカンファレンス「DESIGN for Innovation」を開催していますが、サンフランシスコでもビジネスやデザイン、スタートアップに関連するミートアップイベントを定期的に開催しています。
今年のイベント第1回目として、2/15(金)に「btrax meetup 01 ワインと共に新規事業の創出方法を学ぶ」と題して、カリフォルニアワインを飲みながら新規事業の創出プロセスについて学ぶミートアップイベントを開催します。
当日は、弊社CEOによるセミナーを行い、btraxが普段プロジェクトで採用している新規事業のためのフレームワークやノウハウをご紹介します。また、イベント参加者の中から先着5名の方にはビジネスアイディアに対してフィードバックも提供いたします。
イベントの詳細、参加方法はこちらより。シリコンバレーに駐在されている方やサンフランシスコに出張の予定がある方はぜひ奮ってご参加ください!
今年は1月6日から12日まで開催される世界最大のテクノロジーカンファレンス。4000を超える出展企業、150カ国から18万人を超える来場者が訪問します。
メインの日中のイベントの見どころなどに関しては、電通の森さんがこちらの記事にてまとめていますので、僕の方は自分用に夜のパーティーに関するリストを作成してみました。行かれる方は活用いただければ幸いです。
CES Unveiled Las Vegas
5:00-8:30 PM
Shorelines Exhibit Hall, Mandalay Bay
NVIDIA News Conference
8:00-10:00 pm
MGM Grand Hotel & Casino
Level 1 Grand Ballroom
CoinAgenda Showcase
8:00 pm – 11:00 pm
Cromwell
Pay Per Callers Party
6:30 pm – 9:00 pm
Alexxa’s Bar @ Paris
Conversation and Cocktail Party
4:30 pm – 6:30 pm
Piero’s Italian Cuisine
Caller Meetup West 2019
5:00 pm – 8:00 pm
Marquee Nightclub & Dayclub
Cocktail reception at CES, hosted by The NPD Group
7:00 pm – 9:30 pm
1OAK at the Mirage
Digital Experience
7:00 pm – 10:30 pm
Mirage
Game Changer Cocktail Reception
7:00 pm – 9:30 pm
1OAK at the Mirage
Pepcom’s Digital Experience
7:00 pm – 10:30 pm
Mirage Events Center (MEC), Ballrooms B&C,
The Mirage.
MediaLink CES Kick-Off Party
8:00 pm – 11:59 pm
Encore XS Nightclub
Technics Party
9:00 pm – 11:00 pm
Hyde Bellagio
C Space Party
10:00 pm – 11:55 pm
JEWEL Nightclub
Unwind: Swingers Exotic Lifestyle Party
9:00 pm –
登録者のみに公開
Digital Money Reception
5:30 pm – 7:00 pm
Venetian, Level 4, Lando 4202
International Matchmaking Reception
6:00 pm – 7:30 pm
LVCC, South Hall Connector, S222
Consumer Technology Association Member Party
6:00 pm – 8:00 pm
Venetian, Level 2, Bellini 2003
ShowStoppers
6:00 pm – 10:00 pm
Lafite Ballroom @ Wynn Hotel
Reception: New Media Built for a Blockchain World
6:30 pm – 7:30 pm
Venetian, Level 4, Lando 4302
SVIEF VIP Reception at CES 2019
6:30 pm – 9:30 pm
Caesars Palace
Adomni + DPAA CES 2019 Party at Rockhouse
9:00 pm – 12:00am
Rockhouse Bar
Venetian Grand Canal Shoppes
CES Opening Party
10:00 pm – 12:00am
Caesars Palace,
OMNIA Nightclub
Hardware Massive Happy Hour Bash
5:00 pm – 9:00 pm
Hangover Suite @ Caesars Palace
Ignite the Night CES Pitch Competition
6:00 pm – 9:00 pm
Venetian Level 4, Marcello 4405
Crowdfunding And Beyond
6:00 pm –
Treasure Island
Amazon Seller CES Cocktail Reception
6:00 pm – 10:00 pm
Parasol Down at Wynn Las Vegas
TechCrunch Las Vegas Hardware and Crypto Meetup
6:00 pm – 9:00 pm
Work In Progress
CES Media Reception: Afterwork – The Future by Région Sud
6:30 pm – 8:30 pm
Trevi Restaurant at Caesars Palace
ShowShare After-party
7:00 pm – 11:30 pm
Troy Liquor Bar at the Golden Nugget Hotel & Casino
10th Annual KAPI (Kids At Play Interactive) Awards Reception
6:00 pm – 7:30 pm
Venetian Level 4, Lando 4302
Entrepreneur’s Reception
7:00 pm –10:00 pm
The LINQBrooklyn Bowl
LederhosenLab 2019 – The most casual after-show dinner for CES-exhibitors
7:00 pm –11:00 pm
Hofbrauhaus Las Vegas
CES Hakkasan After Party
10:00 pm – 11:59 pm
Hakkasan Nightclub @ MGM
以前にラスベガスに住んでいたスタッフに聞いたオススメのメキシコ料理屋さん
Nacho Daddy
場所: 3663 Las Vegas Blvd Ste 595, Las Vegas, NV 89109
https://nachodaddy.com/
btraxでは日本企業の海外進出やイノベーション創出をサポートしています。上記のイベント参加を含め、ご興味のある方はこちらからお問い合わせください。