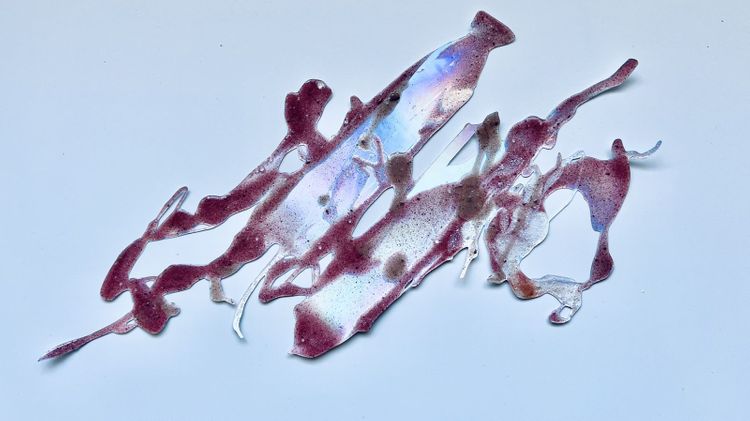大阪梅田駅近くに工房を構えるカットソー製品の三恵メリヤスは2023年5月、オーガニックテキスタイル世界基準のGOTS(Global Organic Textile Standard )認証を取得した。従業員14人の小さな工場にとって国際認証取得のハードルは高いが、小規模事業者がグループで取得する認証「管理型サプライチェーンスキーム(Controlled Supply Chain Scheme、以下CSCS )」を活用して実現した。
内部監査とグループでの認証取得が可能
WWF(世界自然保護基金)ジャパンとGOTSはこのほど、GOTS CSCSに関連する工場の視察ツアーを実施。メディアや業界関係者にCSCSの意義を伝えた。
GOTS CSCSは、GOTSを開発した4団体の一つ日本オーガニックコットン協会が起案した仕組みで、分業化が進み小さな工場が多い日本で、小規模事業者がGOTS 認証を取得する上でのハードルを下げるために開発され、22年にパイロットプロジェクトが始動した。CSCSの対象は最低8サイト、最大30サイトで構成した事業者で、各サイトの従業員が20人以下であること。現在グローバルでのCSCSの運用も検討中で評価を経て運用を開始する予定だ。CSCSのポイントは内部監査が可能になり、グループでの認証を受けることが可能になった点にある。内部監査を行うことで認証にかかるコストの負担を軽減する。認証取得、または更新の際には第三者の認証機関は内部監査の評価に加え、選定した数サイトで外部監査を行う。
GOTS認証は綿繰りから紡績、編み・織り、染色、裁断、縫製、仕上げなどを行う全ての工場での個別監査が必要なため、分業制で工程が多い製品は認証取得のハードルが高く、認証取得が困難になっている。日本製でGOTS認証を取得している製品は、糸や生地、最終製品ではベビー服や寝具があったが、現在の認証を取得したアパレル製品の多くは、縫製まで一気通貫型で製造を行う工場が取得していた。
「日本の伝統と品質だけでは難しいと感じていた」
三恵メリヤスはヴィンテージ調の風合いを再現することを得意とし、スウェットやTシャツといったカットソーの企画・縫製を行う。昔ながらの作り方を再現できる強みから、海外ブランドとの取引が増えている。三木健社長はGOTS CSCS参加の決め手について、「本格的に海外に出るための武器になると考えた。海外輸出が徐々に増えており、日本の古き良きモノ作りの発信はできていたが、それだけでは難しいとも感じていた」と語る。そんなとき、取引先の英国ブランドのデザイナーからの言葉が後押しした。「こだわりがとても強くその理由を聞いたときのこと。『小さいブランドこそやりたいことや必要なことを全力で行わないと戦えない。無名ブランドは最低条件(認証など)をクリアしていないと話も聞いてもらえない』と明かしてくれた。そのブランドからの発注は5年で40倍に増えており、こだわり抜いたモノ作りの姿勢がビジネスの成長を支えていた」と振り返る。さらに「整理整頓、情報整理、社内の意識改革、書類作成能力など審査を通じて世界に通じる工場にしたいとも考えた」。
取得に向けたチームメンバーへの共有
まず、チームメンバーに取得に向けて動き出すことを伝えた。「GOTS認証とは何か?取得することで三恵に何をもたらすかなどを丁寧に伝え、認証取得に重要な整理整頓や分別管理の協力を求めた。価値共有のために活用したのはビジネス本だ。『マンガでわかる!トヨタ式仕事カイゼン術』『マンガで優しくわかる5S』『まんがで身につくPDCA』『トヨタ流「5S」最強のルール』『A4一枚で成果を出す!マンガでわかる経営計画の作り方、進め方』を購入して、チームメンバーみんなで回し読み、読書後に感想を記載してもらった。ただ、PDCAなどは難しくて自社には活かせないなど、チームメンバーからの反応はテーマによって濃淡があった。その後、整理整頓を徹底することから始め、すでに管理されていた帳簿は、よりよい記録の取り方を検討した」。
社内共有の次はCSCSをともに取り組む企業へ協力を要請した。23年の1回目の監査では、生地を編み立てる和歌山の「津村メリヤス」「和田メリヤス」、染色の大阪「V-TEC」、生地の裁断を行う大阪の「白鳩メリヤス」、縫製を行う大阪の「田中メリヤス」、ボタンホールを縫う大阪の「イシカワ縫製」、仕上げの「浜崎プレス」(24年の2回目の監査で高木メリヤスを追加)に対して、三恵メリヤスは申請書などを準備して認証機関に代わり工場が規定に反していないかをチェックする必要がある。「行動指針や各工場が当てはまる部分を拡大コピーして配り、整理整頓は当社のチームメンバーと一緒に手伝いに行った」。実際に足を運び手伝うことで本気度が伝わった。
GOTS認証取得には対象製品と他の製品のラインを分ける必要があり、そのトレーサビリティがポイントになる。「皆さんの仕事の流れを理解したうえで、普段の業務の負担にならないように考えて、GOTS製品を作る際の専用の記録を取るシートを作成し、それを協力工場に配った」。認証取得に向けては人権および社会的要件も重要になる。「最低時給や残業代も確認しなければならない。協力工場で最も給料が少ないスタッフへのインタビューを行うなど、認証取得を目指さない限り、通常は聞くことがないようなことも確認しなければならなかった。先代から取引がある工場さんで、積み重ねた信頼関係があったからこそできた」と振り返る。
「過剰反応し過ぎていた」。取得して気づいたこと
終わってみて思うことは、「日本語情報がなく、全体像が全く見えず、それこそレギュレーションを全部読んで暗記しないと!と過剰反応していた」ということ。「けれど今まで行っていたことを丁寧に見直し、それを認証機関に伝えることで多くのことがクリアできた。僕的にGOTS認証を要約すると『トレーサビリティと社会性を適切に記録して、いつでも見ることができる仕組み作り』。皆が理解しやすく説明することも大切だった」と振り返る。「例えばトレーサビリティを担保するための記録作業は、各工場ですでに伝票を作っているので問題は発生しない。また、すでに各社が残業をなるべくしないように効率化しているため、残業や最低賃金の問題も発生しない。人権問題は国内事業で日本人を雇用しているケースが多いので問題になりにくい。個人経営者も多く、労務上の制限も少ないなど、クリアしやすかった」。
チーム内での変化も起きた。「若手のチームメンバーが、認証が下りたときに『やった!』と喜んでくれるなど、チーム一人ひとりが自分事化できている実感がある。メディアやインタビューに否定的だった工場も少しずつ前向きになり見学を受け入れている」。
一方、ハードルもある。「国内でGOTS認証の製品が普及していないため、GOTS認証を取得した染料や、漂白する際の添加剤や助剤がそろっていない。そのため、GOTS認証の製品を作ろうとすると、現状は無染色・無漂白の製品しかつくることができない。先日ようやく、脱色しやすくするためにアルカリ化する助剤の認可が下りた。これで白いTシャツを作ることができる。認証を取得してから特に海外からの問い合わせが増えていたが、生成りしかできないことがネックになっていた。GOTS認証に基づく漂白が行えるようになったのは大きな一歩だ。CSCSチームのV-TECさんでの試験を得て製品化していきたい。一つ一つ調べて発信し、相談していくことで徐々にさまざまな課題がクリアできて日本でのものつくりも進化していくのでは」。

三木健(みき・けん)/三恵メリヤス社長
PROFILE:1926年創業の三恵メリヤスの4代目。幼少期から町工場でお手伝いをしながら育つ。大学卒業後は、ニューヨーク、ロンドン、トロント、バンクーバーなど世界各国を拠点に事業を行う。14年三恵メリヤスに入社し服作りに携わり始める。世界に誇れる一生もののTシャツを提供したいと考え、2年の試行錯誤の末に着心地に徹底的にこだわったTシャツ「エイジ(EIJI)」を立ち上げる。「人生で最高の一枚を」届けるために日々服作りを行う
The post 大阪の町工場がGOTS認証取得 日本製GOTS製品の生産が可能に appeared first on WWDJAPAN.























































 「ミュウミュウ(MIU MIU)」は、2020年から始動したサステナブルプロジェクト“ミュウミュウ アップサイクル(MIU MIU UPCYCLED)”の第5弾を発売した。同プロジェクトは世界中のヴィンテージショップなどから厳選したアイテムを「ミュウ ミュウ」らしくリメイクしたコレクション。これまでドレスやドレスやレザージャケットなどを扱ってきた。その趣旨について同ブランドは「ヴィンテージウェアを称えるとともに、循環型ファッションをうながし、歴史や時代を超えた美しさに備わる価値が現在と未来を豊かにするものとして受け継がれる」と説明する。
「ミュウミュウ(MIU MIU)」は、2020年から始動したサステナブルプロジェクト“ミュウミュウ アップサイクル(MIU MIU UPCYCLED)”の第5弾を発売した。同プロジェクトは世界中のヴィンテージショップなどから厳選したアイテムを「ミュウ ミュウ」らしくリメイクしたコレクション。これまでドレスやドレスやレザージャケットなどを扱ってきた。その趣旨について同ブランドは「ヴィンテージウェアを称えるとともに、循環型ファッションをうながし、歴史や時代を超えた美しさに備わる価値が現在と未来を豊かにするものとして受け継がれる」と説明する。
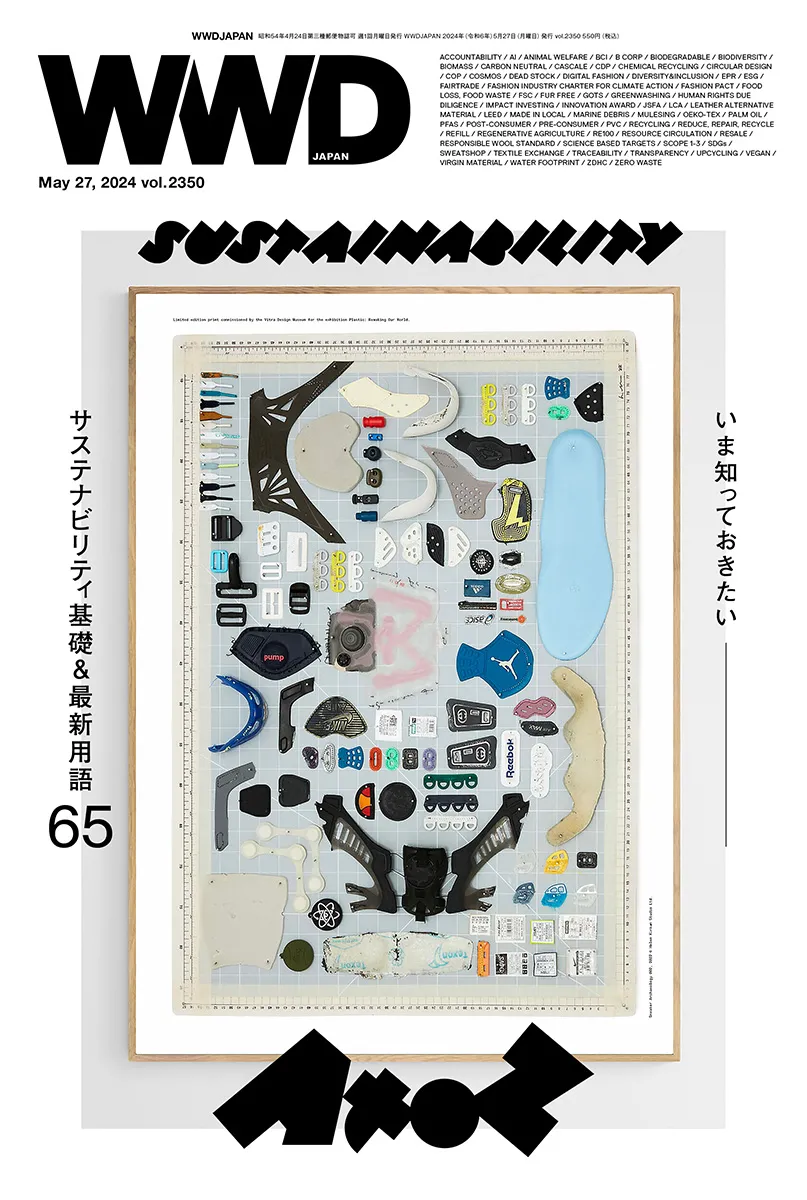
































 経済産業省は、次世代ファッションクリエイター育成を目的にした補助事業「みらいのファッション人材育成プログラム」を実施し、26日から公募を開始した。同プログラムは、プログラムパートナーによる持続可能なサプライチェーン構築に向けた実践的な教育機会の提供、事業創出支援を通じ、未来のファッション産業を担う卓越人材育成事業を行う。
経済産業省は、次世代ファッションクリエイター育成を目的にした補助事業「みらいのファッション人材育成プログラム」を実施し、26日から公募を開始した。同プログラムは、プログラムパートナーによる持続可能なサプライチェーン構築に向けた実践的な教育機会の提供、事業創出支援を通じ、未来のファッション産業を担う卓越人材育成事業を行う。