ネパール国内では経済成長を促すような産業が育っていないため、働き盛りの若者の多くは海外に出ます。日本でも最近は技能実習生の出稼ぎをはじめ、ネパール人の在留者数が増加(日本におけるネパール人労働者数は2022年10月に12万人近くになり、前年比で約20%増加)。もしかすると、職場など身近なところで彼らに接する機会があるかもしれません。そこで、ネパール在住のジャーナリストが、現地で知ったネパール人の国民性や思考パターンを説明します。
多民族国家だからこそ

ネパールは約125の民族が共生する多民族国家であるため、一言で国民性を表すのは容易ではありません。
日本人は出身地が異なっていても同じ日本語を話し、共通する文化的な価値観を持っています。ところが、ネパールでは一応ネパール語を共通語として用いるものの、民族ごとに言語が異なり、家族の中ではそれぞれの民族語が話されます。民族によって宗教、祝日、習慣がまったく異なり、容姿もインド系、アジア系、ヨーロッパ系とさまざまです。
そのような環境で育ったネパール人は、自分と異なる環境で育った人に抵抗感を持たずに接することができる柔軟さを有しています。それぞれの価値観を尊重し、他人の個性や発言を寛容に受け入れる人が多いのです。その分ストレスを溜めにくいという長所もあるでしょう。
このように、おおらかな思考パターンが特徴である故に、日本でもネパール人は思ったことを何でも口に出したり勝手に行動したりしてしまうかもしれません。言動がストレート過ぎてトラブルに発展してしまう可能性もありますが、彼らの育った環境を理解していれば、日本人の国民性や慣習を丁寧に伝えることで良い関係を築けることでしょう。
責任を回避しがちな理由

ネパール人を理解するうえで欠かせない、もう1つの考え方は、「負わなくてもよい責任はとことん回避して自分を守る」こと。無責任なように聞こえますが、これはネパールという国を理解すると納得できます。
ネパールは南アジアの最貧国であり、植民地になった歴史がないため良くも悪くも外国からの影響や支援が遅れています。いまだに停電は日常茶飯事で、雨が降れば脆弱な下水道施設から水が溢れ、外出などままならない状況になります。
先進国のインフラが整った国で生活しているとほとんど感じない人間の無力さを、ネパールでは日々痛感します。そのような不測の事態が頻発する国で、約束を守ったり、責任を最後まで全うしたりするのは大変困難といえるでしょう。
約束を果たせなかった言い訳が無数に存在するので、約束を破られた側も一方的に怒ることはできません。なぜなら、いつ自分が不測の事態で約束を破る側になるか分からないからです。このような社会的背景があるため、ネパール人はよく言い訳をしますし、相手もある程度はその言い訳を受け入れるのです。
このように、ネパール人の柔軟かつ寛容な性格や思考パターンを理解すれば、貴重な労働力として活躍している彼らと不要なトラブルを避けることができるでしょう。一方で、来日したネパール人は、日本人の勤勉さや時間厳守を徹底する姿勢に感銘を受けているようです。ネパール人に限らず、どの国の人であっても、互いの国民性の長所を認めて尊重し合う関係性を築いていきたいものです。
執筆・撮影/延原 智己







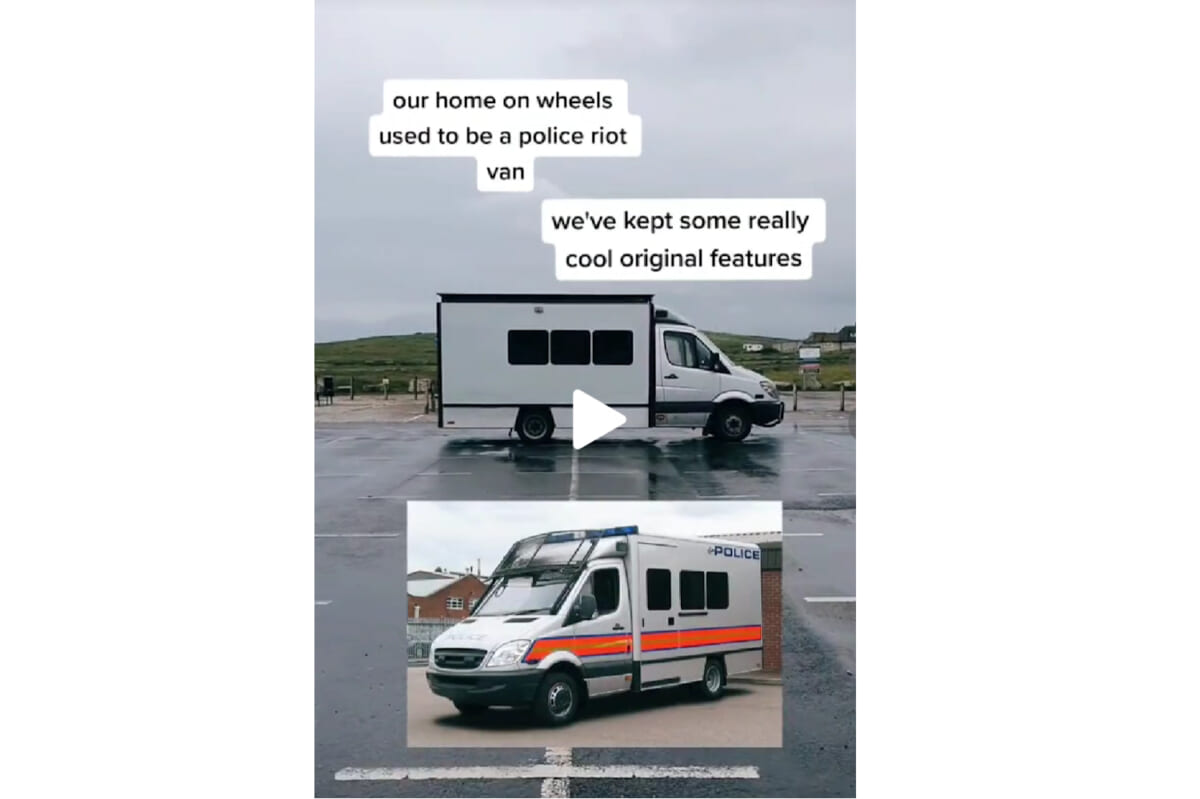
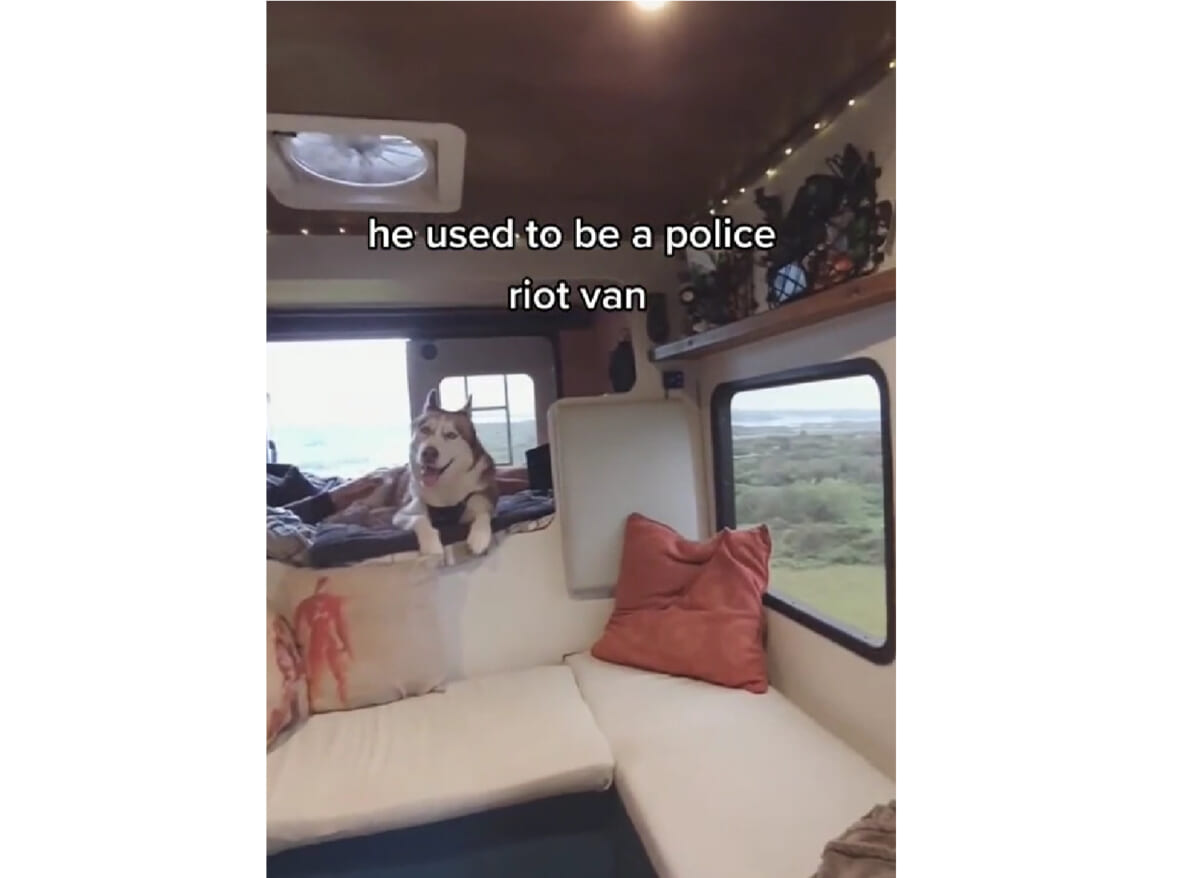














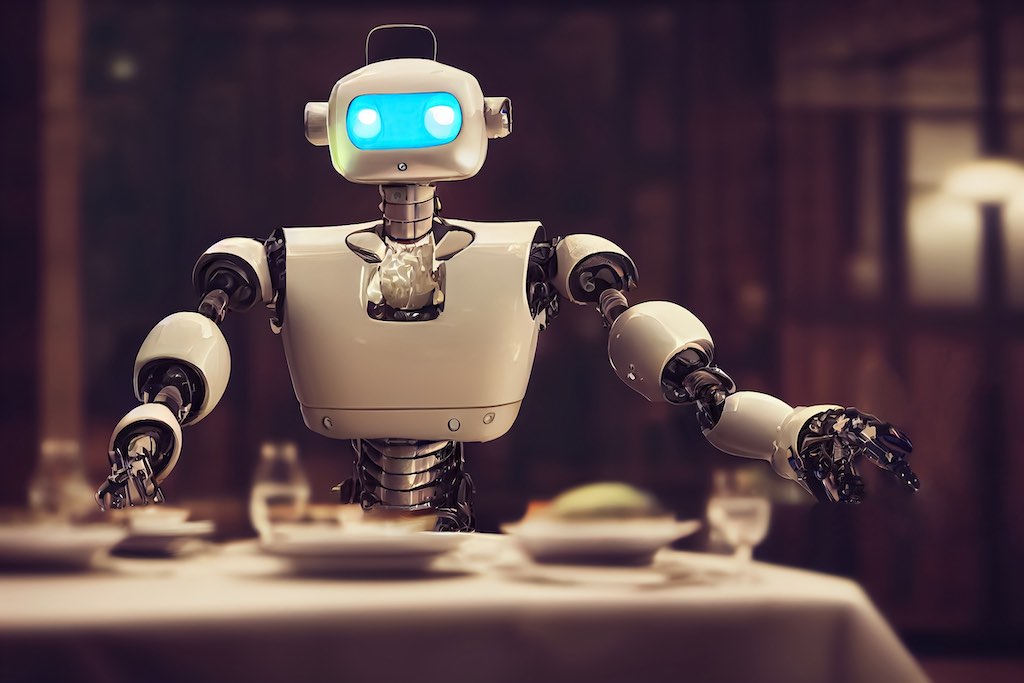
















 ︎ (@EGaraad_)
︎ (@EGaraad_) 








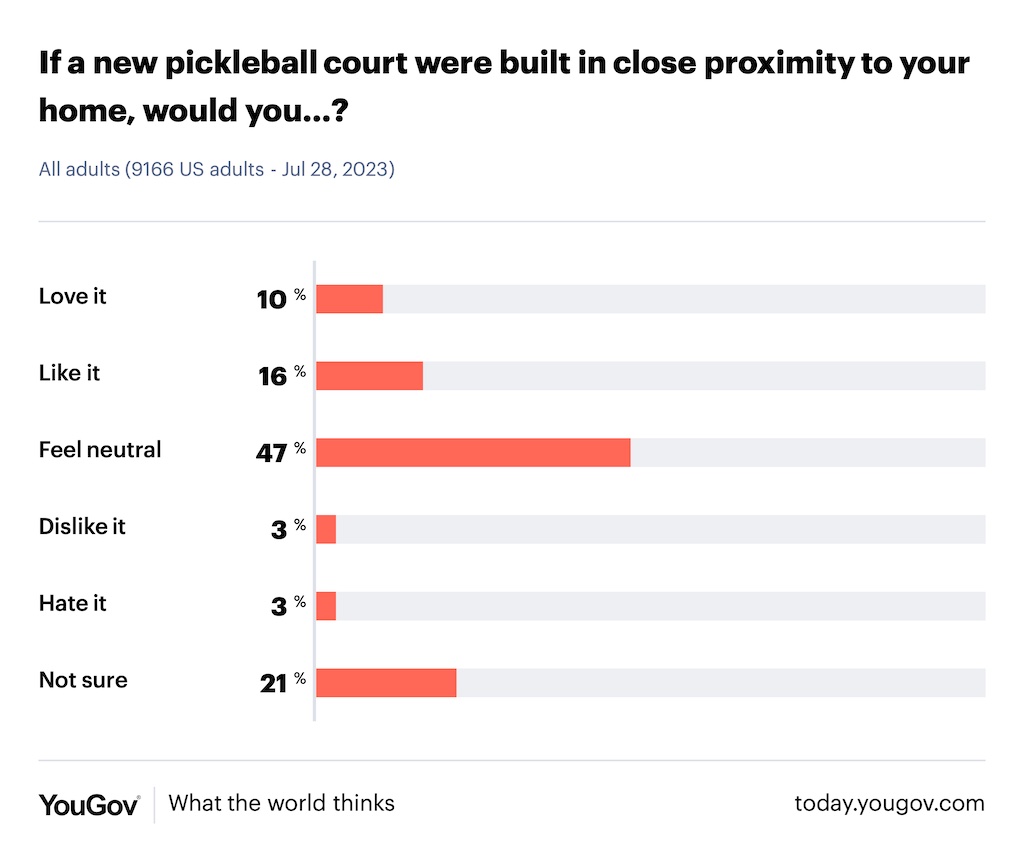







 /
/ (@onceuponasaga)
(@onceuponasaga)



































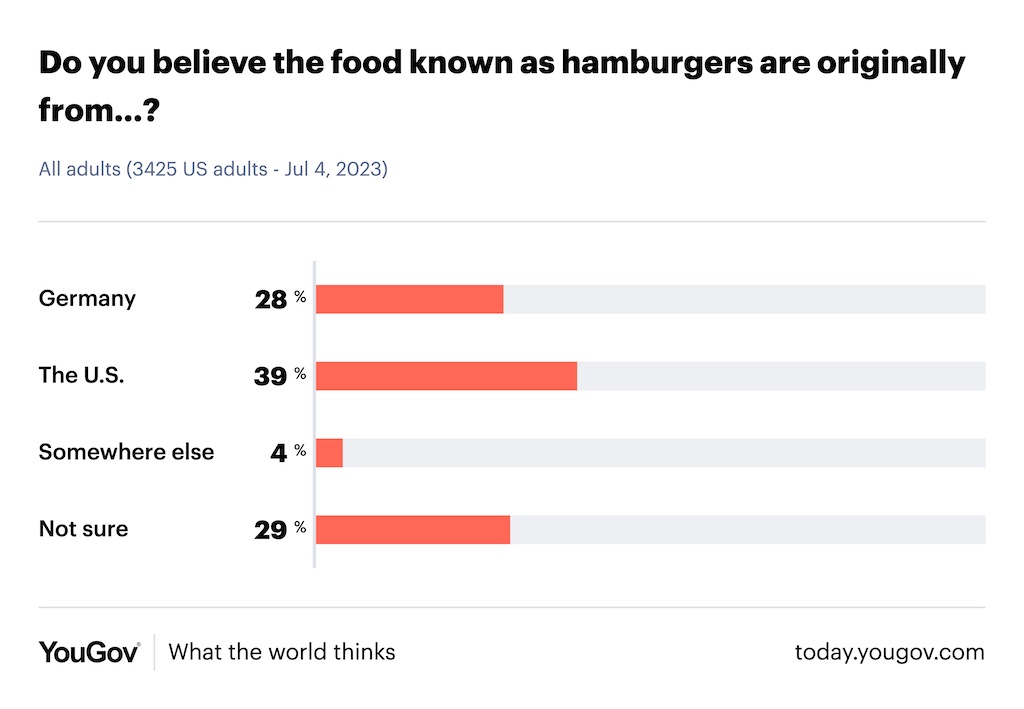
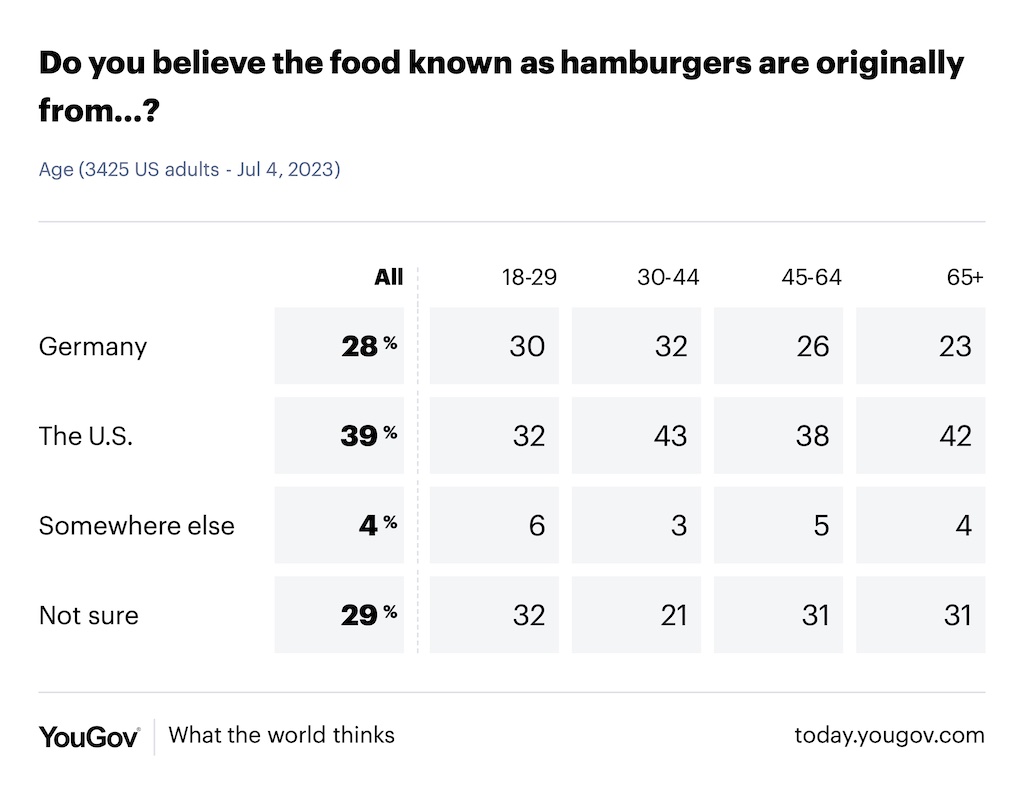


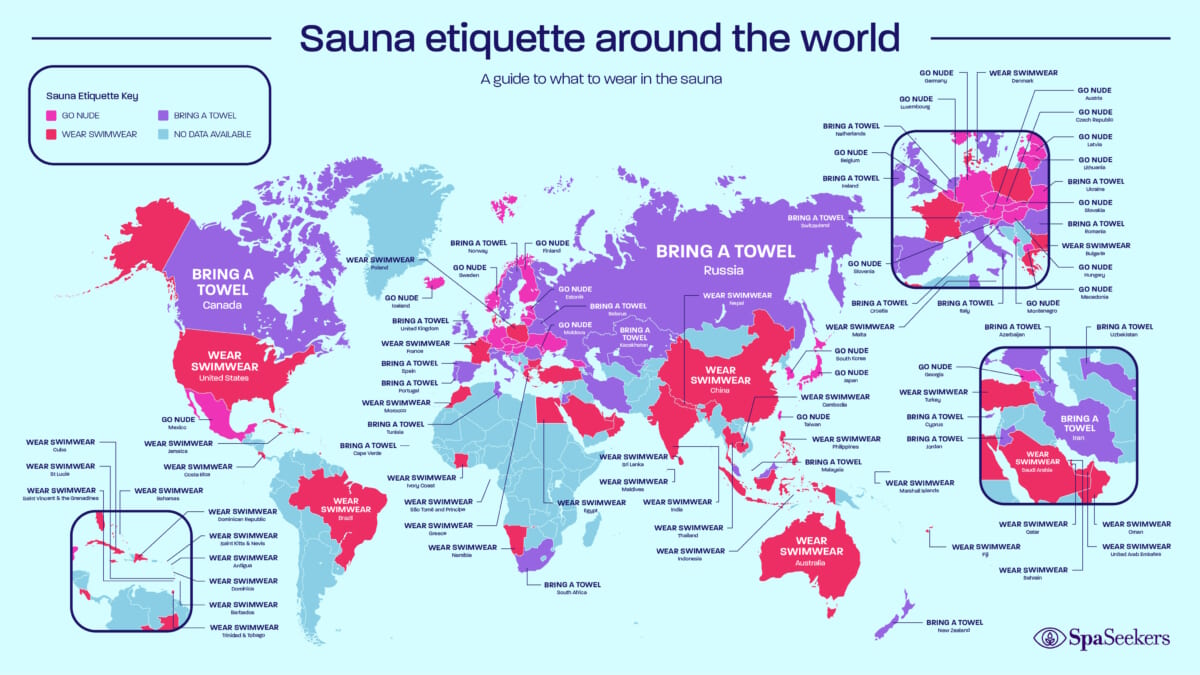





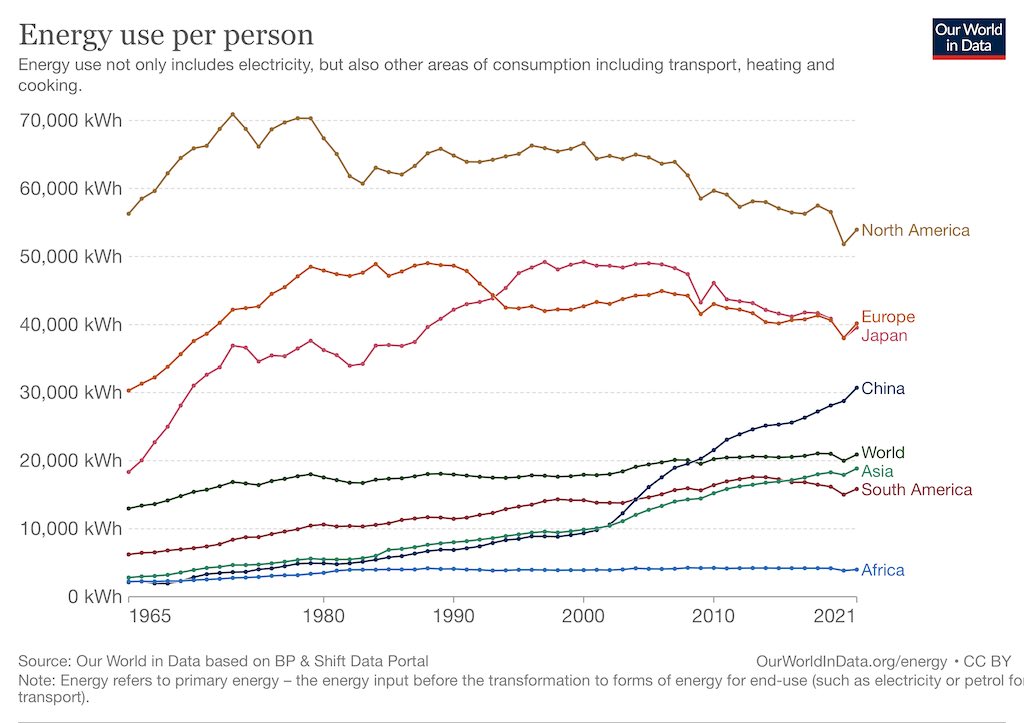

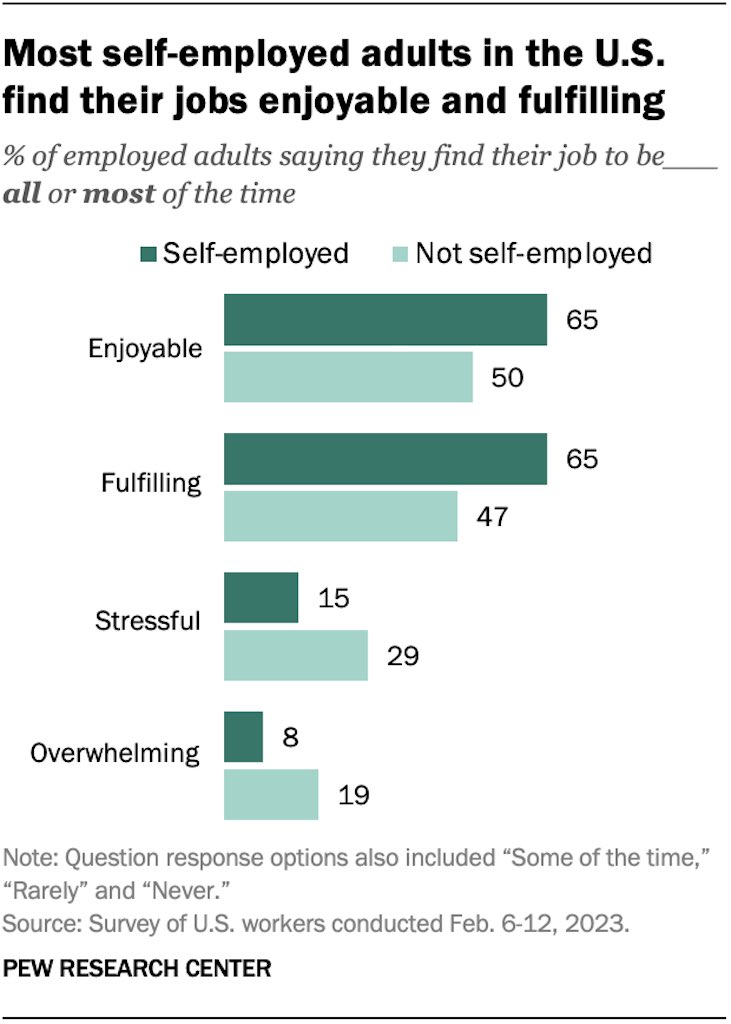
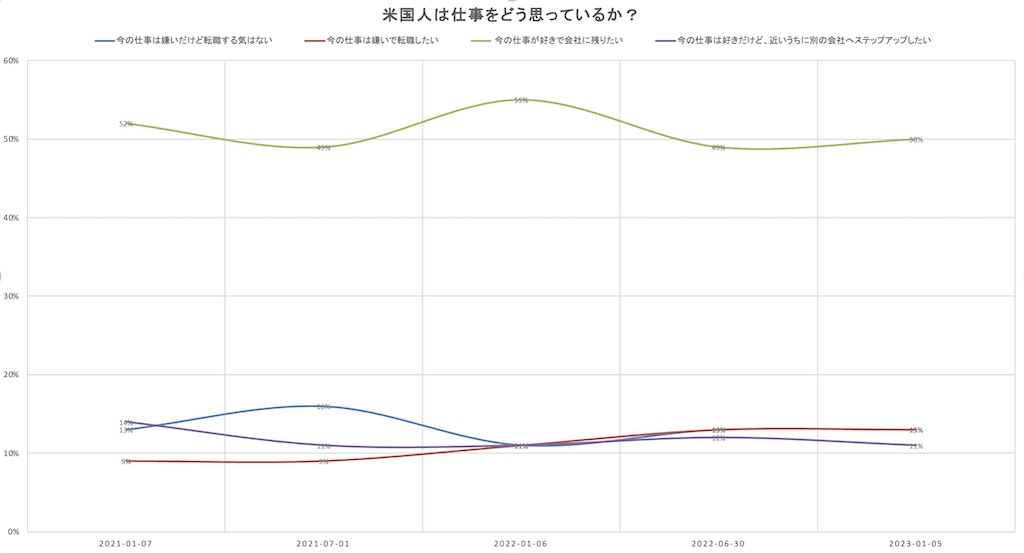
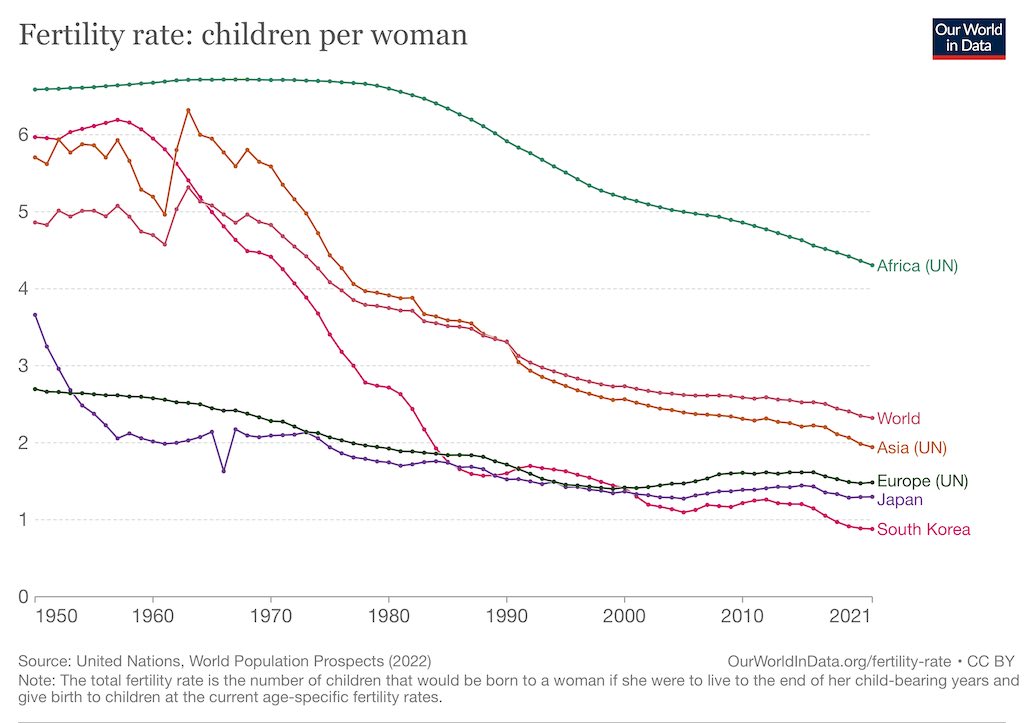

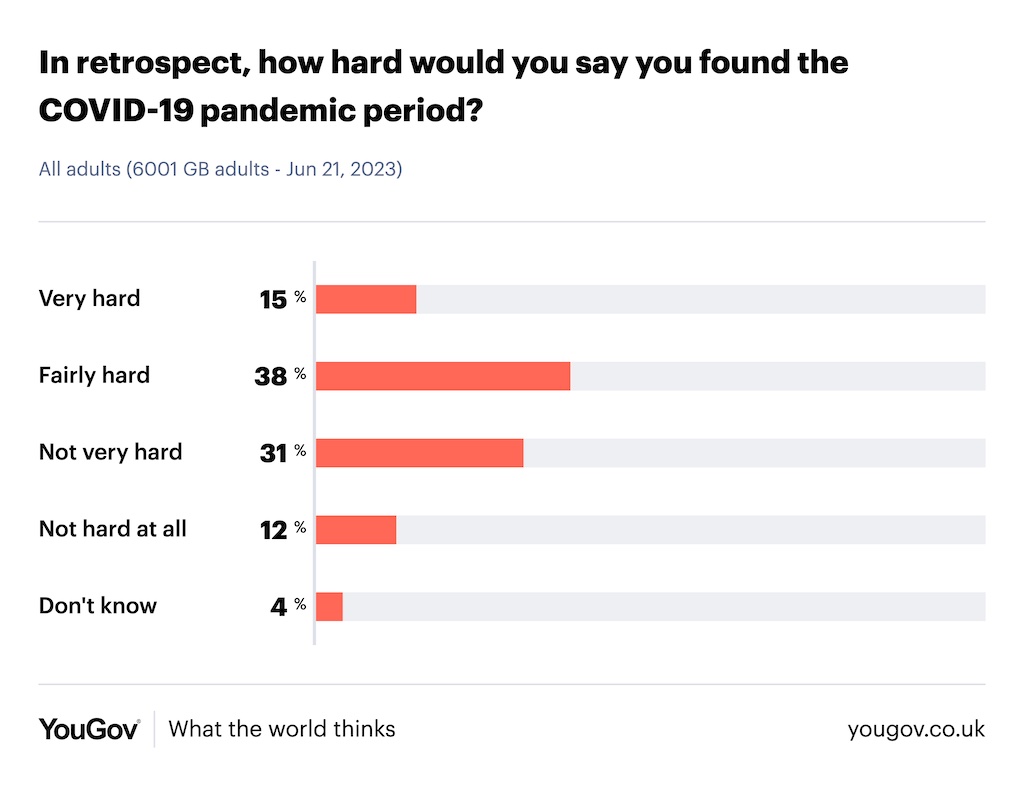
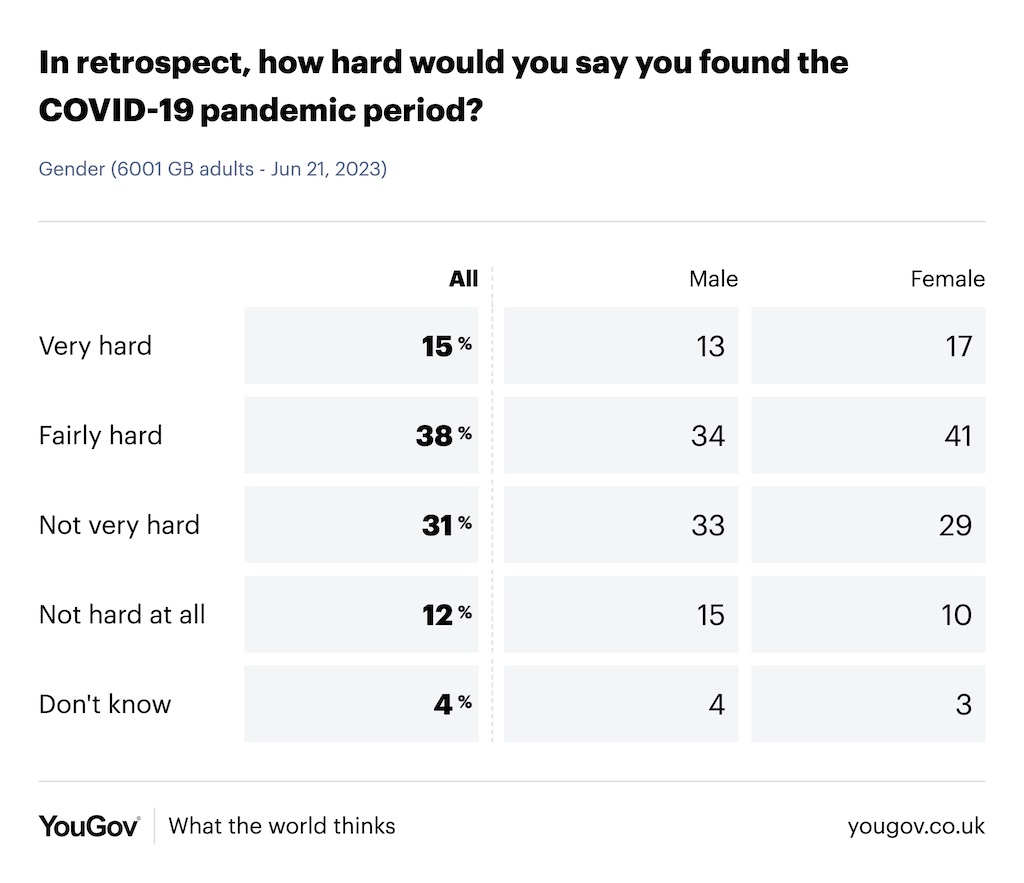
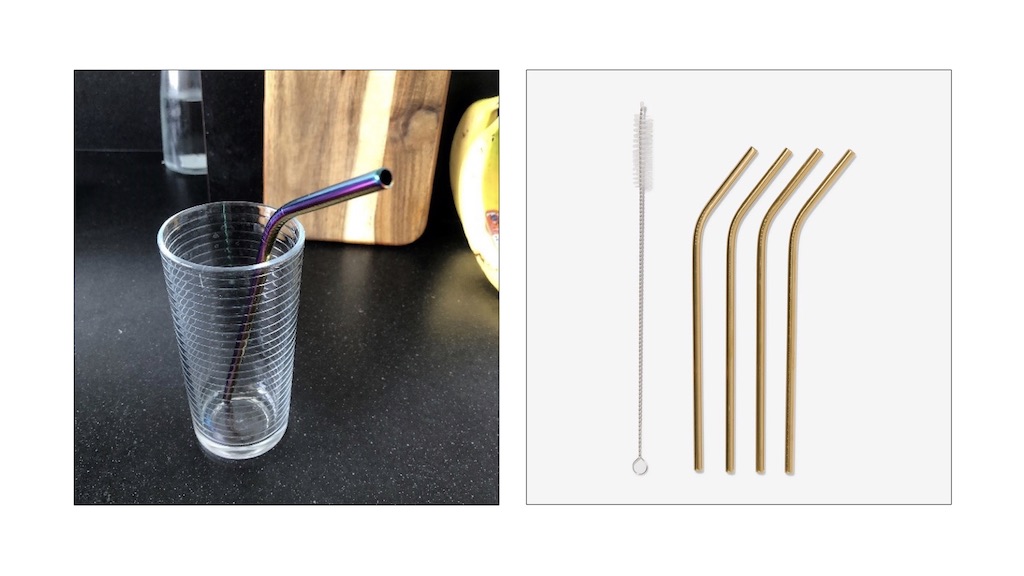


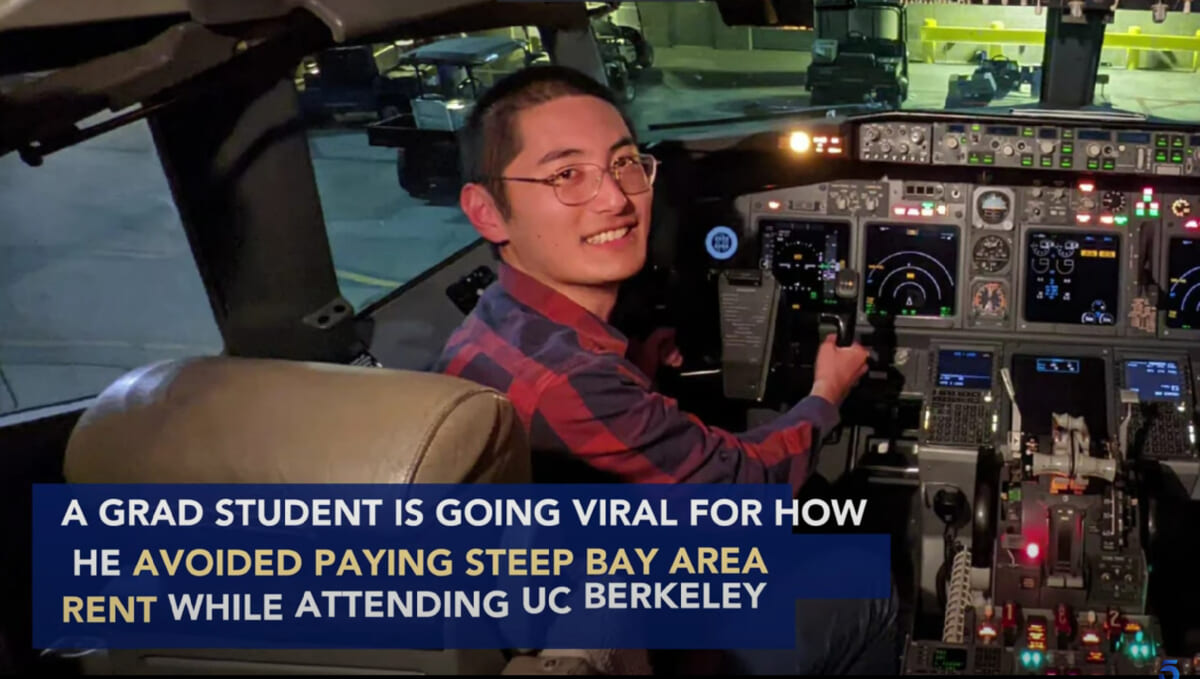

 思わずギョッとしてしまうこのラーメンは、その名も「ゴジララーメン」。台湾にあるレストランで登場して、話題になっています。
思わずギョッとしてしまうこのラーメンは、その名も「ゴジララーメン」。台湾にあるレストランで登場して、話題になっています。














