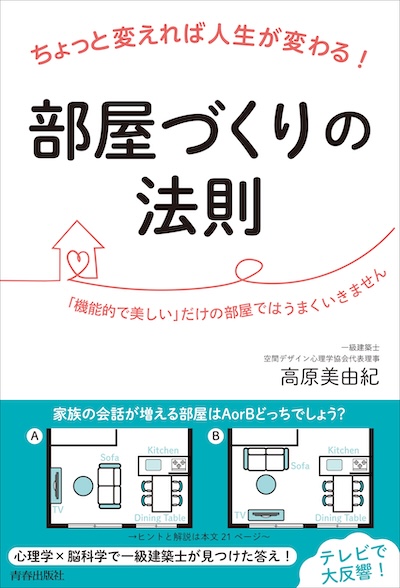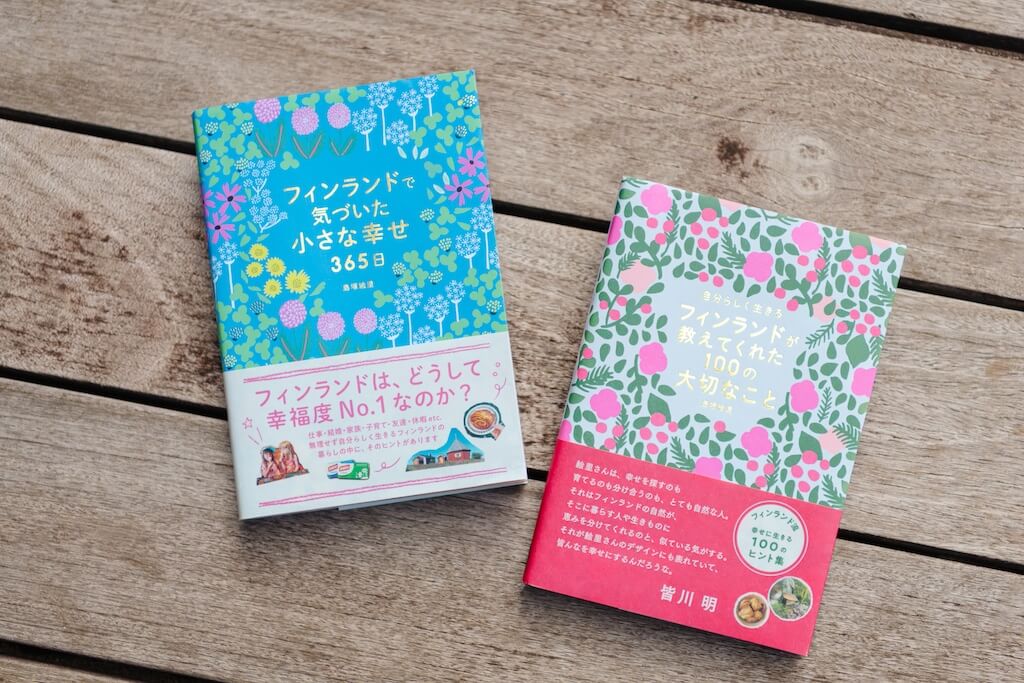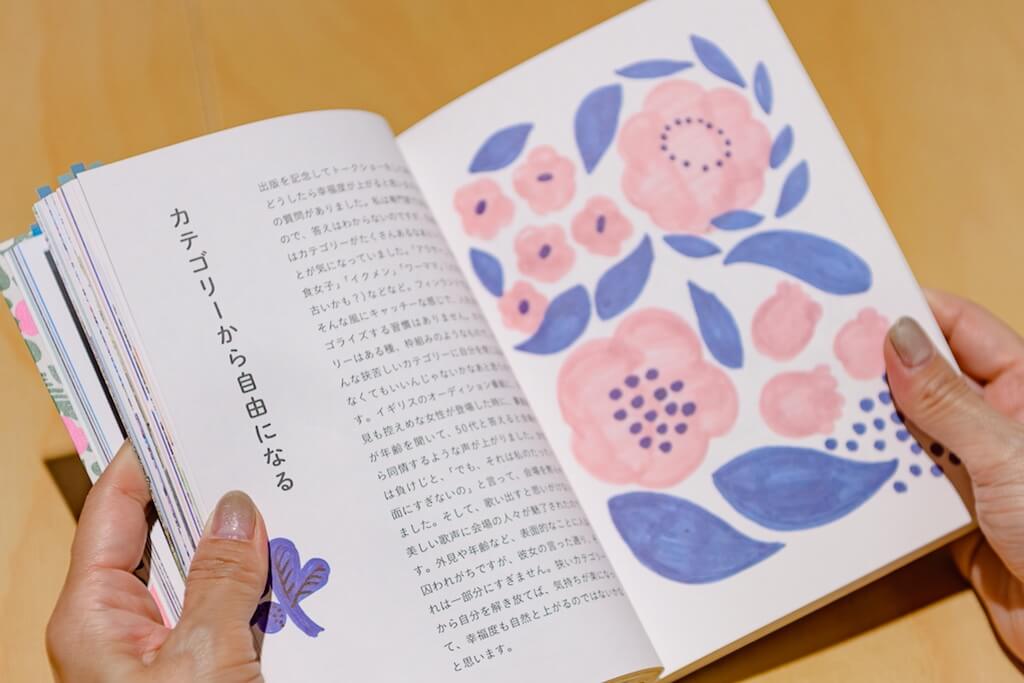日々、仕事に追われている人は多いでしょう。細々としたタスクが多いせいで使う時間も細切れになり、“今やるべきこと”に集中するのがむずかしくなっているのでは?
気持ちに余裕をもってマインドフルな時間を過ごすには、いま住んでいる部屋の環境を見直すことで解決策が見つかるかもしれません。そんなマインドフルネスの概念を取り入れた部屋作りのコツを、一般社団法人空間デザイン心理学協会代表理事の高原美由紀さんに教えていただきました。
マインドフルな状態=マインドフルネスとは?

瞑想などによってマインドフルネスを日常に取り入れると、心を落ち着かせたり思考をリセットできたり、集中力が高まったりという効果があるとされています。まずは、この「マインドフルネス(mindfulness)」とはなにか、“マインドフルな状態”とはどういったものか、確認しておきましょう。
「マインドフルな状態とは、過去や未来に向きがちな意識を手放し、『意識を今に向けている状態』のこと。過去や未来に対して抱く不安や雑念をいったん切り離して、今に意識を持ってくることが大切とされています」(一般社団法人空間デザイン心理学協会代表理事 高原美由紀さん、以下同)
もちろん、感じる“今”の気持ちがいつでもハッピーなわけではありません。
「その時に感じる気持ちが、たとえ“悲しみ”や“苦しみ”といったネガティブなものであっても、無理に『ポジティブな気持ちにならなければ』と思う必要はありません。ただ客観的に“今”を見つめて、『今、悲しみがあるのだな』と『自分の感情や思考』に気づいたら、また手放していく、その繰り返しがマインドフルネスなのです」
とはいえ、悲しさや苦しさが心にあると、早く解決したくなってしまうもの。こうした気持ちはどのように落ち着かせればいいのでしょうか?
「例えば今、苦しい気持ちがあったとすると、そんな気持ちを押さえつけて、何とか前向きになろうとしますが、それは逆効果。かえって苦しい気持ちが大きくなってしまうのです。
まずは、『頑張らないでありのままの自分を受け入れる』こと。そのときに、『自分の状況を俯瞰して見つめること』が大事です。そうすることで、苦しい気持ちが次第に落ち着いていき、解決策を見出すことができます」
自然や視覚情報にも気を配る
マインドフルな住環境の条件
ただし、マインドフルな状態になるには、落ち着ける環境を作り出すことも重要。その条件とはどういったものでしょうか?
1.自然に触れられる環境であること

「まず、『自然に触れられること』が大事です。窓から良い景色が見える、緑や空が見えるといった環境が理想的です。家の中に観葉植物などを置いて、自然に触れられる環境を作り出すのもおすすめです」
2.物が片付き視覚からインプットされる情報が少ないこと

「次に、『視覚情報を少なくする』こと。全体的にすっきり片付いている状態がのぞましいですが、それが難しければ、部屋の一部だけでも物が少ない場所を設けてみるといいでしょう。そちらの方に視線を向けて過ごすことでも、マインドフルな状態が作りやすくなります。
ただし、必要なもの以外は配置しない“ミニマル”な状態だけが良いのではなく、自分が気に入っているものだけを視界に入るようにするメリハリが大事です」
3.散らかりにくく動線が確保されていること
「また、片付けと関連して、『散らかりにくく、動きやすい環境を作ること』も大切です。生活空間の中にある余計なストレスを減らすことで、マインドフルネスに繋がりやすくなるのです。片付けがどうしても苦手な方は、日々の生活の中で自分がいつも通る場所に収納場所を多く作るといいでしょう」
ほかに、日当たりや通気の良し悪しもマインドフルネスに影響するとのこと。もし、転居を検討していたら、住環境としてネガティブな要素が少ない部屋を探してみてください。
部屋作りに取り入れたい、
マインドフルなインテリアの条件
マインドフルな住環境の条件を踏まえ、部屋に取り入れたいマインドフルなインテリアについても具体的に教えていただきました。
・アースカラーを基調とした色合い

「人肌の色に近いベージュやアースカラーを、面積が大きい部分に取り入れるといいでしょう。例えばテーブルやソファのような大きい家具や、ラグ、カーテンなど。緑や空色などの落ち着いた色合いのものならアクセント的に壁紙やカーテンに使うのもいいでしょう」
一方、オレンジや赤のような濃くて明るい色が好きなら?
「クッションやランチョンマット、テーブルクロスのような小物類で取り入れるのがおすすめです。部屋のベースの色としては、アースカラーを基調とした色にまとめておいた方が、落ち着いた気持ちで過ごせます」
・副交感神経を高め体をリラックスさせる照明
「夕方から夜間の時間帯に用いる照明は、低い位置で赤みのあるランプを選びましょう。まぶしい光源が直接目に入らないよう、光を壁にあてるなどして優しい光にしてください。
夕方以降の時間帯に強い青白い光が目に入ると、交感神経が高まってリラックスしづらくなります。そのため、夜になるにつれて赤く暗い光に調光できる照明器具を選ぶといいでしょう。そうして副交感神経を高め、体がリラックスできる環境を作ってあげると、落ち着けてマインドフルネスになりやすいのです」
また、持ち運びのできるランプがあれば、落ち着ける場所や好きな場所に持って行って、マインドフルな時間を持つことができそうです。

・触感に意識を向けられるファブリックや家具
「現代人はとても忙しいですよね。スマートフォンのおかげで目から入る情報量も多いし、日々こなさなければならないタスクもたくさんあります。そうしたときに、触感に意識を向けられる環境があると、体から伝わる感覚を通して、今に意識を引き戻すことができるのです。
例えば、カーペットやラグ、玄関マットなどをふかふかで肌触りの良いものや、麻のような自然素材にすると、触感を意識しやすくなります。床材が無垢材や畳の部屋なら、そこを歩くだけでも効果がありますよ」

「触感を意識するという意味で、テーブルや座椅子なども、自然素材のものを取り入れてみるといいでしょう。テーブルの天板は無垢材を使ったものにする、座椅子にはふかふかのクッションを置く、という形で取り入れてみてください」
・ゆったりとした気分で過ごせる椅子やハンモック
マインドフルな気分になれる家具を取り入れるなら、ロッキングチェアやハンモック、パーソナルチェアなどもおすすめだそう。
「揺れる感覚を得られる、ハンモックやロッキングチェア。ゆったり揺れて過ごすことで、いったん仕事やタスクに向けていた思考を手放すことができますし、リラックス効果につながると思います。
たとえばアルネ・ヤコブセンがデザインした『エッグチェア』のような、頭まですっぽり包み込まれるようなデザインの椅子もいいですね。余計な視覚情報が入ってこないので、落ち着いて過ごすにはぴったりです」

・テレワークをしている部屋には気分を切り替えられる小物

自室でテレワークをしていると、オンとオフの切り替えが難しくなりがちです。その解決には、作業スペースを別にする手段が有効だそう。
「作業スペースと食事をするテーブルは別であることが好ましいです。このテーブルでは仕事をする、この場所では食事をするというように、場所の意味づけを行動とセットにして決めておくと、気分のリセットができますよ」
ただ、部屋の広さなどの都合上、どうしても仕事と食事をするスペースが一緒になってしまう場合、自分の中でリセットサインを設定するのも効果があるそう。たとえば、仕事の時はデスクランプを点けておき、仕事終わりにはランプを消して仕事道具を片付ける、食事の場合にはランチョンマットを敷くといったことが挙げられます。こうした小物を活用した取り組みなら、すぐに実践できそうです。
日々の暮らしのなかでも
マインドフルは実践できる
これまで、住環境やインテリアの整え方としてのマインドフルネスについて伺ってきました。高原さんは「日々の生活の中でもマインドフルネスを作り出すことができる」と言います。
「お皿洗いや歯磨き、お風呂に入って髪を洗うといった日常の動作も、実はマインドフルな体験につながるのです。たとえばお皿洗いは、水に触れたり指先を動かしたりして、手の触感を意識しやすい動作です。また、歯磨きであれば、歯ブラシが歯茎などに触れることでで、口の中の感覚に意識を向けやすくなります。
普段こうした日常動作に面倒くささを感じている方は、自分の感覚に意識を向ける時間と考えて、取り組んでみるとよいでしょう。思考がリセットされて脳の処理がいったんストップし、マインドフルネスにつなげることができます」
マインドフルな状態を意識して過ごすことで、ストレスが減り、睡眠改善や体調にもよい影響が期待できるそう。まずはマインドフルな部屋に整えることから始めましょう。
Profile

一般社団法人空間デザイン心理学協会代表理事 / 高原美由紀
有限会社カサゴラコーポレーション一級建築事務所代表取締役。空間デザイン歴30年、指導歴25年以上。累計1万件以上の間取り指導実績を持つ一級建築士。心理学・脳科学・行動科学・生態学など科学的根拠をもった空間づくりの法則を「空間デザイン心理学(R)」として体系化した。そこで過ごしているだけで自然に幸せになる「人生を応援する空間づくり」を伝えるべく、講座やセミナーなどを多数開催。世界中の人が、愛と輝きで満たされる居場所をもつことをミッションに、「幸せな人生と空間」を伝える活動している。