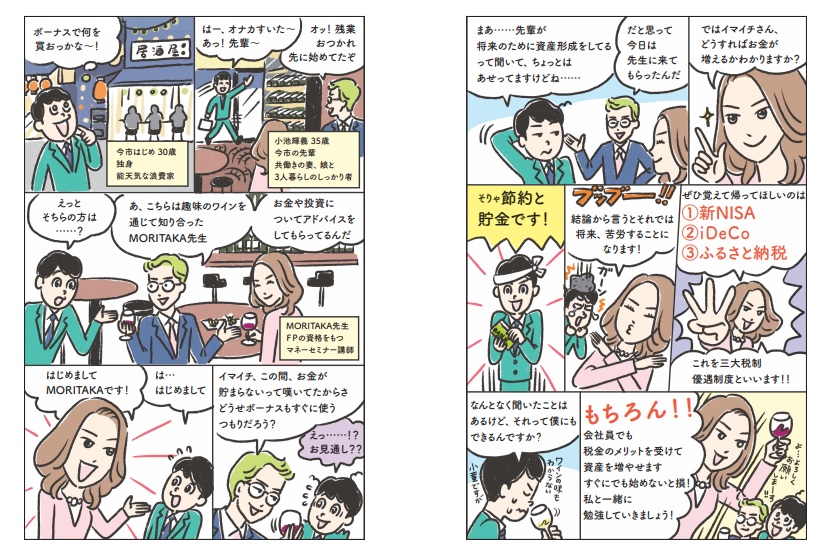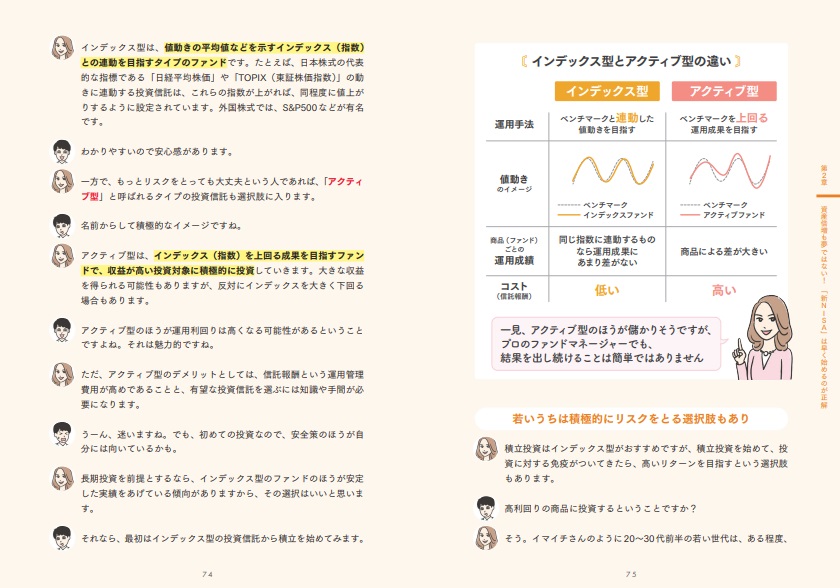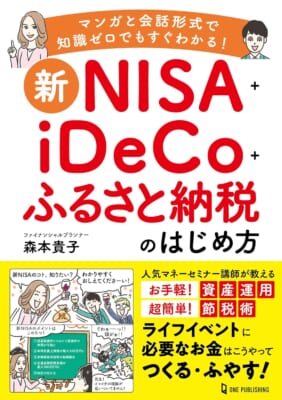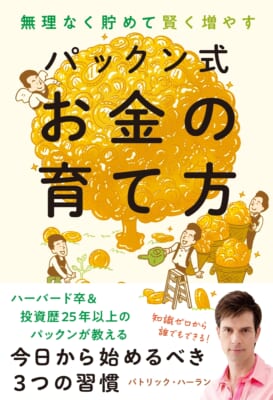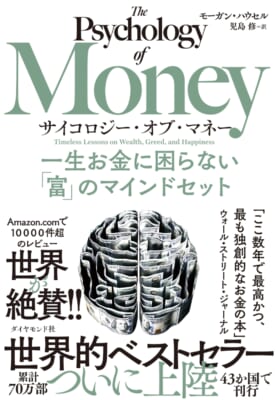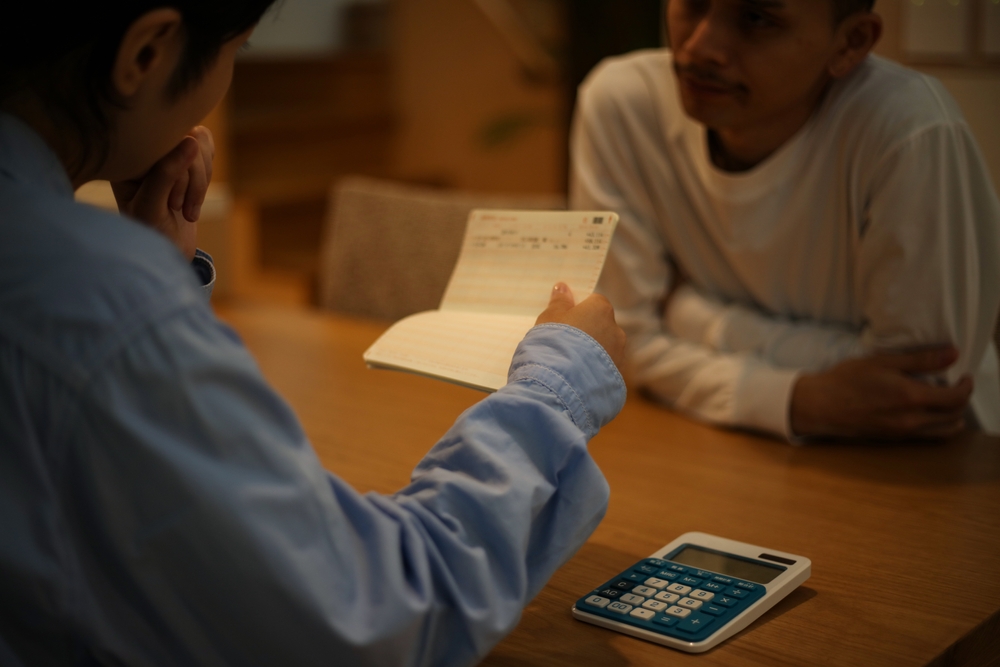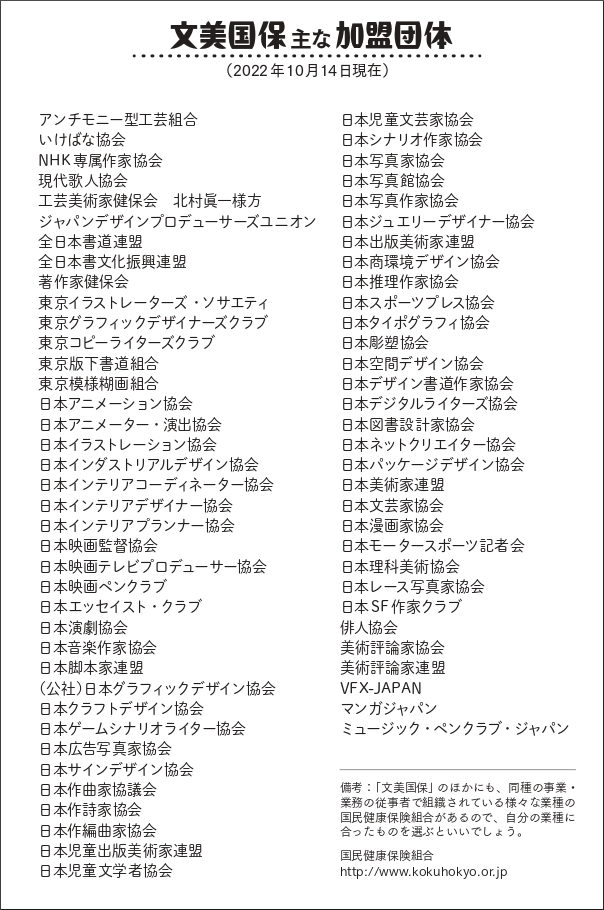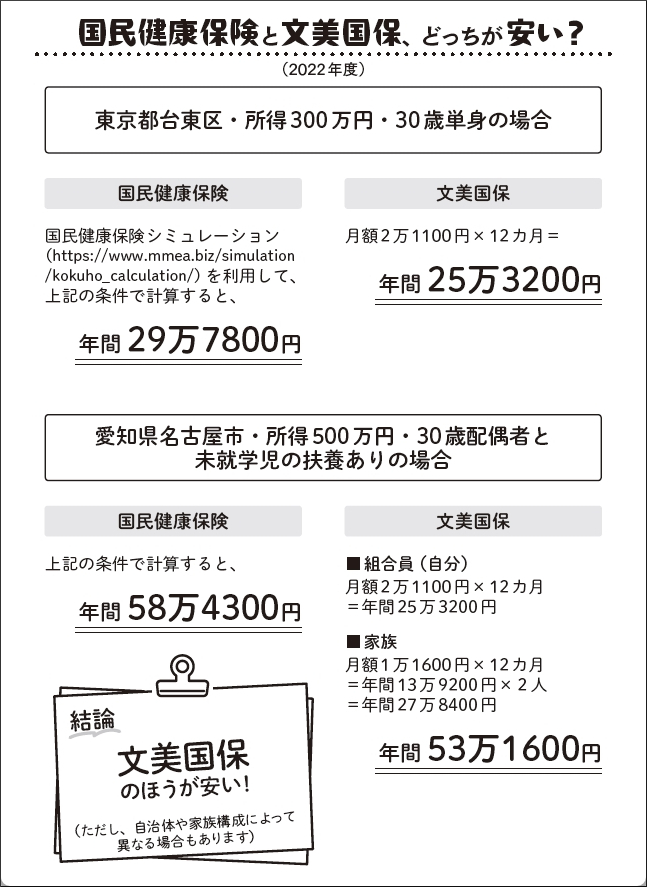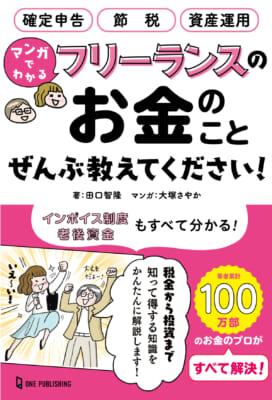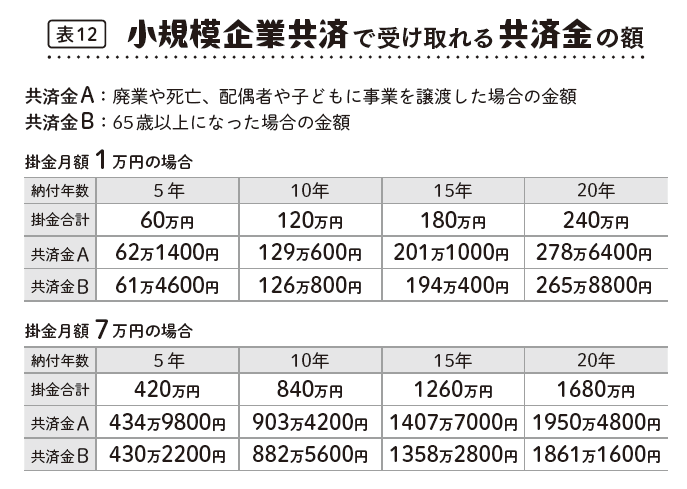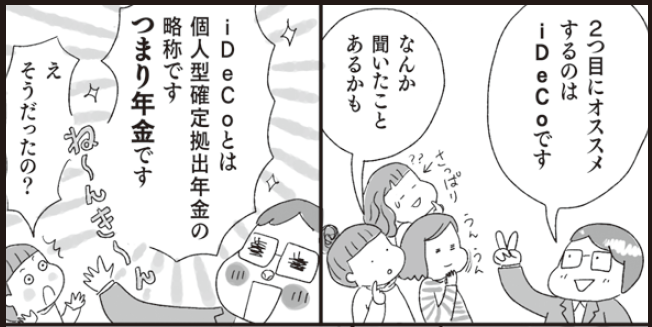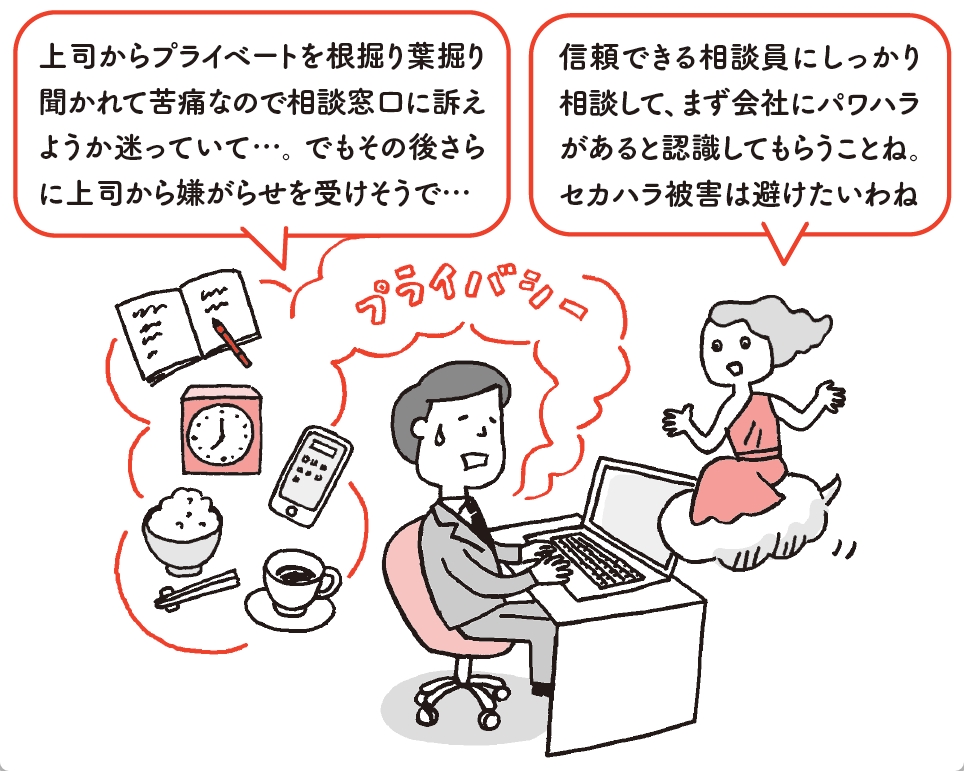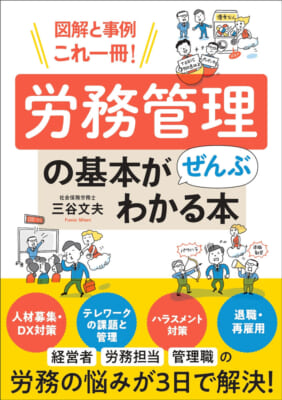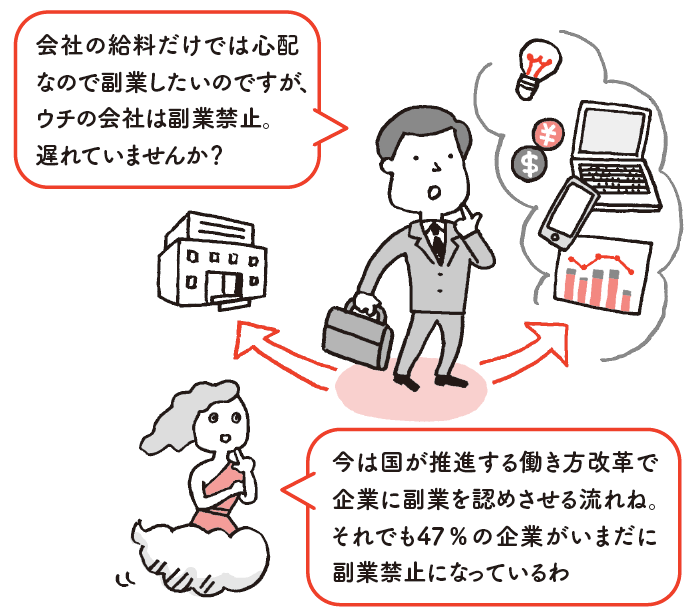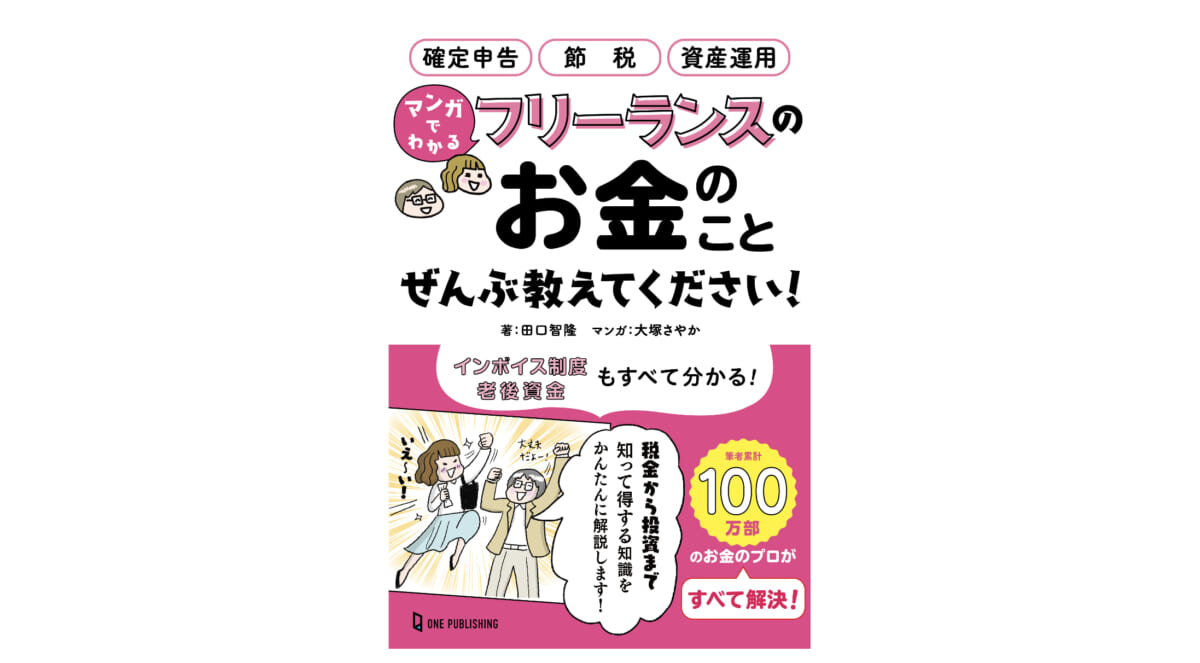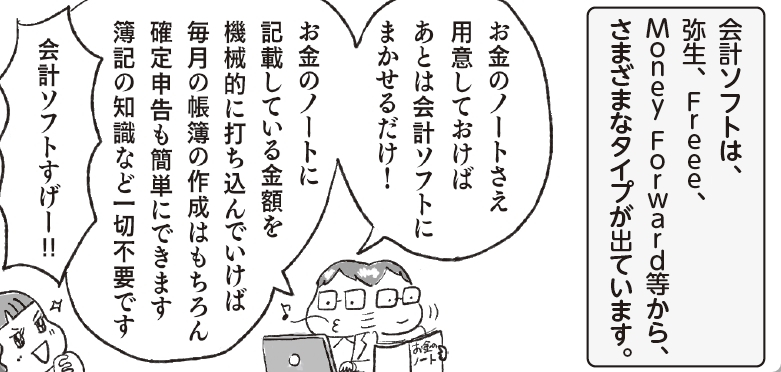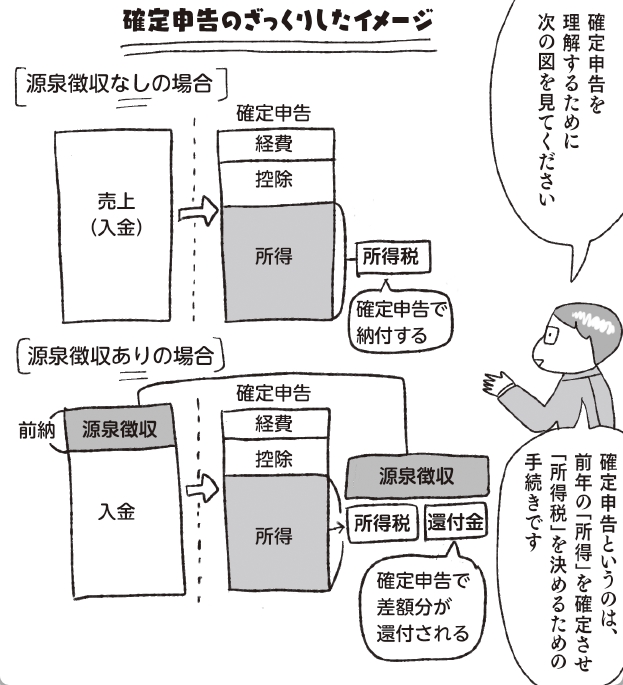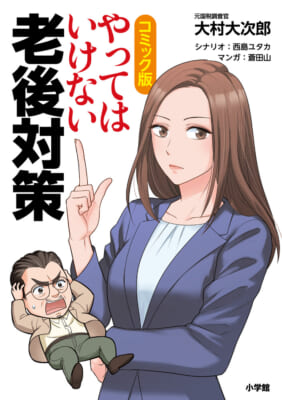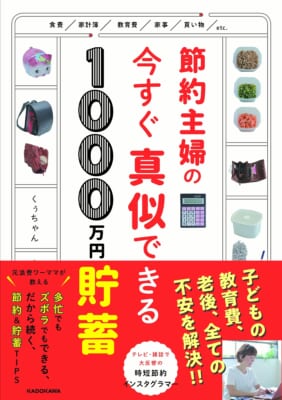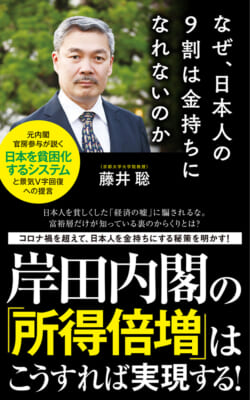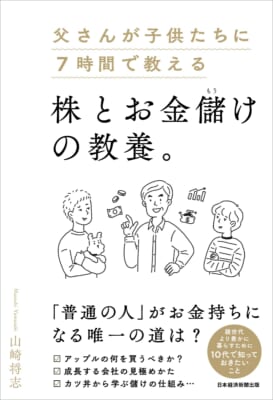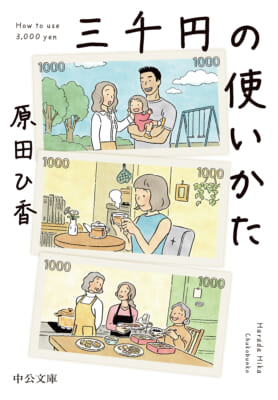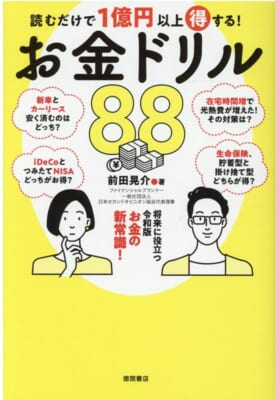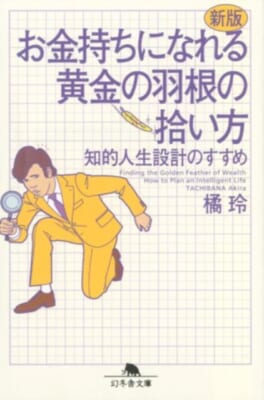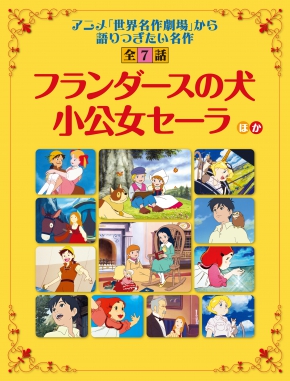株式投資を始めてからもうすぐ4年になる。ただ銀行口座に置いておくよりも、お金との関係性が積極的になると感じたからだ。
筆者はスイングトレード派です
でも、優良株を買ってずっと持ち続けるだけの長期保有という王道的な方法はちょっと性格的に合わない。かと言って、毎日チャートを何時間も見続けなければならないデイトレードはライフスタイルに合わない。そこで筆者が選んだのが、2~3日から数週間で売買を完結するスイングトレードという方法だ。
奥さんと一緒に始めたのでお互いに情報交換しながら、それなりに利益を出した時期もある。そもそもの目的が「1週間分の晩御飯のおかず代」を稼ぎ出すというレベルだったので、プレッシャーは一切なかった。入り口としては正しかったと思う。
推し感覚銘柄
筆者は、銘柄を“推し”の感覚で選ぶことにしている。大好きな腕時計を作っている会社。昔通っていたジムの経営母体となっている会社。使い勝手のいいサイトを運営している会社など、業績とか経営実績も大切なのだが、皮膚感覚でのシンパシーが重要な要素になると思う。こういう気持があると、消極的で速すぎる損切り行動を防げる。ここまでは、筆者の体験的な話。
ここからは、ギアがぐっと上がった世界の話になる。“億り人”という言葉をご存知の方はたくさんいらっしゃると思う。投資によって資産が1億円を超えた人たちだ。しかし、実際に億り人と会ったことがあるという人はそういないのではないか。『1年で億り人になる』(戸塚真由子・著/サンマーク出版・刊)で語られる世界と筆者の投資体験を比較するなら、メジャーリーグの常勝チームと立ち上げたばかりの草野球チームくらいの差がある。ただ、たとえレベルが草野球であっても、いや、それだからこそメジャーのマインドを学ぶことが大切なはずだ。
億り人のマインドセットを作る
章立てを見てみよう。
第1章 常識から逸脱せよ
第2章 人も時間も容赦なく見極めろ
第3章 お金集めを躊躇するな
第4章 「現物」に投資せよ
第5章 詐欺師を警戒せよ
第6章 日常をリセットせよ
第7章 誰よりもお金持ちに憧れて
この本のエッセンスをひと言で表現するなら、「億り人のマインドセット設定法」ということになると思う。著者の戸塚氏によれば、“資産のケタが違うお金持ち”に共通する行動は以下のようになる。
・彼らは絶対に、「自分が年間いくら稼いでいるか」なんて公言しません。
・彼らは絶対に、「高そうで派手な服」なんて着ていません。
・彼らは絶対に、「ゼロからコツコツ稼ぐ」なんてことはしません。
・彼らは絶対に、「ギャンブルのようなバカな投資」なんてしません。
・彼らは絶対に、「銀行にただ定期預金する」なんてことはしません。
『1年で億り人になる』より引用
章立てを見直していただきたい。「お金持ちの思想」「お金持ちの習慣」「お金の集め方」「お金の増やし方」「お金の守り方」「お金持ちの日常」「私が億り人になるまで」という流れになっている。
破壊力抜群の現物投資
実際の方法論は、すでにまえがきで触れられる。
本書で紹介するのは現物投資という、シンプルにしてとんでもない破壊力を持った投資法です。「ケタ違いの資産家」の近くで、私は実際に見てきました。それは決して特別なものではありませんでした。けれど、ふつうに生活していたのでは、この「現物投資」には、決して乗り越えられない壁もあります。
『1年で億り人になる』より引用
戸塚氏は、これまで1700人もの人たちに対して資産構築の指導を行ってきた。大多数がFIREを達成し、3000万円の借金を解決した人、資金ゼロからお金のスペシャリストになって起業した人も含まれる。戸塚氏は言う。
ですから皆さんも、1年以内に資産を「億」にすることは、まったく夢なんかではありません。まずは頭のなかの「常識」や「先入観」という固定観念のリミッターを外すつもりで、読み進めてみてください。
『1年で億り人になる』より引用
やはり、本当に大切なのはマインドセットなのだ。
ドラスティックで非常識な方法でケタを外そう
地上波のビジネスニュース番組のコメンテーターの話を聞いていると、投資のコツはリスク回避であるということに集約される。しかしこの本で語られるアプローチは正反対。
私の出会ったケタ違いの資産家たちは、たいていが一般家庭の出身で低学歴です。だから親からの資産も、華やかなコネクションも持っていませんでした。しかし彼らは「お金を持っていない時代」から投資をしています。どうしたかと言うと、「お金を借りた」のです。借金をしても大きな元本を作り、ギャンブルではない、確実に負けない投資で増やすことが大切です。
『1年で億り人になる』より引用
王道の投資術では大きなリスクであるはずの借金に関しては、具体的な資金調達法も語られている。興味がある方、そしてここまで読んでいただいて疑念が生まれた方も、ぜひともご自分でご確認いただきたい。
1年で億り人になる。それを実現するには、ドラスティックで非常識な方法論が重要なのだ。
コロナ禍の3年間で学んだことがある。何かをしたいと思ったら、一切躊躇せずに直ちに行動に移すことだ。投資におけるメジャーリーガーのマインドセットを知ってしまった今、タガを外したい気持ちが抑えきれなくなっている。
【書籍紹介】
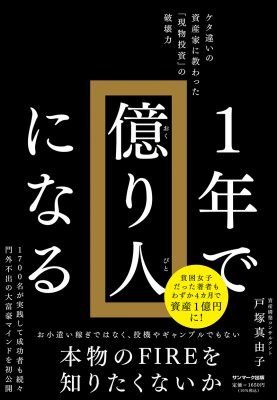
1年で億り人になる
著: 戸塚真由子
発行:サンマーク出版
1700名が実践して、続々と「億り人」が誕生している投資法がある。それは大富豪や「ケタ違いの投資家」の間だけで伝えられてきたもので【現物投資】と呼ばれる破壊力バツグンの投資法だ。著者は、資産構築コンサルタントとしてカードローンで借金3000万円を背負った人など、さまざまな生徒を「億り人」にしてFIREを達成させてきた人物。世界中の大富豪とも交流を持ち、著者自らも、「現物投資」を始めてからわずか4か月でFIRE達成。その極意を日本で初めて公開する。お小遣い稼ぎではなく、ギャンブルでもない。本物のFIREを知りたいすべての人に、必読の書。