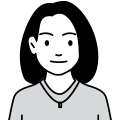玄米から白米へ、精米する際に出る「米糠(こめぬか)」。漬物用のぬか床や、たけのこのあく取りに活用するもの、というイメージがあるのではないでしょうか。実際、大半の米ぬかは肥料や家畜の餌などになりますが、実は玄米に含まれる栄養素の約8割がこのぬかに含まれていることは、案外知られていません。
それほど栄養価が高いなら「米ぬか」も食用にしよう、という取り組みをおこなっているのが、国内最大手の米問屋、株式会社神明(しんめい)。今回は、米ぬかや米油の商品化を手掛ける神明きっちんの取締役社長・藤尾益人さんを直撃。ぬかが持つポテンシャルと食用のメリット、さらには日本の農業と米をとりまく課題などに迫ります。
米は糖質の塊? 実は米ぬかは “糖質オフ” にも効果的だった

数年前からムーブメントになっている「糖質制限」。健康のためにと、白米ではなく糖質を抑えることができる玄米を食事に取り入れている、という人も多いのではないでしょうか?
「玄米が体に良いとされている理由は、お米の白い部分を守る皮、つまり『ぬかの層』にある」と藤尾さん。まずは、その豊富な栄養素について教えていただきました。
「お米はそもそも、ビタミン・ミネラル・食物繊維などをバランスよく摂取することができる食材。ひとつの食材に、これらのマルチな栄養素が入っているものはなかなかありません。
さらにお米は、数年間常温で置いておいても腐ることのない備蓄品。それはなぜかというと、お米の白い部分を守る皮・ぬかの層に、強い抗酸化作用があるからなんです。米のぬか層には、抗酸化作用をもつビタミンEの他にも、タンパク質や整腸作用がある食物繊維、鉄分や葉酸などのミネラル、さらには糖質の消化を助けるビタミンB1などのビタミン類が豊富に含まれています。
つまり、『糖質オフ』ということで避けられているお米ですが、実はぬかの層には糖質を抑える作用がたっぷり含まれているのです。その部分を捨ててしまうのは、なんだかもったいないと思いませんか?」(株式会社神明きっちん 取締役社長・藤尾益人さん、以下同)

日本のスーパーフード、米ぬかを“食べる”メリット
そんな栄養豊富な米ぬかを活用しようと、米油や化粧品など、さまざまな商品開発に取り組んでいるのが、神明きっちんです。なかでも注目なのは、ぬか自体を“食べる”というアイデア。ぬかを食べることで得られるメリットとは?
メリット1.豊富な栄養素で、美肌効果・腸内環境の改善に
「さきほどご説明したとおり、米ぬかには豊富な栄養素が含まれているのがなによりの魅力。抗酸化成分やビタミン類で美肌効果が期待できるのはもちろん、食物繊維が豊富なので腸内環境の改善もサポートしてくれます。必要な栄養素をサプリメントで補う人も多いかもしれませんが、日本人の食生活に身近な“お米”という自然由来のものからマルチな栄養素を摂取できるのは安心ですし、大きなメリットだと思います」

メリット2.加熱しても冷やしても、栄養価が失われにくい
「米ぬかは、熱したり冷やしたりしても栄養成分が失われにくいというのが、大きな強みです。さらに、料理に加えても味を邪魔しない。ですので、普段の食事に取り入れやすいというメリットがあります。玄米で食べても栄養成分が豊富ですが、食感がかたくて食べにくいという人もいらっしゃるかと思いますので、代わりにより手軽な米ぬかで、その栄養素を摂取してみるのもいいかもしれません」
メリット3.食材のアップサイクルに貢献できる
「これまで米ぬかは、廃棄されるか家畜の餌として利用されるくらいで、我々の業界でも邪魔者扱いされてきました。しかし、SDGsの意識が高まっている今、玄米の1割にあたる米ぬかを捨ててしまうのではなく、そこに付加価値を付けて有効活用していくのがいいと考えたんです。これはアップサイクル的な考え方ですよね。米ぬかを取り入れることで、食品ロス削減や世界的な食糧危機を考えるきっかけにもなると思います」
食用化は難しい これまで米ぬかが活用されてこなかった理由
これまで米ぬかが活用されてこなかった理由

それではなぜ、こんなにも栄養満点な米ぬかが、これまで食品原料として使われてこなかったのでしょうか?
「実は、米ぬかは玄米の皮をむいた瞬間から酸化がはじまるため、劣化がとても速いんです。さらに、すぐに処理をしないと菌が繁殖してしまうため使い道が限られていました。『米ぬかの栄養素が高い』ということをわかっていながらも、有効活用されてこなかった理由はそこにあるのです」
米ぬかをそのまま食べられるようにするには、とてもハードルが高かったと藤尾さん。酸化を抑えて食用化するための研究に、約2年もの歳月を費やしたといいます。
「我々が使うことにしたのは、精米直後にできた新鮮な米ぬか。その米ぬかを高温で加熱した後に、酸化の原因となる油を独自の圧搾方法である『ナチュラル・プレス製法』で絞り出すことにしました。ちなみに、その時に絞りだされた油は米油として販売しています」

「本来、米ぬかから油分を抽出するためには、ヘキサンという薬剤を使用するのですが、そうするとぬかにも薬剤が少なからず残ってしまい、食用には適していません。ですが、弊社が行っているのは、薬品を使わない圧搾製法。薬剤完全不使用の安全な食品素材として利用することができるのです。ぬかの酸化を抑えるためにしている作業の過程で、米油も生まれる。一石二鳥ですね」
「食材を余すことなく使う」 そのポリシーから生まれた、米ぬか商品
そうした研究開発を経て生まれたのが「飲める米糠」。2018年に販売を開始した、米ぬかをより手軽に生活に取り入れることができるナチュラルサプリメントです。

「『飲める米糠』は、牛乳や豆乳、アーモンドミルクに混ぜてシェイカーで振ってもらえれば美味しく米ぬかを飲むことができる商品です。好きな材料と混ぜて、スムージーを作るのもいいですね。味のついていない『ナチュラル』は、食事にプラスするのもおすすめ。お好み焼きや味噌汁に入れるなど、料理の美味しさを損なうことなく米ぬかを取り入れることができます」


「ドレッシングやクッキーなど、数多くの米ぬかを使った商品を開発・販売しています。米ぬかをただ売るだけではなく、いろいろな形にすることで興味を持ってもらう、食べてみようかなと思ってもらえる。まずはそのきっかけになるような商品を開発していくことが大切だと思っています。食事に米ぬかを取り入れようとしても、すこし難しいなと感じる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、例えばドレッシングは毎日のように食卓で使うもの。そうした普段使いしているものから試してみるのが一番かもしれません」
負のループが止まらない? 日本人と米をとりまく課題
同社が多様な米ぬか商品の開発し、その魅力を発信し続ける理由は「まずは、若い人にお米についてもっと興味をもってほしい」という思いから。その背景には、日本と米産業をとりまくさまざまな課題がある、と藤尾さんはいいます。
「お米は、食料自給率が低い日本で、唯一自給率約100%を誇る作物です。そして面白いのが、お米はここ25年間価格が変わっていないということ。このような食材は、他には考えられないですよね。
にもかかわらず、米の消費は年々減少しています。1人あたりの消費量で見てみると、1960年代に年間で117kg食べていたものが、2020年で50kgに半減しているんです。米の消費が減ると、当然農家も作らなくなってしまいます。誰も買ってくれないもの作っても仕方がないですから」

「その結果問題となっているのが、担い手不足。農業全般で見ても、1975年には790万人いた農業就業者が、2015年に210万人と4分の1にまで減っています。2050年には100万人を切るのではないかともいわれており、深刻な事態に陥っているのです。
さらに、その農業従事者の3人に1人が65歳以上の高齢者。若い世代がいないというのも大きな課題です。国も、農業を絶やさないために補助金を出しているのですが、それでも専業でお米を作っている人達の平均年収は、200万円レベル。この現状では、若い人たちもやはり離れてしまいます。
お米を食べないと、お米を作る人もいなくなる。最終的には、耕作放棄地となったほったらかしの田んぼが増え、日本の美しい田園風景さえも失われてしまいます。そうした負のループに陥っているのが現状なのです」
若い世代の参入が、農業の活性化につながる

「日本の農業、米産業が抱える負のループを断ち切るためにも、まずはやはり若い世代に興味を持ってもらうことが重要だと思っています。若い世代が米に関わる仕事をする、若い世代が米を食べる、そして若い世代が米に関わる新しい何かを生み出す。米がただの米で終わるのではなく、形を変えた提案をしながら新しいマーケットをどんどん開拓していくことができれば、しいては農業の活性化につながっていくはずだと考えています。
私たちが開発を行っている米ぬか商品も、少し切り口を変えただけ。いままで捨てていたものの価値を見直し、スーパーフードとして活用するというアイデアから生まれたものです。それでも若い人たちに手に取ってもらうには、やはり若いスタッフたちの視点や発想が欠かせません。若い世代の意見を取り入れて、米の活用方法をもっともっと広げていく。それが我々に与えられた課題でもあると思っています」
同社が現在、新たに取り組んでいるのは、『そのまま食べられるぬか床』の販売。ぬか漬けは本来、野菜が持っている乳酸菌がぬか床に含まれる他の菌を食べることで発酵し、旨味が生まれるもの。野菜を取り出したら洗って食べるのが一般的ですが、同社の商品は洗わないで食べられるのです。
「ぬか漬けと聞くと、ハードルが高いと感じる人もいると思います。しかし、手軽に作れることができれば『やってみようかな』と興味を持ってもらえるのではないかと考えています。これからも、若い人たちにまずは一回試してみようと思ってもらえるような、お米や米ぬかの商品を提案していきたい。そこから、米ぬかの栄養素や魅力を実感してもらえたらうれしいです」
【プロフィール】

株式会社神明きっちん 取締役社長 / 藤尾益人
1974年生まれ、兵庫県出身。1996年神明に入社、2015年より株式会社神明精米(現・神明きっちん)代表取締役社長を務める。
【ショップ】

おこめぶらん 南青山本店
“ファクトリー”をコンセプトにした店舗。フードメニューとして、“ぬかごと食べられるぬか漬け“が楽しめる発酵ランチや“焙煎米ぬか茶”といったこだわりのメニューも展開。飲める米糠と圧搾米ぬか油を使ったさまざまなワークショップも開催予定。
所在地=東京都港区南青山2丁目27番地19号 エムプレイス青山1階
TEL=03-6863-1540
営業時間=11:00~19:00 ※ランチは11:30~15:00(20食限定)
定休日=毎週月曜日(祝日の場合は通常営業)