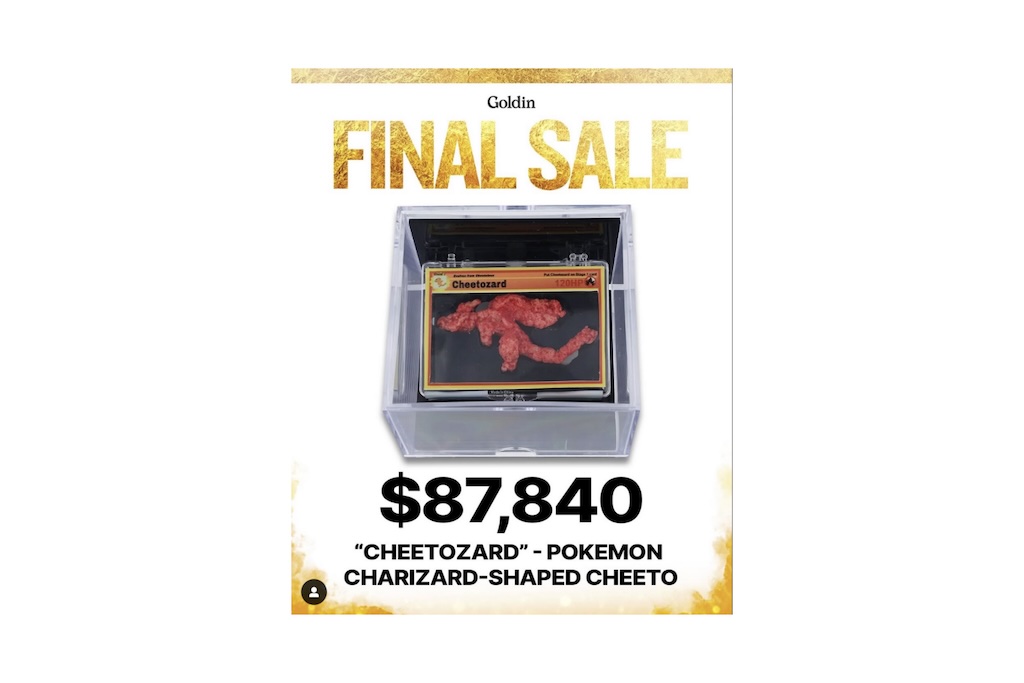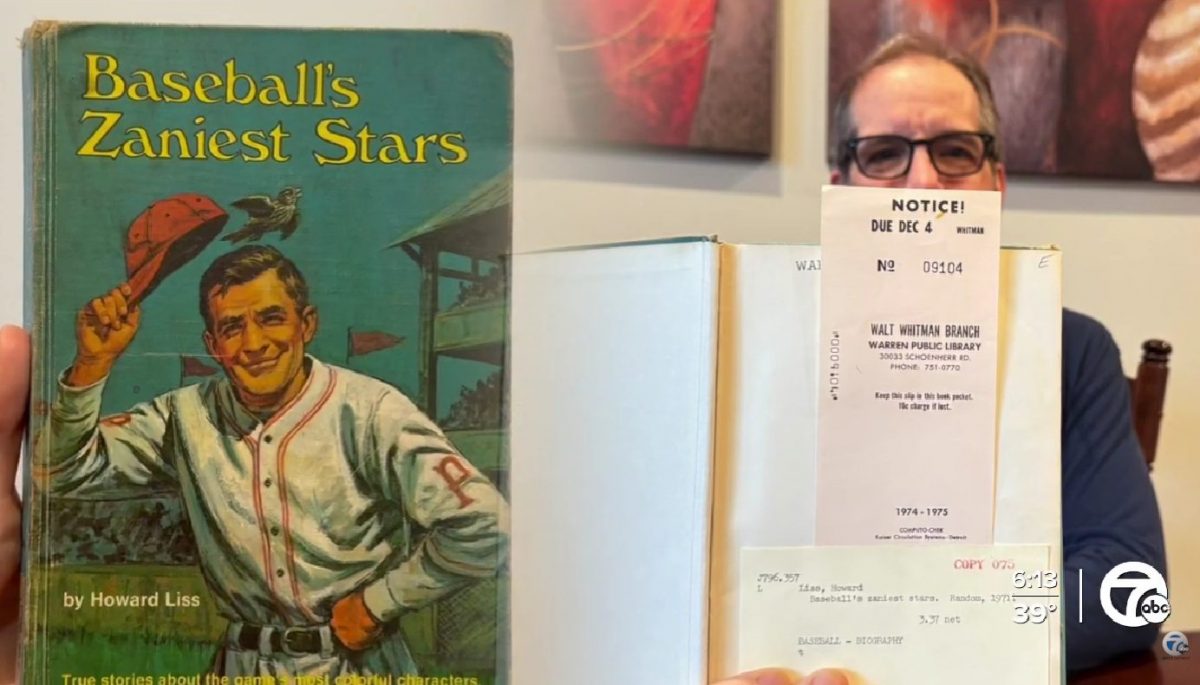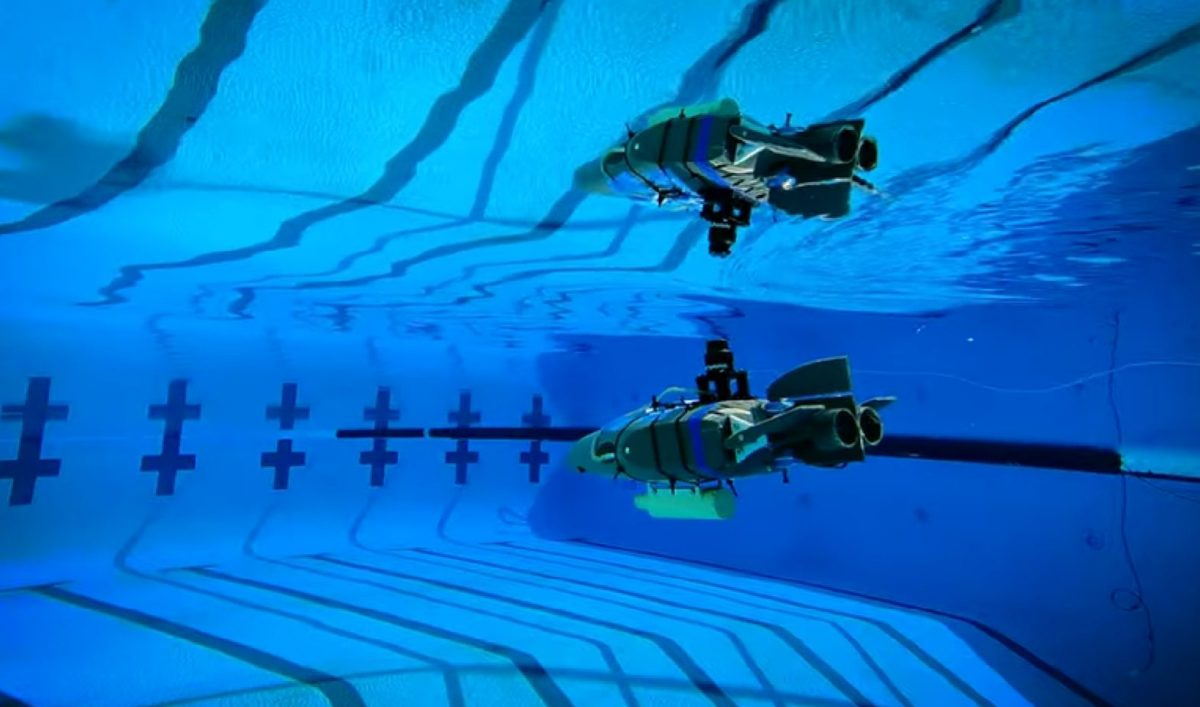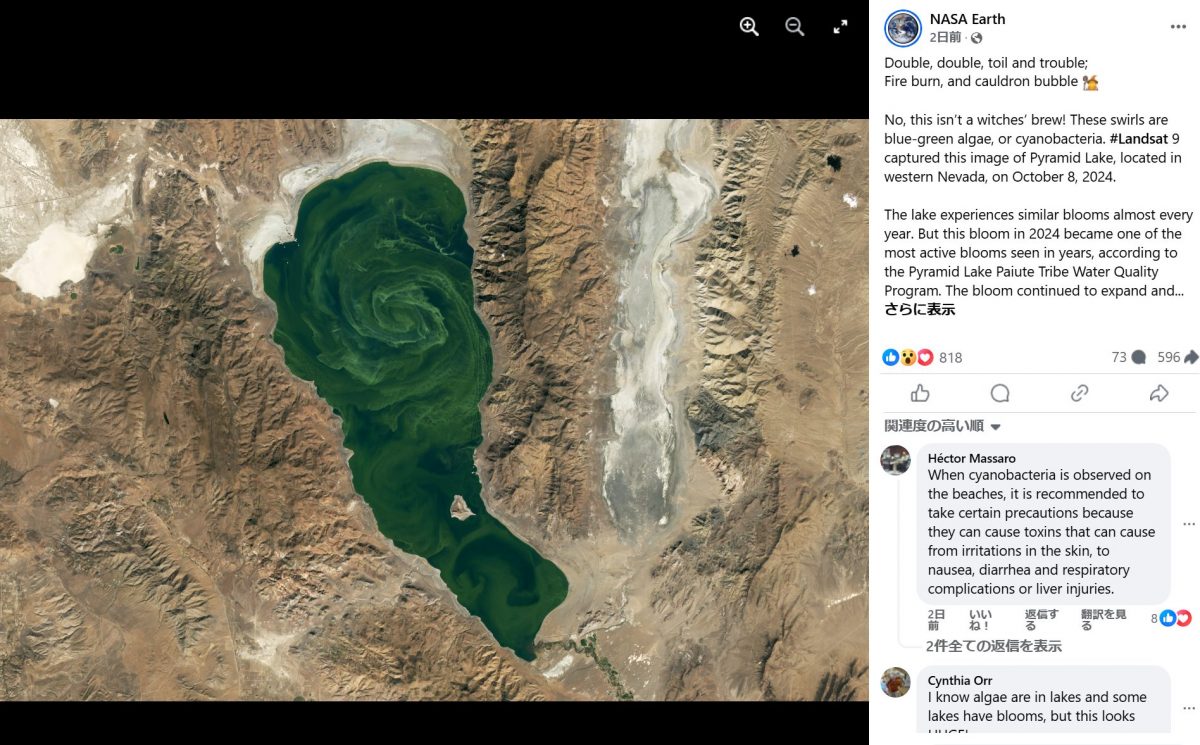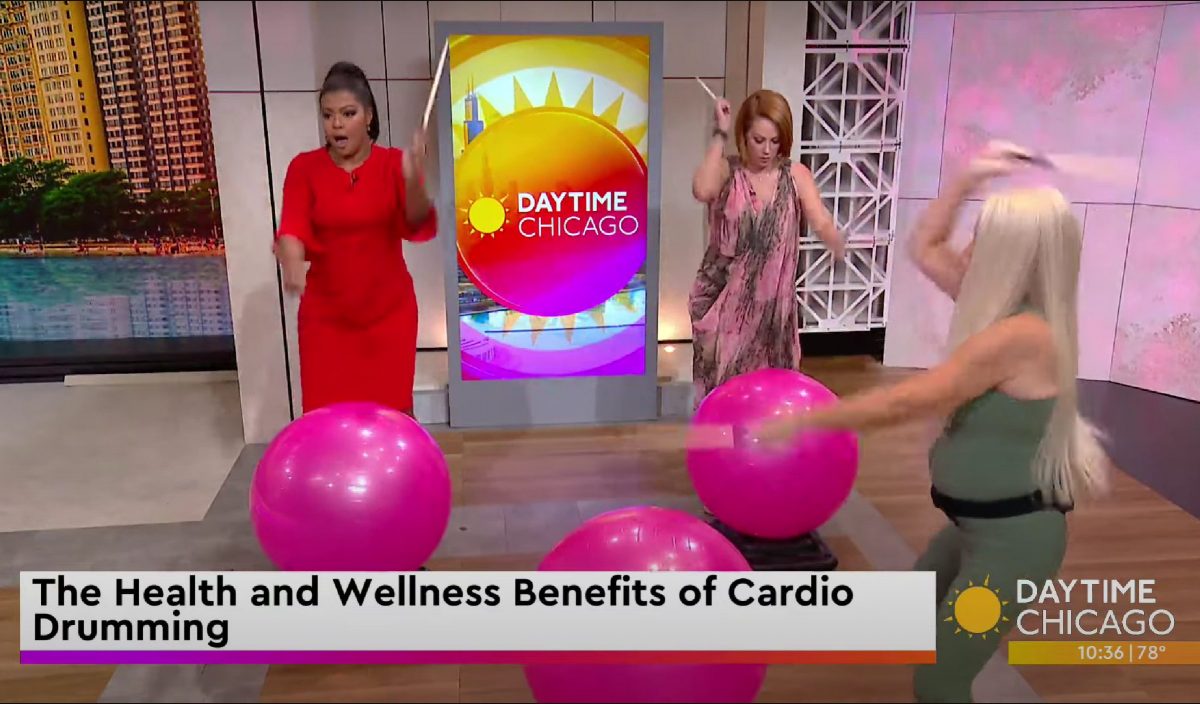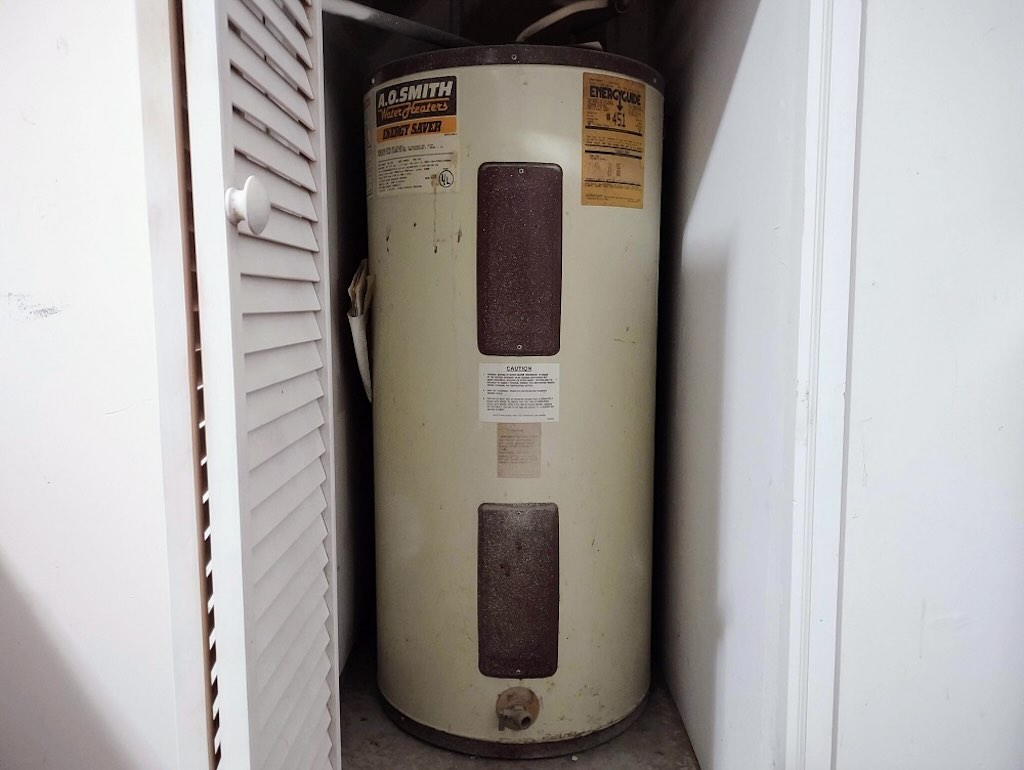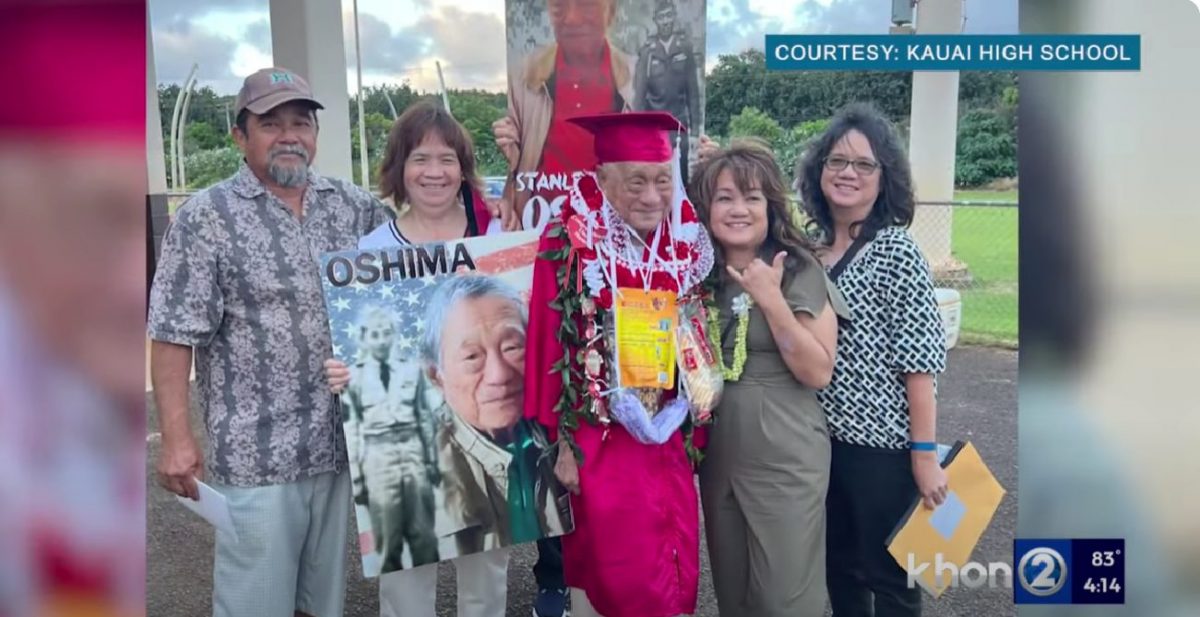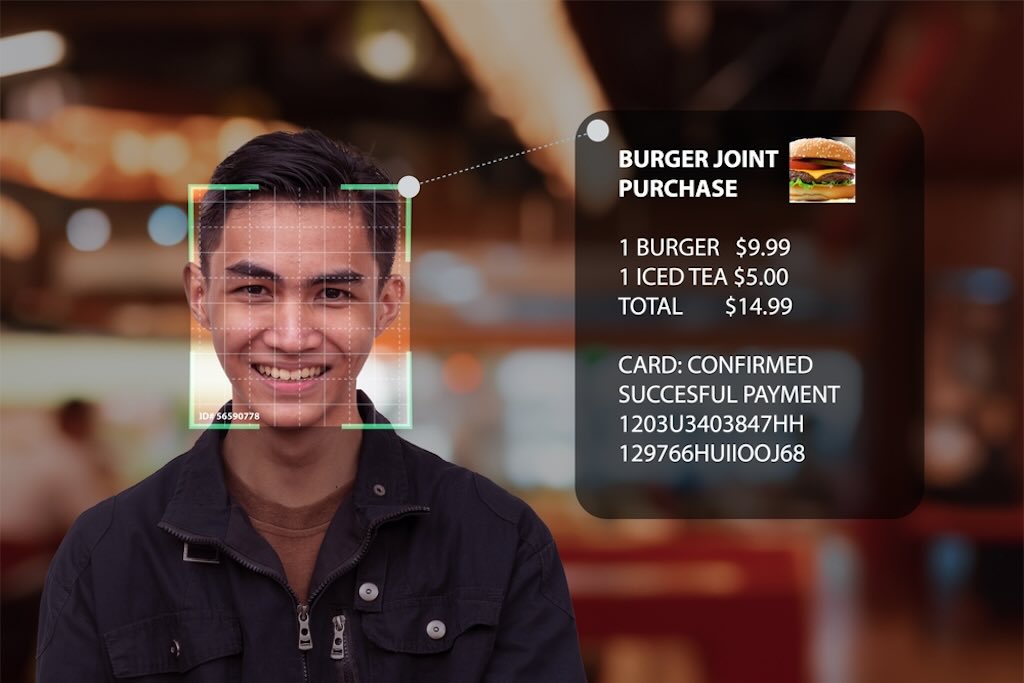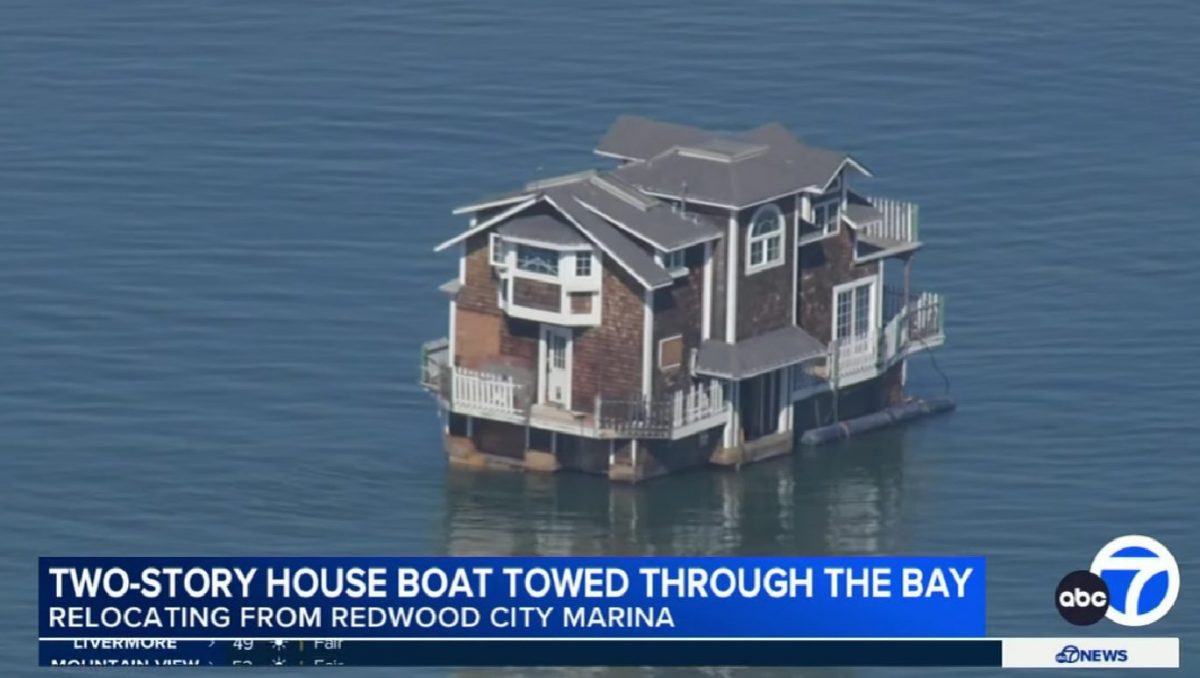米国の田舎の町から、ほっこりするニュースが届きました。300人以上の住民がバケツリレー式で、ある書店の引っ越し作業を手伝ったのです。

子どももお年寄りも、男性も女性も。集まった300人以上が列になり、隣の人からまた隣の人へ、次々に本を手渡していきます。これは、ミシガン州チェルシーという小さな町にある書店の引っ越しのワンシーンです。
書店のオーナーであるミシェル・タプリンさんは、店の移転にあたり、引っ越し作業をどう行うべきか困っていました。店にある書籍は、9100冊。わずか100メートルほどしか離れていない場所への移転ですが、これだけの書籍を移動させるには、何日も店を閉めて、一度段ボールに書籍を詰めて、新しい店でそれを開けて棚に入れ直す……という作業を行わなければいけません。
そこで彼女が思いついたのが、バケツリレー式での書籍の移動です。早速、町の人々にボランティア募集を呼び掛けたのです。
結果、集まったのは300人以上の人たちと、ワンちゃん1匹。集まった人々が2列になって、既存の店から、移転先となる店舗の中にある本棚の前までずらりと並び、順に本を手渡ししていったのです。途中、道を歩いていた人や、移転作業を聞きつけた人々も加わったそうで、驚くことに2時間もかからず、すべての書籍の移動が終わったそうです。
重い荷物を持ち上げることもなく、中には90歳以上の高齢の方もいたり、車椅子の方がいたりしたよう。本を渡すときは「この本、読んだ? これ、とっても面白かったよ!」などと、声をかけあって、みんな楽しみながらお手伝いしていたそうです。
タプリンさんも、集まった人たちも、自分たちのコミュニティの目に見えない絆や温かさを改めて実感できた出来事になったのではないでしょうか?
【主な参考記事】
ABC News. A Michigan community takes a novel approach to moving 9,100 books for shop’s next chapter. April 16 2025
※この記事は本サイト(GetNavi web)でご覧になるとアフィリエイト広告が掲載されています。リンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。 ※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。





![[公式] ソーダストリーム GAIA(ガイア) スターターキット ブラック マシン本体 60Lガス1本 ボトル1本 (1.0L...](https://m.media-amazon.com/images/I/316oehPAX9L._SL500_.jpg)

![[ニューバランス] スニーカー CM996 現行モデル グレー(GR2) 26.5 cm D](https://m.media-amazon.com/images/I/31SFmOdFf5L._SL500_.jpg)