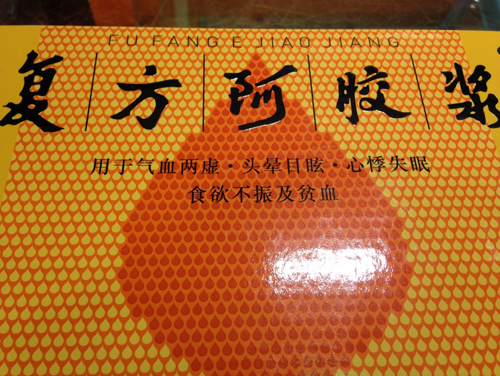若い頃は、「シワもシミも美しさのうちだ」などと、考えていました。
実際、シワがあっても、シミができても、白髪が増えても、素敵な女性は変わることなく素敵でいるのを知っていたからです。ウィスキーグラスを片手に「暁子ちゃんにはまだわかんないだろうけど、トシを取るってのもいいもんよ」などと言われると、「あ~~~、なんてかっこいいのだろう」と憧れて、クラクラしていました。

老化は病気ではないはずなのに
けれども、実際、自分がその年齢に達してみると、そうは余裕を持ってはいられません。人間としてのスケールが違うといえばそれまでですが、シワもシミも白髪も「こりゃ、なんとかしなくちゃ」と、なります。
そして思うのです。「手遅れになる前に手を打とう」と。病気ではないのですから「手遅れ」はおかしいのですが、よる年並みに抵抗せずにいると、坂道を転げ落ちるように老婆になってしまうような気がします。
加齢はいつも初めての体験
おまけにトシをとるのは誰にとっても初めての経験です。風邪をひいたときのように、経験から対策を立てるのは難しいものです。
風邪をひいても、ヒトはそれまでの経験値で対処できます。たとえば、「去年、ぞくぞくするのに無理をして、結局一週間も寝込んだから、今年はこじらせないようにしなくては」と、自分なりに案配するものでしょう。ひどくならないうちに、予防接種をすることもできます。けれども、老化はそうはいきません。
誰もが毎日確実にトシをとり、そして、毎朝初めての自分、トシを取った症状、言い換えれば病状と向き合うのです。これって残酷なことだと思いませんか? おまけに、トシを取るのは肌や髪だけではありません。
眼がしょぼしょぼしたり、耳鳴りがしたり、腰が痛んだりします。最初は「疲れているのよ」と、ごまかしていても、やがて「これは立派な病気だ」と確信するに至ります。
美しく痩せ、加齢にあらがう
私は先日、眼に蚊のようなものが飛ぶので病院に行ったら、まだ若いお医者様に「これは加齢によるものですね~~」と、きっぱり診断されました。
か、加齢?! そ、そんな~~。しかし、それは過酷な現実として、私に降りかかってくるのでした。では、私は何をしたらよいのでしょう?
救いを求めて手に取ったのが『美しくやせる食べ方 ディフェンシブ~体を守る~栄養学』(藤本幸弘・著/学研プラス・刊)です。この本には加齢に対処する食事法が示されています。
タイトルからすると、痩身美容について書かれているようですが、読んでみるといかにして健康を維持し病気にならないようにするか教えてくれる本なのです。健康でいたいなら、病気になる前に、すべての臓器の予備力を上げ、防御能力を高めることが大切だといいます。そのためには「ディフェンシブ」な栄養学を実践することが大事だと教えてくれます。
未病の段階でせき止めろ
著者の藤本幸弘医師は驚くべき経歴の持ち主です。医学博士であり、工学博士であり、そして、薬学博士でもあります。物事のしくみを考えるのが好きだった著者は、医学・工学・薬学の博士号をとるため大学院に通い、十年かけて目的を果たしたといいます。
そして、病気を治すのが医師のつとめではあるけれど、病気になってから治すのではなく、未病の段階で健康を害する可能性があるリスクを回避するべきだというのです。そのためにすべきことを5章に分けて専門的に説明していきます。
第1章 美肌・美ボディを作る食べ方
第2章 もっとも重要な三大栄養素
第3章 代謝に不可欠なビタミン&ミネラル
第4章 抗酸化と抗糖化
第5章 栄養素を効率よく取り入れる
アンチエイジングに大事なものは
私は今までアンチエイジングとは、シワシミ白髪を押しとどめ、少しでも若く見えるように頑張るための医学的措置だと考えていました。
著者もレーザーを使い、シミやあざを取ったり、肌を若く保ったり、痩身に役立てたりする専門家です。私もトライしたいなと思いますが、美の土台である健康をしっかりと確立させることが大切です。バランスの良い食事こそが、健康の源であり、アンチエイジングの基本となります。「病は気から」とよく言いますが、「病は食事の偏りから」なのかもしれません。
がんを避ける免疫力
多くの人はがんを怖れます。もちろん私も怖いです。家族にもがんになって欲しくありません。けれども、健康な人間の体にも毎日、がん細胞ができているといいます。ただし、免疫力をあげれば、がんにならずにすむかもしれません。がんも一種の老化だからです。
『美しくやせる食べ方 ディフェンシブ~体を守る~栄養学』を教科書に、まず体の代謝をあげて美しい肌とボディを手に入れましょう。6大栄養素(糖質・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラル、そして食物繊維)を食事から摂取し、体を酸化させないようにすれば、健康で若く綺麗な自分を維持できると信じて、食事を大事にしたいと思います。
「まだまだあきらめないぞ」。そう思える本に出会えた幸福をかみしめているところです。
【書籍紹介】

美しくやせる食べ方 ディフェンシブ~体を守る~栄養学
著者:藤本幸弘
発行:学研プラス
アンチエイジング医療の第一人者である著者が提案する、「キレイにやせて、見た目を10歳若返らせる」食事術。主軸である「代謝、酸化、糖化」のメカニズムを中心に、女性の代表的な悩みに対応する食事法や、生活術を具体的に紹介する。