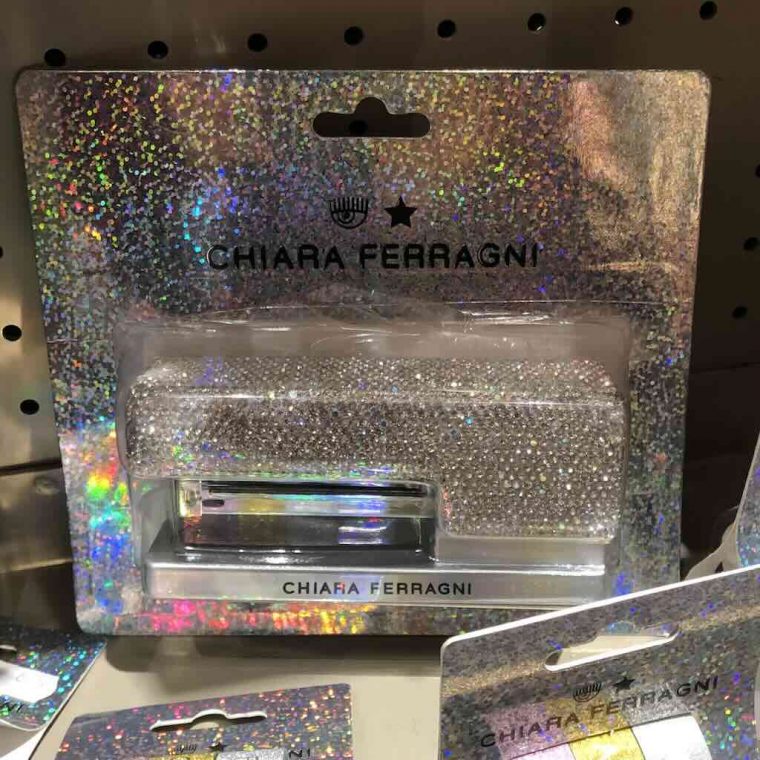自宅でワインを楽しみたい、できれば産地や銘柄にもこだわりたい、ワインを開けて注ぎ、グラスを傾ける仕草もスマートにしたい……。そう思っても、基本はなかなか他人には聞きにくいもの。この連載では、そういったノウハウや、知っておくとグラスを交わす誰かと話が弾むかもしれない知識を、ソムリエを招いて教えていただきます。
「ワインの世界を旅する」と題し、世界各国の産地について、キーワード盛りだくさんで詳しく掘り下げていくこのシリーズ、「フランス」に続く今回は、「イタリア」。寄稿していただくのは引き続き、渋谷にワインレストランを構えるソムリエ、宮地英典さんです。
【関連記事】ワインの世界を旅する 第1回 ―フランスと5つの産地―
イタリアワインを旅する
紀元前にイタリアに入植したギリシャ人は、イタリアの地を“ワインの大地=エノトリーア”と呼んだといわれています。現代でも、イタリアのように国中の全土と言っていいほど、さかんにブドウ栽培が行われている国は珍しく、フランスと肩を並べるほどのワイン生産国。20州それぞれの多様な個性を表現したワインは、その文化と郷土料理と相まって、多くの人を魅了しています。
ですが裏を返せば、その多様性はイタリアワインを“難解で選びにくいワイン”にしていることも事実です。その原因のひとつには、現在進行形で議論されていますが、ラベル表示のわかりにくさが挙げられるでしょう。州ごとの個性とはいっても州の名前自体は記載されておらず、「DOCG」や「DOC」、そして「IGT」といった原産地呼称と合わせて消費者目線に立ったラベル表示は、これからイタリアワインがより個性を発露するためにも、課題としてとらえ解決に取り組む必要があるのではないでしょうか。
今回は、初心者に向けたイタリアワインの入り口として、代表的な5つの州と5つのワインをご紹介しながら、私が考えるよりわかりやすいイタリアワインの表示と、イタリアワインの選び方をお伝えすることができればと思います。
・ピエモンテ州 ・トスカーナ ・シチリア ・ヴェネト ・トレンティーノ=アルト・アディジェ
ピエモンテ州 ~尾根に連なる美しいブドウ畑と「バローロ」~
ピエモンテの州都トリノは、2006年に冬季五輪が開催されたことでも知られるほか、サッカーチーム「ユヴェントス」のホームタウンといえば、ワインに馴染みのない方でもピンとくるかもしれませんね。
19世紀、イタリア王国時代には首都だったということもあり、歴史のあるバロック建築の街並みは荘厳で、往時を想像させる魅力的な都市です。当時からそのままに残る数々の老舗カフェで、原産地呼称指定されているチョコレートドリンク“ビチェリン”を楽しむのも、トリノでの素敵な時間の過ごし方です。
ホットチョコレート、エスプレッソ、生クリームの3層からなる、トリノ伝統の飲料。カフェ・アル・ビチェリンが発祥とされます
このピエモンテは、イタリア屈指のワインの銘醸地でもあります。トリノの南東に位置するランゲ&ロエーロ地方では尾根が複雑に絡まりあい、東西南北の斜面にはブドウ樹、平地にはヘーゼルナッツが整然と並び、世界でも類を見ないほどに美しい田園風景が望めます。そんなランゲ&ロエーロのみならず、イタリアを代表するワインのひとつが「バローロ」。バローロ村を中心にカスティリオーネ・ファレット、セッラルンガ・ダルバ、モンフォルテ・ダルバ、そしてラ・モッラの五つの村周辺の畑、バローロの丘に植えられた晩熟のネッビオーロから造られるバローロは、長い熟成を必要とする骨太で重厚な果実とタンニンを持つものから、鮮やかにも感じる芳香を早いうちから楽しめるタイプまで幅広く、ブルゴーニュと比較されるほど、バローロの丘の地質や環境は多様なワインを産み出します。「王のワインにして、ワインの王」ともいわれ、高級イタリアワインの重厚なイメージがあるかもしれませんが、下で紹介する「レヴェルディート」などラ・モッラ村周辺で造られるものは比較的軽やかでリーズナブルなものもあり、初めてバローロに親しまれる方にはおすすめです。
バローロの中だけでも、前述したいくつかのエリアでワインのキャラクターは違います。もちろん生産者によって畑を飛び地で所有していることもありますし、ブルゴーニュのように、より地域表示を明確にすることで“テロワール表現”というワインの最大の魅力を表現していくことができるように思います。
バローロを飲む機会があったならば、そのワインがどの地域で造られたものなのかを意識してみると、“王のワイン”もより身近なものになるのかもしれません。
Reverdito (レヴェルディート) 「Barolo2016(バローロ2016)」 5000 円 輸入元=ミレニアムマーケティング
次のページで取り上げるのは、キャンティ・クラシコで知られる産地、トスカーナです。
トスカーナ ~歴史ある「キャンティ・クラシコ」は、今も進化し続ける~
フィレンツェの南、シエナの北に、「キャンティ・クラシコ」の畑は広がっています。イタリアワインにおいて“クラシコ”とは元来、銘醸畑として認められていたエリアを指しますが、とくに“キャンティ”はラッダ、ガイオーレ、カステッリーナに加えグレーヴェが、18世紀に線引きされた歴史のあるクラシコといえます。これは現在の原産地呼称のオリジナルともいえる、画期的な出来事でもありました。
けれどもキャンティ・クラシコとキャンティの“サブ・ゾーン”(キャンティ〇〇とエチケットに記載)、キャンティとだけ表示された広域ワインのエチケットには、どれも「Chianti」の表示が。ワイン初心者にとっては、その品質の差の割に、店頭では区別のつきにくいワインとして長く流通してきたのです。“キャンティ”という響きが銘醸ワインの響きも併せ持っていること、一時期の大量生産の広域ワインが多く流通したことも、日本の消費者にとってはハズレの多いワインのような印象を与えてしまったように思うのです。
2014年に、「グラン・セレツィオーネ」という単一畑のキャンティ・クラシコの最上位にあたる新しい呼称が設けられ、キャンティ・クラシコはその品質に見合った高級ワインのイメージを取り戻そうとしています。キャンティ・クラシコの地域ごとの個性、そしてその単一畑の個性が評価されていくのも、これからのことです。例えばボルドーのように、生産者の格付けのようなものが制定されたなら、格付けシャトーとAOCボルドーとの差以上に、優れた生産者と単一畑とキャンティのサブゾーン、広域キャンティがより消費者にとってわかりやすく、また素晴らしいワインを産み出すことにつながらないかと日々夢想しています。
長い時間が必要だとは思いますが、イタリアワインを代表する銘醸ワインとして、キャンティ・クラシコがこれからワインを親しむ方にとっても、とっておきの選択肢になることを願っています。
そう、フィレンツェの名物料理といえば、赤身のキアーナ牛の「ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ」。ステーキに合わせるワインとしてキャンティ・クラシコを選べるようになったなら、相当なワイン愛好家といえることでしょう。
Rocca di Montegrossi (ロッカ・ディ・モンテグロッシ) 「Chianti Classico2017(キャンティ・クラシコ2017)」 3800 円 輸入元=ミレニアムマーケティング
3つ目に紹介していただくのは、シチリアです。
シチリア ~地中海最大の島にしてイタリア最大の州~
地中海に浮かぶシチリアは、さまざまな文化の影響を受けてきた土地でもあります。ことワインに関しても、アグリジェント市のギリシャ神殿、ピアッツァ・アメリーナのローマ時代のモザイク、パレルモのムーア人の寺院などなど、地中海における宗教の歴史的な遺産を今も多く残しています。
ただ、イタリアワインの世界では、ほんの四半世紀前まで輸出用ワインを大量に、それこそイタリア最大規模の生産量を産出する個性のない地域でもありました。それからの10年で、シチリアワインは量から質へ、大きな転換を果たし、ブドウ畑の面積はほとんど変わらないものの、生産量は3割以上減らしました。パレルモ周辺の協同組合も土着品種への関心を高め、さまざまなルーツを持つマスカット品種もまた、成功を収めつつあります。
そして、安定して高品質なワインを産み出すようになった産地として、シチリア島の東にあるエトナ山が挙げられると思います。エトナ山は、オリーブやピスタチオ、さまざまな果樹が育つ豊饒な火山灰土壌が特徴で、黒ブドウは「ネレッロ・マスカレーゼ」、白ブドウは「カリカンテ」が、約800mの標高に植えられています。高品質ワインが造られるようになったのはここ最近のはずなのに、品質の安定感はイタリアワイン随一といっても大げさではないほど。徐々に価格も上がってきている銘柄もありますが、ワインショップで見かけたら、ぜひ一度お試しいただきたいとおすすめできる銘柄です。
写真の「エトナ・ロッソ」は、スパイスの効いた鮮やかなベリー系の果実に芯のあるストラクチャー、軽やかで、魚介にも肉料理にも幅広く合わせられるワインです。あまりにも幅の広いシチリアのワインも、西と東や南などのイメージがワイン初心者にも伝わるようになったなら、ワイン選びももっと楽になるのかもしれません。
Valenti (ヴァレンティ) 「Etna Rosso “Norma ”2014 (エトナ・ロッソ“ノルマ”2014)」 3200 円 輸入元=ミレニアムマーケティング
4つ目は、中世の街並みを残すヴェローナを擁す、ヴェネトにまつわる話。
ヴェネト ~北イタリア、ヴェローナはロミオとジュリエットの舞台~
中世の街並みを残すヴェローナは、シェイクスピアの戯曲『ロミオとジュリエット』の舞台であり、あのジュリエットのバルコニーがある家は観光名所のひとつとして、旧市街の一角に現在も残っています。また、毎年4月にイタリア最大の見本市「ヴィニタリー」が開催されるのも、ヴェローナ郊外。期間中は、街の商店のウインドウには贔屓(ひいき)の「ヴァルポリチェッラ」や「ソアヴェ」のボトルがディスプレイされ、ワイン好きにとってはウインドウ・ショッピングをも楽しめる街でもあります。2020年は残念ながら開催されませんでしたが、イタリア中のワインが一堂に会するビッグイベントですから、春にイタリアに行く機会があれば、ぜひスケジュールに組み込むことを検討してみてください。
ヴェネト州の代表的なワイン畑は、ヴェローナの北側、東のソアヴェから西のガルダ湖へ40kmほどに伸びるヴェローナ丘陵に広がっています。白ワインの代表的な産地に「ソアヴェ」、赤ワインの代表的な産地に「ヴァルポリチェッラ」があり、それぞれ辛口の軽やかなものから干しブドウから造る甘口の「レチョート」と、幅広いワインが造られています。
ヴェネトは、イタリアのなかでもとくに生産量の多い地域であるため、比較的安価なワインが多いエリアでもあり、やはりこの地域でも“クラシコ”表示を基準に選んだほうが良質なワインに巡り会う可能性は高まります。「ヴァルポリチェッラ・クラシコ」は、チェリーのようなチャーミングな風味にほのかなアーモンドの皮の苦みが特徴で、コストパフォーマンスに優れたワインが多くあります。また、ヴァルポリチェッラの高級レンジには、乾燥させて糖度を高めたブドウから造る甘口の「レチョート」と、辛口で苦みと甘みを併せ持った「アマローネ」があり、アマローネを圧搾した後の果皮の上でワインを発酵させる「ヴァルポリチェッラ・リパッソ」(またはスペリオーレ)も、ヴァルポリチェッラ寄りの価格帯ですので気に入った生産者のワインに出会ったら、それぞれのワインをお試しいただくのもおすすめです。
Begali Lorenzo (ベガーリ・ロレンツォ) 「Valpolicella Classico2016(ヴァルポリチェッラ・クラシコ2016)」 2500 円 輸入元=ミレニアムマーケティング
最後は、この産地をすでに知っていたら通な「トレンティーノ=アルト・アディジェ」を紹介していただきます。
トレンティーノ=アルト・アディジェ ~イタリア最北のワイン産地ではドイツ語が話される~
トレンティーノ=アルト・アディジェ州は、南のトレンティーノと北のアルト・アディジェに大別され、イタリア20州の中でも特徴的なのは、フランス品種やドイツ品種が多く栽培されていることでしょう。南のトレンティーノでは、シャルドネの高品質なスパークリングワインやイタリアでも最高のボルドー・ブレンド、地場品種では「テロルデゴ」など、魅力的なワインが造られています。
そして今回は北側、イタリア最北のワイン産地、アルト・アディジェのワインを紹介しようと思うのですが、その魅力はなんといってもイタリアでもっともワインが選びやすい点。大半のワインがDOCアルト・アディジェに区分され、表示は基本的に品種名と生産者、加わってもせいぜい畑の名前と、イタリアワインらしからぬわかりやすいエチケットになっています。
赤ワイン用品種はカベルネやメルロー、ピノ・ノワールのほか、固有品種である「ラグレイン」や「ヴェルナッチュ」、白ワイン用品種はシャルドネやソーヴィニヨン・ブランといった国際品種に加え、リースリングやシルヴァーナー、ゲヴュルツトラミネール、この地域では主役になりつつあるピノ・グリージョやピノ・ビアンコと多士済々(たしせいせい)といった趣です。
とくに色調が濃く、力強さもあるピノ・グリージョと、華やかでフローラル、みずみずしさとキリリとしたミネラル感を併せ持ったピノ・ビアンコは、どちらも本家ブルゴーニュやアルザスのワインと比べてもまったく見劣りせず、同時にアルト・アディジェらしさともいえるオリジナリティある魅力的なワインが数多く産み出されています。イタリア語よりもドイツ語が主流で、街の看板にはドイツ語とイタリア語が併記されており、チロル文化の色濃く残る街並みはワイン同様、イタリアらしからぬ魅力的な地方アルト・アディジェ、イタリアワインに馴染みのない方でも手に取りやすいイタリアワインです。いえ、南チロルワインと呼んだほうがいいのかもしれません。
Nals Margreid (ナルス・マルグライド) 「Pinot Bianco”Silmian”2017(ピノ・ビアンコ“シルミアン”2017)」 4000 円 輸入元=ミレニアムマーケティング
※ワインの価格はすべて希望小売価格です
【プロフィール】
ソムリエ / 宮地英典(みやじえいすけ)
カウンターイタリアンの名店shibuya-bedの立ち上げからシェフソムリエを務め、退職後にワイン専門の販売会社、ワインコミュニケイトを設立。2019年にイタリアンレストランenoteca miyajiを開店。https://enoteca.wine-communicate.com/ https://www.facebook.com/enotecamiyaji/