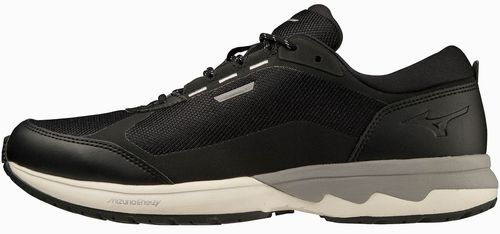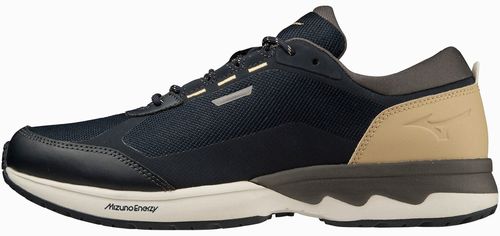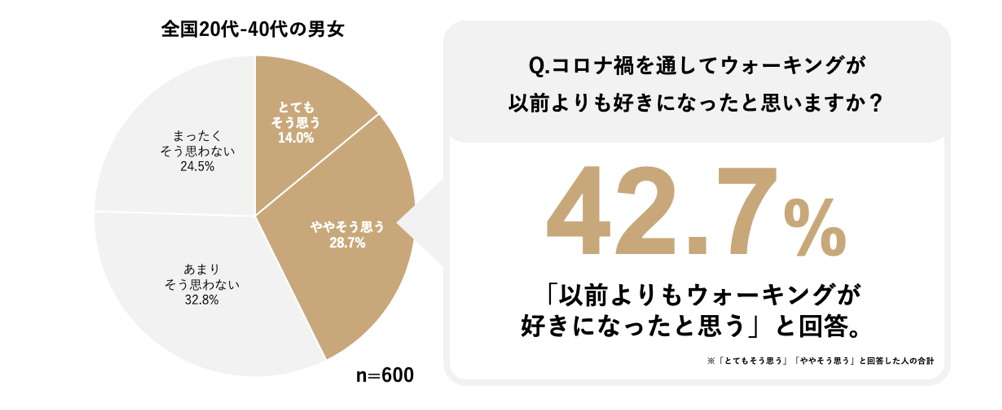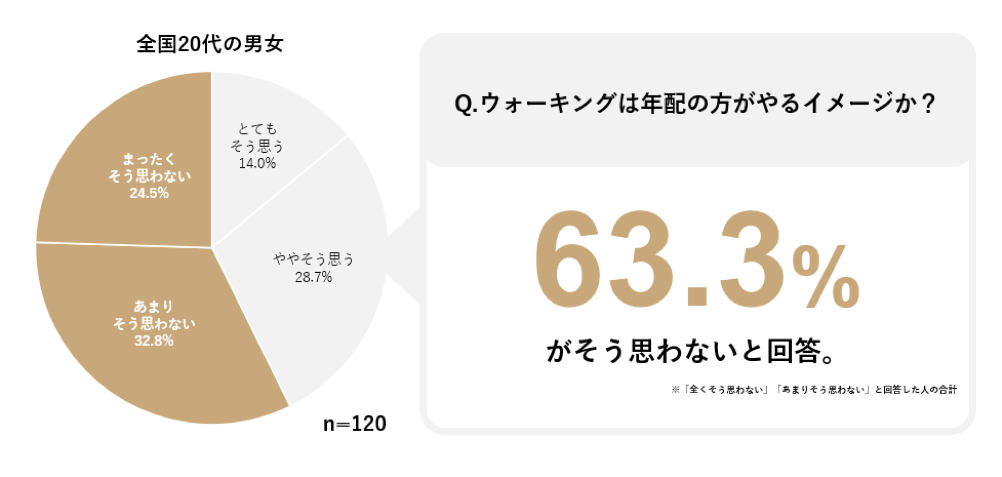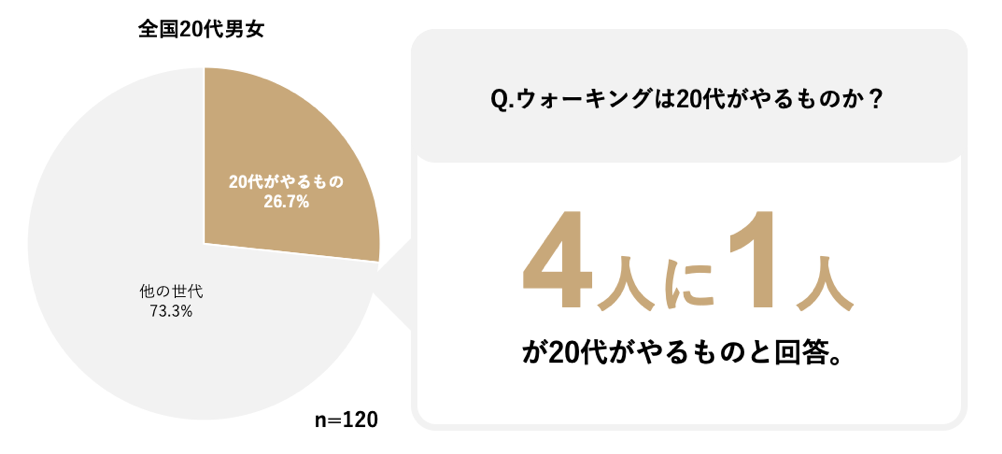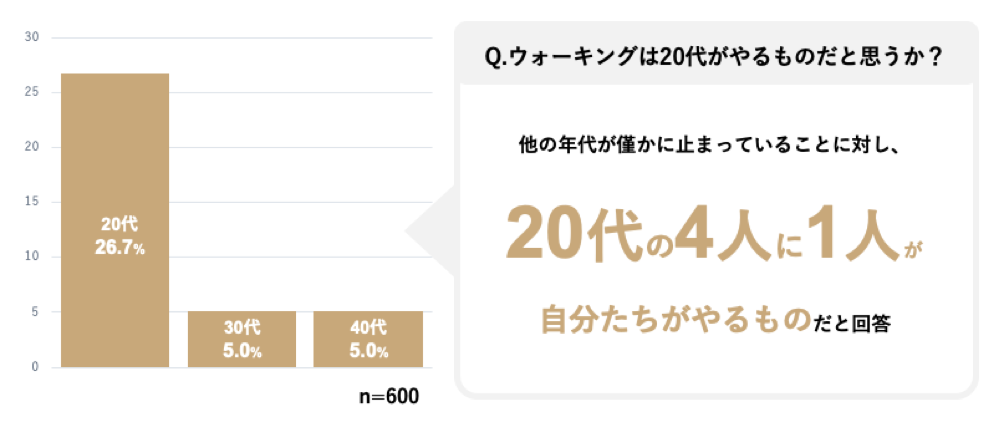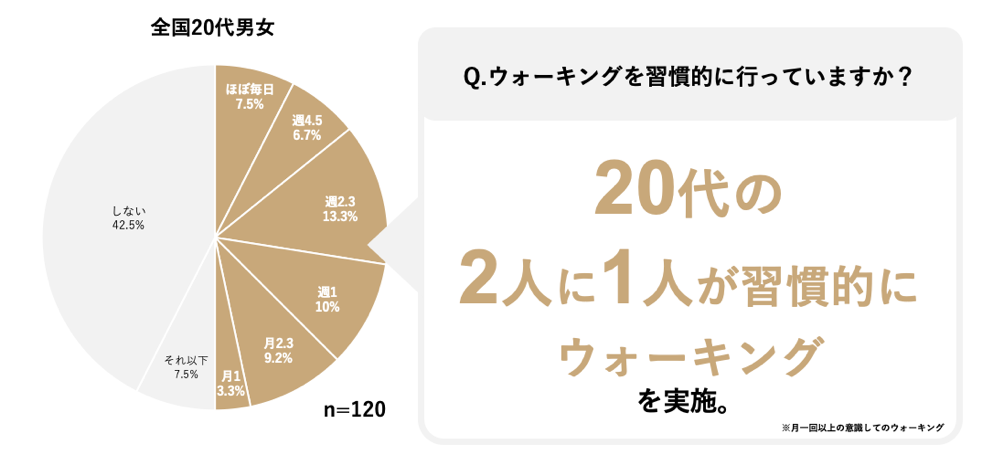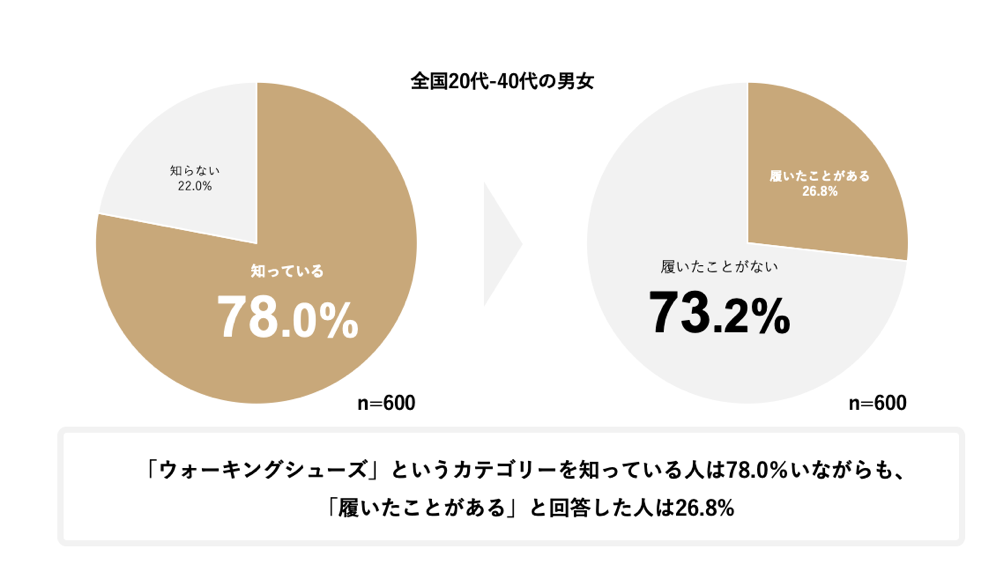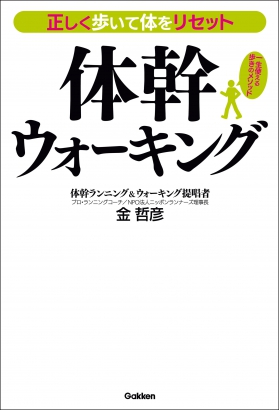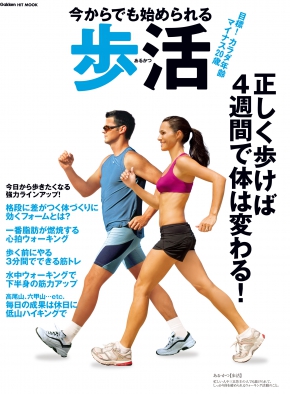健康志向の高まりにくわえ、2020年の東京オリンピックを控えたいま、改めて見直されるウォーキングです。そして、それを傍らで支えるアイテム・万歩計。歩数を自分で把握できる古くからある便利アイテムですが、スマホなどで代用出来ると思ったら大間違い。近年、改めて万歩計が見直され、販売数をグングン伸ばしているようです。今回は、万歩計のトップメーカー・山佐時計計器・営業本部の山田譲二さんに万歩計の歴史と近年の支持の高さを聞きました。
 ↑山佐時計計器・山田譲二さん。万歩計の歴史を知り尽くし、現代のスマホなどの構造にも詳しい
↑山佐時計計器・山田譲二さん。万歩計の歴史を知り尽くし、現代のスマホなどの構造にも詳しい
万歩計は日本が独自に開発した商品だった!
――近年の健康志向の高まりと合わせて、万歩計の利便性も改めて見直されていますね。
山田譲二さん(以下:山田) はい。おかげさまでここ数年は特に販売が伸びています。背景には、やはり健康志向と高齢化で気軽にできる運動――歩くことが見直されたことがあると思います。
もともと万歩計を弊社が開発したのはいまから53年前、1965年のことでした。当時は、自動車社会になっていくだろうと予測された時代で、社会的に「歩け歩け運動」が起こるなど、歩くことが推奨されるようになりました。
そんななかで、弊社の創業者が医師の大矢 巌氏(のちの日本万歩クラブ創立者)から「歩数を計れる機械を作って欲しい」と依頼を受け、最初に完成させたのが万歩メーターでした。
――つまり日本独自のもので、山佐時計計器さんが最初に考えられたものだったんですね。
山田 はい。ですから他社さんから出ている歩数計も、「万歩計」と呼ばれてしまうこともありますが、この「万歩計」という呼称自体は、弊社の商標登録になっています。
一番最初の万歩メーター発売から1980年代中半までは機械のなかに振り子を組み込んで、それで歩数を計るタイプでした。これは弊社からOEMのカタチで提供し、東芝さん、日立さん、三菱さん、富士通さん、タニタさんなど、各社が歩数計を作られました。
後の1987年には初のデジタル式万歩計を発売。これによって歩数から消費カロリーが計れるシステムも搭載できるようになりました。
 ↑1965年に発売された最初期の万歩メーター。以降、1980年代中盤までこの構造が継承されました
↑1965年に発売された最初期の万歩メーター。以降、1980年代中盤までこの構造が継承されました
四足歩行の動物は、歩数を計ることができない?
――万歩計の振り子機能が様々な商品にも転じられたようですね。
山田 はい。ゴルフのスイング回数を計るもの、縄跳びの回数を計る物。あとはネクタイピンやベルトに万歩計を組み込んだものなど、様々な商品がありました。ベルト式万歩計は厚い支持をいただき、2008年まで約20年間、販売した商品です。
――あとは万歩計で歩数を計ることと、ゲームを合体させた商品もありますね。
山田 歩くことで日本地図を完成させる万歩計ですね。ほかにも、四国お遍路歩きをバーチャル体験できるような商品もあります。
あと、変わったところですと、ペット向きのものもありました。もともと弊社では、忙しい方のためにワンちゃん、ネコちゃんの餌の時間をタイマーでセットし、自動給餌出来る餌入れも開発しており、これが万歩計に次ぐヒット商品でした。
そういう経緯からワンちゃんの歩数を計るための商品も開発したのですが、四足歩行だと正確な数が計れないんですよ。
――どうしてですか?
山田 万歩計は振動によって、「本当に歩いたかどうか」をカウントするわけですが、四足歩行だと、それが不明瞭になるわけですね。ですので、これはやむを得ず運動量計測というカタチにして販売していました。
 ↑過去には万歩計の振り子の原理を生かし、腕に巻いてゴルフのスイング回数を計る商品(左)や縄跳びの回数を計る商品も(右)
↑過去には万歩計の振り子の原理を生かし、腕に巻いてゴルフのスイング回数を計る商品(左)や縄跳びの回数を計る商品も(右)
 ↑ロングヒットとなったベルト式万歩計
↑ロングヒットとなったベルト式万歩計
 ↑山佐時計計器の万歩計に次ぐヒット商品、わんにゃんぐるめ。犬猫の2食分をタイマーで自動給餌する仕組み
↑山佐時計計器の万歩計に次ぐヒット商品、わんにゃんぐるめ。犬猫の2食分をタイマーで自動給餌する仕組み

 ↑万歩計とわんにゃんぐるめの知見を活かして開発された、犬用のわん歩計。しかし、正確な歩数を計ることは難しく、運動量を計ることを目的としていたそうです
↑万歩計とわんにゃんぐるめの知見を活かして開発された、犬用のわん歩計。しかし、正確な歩数を計ることは難しく、運動量を計ることを目的としていたそうです
歩数を計る際のスマホの盲点とは?
――長きにわたって万歩計の開発をされてこられたわけですが、万歩計自体もデジタル化が進み、近年ではスマホなども登場し、販売において苦戦されることはなかったですか?
山田 万歩計のデジタル化は1987年から取り組んできましたが、やがて2006年に3D加速度センサーというものを弊社の万歩計にも取り入れました。
前後・左右・上下どの方向からでも下を見て計れるし、センサー自体もすごく小さい。これを元に万歩計からさらに派生させて、活動量計という商品も販売しました。たとえば「家事をしていた」「デスクに座っていた」といった歩いていない状態であっても、総消費カロリーが計れるという画期的な商品でした。
しかし、この3D加速度センサーは同時にスマホやタブレットなどにも組み込まれていまして、特にウェアラブルによって、計数機能がすべてこういったデバイスに集約されていくのではないかと弊社も危惧したところがありましたが、現状では影響がなく、むしろ改めて万歩計はもちろん弊社の計数機の支持が高まっている状況です。
――どうしてでしょうか?
山田 やはり一番健康に気を配る高齢者の方にとって「スマホは使いずらい」ということが一番ですね。あと、たとえばスマホやスマートウォッチで歩数を計る機能があっても、従来の万歩計に比べて、正確に計れないこともあります。
さきほど言った四足歩行の動物は正確な歩数を計ることが出来ないのと同じで、近未来はまだわかりませんが、現状のスマホやスマートウォッチでの歩数機能は、歩くこととは別の振動でもカウントしてしまうことがあります。
その点は弊社が最もこだわりを持ち開発をしているところですので、現状ではスマホやスマートウォッチよりも正確な歩数を計ることが出来るのです。
あと、若い世代の方であっても、健康のために歩くとなったときにスマホやスマートウォッチを持つのは意外と大変です。女性の方ですと、スカートにはポケットがないですから、スマホを手に持って歩かないといけないわけですから。そういう意味で、従来の万歩計の支持が改めて高まっているのだと思います。
いま、弊社でヒットしているのがウォッチ万歩計という商品ですが、必ず左手首上面につけていただくことで、正確な歩数を計ることが出来ます。約30グラムと軽いですし、これはウォーキングには最も適している商品だと自負しています。
 ↑男性用、女性用とあるウォッチ万歩計。スマートウォッチでも勝てなかった、長きに渡る万歩計の知見が反映されたヒット作!
↑男性用、女性用とあるウォッチ万歩計。スマートウォッチでも勝てなかった、長きに渡る万歩計の知見が反映されたヒット作!

1日8000歩・速歩き20分でだいたいの病気は予防できる?
――山佐時計計器が推奨する「歩き方」はどんなものですか?
山田 弊社では東京都健康長寿医療センター研究所の青栁幸利先生監修の万歩計を販売していますが、この青柳先生が世界で初めて「1日8000歩、その中に速歩きを20分すると、だいたいの病気の予防ができます」というエビデンスを取り、発表しています。
それまではだいたいザックリと「1日1万歩歩けば良い」と言っていましたが、こういった識者の方の提唱を弊社でも採用させていただき、推奨しています。
――速歩きでないとダメなんですね。
山田 大股で速く、力強く歩くことで、心拍数が上がって体に良いわけですね。
――マラソンと比べてみると、どうでしょうか?
山田 マラソンは若い方にとっては良い運動と思いますが、高齢者の方には怪我のリスクがあります。それよりは一番安全に出来る運動……歩くこと、ウォーキングを習慣付けることで、病気予防をし、健康を保っていただくほうが良いのではないかと思っています。
 ↑青柳幸利先生が監修した最新万歩計
↑青柳幸利先生が監修した最新万歩計
 ↑都内の環状八号線沿いにある山佐時計計器本社の外壁には、スローガン「歩きを楽しく」が大きく書かれていました
↑都内の環状八号線沿いにある山佐時計計器本社の外壁には、スローガン「歩きを楽しく」が大きく書かれていました
健康志向が高まる今、再注目される万歩計。その世界は奥深く、また日進月歩で進化していることがわかりました。明日からの健康管理に改めて万歩計を加えてみてはいかがでしょうか?
山佐時計計器公式サイト
http://www.yamasa-tokei.co.jp/