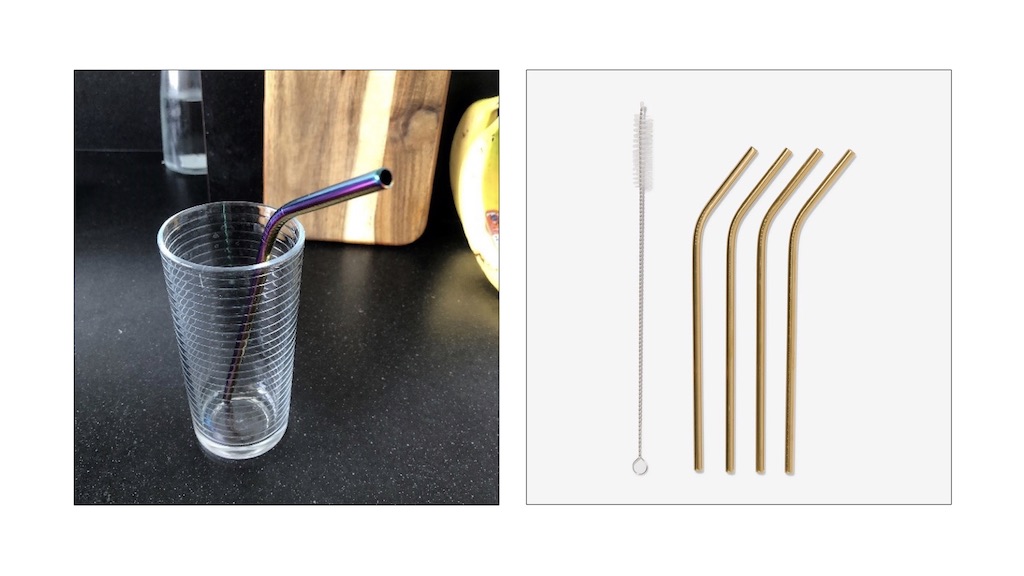お鍋が似合う季節になりましたね。

キムチ鍋に寄せ鍋、ちゃんこ鍋もいいし、あぁ~湯豆腐もいいですよね。そんなお鍋のベストパートナーといえば、せーの、、、ポン酢! 最近では、さっぱり煮などの新しいレシピで注目を浴びたり、サラダに使ったりとオールマイティさを発揮していますが、やっぱり一番合うのはお鍋でしょう。ということで、今回はお鍋に欠かせない「ポン酢」についてじっくりと考えてまいります。
ポン酢には「酢」が入っていない?
ポン酢というからには、「酢」が入っているでしょう~! と思っている方も多いかもしれませんが、『なぜ?どうして? 身近なぎもん5年生』(三田大樹・監修/学研プラス・刊)によると、もともとのポン酢には「酢」が入っていないんだとか。
ポン酢は、ゆず、レモン、すだち、だいだいなど、みかんの仲間のしぼり汁と、しょうゆを混ぜて作る調味料です。これを考えだしたのは、日本人です。
(『なぜ?どうして? 身近なぎもん5年生』より引用)
本当~!? と思って、急いで冷蔵庫に入っているポン酢を確認して見たところ、原材料の五番目に「醸造酢」の文字が。そう、商品によっては入っていましたが、メイン調味料ではなかったのです。私は勝手に、柑橘類の「ぽんかん」あたりと酢を混ぜて、「これだとただ酸っぱいだけだし、醤油でも入れる?」みたいなノリで出来た調味料だと思っていました。
だって「ポンジュース」とか言うじゃない? と思って、こちらも調べて見たところ「ポンジュースのポンは日本(ニッポン)のポンからとりました」って。。。ポンとは一体・・・!
参照:https://www.ehime-inryo.co.jp/pomstory/
ポン酢の語源はオランダ語の「ポンス」
じゃあ「ポン」って何よ! 「酢」って何よ! という方、焦らずに。
ポン酢の語源は、オランダの「ポンス」というお酒から来ているとも言われています。このポンスはぶどう酒やブランデーなどのお酒に果物のしぼり汁と、砂糖、香辛料を加えて作ったカクテルで、オランダ人によって長崎に伝えられ、食前酒として飲まれていたそうです。
日本で、ポンスがポン酢になったことについては、主に二つの話が伝わっています。
一つは、ポンスが「ポンズ」に変化して、「ズ」に「酢」という字を当てたという話。もう一つは、ポンスの「ス」に、「酢」という時を当てて、「ポン酢」と読むようになった、という話です。
(『なぜ?どうして? 身近なぎもん5年生』より引用)
当て字って・・・。
そもそも、お酒が語源だったとは驚きです。つまりは、
日本人A 「オランダ人が食事の前に飲んでるお酒うまかったなぁ」
日本人B 「ポンスって言うらしいよ」
日本人C 「最近さ、醤油に果物のしぼり汁入れるとうまいって発見したんだよね」
日本人A 「どれどれ? なんかポンスみたいな風味があるなぁ」
日本人B 「酸っぱいし、これは『ポン酢』って名前にしたらどうだ?」
日本人C 「いいね! 粋だぜ!!」
みたいな感じで決まっちゃったんでしょうね。オランダ人が、「日本のポンスですか~」なんてグビグビ飲んじゃったらおおごとになってしまいますので、くれぐれも注意しなくてはいけませんね。
そういえば、酢を飲むと体柔らかくなる説があったような・・・。
今回のトリビアは、「何へぇ~」いただけたでしょうか。ちなみに、ポン酢ではあまり使われていないお酢ですが、一時期『酢を飲むと体が柔らかくなる!』なんてトリビアもありました。
昔は、酢を飲むとからだがやわらかくなるといわれたことがありました。しかし、それは必ずしも正しくありません。酢はからだによい働きをしますが、酢が原因でからだがやわらかくなることはありません。
(『なぜ?どうして? 身近なぎもん5年生』より引用)
体がやわらかいと、血の巡りが良くなり、これからの時期冷えの解消にもつながりますし、雪道で転倒しても反応ができるようになりケガの予防にもつながります。お酢に頼らず、ストレッチでほぐしていきましょう。
今回ご紹介した「ポン酢」以外にも、日頃から当たり前に使っているものの中にも「そういえば・・」と、考え込んでしまう言葉はたくさんあります。大人になっても「なんで?」「どうして?」の気持ちを忘れずに、どんどん探求していきたいものですね。
(文:つるたちかこ)
【文献紹介】

なぜ?どうして? 身近なぎもん5年生
監修:三田大樹
出版社:学研プラス
指に指紋がある理由やポン酢のポンの意味、ゲームソフトはどうやってつくるのかなど、5年生が身近に思う40の疑問について楽しくわかりやすい文と絵で紹介。津波が起こるしくみ、液状化現象についても掲載。朝の読書に最適の一冊。
Kindleストアで詳しく見る
楽天Koboで詳しく見る
iBooksで詳しく見る
BookBeyondで詳しく見る
BookLive!で詳しく見る
hontoで詳しく見る
紀伊國屋書店ウェブストアで詳しく見る