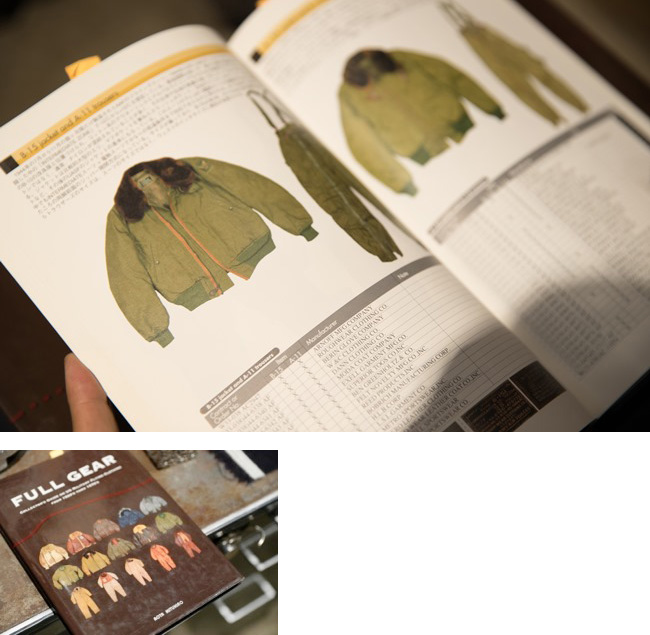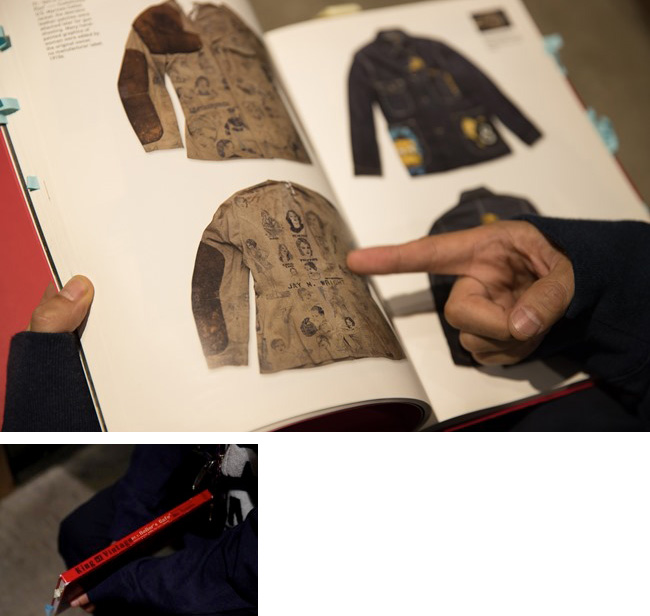【きだてたく文房具レビュー】調合で自分好みの色を作るインクと、色を外から楽しむ透明軸万年筆
昨年夏にパイロットの万年筆「カクノ」の透明軸が登場して以来、文房具ファン全体に「透明軸万年筆、いいじゃん」という声がグッと広がっている。
透明軸は、中に入っているインクの色が楽しめるということで、もともと古くからの万年筆ユーザーに一定の人気はあった。そこへ、カクノから万年筆を覚えた新しい人たちが「万年筆って書き味がいいよね」と加わり、そこからさらに「インクもいろいろ遊ぶと面白いよね」というステップに進んだのだろう。
文具好きの間ではおなじみの“インク沼にはまった”、というやつだ。
そこで今回は、透明軸と一緒にインク沼でちゃぷちゃぷ楽しく遊ぶのに向いたツールを、紹介したい。

2011年にプラチナ万年筆から発売された「ミクサブルインク」は、9色のラインナップからさらに自分で色を混ぜてオリジナル色が作れるというインクだ。
ただ、このミクサブルは大きめの60ml瓶入りということもあり、「ちょっと遊んでみたい」ぐらいの感覚では量を持て余す、という意見もあったらしい。そこで新たに発売されたのが、20mlの小瓶サイズ「ミクサブルインク ミニ」だ。

万年筆のインクは、例えば普通のブルーインクも「青」という単一の色素だけで作られているわけではない。複雑にいくつもの色素を重ねることで、あの発色をしている。つまり、単純にブルーとイエローのインクを混ぜてグリーンを作ろうと思っても、実際には予想外に濁った変な色になってしまうことがありえるのだ。

対してミクサブルインクは、1色が可能な限り少ない色素で構成されているため、混色したときに比較的イメージした通りの色になってくれる、という仕組み。
とはいえあまり何色も混ぜると、やはり濁ったドブ色とか、単なる黒になってしまうので注意。メーカー推奨でも、最初は2色から混ぜてみましょう、ということになっている。

ポイントは、最初から「こんな感じの色にしたい」というイメージを作っておくこと。ただ漠然と混ぜるのではなく、「エルメスのあのオレンジ色」「鹿島アントラーズのあの赤」「阪急電車のあの茶紫色」のように、自分の推し色を目標に据えておくとやりやすいはず。
別売りのインク調合キットには、スポイトや空ボトル、うすめ液が入っているので、インクと一緒に買っておくと作業がスムーズ。特にうすめ液は「ちょっと色が濃すぎるなー」という時に少し調整ができるので、あると便利だ。
このスポイトで1色につき1メモリずつ取って小皿(100均の紙皿でOK)で混ぜると、1:1の混色インクが出来上がり。

このとき、スポイトは使う度に毎回水で洗浄すること(最重要)。紙コップに水を入れておいて、こまめに中まですすがないと、残ったインクのせいで妙な混色ができてしまう。
あとは、使った色と比率を“レシピ”として記録しておくのも重要。レシピさえあればいつでも色が再現できるので、面倒くさがらずにきちんとメモしておくと良い。
できた混色インク、イメージと違う……といって、流してしまうのはちょっと気が早い。これが実際に紙に書いてみるとまったく印象が違ったり、さらには乾くとまた全然別の色に見えたりすることも、ままあるのだ。
ということで、混ぜたインクはまず試し書きをしてみよう。

試筆はガラスペンがあると便利なのだが、そんな洒落たモノを使わなくても、爪楊枝や割り箸で充分に代用になる。これで思ったような描線になったら、オリジナルインクの完成だ。レシピ通りの比率で量産しよう。
さて、インクができたら、やるべきことがふたつある。インクを保存する、と、万年筆に入れる、だ。
保存に関しては、調合キットの空ボトルや100均のミニボトルでも構わないが、ミクサブルインク ミニの空インク瓶も発売されている。気分的にはこちらの方が“インク作った感”が強いので、余裕があればぜひ。

万年筆に関しては、せっかく作ったインクだもの。この稿の最初で述べた通り、透明軸の万年筆に入れて使いたい。
いまはカクノを始め、1000円前後の低価格帯万年筆でも透明軸が出揃っているが、中でもコスパという点で最強なのは、ミクサブルインクと同じくプラチナ万年筆の透明軸「プレピー クリスタル」だ。なんと432円で充分に万年筆の書き味が楽しめるローコストっぷり。オリジナルインクを入れるコンバーター(インク吸入タンク)を足しても、1000円前後で済むのは素晴らしい。現時点では、世界で最も安く揃う透明軸万年筆なのだ。
さらにプレピーは、キャップをしたままなら1年放置してもインクが干上がらないスリップシール機構を搭載しているのも、ありがたい。
オリジナルインク作りにハマると、だいたい次々と新色を作っては万年筆に入れて並べてみたくなるもの。そういう意味でも、高コスパな透明プレピーは使いやすいだろう。

ぶっちゃけた話、ミクサブルインクもミニボトルとはいえ全色+調合キットを揃えて遊ぶとなると、金額的には1万円を超えてしまう。あまり“安価に楽しむ”というレベルではないかもしれない。とはいえ、インク沼にハマって次々と新しいインクを買ってしまうぐらいなら、自分の理想の色を混ぜて作ってしまう方が手早いし、安く済む可能性もある。
なにより、色を混ぜて遊ぶというプリミティブな楽しさは、ホビーとしてかなり魅力的なのだ。
【著者プロフィール】
きだてたく
最新機能系から駄雑貨系おもちゃ文具まで、なんでも使い倒してレビューする文房具ライター。現在は文房具関連会社の企画広報として企業のオリジナルノベルティ提案なども行っており、筆箱の中は試作用のカッターやはさみ、テープのりなどでギチギチ。著書に『日本懐かし文房具大全』(辰巳出版)、『愛しき駄文具』(飛鳥新社)など。近著にブング・ジャムのメンバーとして参画した『この10年でいちばん重要な文房具はこれだ決定会議』(スモール出版)がある。