朝起きると、窓の桟(サン)が水滴でビショビショ……おなじみの「結露」です。ただの水だと放置しておくと、しだいに周囲のカーテンや壁紙にカビが発生。しまいには、健康被害に及ぶこともあります。どう対策すればいいのでしょうか?
そもそも結露とはなぜ起きるのか、メカニズムを知ったうえで、しっかりと対策しましょう。掃除のプロで、清掃マイスターの資格ももつ山口かなさんに教えていただきました。
「結露」はなぜ発生する?

結露とは、暖かく湿った空気が冷やされ、空気の中に存在している水蒸気(気体)が水(液体)に変化すること。
「空気中には水蒸気が含まれていますが、空気中に含まれる水蒸気の量には限度があり、それを『飽和水蒸気量』といいます。この飽和水蒸気量は気温が低くなると小さくなるため、空気中にいられなくなった水分が水滴として現れるのです。反対に、気温が高くなると空気中に存在できる水分量は増えます。身近な例を挙げれば、氷入りのお冷やのグラスには、うっすらと水滴がついていて、やがてこぼれ落ちていきますよね。この現象が結露です。
これと同じように、冬は部屋の中で暖かく湿った空気が、冷たい外気で冷やされた窓にふれることにより、窓の表面に水滴が発生するのです」(日本清掃収納協会・山口かなさん、以下同)
つまり、空気中に水蒸気がたくさん含まれているときに気温差が起きると、結露が発生するわけです。外気温が低い冬に室内をエアコンで温め加湿していると、とたんに窓には結露が起きます。そして結露は冬だけのものではありません。空気中の水分量が多い梅雨には、室内で冷房を使うことで、空気が滞留しやすいさまざまな場所で結露が起きてしまいます。
結露を放置しておくとどうなる? 結露が引き起こすトラブルとは

結露をそのままにしておくと、さまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
「まず、建物への影響がでます。水分が付着した家具、壁紙、カーテンにカビが発生すると見た目にもよくありませんし、カビをきれいに掃除することもとても大変です。さらに悪化すると、壁紙の内部にカビがぎっしりということも。また建物内部の構造を支える木材にも腐食やサビが起こり、住宅自体の耐久性や性能の低下になり、住宅の寿命を縮めてしまう恐れがあります。
建物内にカビが発生すると、それを食べるダニが繁殖していきます。カビの胞子やダニの死骸が呼吸により体内に入ることで、アレルギー性皮膚炎や喘息など、シックハウス症候群の症状が出ることも考えられますね。
カビやダニは、暖かく湿った環境で盛んに繁殖します。カビやダニを増やさないようにするためには、まず結露を発生させないよう、適正な温度と湿度を保つことが大切です。結露を放置せず、毎日の生活の中でこまめに対策していきましょう」
ちなみに、賃貸物件の場合でも、結露を放置した結果カビが発生し部屋内に汚損が発生した場合には、借主の責任になることもあります。このように、 “ただの水” と捉えていると多くの弊害につながるので注意が必要です。
では、やっかいな結露を防ぐために、どのように対策を行えばいいのでしょうか?
結露を予防する正しい対策
まずは、結露が発生しない環境を整えることが大切です。
「温度と湿度を適切に保つことが大切です。結露ができる室内と外気の温度差は、湿度の高さにより変わります。湿度が高い状態では、温度差がわずかであっても結露が発生しやすくなるのです。そのためには、なるべく室内の湿度を下げておくことが大切です。とくに結露の発生しやすい窓まわりの湿度を重点的に下げましょう。結露を発生させない環境を整えるために、以下のようなことに気をつけてください」
1.換気する
「もっとも大切なのが換気です。朝起きたら一番に窓を開ける。部屋がジメジメしてきたなと感じたらそのたびに換気をする。それだけでもお部屋の環境は改善されます。
部屋の作りにもよりますが、対向する場所に窓があるなら両方を開けて風の流れをつくることも効果的です。部屋に窓が少ない場合は、窓を開けると同時に台所の換気扇をつけてください。また、24時間換気システムがある場合は、つけっぱなしにしておきましょう」

2.窓の近くに除湿機を置く
「結露は空気中の水分が冷たい外気で冷やされた窓に接することによりできるので、窓付近の湿度を下げることが大切です。窓際の壁に付近に除湿機を置きましょう。設置の際、除湿機の向きは自由でかまいません」

3.エアコンをドライ設定にする
「湿度が高いとカビが生えやすくなります。カビを防ぐためには湿度を適切にキープするドライ機能を活用しましょう。年中つけておく必要はありませんが、湿度が高くなる梅雨や結露の生じる冬場はおすすめします。ただし、ずっとつけておくと乾燥し過ぎてしまうので、じめじめしていると気になったときにつけるようにしてください」

4.窓の近くに水槽を置かない
「水の入っている水槽は加湿の原因になります。窓際に置くと結露を誘発するので、水槽を置く場合は外気に面した壁側ではなく、部屋の中心に近い場所に置きましょう。観葉植物も多少は加湿になりますが、植物には水のほか太陽の光や、風も必要ですから、そう気にすることもありません。気持ちの良い窓際に置いてください。お世話するときに時に窓を開け、風通しを良くしてあげましょう」

結露が発生しやすい場所と掃除方法
このように対策しても結露が発生してしまったら、まずは換気をする。そして水滴のうちに取り除くことが何よりも大切、というのが原則。でもこまめに掃除するのは大変です。無理なくお手入れが続けられる方法を、具体的に解説していただきましょう。
【準備】揃えておきたい結露対策3アイテム
「結露の掃除には、スクイジー、吸水タオル、クロスこの3つを揃えておけば十分です。最近ではいろいろな、結露掃除のアイテムが販売されていますが、『ここにはこの道具。あちらにはこの道具……』と用途を分けてしまうと複雑になり、かえって掃除が面倒になることも。すぐに行動に移せるように、アイテムは必要最低限のものだけでOKです」

アイテムの選び方のポイント
・スクイジー
「持ち手と先端のゴムの部分が一体化されているものよりも、先端のゴムの部分が劣化してしまうので交換可能なものを選ぶといいでしょう。最近では、持ち手の部分がボトル形状になっていて水滴が溜まる仕組みのものもあります」
・吸水タオル
「掃除用道具として販売されていますが、カー用品や水泳用の吸水タオルもあります。基本的にはどれを選んでもかまいませんが、吸水しやすく、絞りやすいものがおすすめです」
・クロス
「どんな場面にも活用しやすいクロスは吸水性が良く絞りやすいものを。最近ではさまざまなデザインのクロスがあるので、気に入った色や柄を選ぶといいでしょう」
・タオル
「クロスがない場合にはタオルで代用してもかまいません」
・吸水スポンジワイパー
「高いところも拭き取れるのであると便利なアイテムですが、必須ではありません」
1.窓と窓枠

「もっとも結露が発生するのが窓と窓枠。とくに発生しやすい時間帯が朝です。忙しい時間帯ではあるものの、このタイミングでのお手入れがカビやダニを繁殖させないためにも重要です」
【掃除方法】
(1) 窓枠の下に吸水タオルを置く

「垂れてきた水滴をキャッチするための吸水タオルを置きます」
(2) スクイジーを上から下に動かす

「スクイジーの傾きは中心の方を下げるように使うと、窓の端に水が落ちることなく、吸水タオルの上に落ちていきます」
(3) 前列の拭いたところとかぶるようにスクイジーをあてる

「次は、前に拭いたところとかぶるようにスクイジーをあて、上から下に動かします。拭いたところを重ねることで拭き残しを防ぎます」
(4) スクイジーを右から左に動かす

「ガラス全体を上から下にと拭き終えたら、下部を右から左に一拭きしましょう。下に溜まった水をまとめて落とすことができます」
(5) 窓枠の水滴も忘れずに拭き取る

「最後にクロスで窓枠の水滴を吹き取ります。結露はガラス面につきやすい印象ですが、実は窓枠のサッシにも多く付いているので注意が必要です。この部分は窓の木枠等と直に接しているため、放置してしまうと木製の枠の場合はそこから腐食してしまう恐れがあります。ぜひ忘れずに水分を拭き上げてください」
2.玄関ドア

「南側にリビング、北側に玄関がある間取りをよく見かけます。北側は太陽の光がが入りづらく寒いので、結露が発生しやすい場所です。とくに玄関ドアの素材が金属である場合、結露しやすいので確認してください」
【掃除方法】
(1) 吸水スポンジワイパーでさっと拭きあげる

「玄関扉には柄のついた吸水スポンジがあると一拭きですべて終わらせることができて時短に。柄があることにより手では届かない上や、腰をかがめないといけない下の部分を、姿勢を変えずに掃除することができる点でもおすすめです」
3.トイレのタンク

「意外と見落としがちなのがトイレのタンクです。トイレはほかの場所に比べ温度が低いことも原因の1つ。また雑菌などが繁殖しやすい空間でもあるため結露を放置するとカビの温床になりかねないのです」
【掃除方法】
(1) こまめにクロスで拭く

「トイレのタンクの素材が陶器の場合は結露になりやすいのです。確認して結露がある場合には、クロスでこまめに水滴を拭き取りましょう」
カビの発生する3つの要因と対策方法
それでもカビが発生してしまった場合の対処法についても教えていただきました。カビは「温度」「湿度」「ホコリ」の3大条件が揃った時に発生します。つまり、この条件が揃わない環境づくりが大切です。
・温度
「カビは通常0〜40℃の範囲で生育可能ですが、種類によっては0℃以下で生育したり、高温でも死滅はしないものもあります。人間が快適な20〜30℃がカビにも快適で繁殖しやすいため、温度を調節してカビ繁殖を防ぐのは難しいかもしれません」
・湿度
「カビは80%以上で活発に繁殖します。中には60%以下でも繁殖できるカビもいます。大切なのは、湿気のもととなる水分をこまめに拭き取ること、また通気をして湿気をため込まずお部屋の空気循環をよくすることが大切です。24時間換気システムは常時つけておき、換気システムがない場合は換気扇を常時つけておくことをおすすめします」
・ホコリ
「カビは、ホコリだけでなく食べ物、人のアカや髪の毛、プラスチックなども栄養にします。汚れているものはすべてがカビのエサになると肝に銘じて、日ごろからこまめに掃除するように心がけましょう」
では、カビを増やさないための具体策とは?
1.窓、カーテン、そしてカーテンレールを掃除する

「カーテンを開け閉めすると、ホコリが舞います。ホコリに水分が付着することによりカビを繁殖させてしまいます。ぜひカーテンやレースカーテンの洗濯も定期的にしていただきたいですね。カーテンの洗濯時期としては、結露が増える冬の前の秋頃がいいタイミングです。また、見えていないカーテンレールにもホコリが堆積してしまいます。ホコリが溜まってないかチェックしてください」
2.カーテンを買い替えの際に防カビ仕様の商品を選ぶ
「結露が発生しやすいお宅では、カーテンの買い替えを検討してみてはいかがでしょうか? 定期的なお洗濯はもちろんしていただきたいのですが、『防カビ』仕様のカーテンにするだけで、日々のお手入れはしやすくなります」
3.窓の出窓などに本や布を置かない
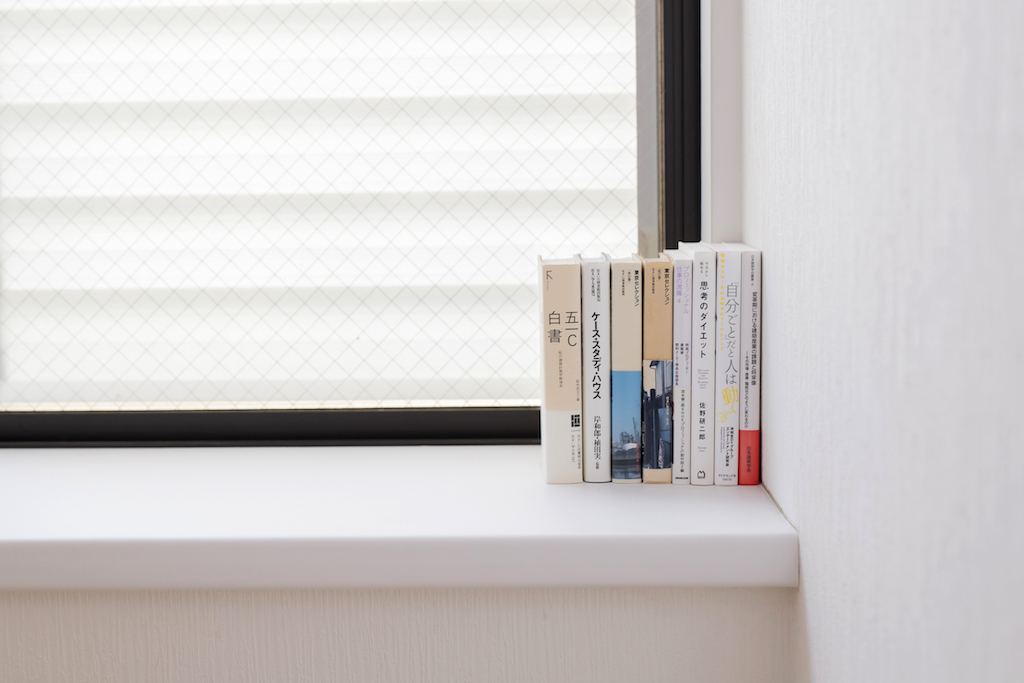
「窓付近は湿度の高い場所なので紙や布を置いておくとカビが発生する原因となります。また、物を置くことで、掃除をするたびにものをどかさないといけません。そうなると窓周辺のお掃除も行き届かなくなります。窓の周りはできるだけものを減らし、いつでも掃除しやすい状態にしておくことが理想的です」
壁にカビが発生してしまったら? 早めに対処したい掃除方法

壁紙表面にカビが発生すると徐々に繁殖していきます。早めに掃除をしましょう。カビの繁殖段階に応じて掃除方法を教えていただきました。
【STEP 1】
まずはアルコールで軽く拭く
「発生後すぐであれば消毒用のアルコールで拭き取ります」

【STEP 2】
落ちない場合は中性の食器用洗剤を薄めて拭く
「カビが落ちない場合には、食器用洗剤を水に少し混ぜて、やさしくこすりましょう」

【STEP 3】
どうしても落ちない時は塩素系の漂白剤を薄めて拭く
「それでもカビが落ちないときは塩素系の漂白剤を水に100倍程度に希釈して拭き取りましょう。漂白剤は、酸素系でも良いのですが、塩素系漂白剤の方がより殺菌作用が強いためおすすめです。漂白剤を使う際には手袋をしてください。そして最後にクロスでしっかりと水分を拭き取りましょう」

【注意したいポイント】
「壁の素材によりお手入れ方法も違います。今回は一般的な、ビニルクロスのお掃除方法を説明しましたが壁紙のタイプによっては跡が残ってしまうこともあるので注意してください。また、洗剤等使用の際には、事前に目立たない場所で試してみてからおこなうようにしてください」
一見便利そうでも……結露対策グッズの注意点
最近では100円ショップでも結露やカビ対策のアイテムが数多く見られます。しかし山口さんはこのようなアイテムも使い方を間違えると逆に湿度の高い環境になってしまうと言います。
「例えば、最近流行の珪藻土でできたアイテムは、吸水するので一見さらさらに見えるのですが、実際は中に水分を吸収している状態です。定期的にベランダなどで天日干しをする必要があります。また、ガラス下部に貼り付けるタイプの吸水テープも使用期間があります。ところが、その期間や目安を超えて長くそのまま放置して使い続けているお宅も多く見受けられます。テープが窓にくっつき劣化し、糊がくっついてしまい剥がれにくくなることもありますのでご注意ください」
便利アイテムは、どのようなポイントに気をつけながら選べばいいのでしょうか?
「剥がした時に糊が付かないか? しっかりと水分を吸えているか? 効果はどのくらいの期間持続するのか? などをチェックしつつ、こまめに交換、お手入れを行ってください。結局のところ、面倒なことはやりっぱなしにしがちです。ご自身の生活スタイルにあったアイテムを選ぶようにしましょう」
こまめな換気と拭き取りが大切。あらかじめ掃除しやすい環境づくりを

「結露ができやすい環境であるかは、基本的に家の作りに起因してしまうことが多いのです。例えば、家の断熱性の違い、家の向き、家の気密性など。総合的な要因が重なり、結露が発生します。そして結露のある空間は、カビやダニの育つのに快適な環境であることには違いありません。家自体の性能を上げることはなかなかむずかしいですが、日々の改善方法で結露は緩和されます。
私がもっともお伝えしたいのは、やはり、換気をして水滴のうちに拭きとること。こまめにお掃除するのは大変と思うかもしれませんが、いつでもさっと行動できるように、窓周りに物を置かず、使いやすいお気に入りの道具を揃える。自分の中で、お掃除をするハードルを下げていける工夫をしてみましょう」
心地よい暮らしにするための極意は、物を減らして、お気に入りの道具で手入れをする。自分が前向きに行動するための環境をつくる___とてもシンプルで効率的な方法でした。
プロフィール

じぶんサイズ代表 / 山口かな
清掃マイスター認定講師、片付け収納マイスター認定講師、生前整理診断士。掃除や片付けの仕方を知らず苦手と感じていた自身の経験をいかし、依頼者の暮らしにあった最善の方法を提案している。また、親のための家事代行サービスを展開。住まいの整備にとどまらず、介護、施設の提案、葬儀、相続の提案など人生を総合的にサポートしている。
HP












