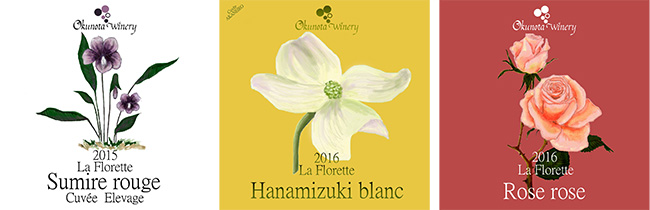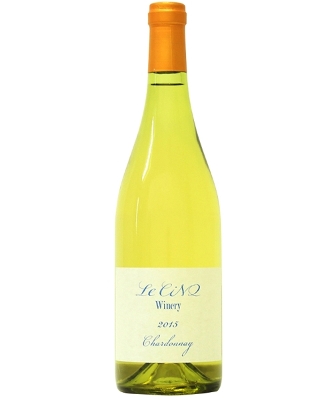自宅でワインを楽しみたい、できれば産地や銘柄にもこだわりたい、ワインを開け、注ぎ、グラスを傾ける仕草もスマートにしたい……。そう思っても、超のつく基本はなかなか、他人には聞きにくいもの。この連載では、その超基本を、ソムリエを招いて手取り足取り教えていただきます。さすがに基本は押さえている、という人にも、プロが伝授する知識には新たな発見があるでしょう。教えてくれるソムリエは、渋谷にワインレストランを構える宮地英典さんです。
第1回は「ワインボトルの開け方」、第2回は「ワインの注ぎ方」を、宮地さんに指南していただきました。第3回となる今回からは、ワインの種類や製法、産地などをそれぞれ取り上げ、解説していただきます。
第3回 スパークリングワインの製法と種類
ワインには、泡のない「スティルワイン」と発泡性の「スパークリングワイン」があります。泡があるということは想像以上に香りや味わいに大きく影響を与えるもの。気が抜けて泡の立たないビールやコーラを飲んだことがあれば、キンキンに冷えてガスがふんだんに含まれた状態とのおいしさの違いは、誰もが経験したことがあるのではないでしょうか。
さらに、スパークリングワインには産地や製法に多くのバリエーションがあります。今回は5つの製法と、5種類のワインを紹介しましょう。ただしもちろん、世界中にはこれだけではなくさまざまな個性のスパークリングワインが存在します。
また、「シャンパーニュ」(シャンパン)というと高級なイメージがあるかもしれませんが、産地のひとつに過ぎず、またハイブランドだけがスパークリングワインの魅力ではないのです。例えば1000円以下のスパークリングワインでも、お決まりのビールの代わりにこれで乾杯すれば、食卓にいつもと違った彩りを添えられるかもしれません。2000円~3000円前後の価格帯になれば、多種多様なスパークリングワインがありますから、ささやかなお祝いの席にぴったりでしょうし、ホームパーティーやBBQにお土産として持っていけば喜ばれるでしょう。
ワインショップの棚にはいろいろなスパークリングワインが並んでいて、もっともハズレが少ないのも、スパークリングワインの特徴です。そう考えると“ワインの入り口”にうってつけなのは、スパークリングワインなのかもしれません。
スパークリングワインの製法
- トラディショナル方式(瓶内二次発酵)
ワインは醸造酒で、アルコール発酵をさせて作ります。最初の発酵である“一次発酵”を終えたワインを瓶に入れ、糖分と酵母を加えて栓をします。すると瓶のなかで二度目の発酵“瓶内二次発酵”が始まり、炭酸ガスが発生します。瓶のなかに閉じ込められた炭酸ガスがワインに溶け込むことにより、きめの細かな泡を持ったワインが造り出されます。
産地によって期間の長さに違いはあるものの、瓶内でワインを澱(おり)とともに熟成させ、いわゆる“ブリオッシュのような”と表現される香ばしい風味をワインにもたせるのも、この製法の特徴です。
- シャルマ方式(タンク内二次発酵)
一次発酵を終えたワインを密閉式タンクに移し、糖分と酵母を加えて二次発酵を行う製法です。瓶内二次発酵に比べ、一度に一定量を生産することができるため、手間とコストの面で優れています。
ちなみにシャルマ方式とは、1910年にフランス人のユージン・シャルマが考案し命名されたものですが、1896年にイタリア人のフェデリコ・マルティノッティが実用化に成功していたという説もあります。こういった事柄からも、ワイン生産において今よりもフランスがリーディングカントリーだったことが伺えます。
- トランスファー方式
瓶内二次発酵で炭酸ガスを発生させたのち、一度密閉タンクにワインを移し、まとめて澱引き(澱を取り除くこと)を行う製法です。トラディショナル方式では瓶口に澱を集め、1本づつ澱引きを行いますが、トランスファー方式ではその工程をまとめて行うため、コストと手間を省略することができます。
- リュラル方式(アンセストラル方式)
一次発酵が完全に終わる前に瓶詰めし、発酵を継続したまま瓶内で炭酸ガスを発生させワインに溶け込ませます。フランスの「ペティヤン」(微発泡性ワイン)を始め、現在では小規模な生産者を中心にこの製法でスパークリングワインを造る生産者も増え、見直されている製法とも言えます。
- 炭酸ガス注入方式
スティルワインに炭酸ガスを注入して、人為的にスパークリングワインを造ります。コスト面で安価に仕上がるため、大量消費用スパークリングワインに用いられる製法です。
次のページでは、産地とそれぞれの呼び名や特徴、使用するブドウ品種などを、具体的におすすめの銘柄を挙げながら解説していただきます。
スパークリングワインの種類と特徴

産地については、具体的な銘柄を挙げながら説明していきましょう。スパークリングワインをより日常で楽しんでいただくために、比較的リーズナブルなワインを選びました。
スパークリングにはいろいろな呼び名があることは、是非とも覚えておいてください。また、生産国・地方やブドウ品種からでもイメージを膨らませることができると思いますが、わからない時には購入時に定員さんに相談するのもいいでしょう。
「シャンパーニュ」
シャンパーニュ地方で造られなければシャンパーニュにあらず
フランス北東部シャンパーニュ地方で造られるスパークリングワインを、シャンパーニュと呼びます。日本ではシャンパンとも呼びますが、これはイギリスの英語読みがシャンペンであることに由来するようです。
シャンパーニュは、現在では世界最高のスパークリングワインの産地でもあり、ブドウの価格の下限が世界でももっとも高価な産地でもあります(ワインの価格はブドウの価格とセミイコールと言っていいと思います)。もともとはブドウ産地としては最北(ドイツとイギリスなどは例外)に当たり、スティルワインの生産に不向きだったことが、この地域のスパークリングワインを特別なものにしました。
一般的には黒ブドウである、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、白ブドウであるシャルドネの3品種の果汁を使い、ワインを醸します。そして、瓶のなかで糖分と酵母を加え再び発酵させて産まれた炭酸ガスがワインと溶け込むことによって、あのグラスを立ち上る泡が造られます。つまりシャンパーニュの泡は、ブドウ果汁がワインになる過程で産まれるガスがそのまま一緒に瓶に内包され、ワインに溶け込んでいるということになります。この3品種のブレンドと瓶内二次発酵は、世界中のスパークリングワインのフォーミュラ(基本形)となっています。
また、シャンパーニュの立ち上る泡を「ペルル(真珠)」、液面で丸く輪状に広がる泡を「コリエ(首飾り)」とフランス語で呼びます。こういったシャンパーニュの華やかなイメージは、お祝いごとなど特別な日を楽しむのにうってつけ。気分を高揚させてくれるワインとして人気を集めています。

「Brut Tradition NV/Janisson&Fils(ブリュット・トラディションNV/ジャニソン&フィス)」
希望小売価格=6000円
【Info】
・ワイン名=ブリュット・トラディションNV
・生産者=ジャニソン&フィス
・生産国 / 地域=フランス / シャンパーニュ地方ヴェルズネイ
・ブドウ品種=ピノ・ノワール70%シャルドネ30%
・製法=トラディショナル方式(瓶内二次発酵)
・輸入元=ヴァンクロス
「プロセッコ」
実は世界一売れている、イタリアのスパークリングワイン
イタリアで造られるスパークリングワインは「スプマンテ」(後述)と呼ばれますが、中でも水の都ヴェネツィアで愛されるのがプロセッコ。2013年にシャンパーニュを抜いて世界でもっとも売れているスパークリングワインになりました。プロセッコに85%以上使われるグレーラは、フローラルで柔らかなワインになります。
プロセッコは、前述のシャルマ方式と呼ばれるタンク内二次発酵で造られます。シャンパーニュが瓶ごとに再度の発酵で炭酸ガスをワインに溶け込ませていたのと同様の工程を、大容量の密閉タンクの中で行うため、シャンパーニュに比べリーズナブルな価格でワインショップの棚に並びます。またワインの甘さの指針である残糖も大半のシャンパーニュが12g /L以下であるのに対し12g/L以上のものが多く、アルコール度数も12.5%前後のシャンパーニュに対し11%前後、熟成期間の違いから酵母由来のブリオッシュのような香りも産まれません。
こうして甘やか、優しい飲み口で軽やかというスタイルのプロセッコは、気軽にワインに親しむ文化を持つヨーロッパを中心に大流行しています。酔うためというより、少し気分を上げたい、理屈抜きで気軽にワインを楽しめるという点で、プロセッコはとても現代的なワインと言えます。例えば「ワインに氷を入れる」なんていうと抵抗がある人もいるかもしれませんが、プロセッコはそんな堅苦しいことも考えなくていいほど包容力のあるワインなのです。
若い世代のお酒離れが言われて久しいですが、プロセッコスタイルのワインがより広まり、さまざまな楽しみ方がなされれば、「ワインは難しい」というイメージを覆すことができるのでは、と個人的には期待しています。

「Prosecco Extra Dry NV/SanGiovanni(プロセッコ エクストラ・ドライNV/サン・ジョバンニ)」
希望小売価格=2600円
【Info】
・ワイン名=プロセッコ・エクストラ・ドライNV
・生産者=サンジョバンニ
・生産国 / 地域=イタリア / ヴェネト州コネリアーノ
・ブドウ品種=グレラ100%
・製法=シャルマ方式(タンク内二次発酵)
・輸入元=MONACA
「スプマンテ」
地方ごとの多様性こそがスプマンテの魅力
イタリアを代表する高品質スプマンテとして、ロンバルディア州東部で造られる「フランチャコルタ」(北イタリアのロンバルディア州で造られるスプマンテ全般を指す)があります。シャンパーニュと同様の品種製法により、高品質スパークリングの評価を勝ち取っているワインです。
よく「イタリアワインは品種が多すぎてわかりにくい」といった声を聞きますが、裏を返せばイタリアほど州によって栽培品種が異なり、地方ごとに料理と結びついたさまざまなワインが造られている国は、他にありません。なんと、イタリア全土で2000以上のブドウ品種が栽培されているのです。
つまり、イタリアのスパークリングワイン=スプマンテを特別にしているのは、その多様性にあるのではないかと個人的には感じています。下の写真は、トスカーナ州モンタルチーノで栽培される品種、サンジョベーゼを使ったロゼスプマンテ。サンジョベーゼはトスカーナの銘醸ワイン、キャンティやブルネッロの主要品種です。
同じようにさまざまな州で有名無名に関わらず、土地土地のブドウ品種でスプマンテが造られているのです。そう思うとイタリア語のスプマンテという語感には、包容力や多様性といった魅力的なイメージを感じずにはいられません。

「Spumante Rosato Brut NV/Ridolfi(スプマンテ ロザート・ブリュットNV/リドルフィ)」
希望小売価格=2500円
【Info】
・ワイン名=ロザート・ブリュットNV
・生産者=リドルフィ
・生産国 / 地域=イタリア / トスカーナ州モンタルチーノ
・ブドウ品種=サンジョベーゼ100%
・製法=シャルマ方式(タンク内二次発酵)
・輸入元=ミレニアムマーケティング
「カヴァ」
スペイン代表のカヴァは世界3大スパークリングワインのひとつ
カヴァとは、スペインで瓶内二次発酵で造られるスパークリングワインのこと。もともとカヴァの規定がブドウの原産地ではなく製法を定めたものだったこともあり、9割以上がカタルーニャ産ですが、その他内陸や沿岸部などそれ以外のさまざまな地域でも造られています。
シャンパーニュ、プロセッコに次いで消費されている世界3大スパークリングワインの一角、という言い方もできます。カヴァとシャンパーニュ(及びその他のピノ、シャルドネ系のスパークリング)との大きな違いは、最北のワイン産地シャンパーニュに比べ、スペインはより南の温暖な地域であり、栽培に適した品種が異なっていることではないでしょうか。
主要3品種はすべて白ブドウで、強いフレーバーがカヴァらしさを演出するチャレッロ、ニュートラルでバランスを取るマカベオ、デリケートな酸味をワインに加えるバレリャーダ。それぞれ南品種らしい果実感とアロマティックなニュアンスが特徴です。そのほかにシャルドネ、スビラ・パレンの白ブドウ、ガルナッチャ、モナストレル、トレパ、ピノ・ノワールの黒ブドウが、原産地呼称の認可品種となっています。
現地でも最大手となる「フレシネ」はサントリー、「コドルニュー」はメルシャンといった大手で取り扱われ、日本でもコンビニエンスストアやスーパーマーケットにも並ぶ親しみやすいワインです。なにより品質の割に価格がリーズナブル。ワインに親しむ入り口のひとつになる可能性は充分です。

「Cava TempusⅢ Brut ReservaNV/Torre Oria(カヴァ テンプス・トレス・ブリュット・レゼルバNV/トレ・オリア)」
希望小売価格=1500円
【Info】
・ワイン名=テンプス・トレス・ブリュット・レゼルバNV
・生産者=トレ・オリア
・生産国 / 地域=スペイン / カタルーニャ州
・ブドウ品種=マカベオ90%パレリャーダ10%
・製法=トラディショナル方式(瓶内二次発酵)
・輸入元=東亜商事
「ゼクト」
ビール好きのドイツ人はスパークリングワインの消費量も世界一
ドイツといえばビール大国というイメージがありますが、お祝いの席にはスパークリングワインが欠かせません。意外にもスパークリングワインの消費量は世界一、一人当たり年間4本以上というのは日本人の年間ワイン消費量と同程度です。
ゼクトとはドイツにおけるスパークリングワインの総称ですが、オーストリアやハンガリー、チェコといった近隣のエリアでも同様に呼びます。
近年、ドイツやオーストリアでは、シャンパーニュに倣って瓶内で酵母の澱と長期間に渡って熟成させる高級レンジのゼクトが注目されていますが、やはり消費量が多い要因は何といっても、低価格帯ながら高品質な点にあります。シャンパーニュと同様の品種を使用することもありますが、スプマンテのように地域ごとの固有品種が使われていることも魅力のひとつです。
日本のワインショップに並んでいるゼクトにはまだまだ限りがあると思いますが、コストパフォーマンスもよく、個性的なものも多いため、品ぞろえの良いお店では思い切ってゼクトを探してみるのもおすすめです。カヴァは日本ではリーズナブルで美味しいというイメージを獲得しましたが、個人的にはゼクトももっと認知が広がって、幅広いワインが輸入されることを願っています。

「Bacharacher Riesling Sekt Brut2014/Ratzenberger(バッハラッハー・リースリング・ゼクト・ブリュット2014/ラッツェンベルガー)」
希望小売価格=3700円
【Info】
・ワイン名=バッハラッハー・リースリング・ゼクト・ブリュット2014
・生産者=ラッツェンベルガー
・生産国 / 地域=ドイツ / ミッテルライン
・ブドウ品種=リースリング100%
・製法=トラディショナル方式(瓶内二次発酵)
・輸入元=ヘレンベルガー・ホーフ
スパークリングワインを楽しむ際には、よく冷やしてください。温度が高いとガス圧でワインが吹きこぼれやすくなるのと、ぬるいビールや炭酸ジュース同様、温度が味わいに大きく影響を与えるのがスパークリングワインです。
【プロフィール】
ソムリエ / 宮地英典(みやじえいすけ)
カウンターイタリアンの名店shibuya-bedの立ち上げからシェフソムリエを務め、退職後ワイン専門の販売会社ワインコミュニケイトを設立。2019年にイタリアンレストランmiyajiaraiを開店。
https://www.facebook.com/miyajiarai/