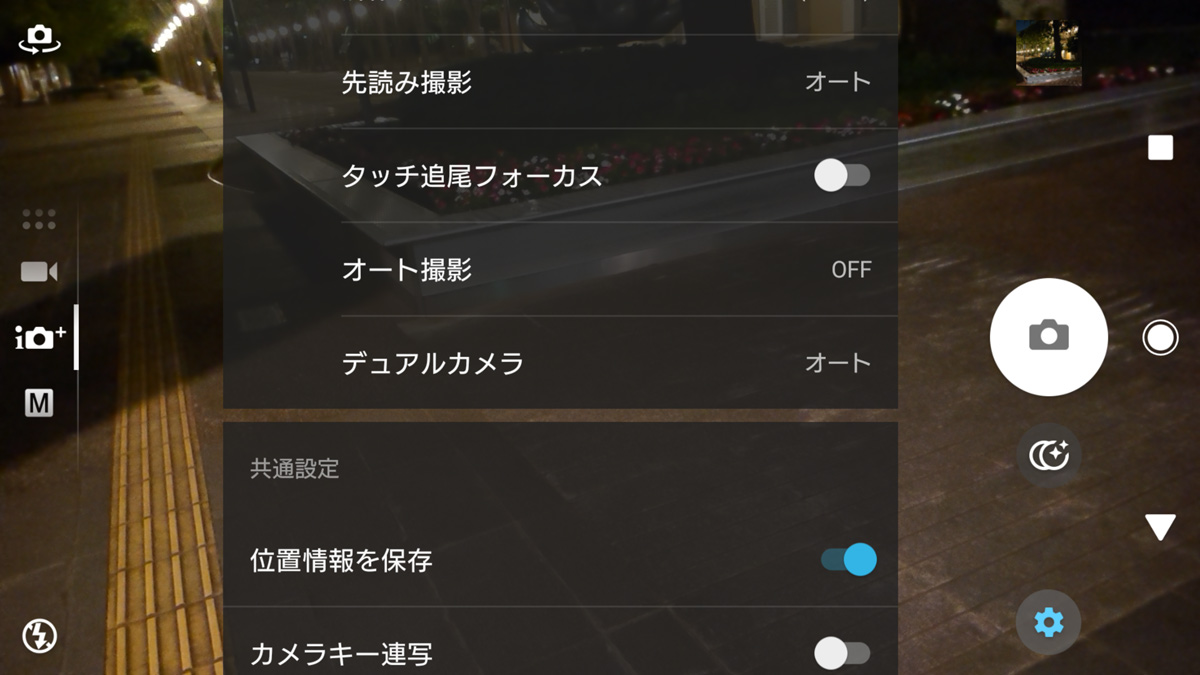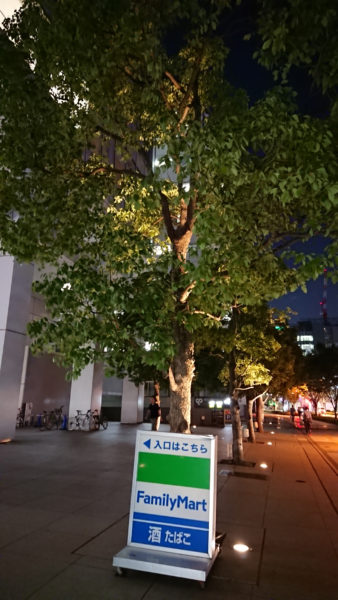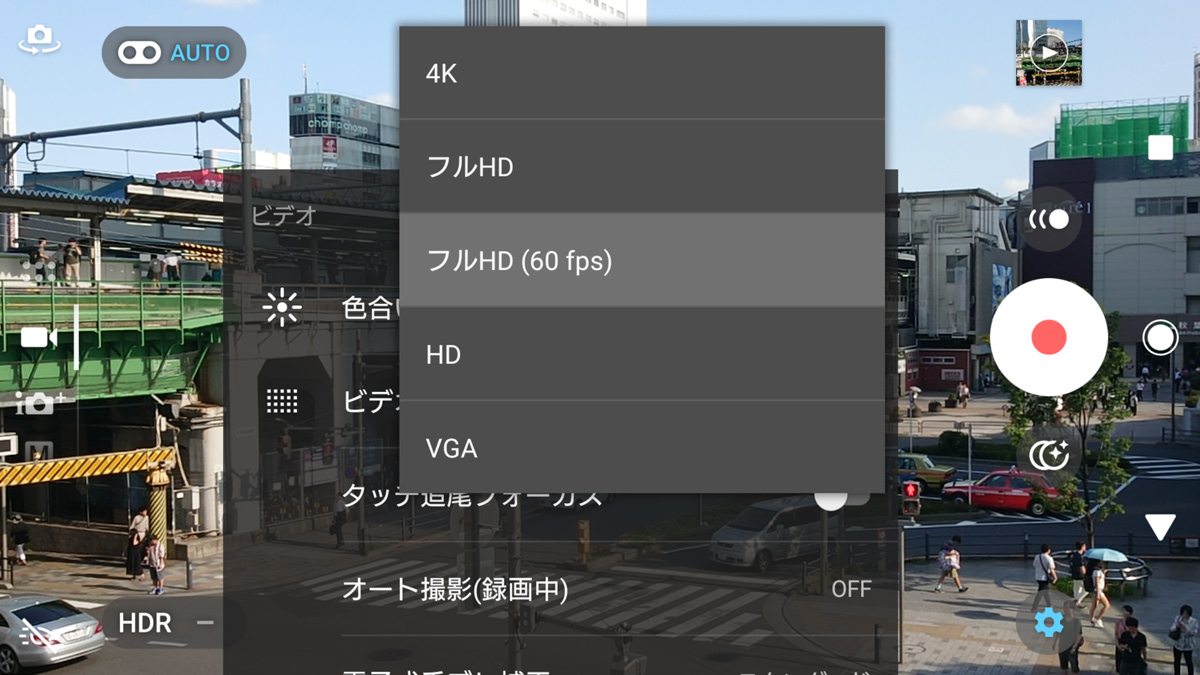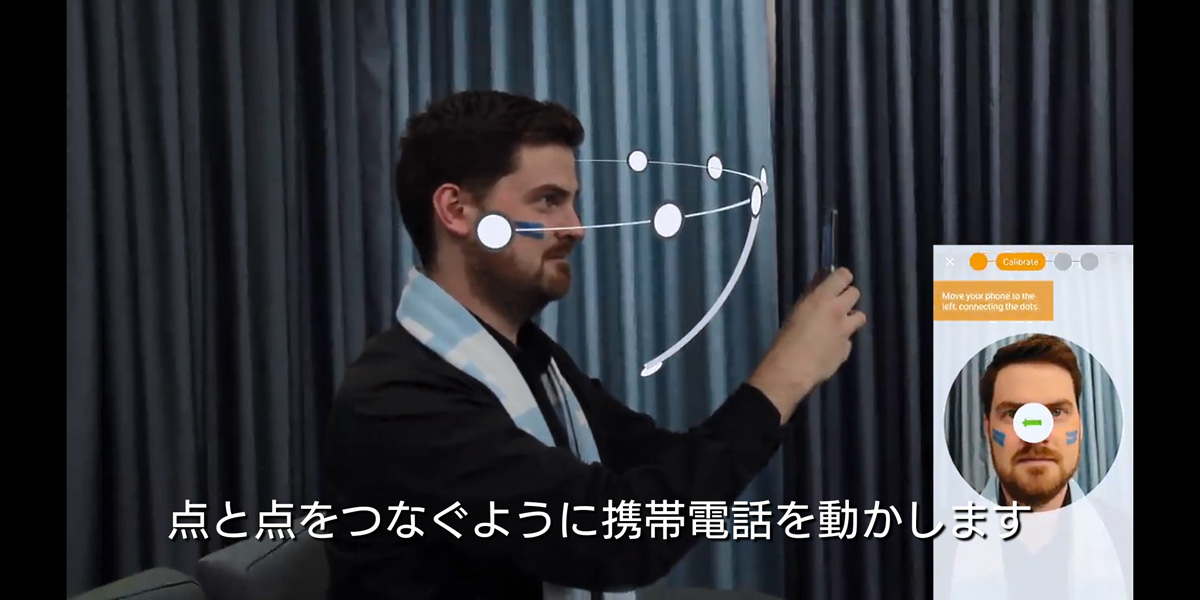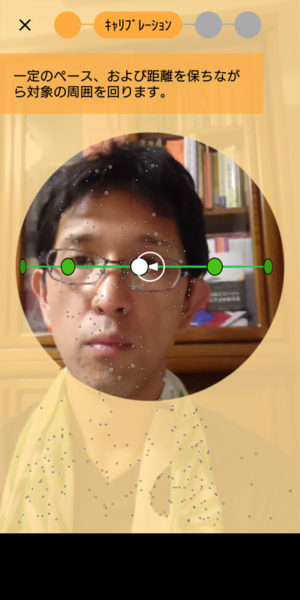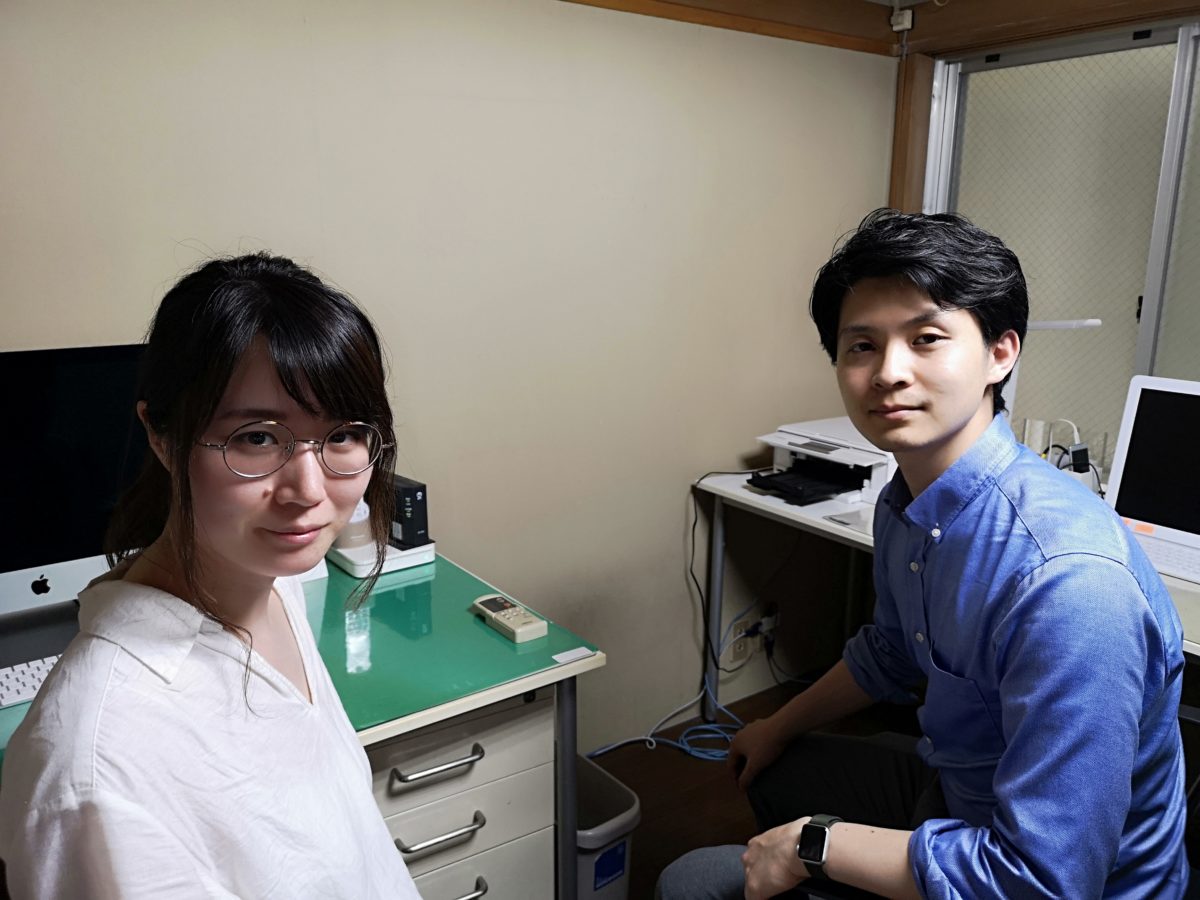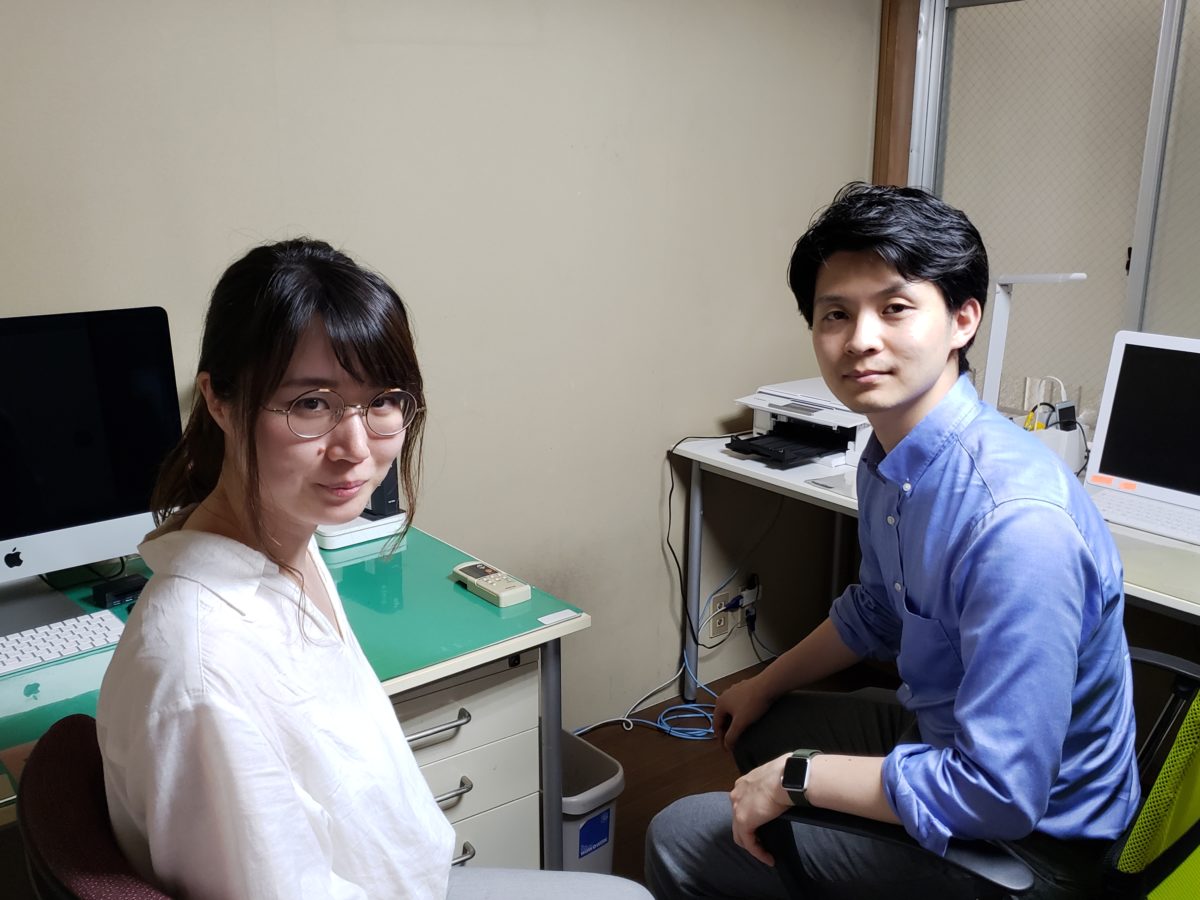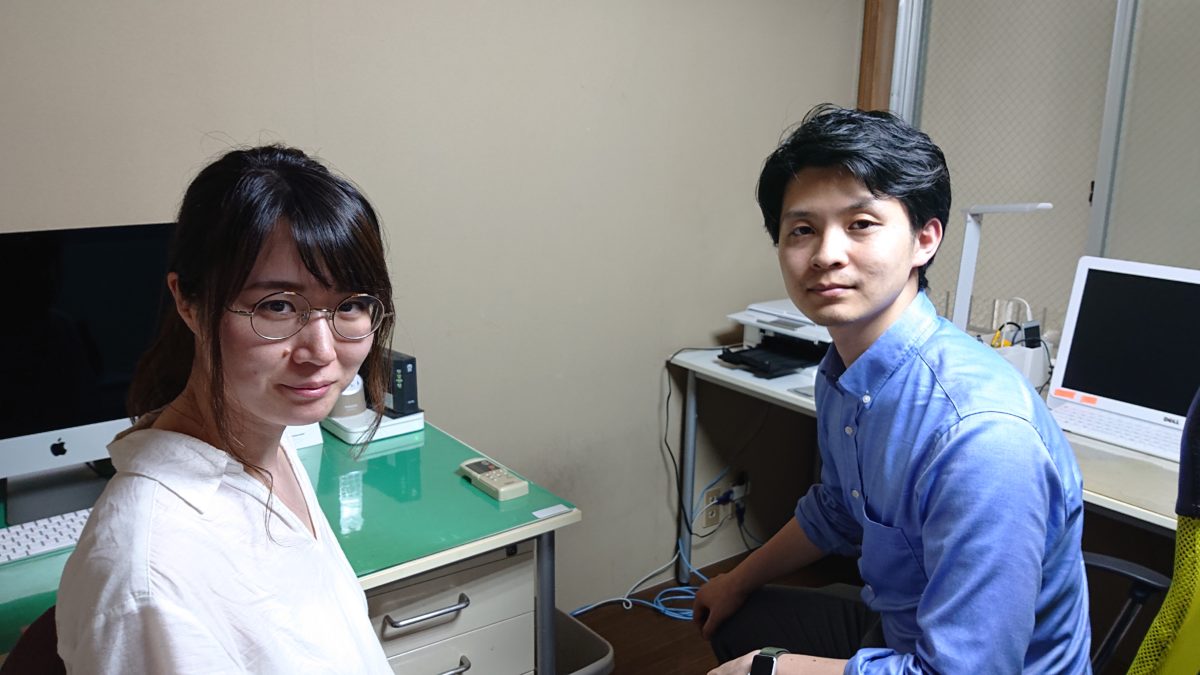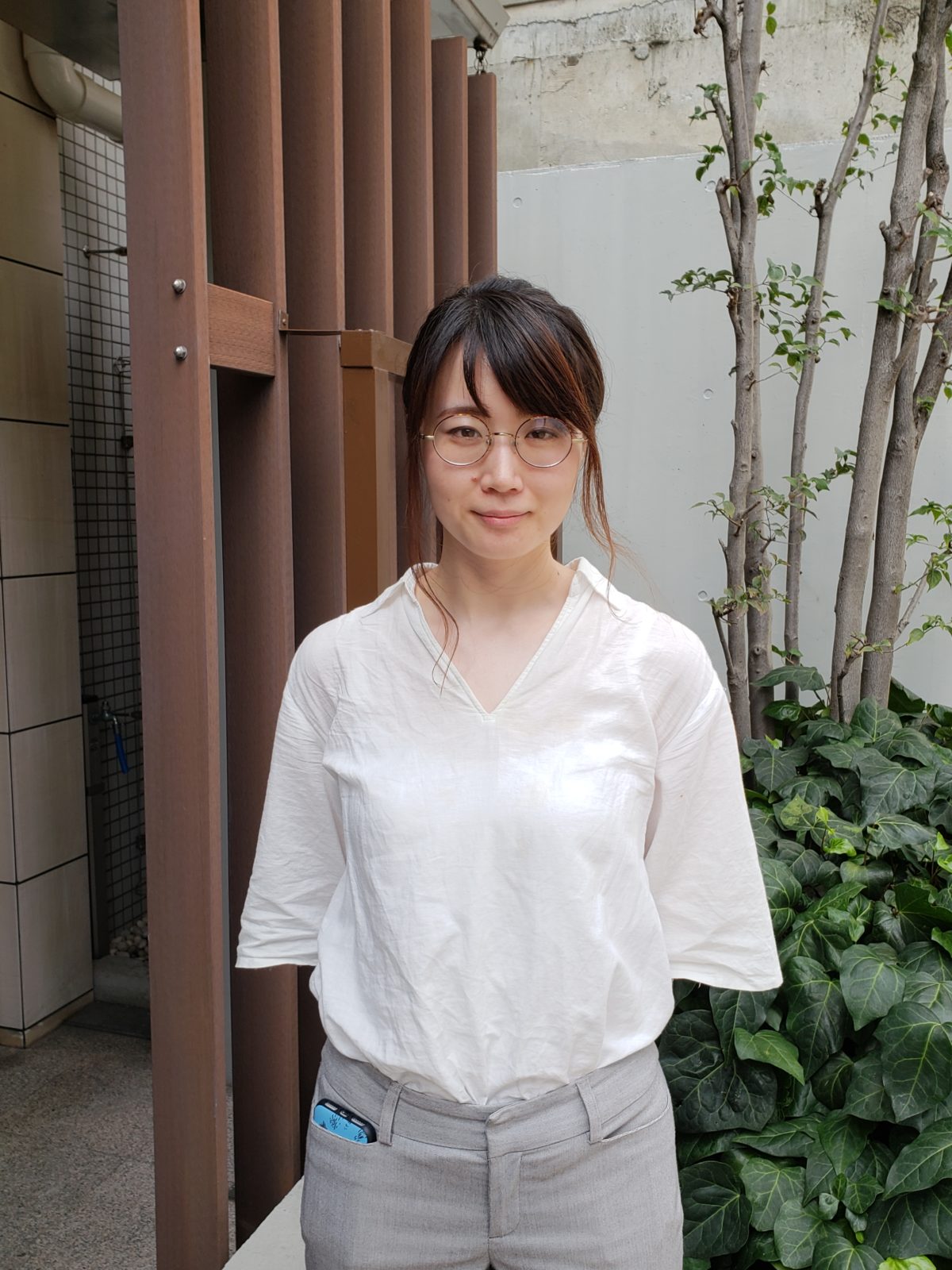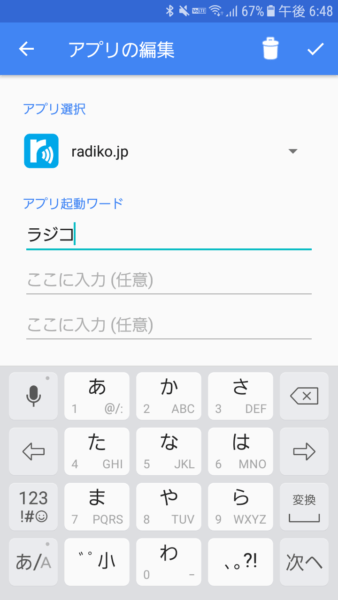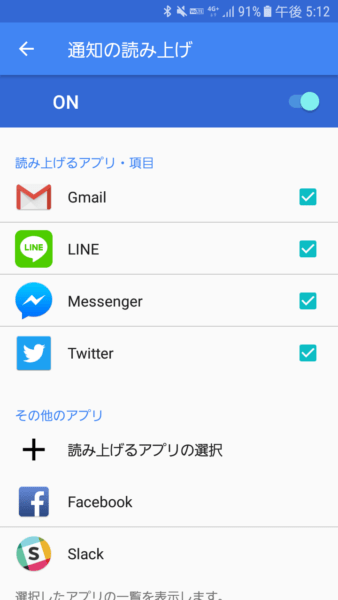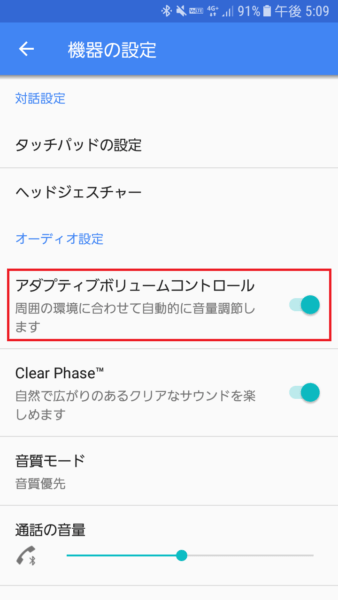8月31日〜9月5日にドイツ・ベルリンで開催された、世界最大級の家電展示会「IFA 2018」に行ってきました。白物家電やオーディオ製品が主役のイベントですが、スマートフォンの出展も多く、ソニーモバイル、シャープ、モトローラなど、新モデルを発表するメーカーも。
スマホはこれからどのように進化していくのか? IFAで注目を集めたモデルを紹介しつつ、ひと足早く2019年を展望。ハード、OS、通信の3つの視点から見ていきたいと思います。

【ハード編】ディスプレイの主役は有機ELに
IFA 2018において、最も注目を集めていたスマホは、ソニーモバイルが発表した「Xperia XZ3」でしょう。同社初の有機ELディスプレイを搭載し、画面アスペクト比は18:9で6インチ、解像度はクアッドHD(2880×1440ドット)というハイエンド仕様。

Xperia XZ3の有機ELディスプレイは、ソニー製のテレビ「ブラビア」で培った高画質化技術を採用していることがアドバンテージ。従来の液晶ディスプレイ搭載モデルよりも精細で鮮やかな色を表示できるといいます。HDR表示に対応していることもセールスポイント。


かつては “液晶のシャープ” と呼ばれることもあったシャープも、有機ELディスプレイ搭載モデルを参考出展した。まだ、製品名はなく、スペックも公表されていないが、筆者がプロトタイプを見た限りでは、画面サイズは6インチ相当で、上部にはノッチもあった。


シャープ製の有機ELディスプレイ搭載モデルは、表面に緩やかなカーブが施されていることが特徴。これは、同社が液晶ディスプレイで培った「フリーフォームディスプレイ」技術を生かしたもので、フレームを細くするメリットが得られます。

アップル、サムスン、ファーウェイなど主要なグローバルメーカーは、すでにハイエンドモデルに有機ELディスプレイを採用しています。有機ELはバックライトを要しないので、黒い背景の画面ではほとんど電力を消費しません。スマホの省電力化に貢献し、同時にアプリの仕様にも変化を及ぼすのではないかと予想しています。
【ブランド】増加が予想される「Android One」の魅力をあらためて
モトローラは、IFA 2018にて新モデル「motorola one」と「motorola one power」を発表しました。これらは、同社が初めて「Android One」としてリリースするモデル。
Android Oneは、Googleが主に新興国向けに展開するブランドです。Androidの純正OSを搭載し、発売から18か月間のOSアップデートを保証し、毎月セキュリティーアップデートが行われます。日本ではワイモバイルが取り扱っており、シャープ、京セラ、HTCが端末を供給。
motorola oneは、5.9インチのHD+ディスプレイを搭載し、1300万画素+200万画素のデュアルカメラや指紋センサーも備えるイマドキの仕様。ヨーロッパを含む世界での発売を予定しており、ヨーロッパでの販売価格は299ユーロ(約3万9000円)。高コスパモデルといえるでしょう。

なお、motorola one plusは、インド市場向けモデルで、約6.2インチのフルHD+ディスプレイや1600万画素+500万画素のデュアルカメラなど、スペックはmotorola oneを上回ります。また、5000mAhの大容量バッテリーがアドバンテージ。

LGは、フラッグシップ「LG G7 ThinQ」の派生モデルとして、「LG G7 One」を発表。これも「Android One」ブランドを冠するモデルです。
LG G7 Oneは、CPUにSnapdragon 835を採用し、6.1インチのクアッドHD+(3120×1440ドット)ディスプレイを搭載するなど、Android Oneとしては珍しいハイスペックモデル。左側面にGoogleボタンを搭載し、ワンタッチでGoogleアシスタントを起動したり、Googleレンズを起動して、カメラで写して情報検索できることが特徴です。


現在、日本では販売していないノキアも、Googleと “がっぷり四つ” の態勢だ。IFA 2018のブースは、さほど広くはなかったが、Android Oneモデルを中心に展示していました。ヨーロッパでは発売済みの「Nokia 7 plus」は6インチのフルHDディスプレイを搭載するミドルハイモデル。



ほかにも、日本では馴染みのない端末メーカーのブースでもAndroid Oneモデルを見かけました。GoogleがAndroidブランドの強化に力を入れていることの現れでしょう。
Googleは10月9日に新製品発表イベントを予定しており、そこで自社ブランドのスマホ「Pixel 3」シリーズが発表され、日本でも発売されるのではないかと噂されています。AndroidはiOSと並ぶOSではありますが、これまでは「アップル、サムスン、ファーウェイ……」と、端末メーカーが市場を牽引している印象が先行していました。しかし、2019年は「アップル vs Google」という構図が、より鮮明になっていくかもしれません。
ファーウェイ、ルーター内蔵スマートスピーカーを発表。通信端末の新たな流れ?
ファーウェイは、Consumer Business GroupのCEO、リチャード・ユー氏がIFA 2018の基調講演に登壇。講演タイトルは「The Ultimate Power of AI」で、AI専用プロセッサーを内蔵する新しいSoC「Kirin 980」を発表しました。
Kirin 980は “世界初の7nmプロセスのモバイルAIチップセット” として発表されましたが、9月12日(日本時間は9月13日未明)に、アップルが7nmプロセスの「A12 Bionic」を搭載するiPhoneの新モデルを発表したので、実際に商用モデルに搭載されるのはアップルが世界初となります。
アップルは「AI」という言葉は使っていませんが、Kirin 980と同じく、AI関連のデータ処理に優れた「ニューラルエンジン」を搭載しています。クアルコムの最新チップセット「Snapdragon 845」もAIの性能を強化していることを謳っており、スマホの進化にAIは欠かせないものになりそう。



そんななか、ファーウェイが新しいデバイスとして発表したのが「HUAWEI AI Cube」。Amazon Alexaを搭載するスマートスピーカーなのですが、4G LTEの通信機能を備え、さらにWi-Fiルーターとしても使えるというスグレモノ。4つのマイクを内蔵しているため、音声認識の精度が高いこともアピールしていました。

日本でも、じわじわと普及しつつあるスマートスピーカー。4Gルーター機能を備えたHUAWEI AI Cubeは、ブロードバンド回線を導入していない環境でも利用でき、省スペースにもつながりそう。次世代のスマートスピーカーとして、今度の動向にも注目したいです。