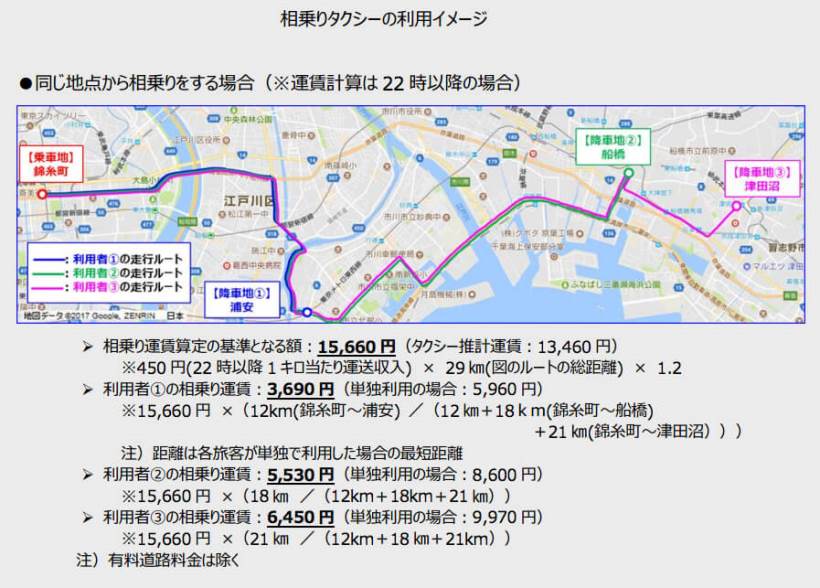世界のさまざまな都市と同じように、ハワイでもUberのほか、アメリカ発のLyftなどの配車サービスの利用者が急激に増えています。しかし、このたびハワイで問題として上がったのが、利用者が増加する時間帯に乗車料金も上がる「ピーク料金」のシステムについて。ホノルル市議会で、このピーク料金に上限を設けようとする法案が可決されました。しかし……
UberやLyftのピーク料金とその問題

一般の人がドライバーとして登録をしておき、利用者は専用アプリを使って、近くを走行する登録車をつかまえて乗車することができるというのがUberやLyftの配車サービス。従来のタクシー料金よりも割安で利用できるとあって、世界中の都市で利用が拡大しています(日本は違いますが)。
ただ気をつけておきたいのが、タクシーの料金とは違って、UberもLyftも乗車料金が高くなる時間帯があること。Uberは「ピーク料金」、Lyftは「プライムタイム」と呼び、ラッシュアワーのように、利用者が増える時間帯やドライバーが少ない時間帯など、需要が多いときに乗車料金も上昇するというもの。この料金の引き上げ率は数パーセントの場合もあれば、2倍、3倍と上昇することもあります。
年末やハロウィンなどのイベントが行われた日は、乗車希望の人は多いのにドライバーの数が極端に少なくなり、「数百ドル(数万円)を請求された」という不満の声がSNS上などであがることも少なくありません。この料金制度には上限が設定されていないため、結果として、タクシーよりも割安で利用できる配車サービスなのに、タクシー料金よりも高額を請求されることになったというケースがあるようなのです。
ホノルル市議会でピーク料金に上限設定を求める法案が可決

6月、ホノルル市議会で論じられたのが、UberやLyftの配車サービスの料金に上限を定める法案を作るというもの。ハワイではUberの料金は、タクシー料金のおおよそ40%と言われています。しかし、Uberのピーク料金が適用されたため、「タクシーで$44の区間を、Uberに$221請求された」というケースも過去にあるそう。そんなUberなどの配車サービスの料金高騰を防ぐことが、この法案制定の目的です。
一方、Uberはこの法案に反発。乗車料金を上げることで、需要があるエリアにドライバーを向かわせて、利用者の待ち時間を短くできると主張。さらにドライバーへのインセンティブとなり、ドライバーのモチベーションを高められるとしています。
しかし、ホノルル市長は自由競争を重視
この法案は議会を通過して、あとは市長の署名を待つのみとなっていました。アメリカで初めて、配車サービスに上限が設定される法案が制定すると思われたものの、ホノルル市長が出した結論は法案の承認ではなかったのです。その主な理由は、交通サービス各社の競争力を高めていきたいから。
その代わり、従来のタクシーで用いられていた、走行距離に応じた料金システムと、乗車前に支払料金が確認できるシステムのどちらかを、利用者が選択できるという立案を提案。タクシー会社への規制についても緩和することが検討されています。

交通渋滞がひどく、公共の交通機関はバスしかないオアフ島ホノルルでは、交通手段の選択肢が増えることは、観光で訪れた旅行客だけでなく地元民にとっても歓迎するべきことと捉えられているでしょう。議会の承認を得た法案に、現市長が異論を唱えることは比較的珍しいケースと言えるかもしれません。タクシーも配車サービスも競争力を高め、利用者にとってさらに便利なサービスを提供してもらえるよう、新しい仕組み作りに今後も期待していきたいところです。それはきっと日本にも遅かれ早かれ影響を与えるでしょう。