最近のデジカメって、エントリーモデルでも高画素で高画質な写真が撮れますよね。ちょっと奮発して一眼レフを購入すれば、素人のお父さんでも立派なアマチュアカメラマンになれちゃう近年のデジカメ事情。
ふと思うのが、いまでこそ最新テクノロジーの結晶のようなデジカメですが、ここに来るまでに紆余曲折の技術革新があったはず。そう言えば、デジカメが普及し始めたころってどんな仕様だったっけ? とオジサンなりの懐古にふけった次第であります。
そこで、20年前に発売された初期のデジカメをいま使うとどうなるのかを検証してみました。
20年前のデジカメなんてどこにあるんだ!?
20年前といえば筆者も20代の半ば。ご多分に漏れず、自作PCやら携帯電話にハマり、ガジェット大好き人間と化していました。デジカメも購入した記憶はあるのですが、当然手元にはありません。もちろん、アキバあたりの中古ガジェット屋さんにもジャンク屋さんにも完動品の20年前のデジカメなんて置いてありません。
そこで、古いデジカメを入手すべくメーカーさんにすがることに。今回、協力して頂いたのは国内最大手のキヤノンさんです。ワラをも掴む思いで、広報さんに泣きついたところ、どうも古いデジカメを資料として保管してあるらしい。
なんとか手配して頂いたのがコレ。
 ↑キヤノン PowerShot 600N。もはやオーパーツ!
↑キヤノン PowerShot 600N。もはやオーパーツ!
キヤノン「PowerShot 600N」は1997年3月発売のモデルで、発売当時の時価は、なんと11万8000円。現在であれば、フルサイズ一眼レフのエントリーモデルが買えそうな価格です。
PowerShotは、現在でも同社の人気シリーズで、その系譜は20年経ったいまも脈々と受け継がれています。600Nはキヤノンのコンデジのなかでも2代目にあたり、コンデジ創世記の遺物といっても過言ではありません。主なスペックは、1/3型CCDで57万画素。1MBの内蔵メモリーを搭載し、ファインモードの解像度は832×608ドットで、内蔵メモリーに記録できるのは4枚のみ。勘違いしないで頂きたいのは、メモリーは1メガバイトですよ、ギガバイトではありません。レンズは、7mm F2.5(35mmフィルム換算50mm)の単焦点。ズームなしのコンデジなんて……と思うかもしれませんが、フイルムカメラ時代は当たり前の仕様でした。
 ↑見よ、この厚み(58.8mm)を! 弁当箱に通ずるものが……
↑見よ、この厚み(58.8mm)を! 弁当箱に通ずるものが……
 ↑もちろん背面液晶なんてありません
↑もちろん背面液晶なんてありません
 ↑ファインダーはレンジ式。若い人には「写ルンです」でお馴染み
↑ファインダーはレンジ式。若い人には「写ルンです」でお馴染み
 ↑専用バッテリー。ニカド式を採用
↑専用バッテリー。ニカド式を採用
 ↑記録メディアは……。ん? なんだコレ?
↑記録メディアは……。ん? なんだコレ?
 ↑そうです、昔懐かしのPCMCIAカード形状のアダプターにコンパクトフラッシュを接続するタイプ
↑そうです、昔懐かしのPCMCIAカード形状のアダプターにコンパクトフラッシュを接続するタイプ
 ↑「カメラステーション」と呼ばれる、ドック形状の充電台。データの転送もコレで可能なのだが……
↑「カメラステーション」と呼ばれる、ドック形状の充電台。データの転送もコレで可能なのだが……
 ↑なんと、インターフェースはパラレルポート。こんなの接続できるパソコンなんて持っていません!
↑なんと、インターフェースはパラレルポート。こんなの接続できるパソコンなんて持っていません!
 ↑現代のカメラと並べてみました。左からPowerShot SX730HS、今回のPowerShot 600N、α7II
↑現代のカメラと並べてみました。左からPowerShot SX730HS、今回のPowerShot 600N、α7II
このPowerShot 600Nのサイズ感をお伝えするために、現代のデジカメと比較してみました。600Nの寸法は本体のみで159.5×92.5×58.8mmで、重量は約420g。最新のPowerShotであるSX730HSが276gなので、約1.5倍の重さ。本体のサイズだけでなら、フルサイズミラーレスのソニーα7IIよりもデカい!
さて、600Nのディテールをご覧頂いたワケですが、さすがに年代を感じさせます。筆者にとっては、PCMCIAやパラレルといった過去のインターフェースに感慨深いものがあり、双方とも現代のパソコンには搭載されていません。デジタル機器の進歩は、転送速度の進歩といっても過言ではなく、現代においても次々と新しい伝送規格が生まれ続けているのも頷けます。
幸いにして、パラレルはなくてもコンパクトフラッシュは読み込める環境がありますので、なんとか撮影したデータを皆さんにお見せすることはできそうです。
見せてもらおうか、20年前のデジカメの性能とやらを!
では、早速このPowerShot 600Nを使用して作例を撮影してみたいと思います。今回は、比較用に最新のPowerShot SX730HSも使用して、PowerShot新旧対決と洒落込んでみました。
 ↑PowerShot SX730HS。光学40倍ズームを搭載した2030万画素機
↑PowerShot SX730HS。光学40倍ズームを搭載した2030万画素機
まずは風景を撮影しようと、ロケの準備をしていたところ、致命的な問題が発生! なんと、さすが20年前のモデルだけあって、バッテリーが経年劣化により死亡寸前……。いくら充電しても、にわかに起動はするものの、起動した瞬間に「LB(Low Battery)」の表示が。
 ↑スゴくシンプルな操作部。12時間充電したバッテリーで起動するも液晶には「LB」の表示が……
↑スゴくシンプルな操作部。12時間充電したバッテリーで起動するも液晶には「LB」の表示が……
さすがの筆者もコレには困り果てました。こんな20年前の専用バッテリーなんて入手困難だし、乾電池を入れるアダプターもありません。本体にACアダプターを直結して電源を確保すれば動作するのですが、それだと屋外ロケが不可能に。そこで、筆者は最近、巷を賑わせているアイテムのことを思い出しました。それがコイツ。
 ↑cheero「Energy Carry 500Wh」
↑cheero「Energy Carry 500Wh」
この巨大なモバイルバッテリーは500Whもの容量を誇り、家庭用コンセントも使えるという代物。スマホなら50回はゆうに充電できるほどの性能を有しています。しかし、その容量がゆえに、重さが5.4kgと無差別級。しかし、600Nで撮影するためには「重い」なんて言ってられません。
 ↑こんな状態でロケを敢行。まるでプロカメラマンが使用するストロボ用のジェネレーターでも接続しているかのよう
↑こんな状態でロケを敢行。まるでプロカメラマンが使用するストロボ用のジェネレーターでも接続しているかのよう
これで600Nに命が吹き込まれました。早速、撮影してみます。再度おさらいになりますが、600Nは57万画素、SX730HSは2030万画素で、その差は約35倍! さてどうなることやら……。
まずは六本木ヒルズ。天気は晴天でしたが、夕暮れ直前というシチュエーション。同じ地点からワイド端(最広角)で撮影したもの。まずは画角の違いに驚きを隠せません。昔のコンデジといえば、風景やスナップを撮影するために単焦点とは言え、もうちょっと広角に撮れるもんだと思っていましたが、換算値50mmというのは中望遠の域なので、こんなもんでしょうか。
 ↑600N
↑600N
 ↑SX730HS
↑SX730HS
光学機器のカメラと言えども、デジカメともなるとデジタル機器としての色合いが強い。レンズの性能はともかく、センサーや画像処理エンジンなどもやはり20年前のもの。見劣りするのは仕方ありません。とは言え、ビルの窓などを見るとなかなかの解像感です。
次に公園にて、逆光を試してみました。このシチュエーションでは最新カメラがさすがとしか言いようがありません。600Nもなんとか撮影できていますが、まるで使い捨てフイルムカメラの写真をスキャンしたような画像になっています。
 ↑600N
↑600N
 ↑SX730HS
↑SX730HS
素早い動きをする動物や子どもはシャッタースピードが命となるわけですが、600Nの仕様は1/30~1/500秒。しかもマニュアルで設定できないのでカメラ任せとなるワケです。下記の写真は何枚も撮影して唯一ブレが少なかった作例。アングルが滅茶苦茶です。
 ↑猛烈に嫌がっているところを決死の覚悟で撮影しました
↑猛烈に嫌がっているところを決死の覚悟で撮影しました
ブツ撮りはご覧の通り。さすがにインスタ映えには程遠いですが、落ち着いてシャッターを切れる環境であれば、そこそこ撮れることが解りました。ただし、背面液晶や電子ファインダーに甘えっぱなしの筆者は、レンジファインダーでの撮影に四苦八苦。パイナップルの葉っぱが見切れてしまうという、非常にお恥ずかしい写真に。
 ↑600N
↑600N
さて、作例を見る限り、20年前とはいえそこそこ撮れることが解ったと同時に、現代の技術のスゴさを改めて知る結果となりました。
写真をパソコンに取り込んだ時どうなる?
なんとか撮影できたのは良かったのですが、気になるのが57万画素という低い画素数の写真をパソコンに取り込んだ時にどうなるのかということ。今回は解りやすく、PCに取り込んで4Kモニターで表示してみました。
 ↑はい、これが等倍で表示した57万画素です
↑はい、これが等倍で表示した57万画素です
 ↑比較としてPowerShot SX730HSで撮影した2030万画素の等倍を並べてみました
↑比較としてPowerShot SX730HSで撮影した2030万画素の等倍を並べてみました
「ちっさ!」という感想が聞こえてきますが、確かに等倍表示でこれだと小さく感じますね。20年前にはコレよりも低解像度のデジカメがいくつもありました。しかし、当時のモニターも低解像度のものが主流だったため、この画素数でも十分だったのです。
一説によると、カメラの起源は約1000年前にさかのぼるそうです。また、300年前には世界初となるコンデジが発明されたとのこと。日本でも坂本龍馬や西郷隆盛など、幕末を生きた人の写真が残っていることを考えると、100年以上の歴史があることが解ります。
しかし、デジタルカメラはまだ数十年。これからも日進月歩で進化し続けて行くことでしょう。今から20年後に、今回の600Nと最新デジカメの比較ができることを楽しみにしている筆者なのでした。



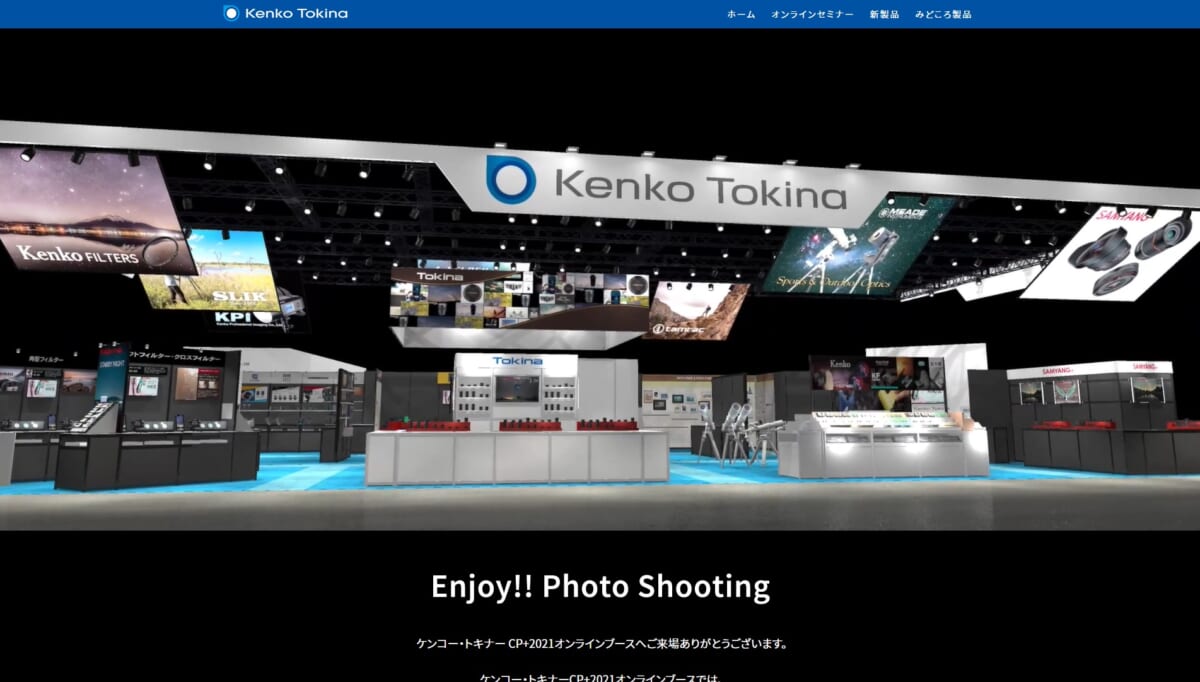











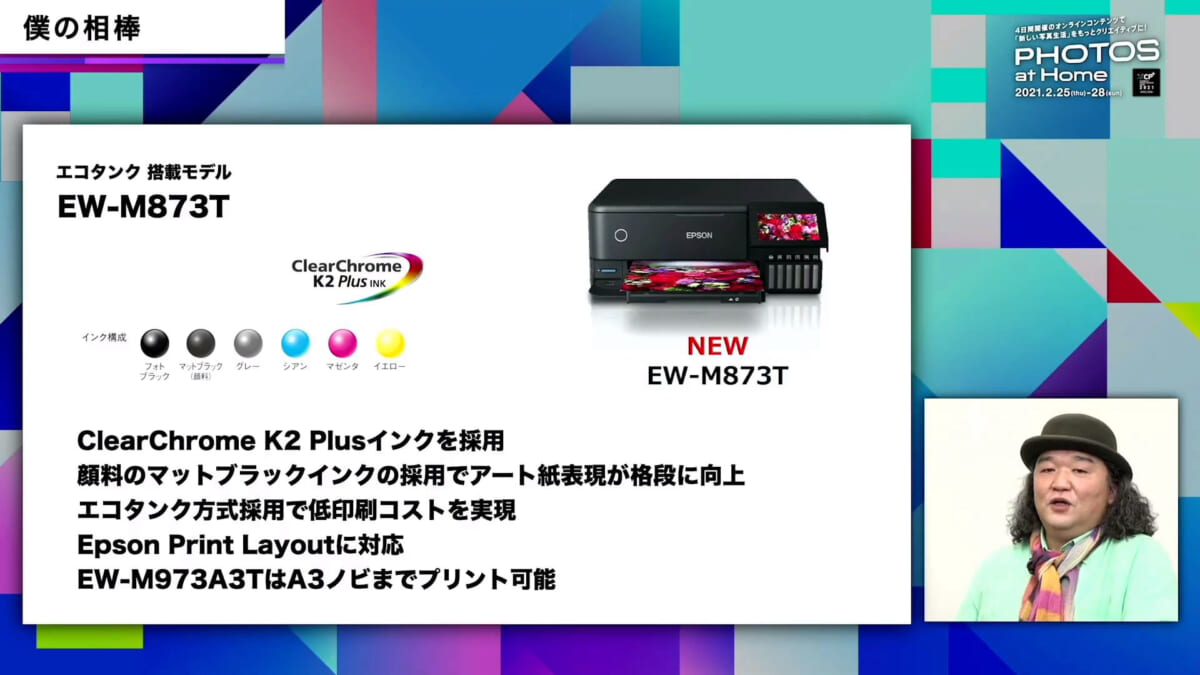




 リコーインダストリアルソリューションズがデンスステレオマッチング技術(高密度視差演算技術)を採用した車載用ステレオカメラをデンソーと共同開発し、2017年9月に量産を開始
リコーインダストリアルソリューションズがデンスステレオマッチング技術(高密度視差演算技術)を採用した車載用ステレオカメラをデンソーと共同開発し、2017年9月に量産を開始 リコーが全天球カメラ「THETA V」向けのプラグインストアを開設。当初は8種類のプラグインを用意しており、無償でダウンロード、利用できる
リコーが全天球カメラ「THETA V」向けのプラグインストアを開設。当初は8種類のプラグインを用意しており、無償でダウンロード、利用できる 今回はソニーの高級コンデジ「DSC-RX100M6」を使って猫撮影。チルト式モニター&タッチパネル採用なので、地面スレスレからのアングルも狙える
今回はソニーの高級コンデジ「DSC-RX100M6」を使って猫撮影。チルト式モニター&タッチパネル採用なので、地面スレスレからのアングルも狙える 夏の猫はいろんな場所で涼んでいるが、よく見るのが階段でくつろぐ光景。そこで今回は階段にいた猫たちの写真を紹介する。
夏の猫はいろんな場所で涼んでいるが、よく見るのが階段でくつろぐ光景。そこで今回は階段にいた猫たちの写真を紹介する。 Amazon.co.jpの大型セール「プライムデー」、パナソニックのHDビデオカメラ「V360MS」もセール登場が予告されている。
Amazon.co.jpの大型セール「プライムデー」、パナソニックのHDビデオカメラ「V360MS」もセール登場が予告されている。 スマホに押され気味のコンパクトデジタルカメラだが、今年は高級モデルで注目機種が登場。パナソニックの「TX2」とソニー「RX100M6」だ。どっちを買えばいいのか迷っている方向けて、この両者を比較してみた
スマホに押され気味のコンパクトデジタルカメラだが、今年は高級モデルで注目機種が登場。パナソニックの「TX2」とソニー「RX100M6」だ。どっちを買えばいいのか迷っている方向けて、この両者を比較してみた 夏の猫はいろんな場所で涼んでいるが、よく見るのが階段でくつろぐ光景。そこで今回は階段にいた猫たちの写真を紹介する。
夏の猫はいろんな場所で涼んでいるが、よく見るのが階段でくつろぐ光景。そこで今回は階段にいた猫たちの写真を紹介する。 生まれたての子猫を友人が引き取ったという話を聞き、これはぜひ写真を撮らねば、ということでお宅に訪問。元気な子猫がはしゃぎ回っておりました
生まれたての子猫を友人が引き取ったという話を聞き、これはぜひ写真を撮らねば、ということでお宅に訪問。元気な子猫がはしゃぎ回っておりました 今回は路上で出会った猫の写真を紹介する。道路のど真ん中にいる猫やマンホールの収まる猫、人なつこい猫など結構出会えるものです
今回は路上で出会った猫の写真を紹介する。道路のど真ん中にいる猫やマンホールの収まる猫、人なつこい猫など結構出会えるものです 「ライカQ」の国内限定モデル「ライカQ Safari」は限定50台。
「ライカQ」の国内限定モデル「ライカQ Safari」は限定50台。 とある公園で2007年に出会った「チロ」と呼ばれていたその猫は、やたら人なつこく人の膝の上で寝るほどだった。もうその公園にいないチロを写真とともに振り返る
とある公園で2007年に出会った「チロ」と呼ばれていたその猫は、やたら人なつこく人の膝の上で寝るほどだった。もうその公園にいないチロを写真とともに振り返る 今回は箱根で猫撮影。鉄道の新車両に乗るのが主目的だったので滞在時間は2時間しかなかったが、それでも数匹の猫と出会いがあり、撮らせていただきました
今回は箱根で猫撮影。鉄道の新車両に乗るのが主目的だったので滞在時間は2時間しかなかったが、それでも数匹の猫と出会いがあり、撮らせていただきました ソニーは1.0型CMOSイメージセンサーを搭載、AFの高速化や高速連写に対応したプレミアムコンパクトデジカメ「RX100 VI」を発売する。
ソニーは1.0型CMOSイメージセンサーを搭載、AFの高速化や高速連写に対応したプレミアムコンパクトデジカメ「RX100 VI」を発売する。 今回も長崎で猫撮影。坂の町と言われるくらいなので坂が多いが、そうなると必然的に猫とも坂道で遭遇。高台から遠くを見通せる道の風景に猫……よく合っています
今回も長崎で猫撮影。坂の町と言われるくらいなので坂が多いが、そうなると必然的に猫とも坂道で遭遇。高台から遠くを見通せる道の風景に猫……よく合っています 優秀なカメラやレンズなどを選ぶ「カメラグランプリ2018」の授賞式が開かれた。受賞したソニー、オリンパス、ニコン、パナソニックの関係者が一堂に会し、受賞を祝った
優秀なカメラやレンズなどを選ぶ「カメラグランプリ2018」の授賞式が開かれた。受賞したソニー、オリンパス、ニコン、パナソニックの関係者が一堂に会し、受賞を祝った 今回も長崎で猫撮影。高台にはお寺が並んでいるが、そこにはやっぱり猫がいた。ミラーレス一眼2台とコンデジ1台を駆使して、遠くの猫や寄ってくる猫を撮りまくる
今回も長崎で猫撮影。高台にはお寺が並んでいるが、そこにはやっぱり猫がいた。ミラーレス一眼2台とコンデジ1台を駆使して、遠くの猫や寄ってくる猫を撮りまくる 富士フイルムはXシリーズの最新モデルとなるエントリーモデルのミラーレスデジカメ「FUJIFILM X-T100」を発売する。
富士フイルムはXシリーズの最新モデルとなるエントリーモデルのミラーレスデジカメ「FUJIFILM X-T100」を発売する。 優秀なカメラやレンズなどを選ぶ「カメラグランプリ2018」の結果が発表された。大賞に輝いたのはソニーのミラーレス一眼「α9」だ
優秀なカメラやレンズなどを選ぶ「カメラグランプリ2018」の結果が発表された。大賞に輝いたのはソニーのミラーレス一眼「α9」だ 今回は長崎で猫撮影。坂が多くて猫が似合いそうな街だなとは思っていたけど、本当に猫の話がよくでてくる街。そこで出会った“尾曲がり猫”がすごかった
今回は長崎で猫撮影。坂が多くて猫が似合いそうな街だなとは思っていたけど、本当に猫の話がよくでてくる街。そこで出会った“尾曲がり猫”がすごかった 富士フイルムがチェキの新製品を発表。自撮りモードや露出補正、二重露光といった多機能さが特徴。発表会にはイメージキャラクターの広瀬すずさんも登場した
富士フイルムがチェキの新製品を発表。自撮りモードや露出補正、二重露光といった多機能さが特徴。発表会にはイメージキャラクターの広瀬すずさんも登場した カシオ計算機がコンデジから撤退するという衝撃のニュースが流れた。そこで、QV-10をはじめ過去のカシオのデジカメを当時撮った猫写真とともに振り返る
カシオ計算機がコンデジから撤退するという衝撃のニュースが流れた。そこで、QV-10をはじめ過去のカシオのデジカメを当時撮った猫写真とともに振り返る 世界初の液晶付きデジタルカメラ「QV-10」を発売したカシオ計算機がコンデジ市場から撤退すると発表。そこで、同社の主なデジカメを振り返ってみた
世界初の液晶付きデジタルカメラ「QV-10」を発売したカシオ計算機がコンデジ市場から撤退すると発表。そこで、同社の主なデジカメを振り返ってみた 実はミラーレス一眼とオールドレンズは相性がいい。そこで、今回はCarl Zeissなど3本のオールドレンズを使って猫を撮影してみた
実はミラーレス一眼とオールドレンズは相性がいい。そこで、今回はCarl Zeissなど3本のオールドレンズを使って猫を撮影してみた 最安レベルだと5万円台でレンズキットが買えるキヤノンのミラーレス一眼「EOS M100」。2017年秋のモデルでそれほど古くなく、基本機能はばっちりなので、ミラーレス一眼を安く買いたいならおススメ
最安レベルだと5万円台でレンズキットが買えるキヤノンのミラーレス一眼「EOS M100」。2017年秋のモデルでそれほど古くなく、基本機能はばっちりなので、ミラーレス一眼を安く買いたいならおススメ 1840年の設計で最近復刻されたロシア製レンズ「Petzval 58mm」というものを入手。面白い写真が撮れるので猫撮影に出かけてみた
1840年の設計で最近復刻されたロシア製レンズ「Petzval 58mm」というものを入手。面白い写真が撮れるので猫撮影に出かけてみた 猫が集まってくるという、京都のとある公園。そこにある池の周りには猫が集まってくる。多くは水を飲むためだが、中には池の水鳥を狙う狩りモードの猫たちも……
猫が集まってくるという、京都のとある公園。そこにある池の周りには猫が集まってくる。多くは水を飲むためだが、中には池の水鳥を狙う狩りモードの猫たちも…… 猫が集まってくるという、京都のとある公園。行って見ると、キジトラにシロキジにミケに……たくさんの猫がいて、中には寄ってくる猫も。そんな猫たちを撮りまくった
猫が集まってくるという、京都のとある公園。行って見ると、キジトラにシロキジにミケに……たくさんの猫がいて、中には寄ってくる猫も。そんな猫たちを撮りまくった 今回は仕事の都合で京都へ。観光客でにぎわう中、街中の大きなお寺で猫を発見。さらに翌日も早朝から猫を求めて散歩。結果何匹か撮れました
今回は仕事の都合で京都へ。観光客でにぎわう中、街中の大きなお寺で猫を発見。さらに翌日も早朝から猫を求めて散歩。結果何匹か撮れました 最近、我が家の猫がこっそり棚の上にいることが多くなった。その様子を買ったばかりの超広角レンズで撮りつつ、棚の上の猫目線の写真も撮ってみた
最近、我が家の猫がこっそり棚の上にいることが多くなった。その様子を買ったばかりの超広角レンズで撮りつつ、棚の上の猫目線の写真も撮ってみた 高級コンデジ「LUMIX DC-TX2」でカメラ初心者が桜を撮影。
高級コンデジ「LUMIX DC-TX2」でカメラ初心者が桜を撮影。 タカラトミーアーツがガチャ(カプセル玩具)として発売した「日本立体カメラ名鑑 Canon ミニチュアカメラコレクション 第2弾」がキヤノン本気の監修でスゴすぎるんです~~
タカラトミーアーツがガチャ(カプセル玩具)として発売した「日本立体カメラ名鑑 Canon ミニチュアカメラコレクション 第2弾」がキヤノン本気の監修でスゴすぎるんです~~ 今回は世田谷区の上馬にある感応寺という浄土宗のお寺の猫に行ってきた。寄ってくる猫は超広角で、遠くの猫は中望遠レンズで、と状況に合わせてレンズを変えてみる
今回は世田谷区の上馬にある感応寺という浄土宗のお寺の猫に行ってきた。寄ってくる猫は超広角で、遠くの猫は中望遠レンズで、と状況に合わせてレンズを変えてみる 「カメラグランプリ2018」の一般投票部門である「あなたが選ぶベストカメラ賞」の投票受付が開始された。投票すると抽選でデジカメなどのカメラ製品が当たる
「カメラグランプリ2018」の一般投票部門である「あなたが選ぶベストカメラ賞」の投票受付が開始された。投票すると抽選でデジカメなどのカメラ製品が当たる カメラにくわしくない編集部員、これ1台あればどうとでもなると言われて高級コンデジ「LUMIX DC-TX2」を購入。
カメラにくわしくない編集部員、これ1台あればどうとでもなると言われて高級コンデジ「LUMIX DC-TX2」を購入。 今回は「不思議の国のアリス」をコンセプトにした原宿の猫カフェで猫撮影。週刊アスキーの特集と絡んでいるが、それとは関係なく猫撮影に興じる
今回は「不思議の国のアリス」をコンセプトにした原宿の猫カフェで猫撮影。週刊アスキーの特集と絡んでいるが、それとは関係なく猫撮影に興じる この春のデジカメ新製品では、インパクトのある製品が多数あったが、個人的に性能対価格比でお買い得だと感じたのがキヤノン「EOS Kiss M」だ
この春のデジカメ新製品では、インパクトのある製品が多数あったが、個人的に性能対価格比でお買い得だと感じたのがキヤノン「EOS Kiss M」だ ソニーの最新ミラーレス一眼「α7III」は約25万円で発売される。初代「α7」は現在約10万円。この両者がどれくらい違うのか、軽く比較してみた
ソニーの最新ミラーレス一眼「α7III」は約25万円で発売される。初代「α7」は現在約10万円。この両者がどれくらい違うのか、軽く比較してみた 新宿5丁目の小さな路地に「カフェアルル」という昭和な喫茶店がある。その店内では猫たちが自由に歩き回り、お客さんたちと遊んだりしている
新宿5丁目の小さな路地に「カフェアルル」という昭和な喫茶店がある。その店内では猫たちが自由に歩き回り、お客さんたちと遊んだりしている ビックカメラはオリジナルモデル第1弾として、ニコンCOOLPIXの新幹線 E5系「はやぶさ」カラーモデルを発売する。
ビックカメラはオリジナルモデル第1弾として、ニコンCOOLPIXの新幹線 E5系「はやぶさ」カラーモデルを発売する。
 春なので、猫のあくび写真を集めてみた。その撮り方も紹介。猫があくびをするときは前兆があるので、それを見逃さずに撮る
春なので、猫のあくび写真を集めてみた。その撮り方も紹介。猫があくびをするときは前兆があるので、それを見逃さずに撮る 3月1日にパシフィコ横浜で開幕したカメライベント「CP+ 2018」。参考展示は少なめだが、レンズ関連でいくつかあったので紹介する。ソニーEマウントのフルサイズ対応レンズが目立つ
3月1日にパシフィコ横浜で開幕したカメライベント「CP+ 2018」。参考展示は少なめだが、レンズ関連でいくつかあったので紹介する。ソニーEマウントのフルサイズ対応レンズが目立つ 3月1日にパシフィコ横浜で開幕したカメライベント「CP+ 2018」。週末は混雑が予想されるので、その前に会場の様子やどこが混みそうかなどを紹介していこう
3月1日にパシフィコ横浜で開幕したカメライベント「CP+ 2018」。週末は混雑が予想されるので、その前に会場の様子やどこが混みそうかなどを紹介していこう 3月1日にパシフィコ横浜で開幕するカメライベント「CP+ 2018」。その会場で触れるであろう、今年発売のデジタルカメラをまとめてみた
3月1日にパシフィコ横浜で開幕するカメライベント「CP+ 2018」。その会場で触れるであろう、今年発売のデジタルカメラをまとめてみた ソニーがフルサイズセンサー搭載のミラーレス一眼「α7III」を発表。発表会で実機に触ってきたのでフォトレポートをお伝えする
ソニーがフルサイズセンサー搭載のミラーレス一眼「α7III」を発表。発表会で実機に触ってきたのでフォトレポートをお伝えする キヤノンがミラーレス一眼としてEOS Kissを投入。エントリークラスとなるが、最新の「DIGIC 8」を搭載することで上位機種を上回る性能を誇る
キヤノンがミラーレス一眼としてEOS Kissを投入。エントリークラスとなるが、最新の「DIGIC 8」を搭載することで上位機種を上回る性能を誇る キヤノンがバウンス撮影に最適な角度に自動で動くストロボや、エントリー向けデジタル一眼レフ、ミラーレス一眼を発表
キヤノンがバウンス撮影に最適な角度に自動で動くストロボや、エントリー向けデジタル一眼レフ、ミラーレス一眼を発表 人とたわむれる猫の姿は見ていてほほえましい。おじさんと一緒にいる猫は多いが、子供とたわむれる猫は珍しい。そんな写真を紹介
人とたわむれる猫の姿は見ていてほほえましい。おじさんと一緒にいる猫は多いが、子供とたわむれる猫は珍しい。そんな写真を紹介 オリンパスはミラーレス一眼カメラ「OLYMPUS PEN E-PL9」を3月9日に発売する。
オリンパスはミラーレス一眼カメラ「OLYMPUS PEN E-PL9」を3月9日に発売する。 リコーがフルサイズ一眼レフ「PENTAX K-1」の後継機種「PENTAX K-1 MarkII」を発表。ISO 819200という超高感度設定が可能となっている
リコーがフルサイズ一眼レフ「PENTAX K-1」の後継機種「PENTAX K-1 MarkII」を発表。ISO 819200という超高感度設定が可能となっている 日ごろ猫を撮っている筆者だが、同じように猫を撮っている人に出会うとついついその人を含めて撮りたくなる……今回はそんな写真を紹介
日ごろ猫を撮っている筆者だが、同じように猫を撮っている人に出会うとついついその人を含めて撮りたくなる……今回はそんな写真を紹介 富士フイルムはボディー内に5軸、5.5段分の手ブレ補正機能を内蔵したミラーレスデジタルカメラ「FUJIFILM X-H1」を発売する。
富士フイルムはボディー内に5軸、5.5段分の手ブレ補正機能を内蔵したミラーレスデジタルカメラ「FUJIFILM X-H1」を発売する。 パナソニックは8K解像度の有機薄膜CMOS撮像素子技術を発表。CMOSでは難しかったグローバルシャッター型で、広いダイナミックレンジを持つ。
パナソニックは8K解像度の有機薄膜CMOS撮像素子技術を発表。CMOSでは難しかったグローバルシャッター型で、広いダイナミックレンジを持つ。 パナソニックがデジタルカメラ2製品を発表。ミラーレス一眼ミドルクラスの「LUMIX DC-GX7MK3」と、高級コンデジ「LUMIX DC-TX2」で、どちらも3月15日発売予定だ
パナソニックがデジタルカメラ2製品を発表。ミラーレス一眼ミドルクラスの「LUMIX DC-GX7MK3」と、高級コンデジ「LUMIX DC-TX2」で、どちらも3月15日発売予定だ 自宅の猫がふいにおもしろい恰好になったとき、カメラを出すのが間に合わない……そんなときはスマホで撮影。いつでも、どっちも使うつもりでいると、いい写真が撮れます
自宅の猫がふいにおもしろい恰好になったとき、カメラを出すのが間に合わない……そんなときはスマホで撮影。いつでも、どっちも使うつもりでいると、いい写真が撮れます ニコンが第3四半期の決算を発表。デジタル一眼レフ「D850」の大ヒットなどにより増益となった。
ニコンが第3四半期の決算を発表。デジタル一眼レフ「D850」の大ヒットなどにより増益となった。 オリンパスがミラーレス一眼「OLYMPUS PEN E-PL9」を発表。3月上旬に発売する。シーンモードが追加されたほか、従来外付けだったフラッシュが内蔵ポップアップ式となっている
オリンパスがミラーレス一眼「OLYMPUS PEN E-PL9」を発表。3月上旬に発売する。シーンモードが追加されたほか、従来外付けだったフラッシュが内蔵ポップアップ式となっている 今回は猫の顔の撮り方を紹介。クロネコとシロネコでは撮り方が違うし、光の当たり方や撮りたい表情によっても工夫が必要。
今回は猫の顔の撮り方を紹介。クロネコとシロネコでは撮り方が違うし、光の当たり方や撮りたい表情によっても工夫が必要。





















 パフォーマンスガールズユニット『9nine』で活躍する、かんちゃんこと吉井香奈恵さんのデジカメ連載。今回は一眼レフカメラやミラーレスカメラの便利な活用方法として、デジカメとスマートフォン、キャプチャーデバイスを組み合わせたリアルタイム動画配信に挑戦してみました。
パフォーマンスガールズユニット『9nine』で活躍する、かんちゃんこと吉井香奈恵さんのデジカメ連載。今回は一眼レフカメラやミラーレスカメラの便利な活用方法として、デジカメとスマートフォン、キャプチャーデバイスを組み合わせたリアルタイム動画配信に挑戦してみました。
 パナソニックがミラーレス一眼「GF10」を発表。自撮り機能を強化し、夜景できれいに撮れる機能や広角自撮り機能などを新たに搭載
パナソニックがミラーレス一眼「GF10」を発表。自撮り機能を強化し、夜景できれいに撮れる機能や広角自撮り機能などを新たに搭載 富士フイルムがエントリー向けミラーレス一眼「X-A5」を発表。ボディーのみで実売6.5万円ながら、4K動画撮影に対応。像面位相差AF搭載でAF速度も高速化している
富士フイルムがエントリー向けミラーレス一眼「X-A5」を発表。ボディーのみで実売6.5万円ながら、4K動画撮影に対応。像面位相差AF搭載でAF速度も高速化している 2万5000円で買えるキヤノンの光学45倍ズームデジカメ「PowerShot SX430 IS」。デジカメとして使えるのかどうか試してみた
2万5000円で買えるキヤノンの光学45倍ズームデジカメ「PowerShot SX430 IS」。デジカメとして使えるのかどうか試してみた 「結構猫がいる」と聞いたので今回は都内のお寺へ。カメラはソニーの高画質ミラーレス一眼「α7RIII」を持って行った。これがなかなか猫撮りにいいのである
「結構猫がいる」と聞いたので今回は都内のお寺へ。カメラはソニーの高画質ミラーレス一眼「α7RIII」を持って行った。これがなかなか猫撮りにいいのである 2016年にサービスが終了した写真共有サービス「Panoramio」のデータ保存期限が2018年1月29日で終了すると米グーグルが発表。
2016年にサービスが終了した写真共有サービス「Panoramio」のデータ保存期限が2018年1月29日で終了すると米グーグルが発表。 富士フイルムはタフネスデジカメ「XPシリーズ」に、Bluetoothを搭載した最新モデル「FinePix XP130」を発売する。
富士フイルムはタフネスデジカメ「XPシリーズ」に、Bluetoothを搭載した最新モデル「FinePix XP130」を発売する。 山の上のお寺に向かい途中。猫とたわむれるカップルに出会う。その様子をソニーの高級望遠デジカメ「DSC-RX10M4」で撮った
山の上のお寺に向かい途中。猫とたわむれるカップルに出会う。その様子をソニーの高級望遠デジカメ「DSC-RX10M4」で撮った 路地の街である鞆の浦で猫撮影。ソニーの高級望遠デジカメ「DSC-RX10M4」で屋根の上や階段の上にいる猫たちを撮った
路地の街である鞆の浦で猫撮影。ソニーの高級望遠デジカメ「DSC-RX10M4」で屋根の上や階段の上にいる猫たちを撮った 富士フイルムはFUJIFILM XシリーズやFinePix XPに同梱したACアダプターが破損するおそれがあるとして無償交換を開始した。
富士フイルムはFUJIFILM XシリーズやFinePix XPに同梱したACアダプターが破損するおそれがあるとして無償交換を開始した。 EマウントレンズにAPS-C用の標準ズームモデルが登場。EDレンズや円形絞りなど、豪華なスペックが盛だくさんだ。
EマウントレンズにAPS-C用の標準ズームモデルが登場。EDレンズや円形絞りなど、豪華なスペックが盛だくさんだ。 オリンパスは「M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO」の発売日を1月26日と発表した。
オリンパスは「M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO」の発売日を1月26日と発表した。 パナソニックがCES 2018で発表したミラーレス一眼「DC-GH5S」が1月25日に発売されることとなった。新しいイメージセンサーで高感度撮影を意識したカメラだ
パナソニックがCES 2018で発表したミラーレス一眼「DC-GH5S」が1月25日に発売されることとなった。新しいイメージセンサーで高感度撮影を意識したカメラだ 年明け1発目は、年末年始に訪れた鞆の浦で猫撮影。持って行ったカメラはソニーの高級望遠デジカメ「 DSC-RX10M4」。猫撮影において最強のデジカメだ
年明け1発目は、年末年始に訪れた鞆の浦で猫撮影。持って行ったカメラはソニーの高級望遠デジカメ「 DSC-RX10M4」。猫撮影において最強のデジカメだ 冬のアクティビティー向けのアクションカメラ特集。アクションカメラといえば動画だが、今回は静止画画質を中心にGoPro「HERO 6」、ソニー「RX0」、カシオ計算機「EX-FR200」、ニコン「KeyMission 360」を紹介する
冬のアクティビティー向けのアクションカメラ特集。アクションカメラといえば動画だが、今回は静止画画質を中心にGoPro「HERO 6」、ソニー「RX0」、カシオ計算機「EX-FR200」、ニコン「KeyMission 360」を紹介する 冬のアクティビティーで写真を撮るために持っていきたいカメラ特集。今回はカシオ計算機とニコンのアクションカメラを紹介。静止画画質をチェックしてみる
冬のアクティビティーで写真を撮るために持っていきたいカメラ特集。今回はカシオ計算機とニコンのアクションカメラを紹介。静止画画質をチェックしてみる アクションカメラの定番であるGoPro「HERO 6」と、超小型高級コンデジであるソニー「RX0」の静止画画質および使い勝手を比較してみた
アクションカメラの定番であるGoPro「HERO 6」と、超小型高級コンデジであるソニー「RX0」の静止画画質および使い勝手を比較してみた 2017年もたくさんの猫写真を掲載してきた本連載。今年最後のまとめとして、テーマにそぐわないと泣く泣くボツにした写真を集めてみた
2017年もたくさんの猫写真を掲載してきた本連載。今年最後のまとめとして、テーマにそぐわないと泣く泣くボツにした写真を集めてみた この年末、いろいろなデジカメの売り上げランキングを見てみると、高額なフルサイズ一眼が上位に食い込んでいるのをよく見かける。30万円以上のデジカメがなぜ売れているのだろう?
この年末、いろいろなデジカメの売り上げランキングを見てみると、高額なフルサイズ一眼が上位に食い込んでいるのをよく見かける。30万円以上のデジカメがなぜ売れているのだろう? GoProは12月14日、HERO5 Black及びHERO5 Sessionの国内正規販売価格を12月15日より変更することを発表した。
GoProは12月14日、HERO5 Black及びHERO5 Sessionの国内正規販売価格を12月15日より変更することを発表した。 11月に発表された「ライカ CL」の発売日が決定。バルナックライカのサイズ感が好みのユーザーは是非!
11月に発表された「ライカ CL」の発売日が決定。バルナックライカのサイズ感が好みのユーザーは是非! 毎年、最先端のカメラをレビューするために参加しているグッドスマイルレーシングのレースクイーン撮影会。今年はソニーのミラーレス一眼「α7RⅢ」を購入して挑んだ!
毎年、最先端のカメラをレビューするために参加しているグッドスマイルレーシングのレースクイーン撮影会。今年はソニーのミラーレス一眼「α7RⅢ」を購入して挑んだ! アクションカムの定番ともいうべき「GoPro」のHERO5セットが11日限定でお買い得。
アクションカムの定番ともいうべき「GoPro」のHERO5セットが11日限定でお買い得。 東京でも表通りの喧噪を避けて古い路地に入るといきなり道の真ん中に猫がいたりする。今回はそういう路地を散策しながら猫撮影
東京でも表通りの喧噪を避けて古い路地に入るといきなり道の真ん中に猫がいたりする。今回はそういう路地を散策しながら猫撮影 Amazonでは12月11日(月)23時59分まで78時間「サイバーマンデー」を開催中だ。
Amazonでは12月11日(月)23時59分まで78時間「サイバーマンデー」を開催中だ。
 Amazonでは12月8日(金)18時から11日(月)23時59分まで78時間「サイバーマンデー」を開催する。
Amazonでは12月8日(金)18時から11日(月)23時59分まで78時間「サイバーマンデー」を開催する。
 Amazonサイバーマンデー、78時間の大セール。
Amazonサイバーマンデー、78時間の大セール。 塀の上を歩くのが猫の王道。でも、その角度から撮るかでイメージが全然違ってくるので悩ましい。何度も撮り直すこともまた楽しい
塀の上を歩くのが猫の王道。でも、その角度から撮るかでイメージが全然違ってくるので悩ましい。何度も撮り直すこともまた楽しい キヤノンが11月30日に発売を開始したG1X MarkIIIは、APS-CサイズセンサーにEVFも搭載して399グラムを実現した夢の次世代高級コンパクトカメラなのであ~る.しっかり試用してみたぞ..
キヤノンが11月30日に発売を開始したG1X MarkIIIは、APS-CサイズセンサーにEVFも搭載して399グラムを実現した夢の次世代高級コンパクトカメラなのであ~る.しっかり試用してみたぞ.. 冬の猫は屋根いる場合も多い。日差しが暖かく、安全だから。なかなかひとめには付きにくい場所だが、見つけると撮りたくなるのが屋根猫だ
冬の猫は屋根いる場合も多い。日差しが暖かく、安全だから。なかなかひとめには付きにくい場所だが、見つけると撮りたくなるのが屋根猫だ 女の子は上から視点で写真を撮ることが多いが、猫も上から目線だとかわいく見えたりする。私は下から目線が好きなので、這いつくばって猫を撮るのだが……
女の子は上から視点で写真を撮ることが多いが、猫も上から目線だとかわいく見えたりする。私は下から目線が好きなので、這いつくばって猫を撮るのだが…… キヤノンマーケティングジャパンは、公式ファングッズ「Canon Official Fan Goods」を発表した。
キヤノンマーケティングジャパンは、公式ファングッズ「Canon Official Fan Goods」を発表した。 パナソニックが静止画最高画質機となるミラーレス一眼「LUMIX G9 PRO」を発表。その発表会で実機に触りまくってきた!
パナソニックが静止画最高画質機となるミラーレス一眼「LUMIX G9 PRO」を発表。その発表会で実機に触りまくってきた! iPhone Xをゲットしてから1週間。持ち歩いているうちに猫を撮る機会も何度もあった。そこで気になったのが広角カメラと望遠カメラの使い分けだ
iPhone Xをゲットしてから1週間。持ち歩いているうちに猫を撮る機会も何度もあった。そこで気になったのが広角カメラと望遠カメラの使い分けだ iPhone Xをゲットしたので早速猫写真を撮る! うちの猫だけでなく、外に出て近所の猫も撮ってみました
iPhone Xをゲットしたので早速猫写真を撮る! うちの猫だけでなく、外に出て近所の猫も撮ってみました 猫は寒くなると布団の中に潜り込む。それを知らずに布団に倒れ込むと悲劇なので、布団をたたいて確認する「猫バンバン」が必要だ
猫は寒くなると布団の中に潜り込む。それを知らずに布団に倒れ込むと悲劇なので、布団をたたいて確認する「猫バンバン」が必要だ ソニーが「α7R III」の体験会を開催。実機に触れる貴重なチャンスだったので、実際に触って、撮ってきた
ソニーが「α7R III」の体験会を開催。実機に触れる貴重なチャンスだったので、実際に触って、撮ってきた