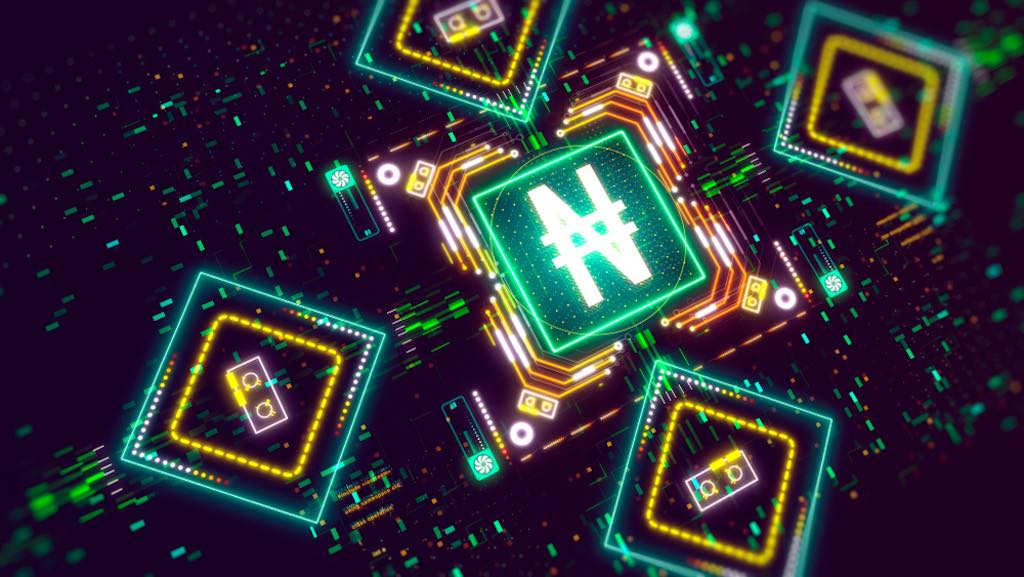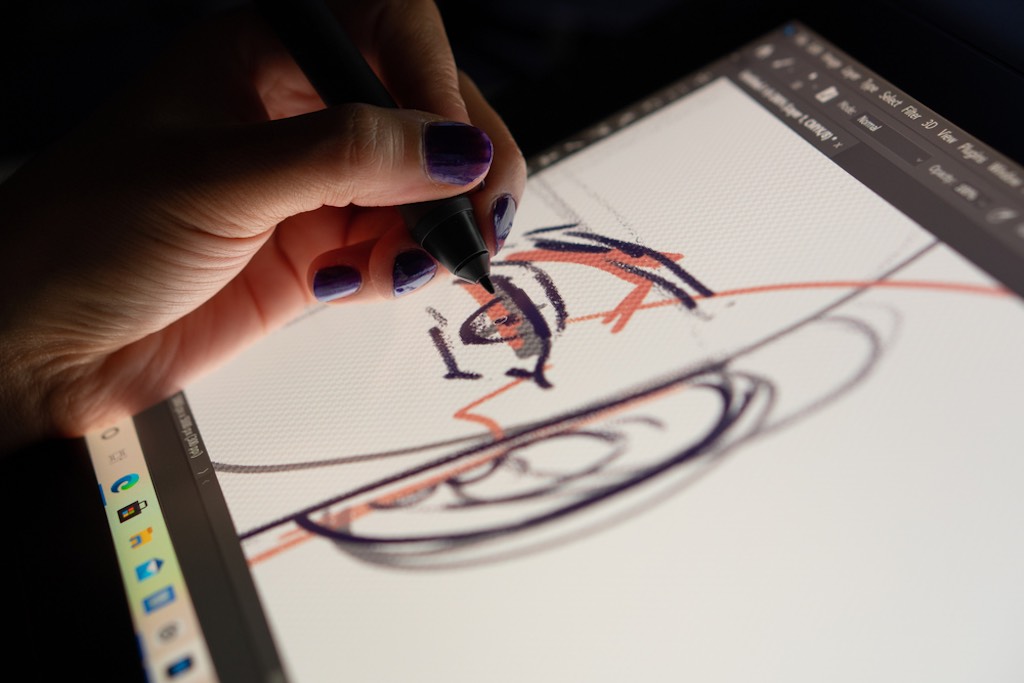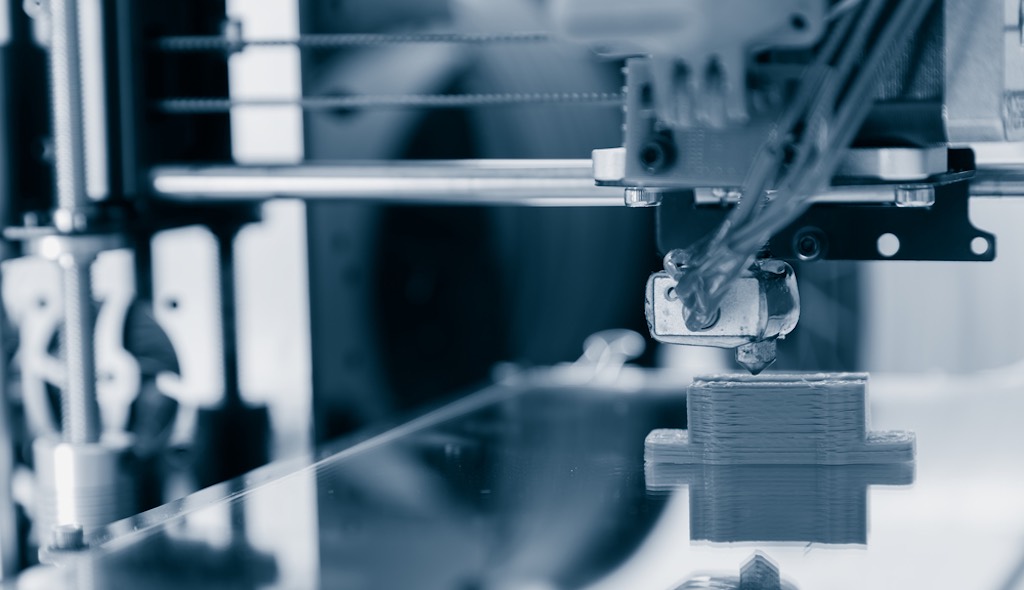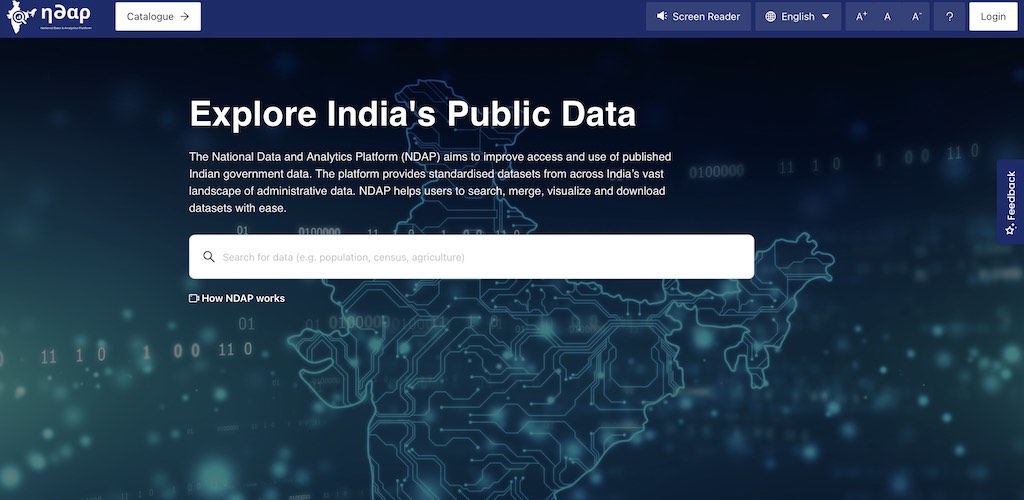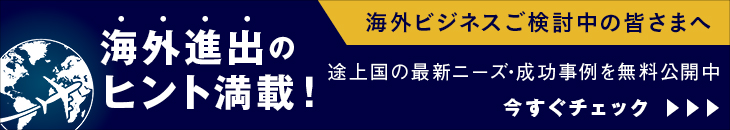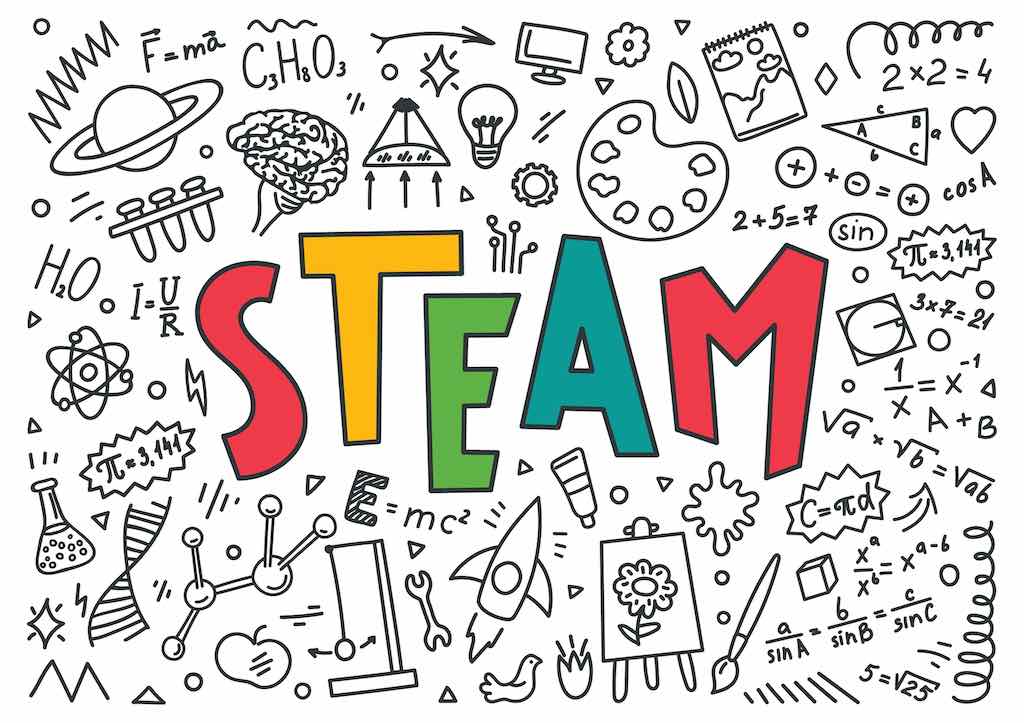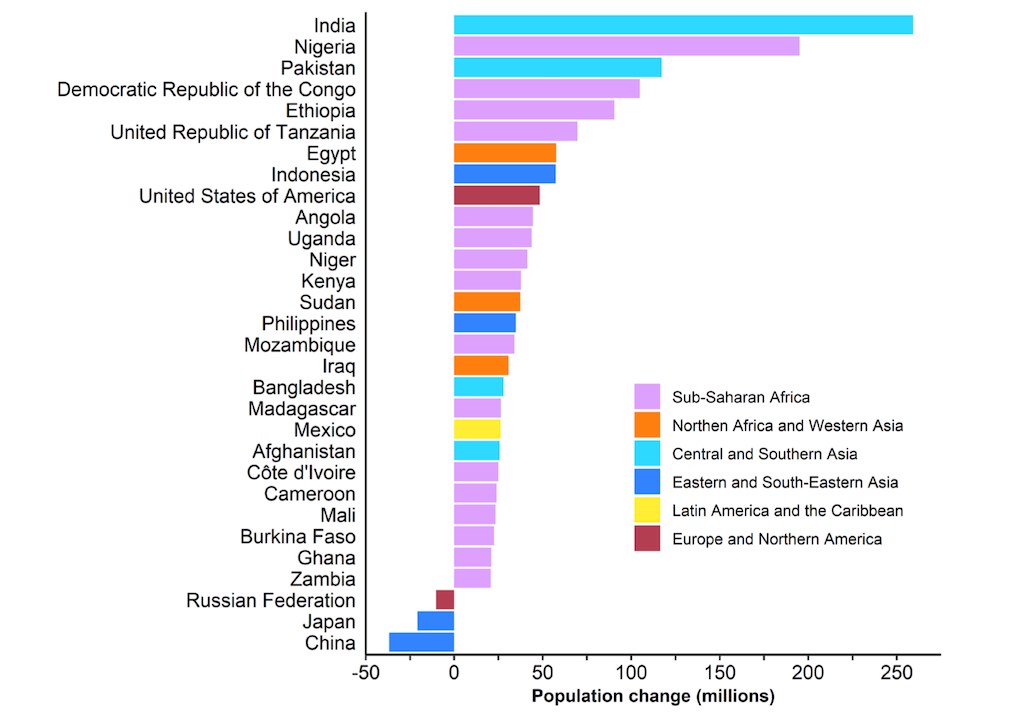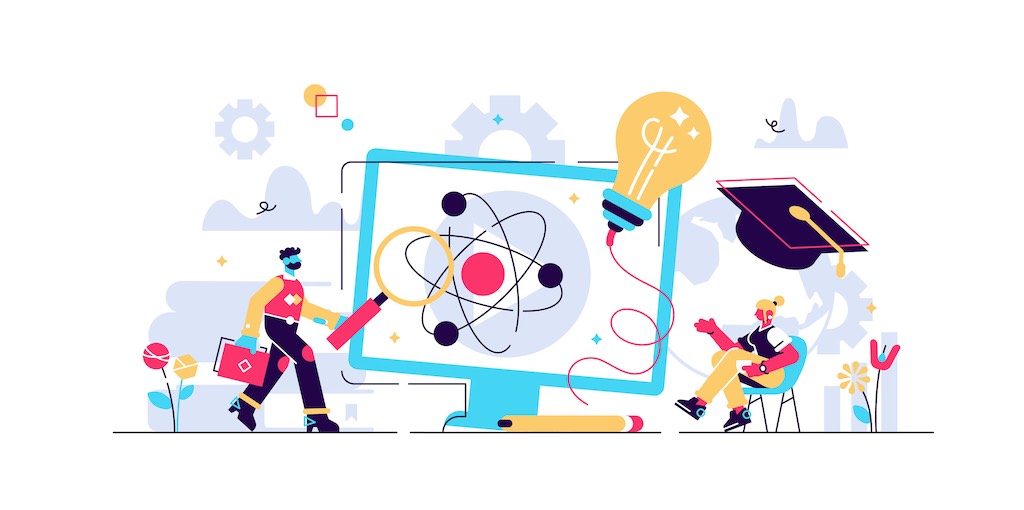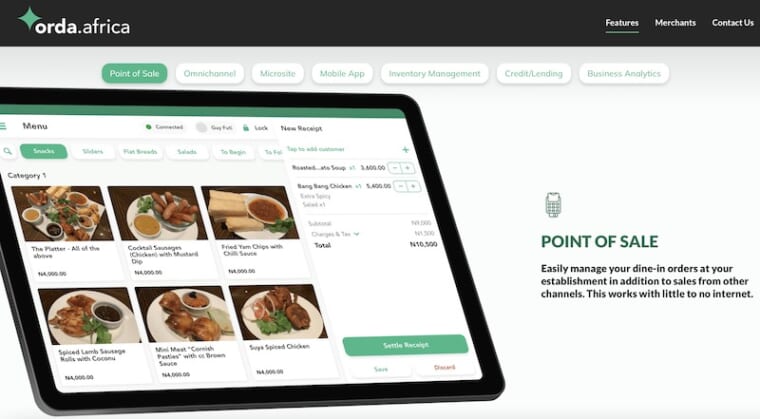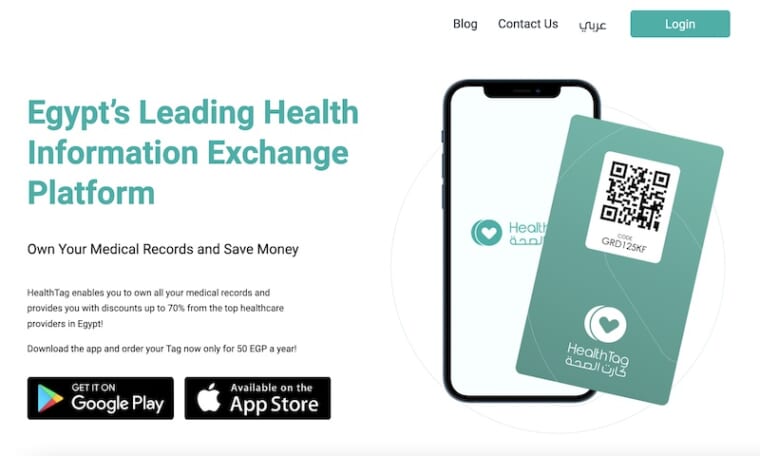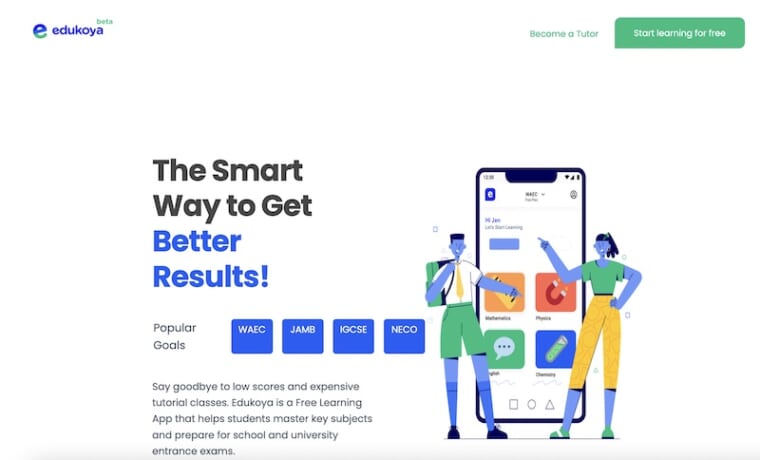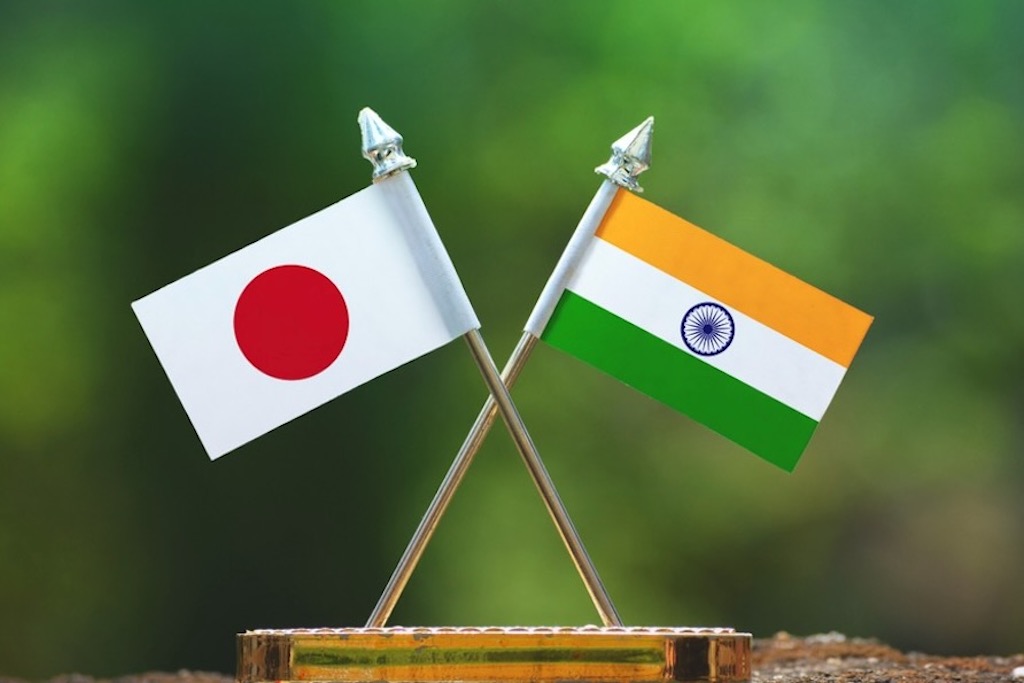ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって2週間が過ぎようとしていますが、いまだ解決の糸口を見出せていない状況です。ロシア軍とウクライナ軍の戦闘はこの瞬間も続いており、現地の惨状や避難民の様子などが連日日本でも報道されています。そんな中、西側諸国を中心にロシアに対する制裁も拡大。それに伴い原油価格や物価の高騰、航空制限による輸送遅延、株価の下落など、世界経済はもちろん、私たちの生活にも深刻な影響を及ぼしています。

情勢は刻一刻と変化していますが、国際機関をはじめ各国の反応はロシアに対してシビアです。国際的な金融決済ネットワーク「SWIFT」からのロシアの排除や、ロシア政府関係者の資産凍結をはじめとするさまざまな経済制裁のほか、スポーツではロシアでの競技の延期や中止、スポンサー契約の解除、選手の出場取り消しという動きもみられます。さらにNETFLIXやTikTokがロシアでのサービスの提供を停止したり、ロシア映画の上映を差し替えたりするなど、幅広い分野でロシアへの風当たりが強くなっています。
活発化するウクライナへの支援
その一方で、国や民間を問わず活発化しているのがウクライナを支援する動きです。現地では多くの民間人が被害を受け、200万人以上(2022年3月8日時点)の人々が避難民として近隣諸国へ脱出。EU加盟国では、難民申請なしに滞在許可証を発行し、就労や住居の支援も行うことで合意するなど、さまざまな国が避難民の支援に乗り出しています。日本でも、政府がウクライナの難民受け入れを開始したほか、群馬県が避難民に対して住宅や物資の提供を表明、横浜市も市営住宅約80戸を避難民向けに確保するなど、自治体レベルでも支援の輪が着実に広がっています。
日本企業も続々とさまざまな支援を表明
こうした状況にいち早く対応したのが民間企業です。その多くは人道支援を目的とした募金活動で、各社が基金を設立し、赤十字やUNHCR(国連難民高等弁事務所)など、ウクライナからの避難民や現地の人たちへの人道支援を行っている組織・団体への寄付が中心ですが、事業を活かした取り組みなど、独自の支援策を打ち出している企業もあります。
●株式会社ファーストリテイリング(ユニクロ)
2006年から世界各地の難民に衣料を支援し、2011年にはアジアの企業としては初めてUNHCRとグローバルパートナーシップを締結した同社。今回も、保温性の高い「ヒートテック」素材の毛布やインナー、エアリズムマスクなど約10万点と、ユニクロ国内店舗で回収したリサイクル衣料の中から、防寒着を中心に約10万点をポーランドなどに避難してきた難民に提供。また、避難所の設置や救援物資の配布に充てる目的で、約11億5000万円をUNHCRへ寄付すると発表しました。
●株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(ドン・キホーテ)
ウクライナの避難民100世帯の受け入れを決定。さらに、経済的支援、生活面のサポート、就業機会の提供にも取り組む方針です。
●楽天グループ株式会社
三木谷浩史会長兼社長がウクライナ政府へ10億円の個人寄付をした同社は、ウクライナ国内のスマートフォンの97%にインストールされている、コミュニケーションアプリ「Viber」において、通常は有料オプションである固定電話や携帯電話への通話料を無料にするクーポンを提供。また、飲料水など物資支援、保険サービス提供、子どもの保護などに活用するための緊急支援募金を行っています。
●株式会社ZOZO
「ZOZOTOWN ウクライナ人道支援チャリティーTシャツプロジェクト」を展開。3月1日~14日までチャリティーTシャツを販売し、その売り上げを全額寄付すると発表。
●APAMAN株式会社
日本への避難してきた人たちへ、同グループが管理している空室物件を短期的に無償提供。反戦を求めるポスターを趣旨に賛同するアパマンショップ店舗に設置するほか、停戦後は復興に向けた住宅や資材提供等の支援を予定しています。
●ワールドポテンシャル株式会社
同社で運営するマンスリーマンション、ホテル、民泊施設の一部を、避難民受け入れ施設として提供。また、沖縄、宮古島、長野、函館で運営するホテルで、社宅の提供を含めた避難民の就労受け入れを積極的に行うそうです。
●株式会社ネクストエージ
日本からウクライナ避難民に自立の選択肢を提供するための「PC1台から勇者プロジェクトforU」を実施。WEB制作、メタバース企画などIT事業において、ウクライナ避難民クリエイターやエンジニアへの発注を企業から募っています。「寄り添われる側と寄り添う側の両方の想いを具現化したもの」として注目されています。
●クックパッド株式会社
紛争により影響を受けた人たちを支援することを目的に、調理環境が十分でない中でもできる料理のレシピを募集するプロジェクト「#powerofcooking」を開始。寄せられたレシピの一部をウクライナ語に翻訳し、ウクライナ版クックパッドの利用ユーザーに提供します。
●株式会社グローバルトラストネットワークス(GTN)
ウクライナ本国の家族や友人と連絡ができる状態を維持できるよう、海外のプリペイドSIMに通話・通話料のクレジットを送ることができるサービス「TOP UP(トップアップ)」を在日ウクライナ人GTNユーザーへ無償提供(2022年3月31日まで)。また、政府の認定を受けたウクライナの避難民を対象に、モバイルSIMを1年間無償で提供します。
●キーン・ジャパン合同会社
米国・ポートランド発のアウトドア・フットウェアブランド「KEEN」は、ウクライナ国内、近隣諸国に避難してきた人へ2500足のKEENシューズを提供。また、人道的な支援のために5万ユーロの寄付を決定しました。
多くのグローバル企業も人道支援を約束
もちろん、海外の企業も支援活動に名乗りを上げています。取り組みの多くは、ユニセフやUNHCR、国際赤十字、セーブ・ザ・チルドレンなど、避難民を支援する組織への資金や製品の寄付が中心となっているようですが、その一部を紹介しましょう。
●Google
2500万ドルを人道支援のために寄付し、さらに1000万ドルをポーランドで人道支援・長期支援を行う団体に寄付。また、人道支援組織・政府間組織が支援情報を届けられるよう広告クレジットを提供するなど支援を強化。主にウクライナの人々をサイバーセキュリティの脅威から守るための対応策も打ち出しています。
●Amazon
ユニセフ、世界食糧計画、赤十字、ポルスカ・アクチャ人道、セーブ・ザ・チルドレンなどの組織に500万ドルを寄付。また、社内からの追加で最大500万ドルを寄付するほか、顧客の支払い処理手数料を免除する寄付リンクをホームページに設定。
●Apple
ティム・クックCEOが従業員による寄付プログラムをスタート。2対1の割合で従業員からの寄付額に上乗せするマッチング方式で実施されます。また、ウェブサイトの上部に寄付用のバナーを追加し、ウクライナ人避難民へのサポートを容易にしました。
●Wells Fargo
アメリカの金融機関である同社は、アメリカ赤十字、ワールドセントラルキッチン、USO(米国慰問協会)を含むウクライナの避難民を支援する非営利団体に100万ドルの寄付を約束。
●Starbucks
ロシア内の全事業を停止した同社。スターバックス財団が、ワールドセントラルキッチンと赤十字に50万ドルを寄付しました。
●Ford Motor Company
グローバル・ギビング・ウクライナ救援基金に10万ドルを寄付する計画を発表。
●Volkswagen
ドイツの国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)に100万ユーロを寄付。
●J.P. Morgan
同行のリッチ・ハンドラー最高経営責任者(CEO)がInstagram上で100万ドルの寄付を表明。
●SpaceX
ウクライナにおいて衛星によるネット接続サービスを提供。
●FedEx
避難民のいる地域に物資を輸送している組織へ、現物出荷で100万ドル以上、ヨーロッパの非政府機関に55万ドルの寄付を行っています。
●Booking.com
ブッキング・ホールディングスは、赤十字国際委員会に100万ドルを寄付し、さらに従業員の寄付総額と同額を寄付する方針。
●Airbnb
ウクライナからの避難民、最大10万人の無料仮設住宅を利用可能にすると発表。宿泊は同社と、利用者によるAirbnb.org難民基金への寄付、宿泊先ホストの善意によって賄われるそうです。
●BASF
ドイツ赤十字に100万ユーロを寄付。近隣諸国に到着した避難民への生活必需品(食料、衣類、衛生キット、通信機器など)の提供に使用されるそうです。
●IKEA
イケア財団が国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)に2000万ユーロを寄付。また、グループ企業としても製品を提供をはじめ、現地で活動するUNHCRやセーブ・ザ・チルドレンに2000万ユーロを支援します。
●Kering
UNHCRに多額の寄付を行うことを表明。傘下であるGUCCIは、グローバルキャンペーン「Chime for Change」を通じてUNHCRに50万ドルを寄付します。
●CHANEL
200万ユーロをCAREとUNHCRなどに支援すると発表。また財団としても女性や子どもへの中長期的な支援を行う計画です。
●NIKE
ユニセフ(国連児童基金)とIRC(国際救済委員会)に100万ドルを寄付します。
●L’Oreal
避難民やウクライナの現地の人々を支援するために、地域のNGOや国際NG(HCR、赤十字、ユニセフなど)に 100万ユーロを寄付。さらにウクライナ、ポーランド、チェコ、ルーマニアのNGOに衛生用品を届けています。
●Samsung
100万ドル相当の家電製品を含む計600万ドルを人道支援に寄付する方針。
他人事ではなく、“自分事”として関心を持ち続けることが大事
テレビやインターネットで連日流れる映像などを観て心を痛めている人も多いと思います。募金やデモへの参加など、ウクライナの平和のために私たちが個人レベルでできることは残念ながら限られますが、何より、問題意識を持って関心を持ち続けることが大切だと思います。1日でも早くこの事態が解決し、ウクライナの人たちに笑顔が戻ることを切に願います。
IC NET「海外展開に役立つ資料集」バナー入れる


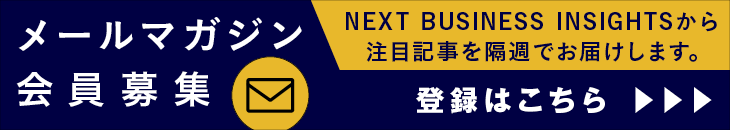






















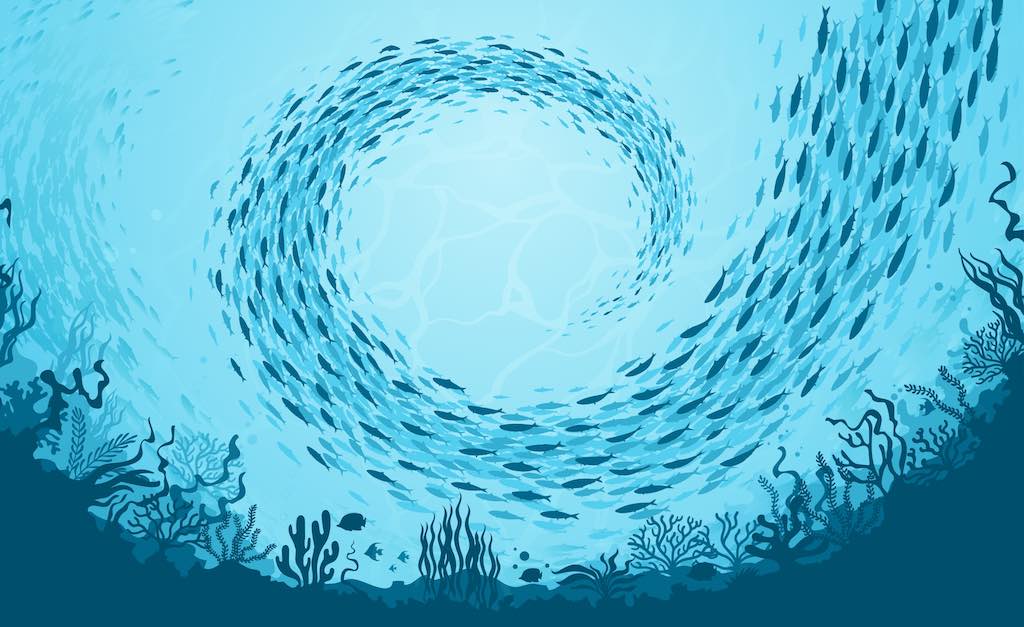








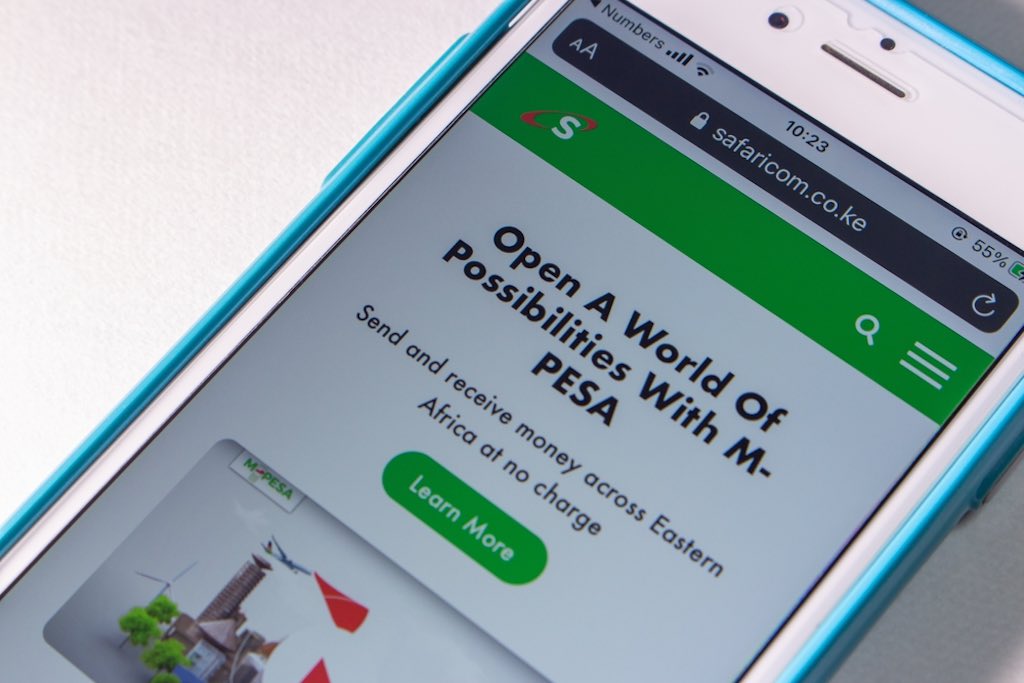



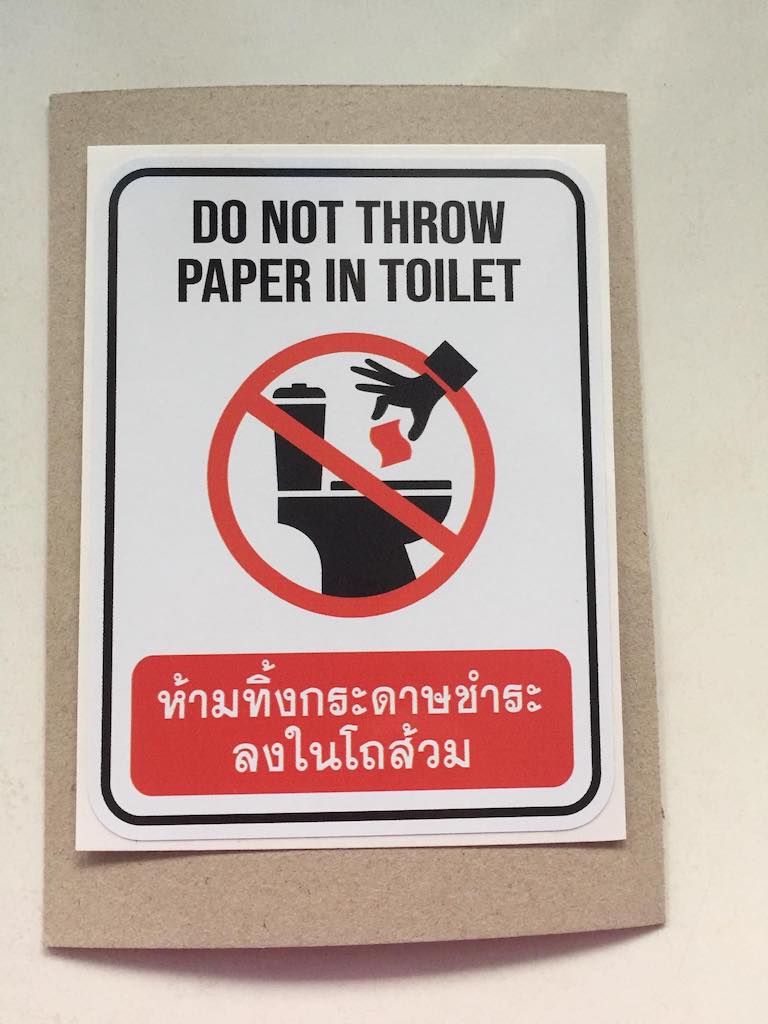




















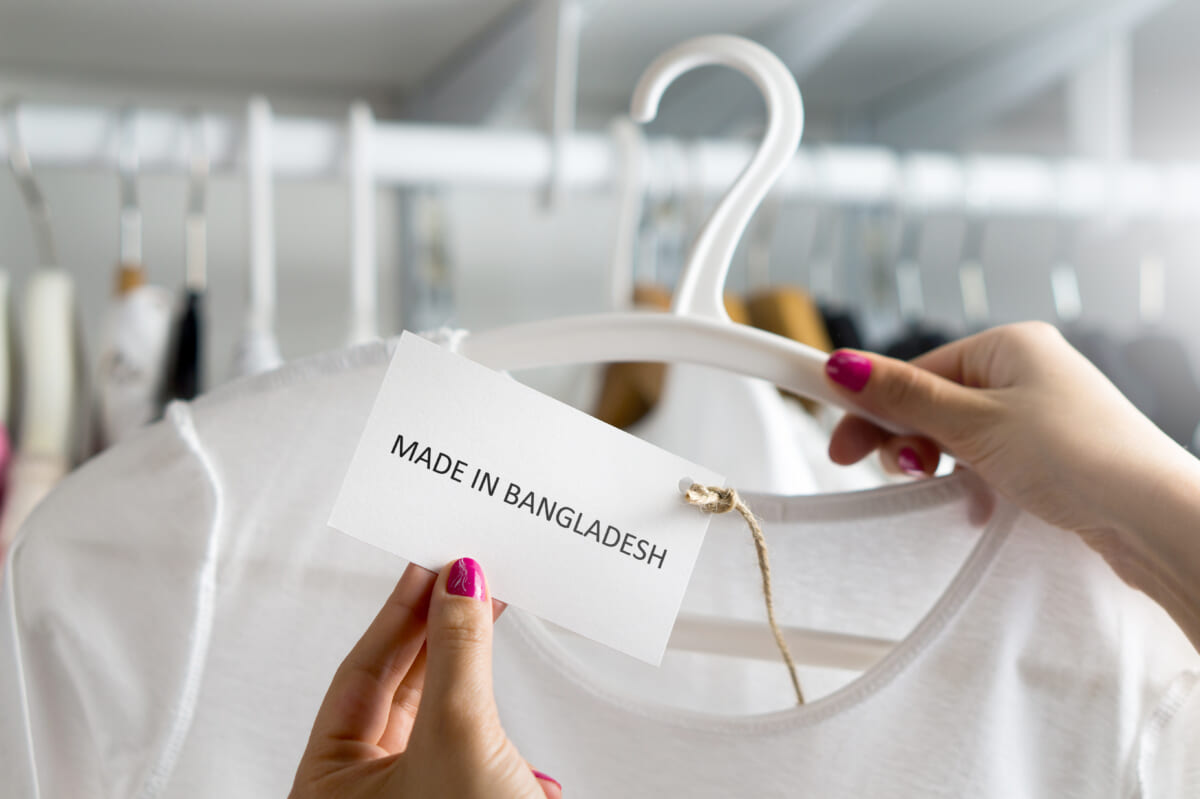





 The time we’ve all been waiting for!
The time we’ve all been waiting for!  The gates are OPEN and the games have now begun
The gates are OPEN and the games have now begun