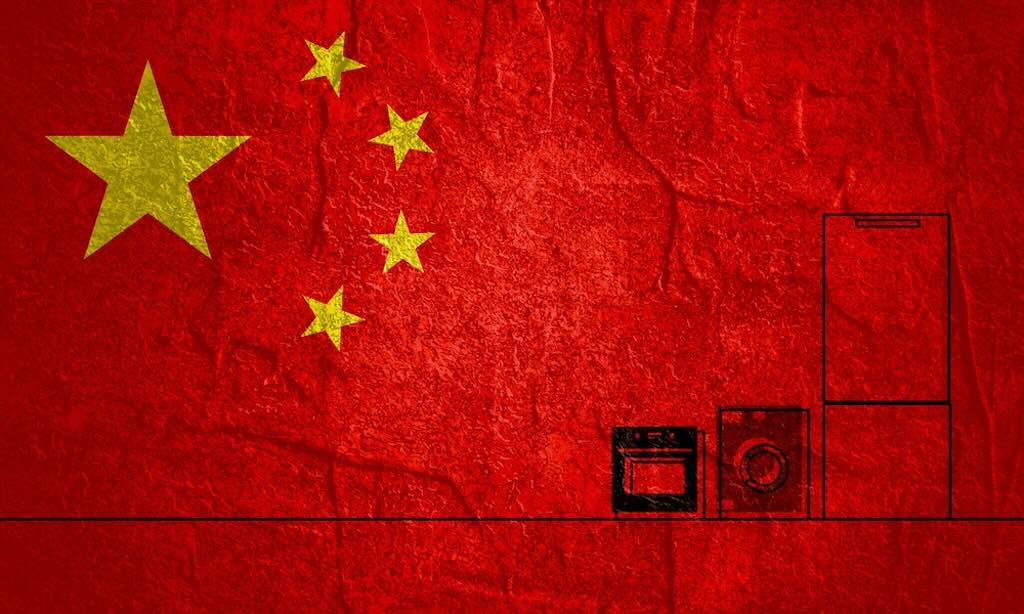中東地域トップクラスの産業大国・トルコ。ヨーロッパ、東欧、ロシア、中央アジア、中近東、北アフリカの中心に位置しているトルコは、その地理的利点も活かしながら、世界各国との外交や関税同盟も積極的に推進しています。
さらに2019年には、年間2億人のハブとなる世界有数の巨大空港が開港。今後さらなる経済成長が期待されています。その中で現在ニーズが高まっているのが「高度産業人材」です。産業の発展のために不可欠な課題解決能力や思考力を持った人材を育成していくために、今後トルコではどのような教育が必要なのでしょうか。今回はトルコで20年以上にわたって、教育省などに技術指導を行ってきた伊藤拓次郎氏に話を聞きました。過去にODA事業として実施された産業人材育成プロジェクトや、現在トルコが求めている人材について解説しつつ、「トルコにおける高度産業人材育成のこれから」を紐解きます。
お話を聞いた人
伊藤拓次郎氏
1996年から20年以上にわたって、トルコ保健省、教育省、家族省などでODA事業を実施。トルコ以外でもこれまで約40か国でODA事業のさまざまなプロジェクトに携わった経験を持つ。専門は、インストラクショナルシステムデザイン、教育・教材開発、トレーナー育成、国際開発におけるプロジェクトマネジメントなど。現在はアイ・シー・ネットのグローバル事業部でトルコを中心に中東STEAM教育事業の立ち上げに従事している。
2001年から日本も支援してきた、トルコの製造業技術者の人材育成
トルコでは1990年以降、製造業が急速に拡大しました。それによって製造業技術者の人材育成が急務となり、国の開発計画の重点課題として取り組まれてきました。日本も2001年からトルコ国民教育省をODAにより支援。2001~2006年にかけて、工場での生産性向上のために必要な「自動制御技術」を持つ人材を育成するための技術協力プロジェクト「自動制御技術教育改善計画」が実施されました。
自動制御技術は、工場などのロボットや製造ラインを制御することによって生産を自動化していくための技術。産業の品質向上や効率化を図るために欠かせないものです。この自動制御技術は、電気、電子、機械など、あらゆる分野の技術で構成されていて、トルコの職業高校でも2001年以前からこれら一つ一つの技術を学ぶ授業が実施されていました。しかしこれらの技術を、ITを使って複合的に制御することを学ぶカリキュラムは、ニーズはあったものの、実施には至っていませんでした。そこで日本が自国の技術を活かし、トルコの2つの職業高校に自動制御技術(Industrial Automation Technology:IAT)学科設立のための支援を行ったのです。
この成果を受けて、国内各地の職業高校20校にIAT学科を新設し、IATトレーナーを養成するための教員研修センターも設立しました。その後も教員研修センターにトルコ独自のシステムを導入したり、民間企業の従業員を対象に実務者研修を行ったりするなど、教員研修の実施・運営体制の強化が進められました。現在はトルコ全国70校以上で自動制御技術が学べるようになり、製造業技術者の人材育成が行われています。
トルコ周辺国にも技術を展開「自動制御技術普及プロジェクト」
トルコ国内への普及がひと段落すると、中央アジアや中近東への技術展開を目指して、新たな取り組みが始まりました。それが2012年から3年間かけて行われた「自動制御技術普及プロジェクト」です。本プロジェクトには伊藤氏も参加していました。
「『自動制御技術普及プロジェクト』は、途上国間で支援や援助を行う『南南協力』と呼ばれる形の取り組みで、私たちはその支援を行うためにプロジェクトに携わりました。このプロジェクトでは、イズミールにある教員研修センターに、中央アジア・中近東の9か国(アゼルバイジャン、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、トルクメニスタン、タジキスタン、パキスタン、パレスチナ、アフガニスタン)のポリテクカレッジや職業訓練校の教員たちを受け入れ、トルコのマスタートレーナーたちが産業ロボット制御の技術指導を実施。産業自動化教材を用いながら、メカニズムや使用する機材についてレクチャーしたり、プログラミングの仕方などを指導したりしました」
 自動制御技術普及プロジェクトでパキスタン教師に技術指導をする様子
自動制御技術普及プロジェクトでパキスタン教師に技術指導をする様子
本プログラムでは、トルコ周辺国の自動制御技術普及をさらに推進するために、トルコに進出している日系企業と9か国のマッチングイベントも実施されました。イベントでは、日系企業がそれぞれ自社の商品を展示したり、カンファレンスを行ったりして技術を紹介。その中で、カザフスタンから「日本企業の産業自動化機材を導入したい」と相談がありました。最終的にODAの普及実証事業を通して、カザフスタンのトップ大学であるナザルバエフ大学に「産業自動化ラボ」を設立。日本の自動制御技術の教育機材を導入し、教員たちのトレーニングも行われました。
 9か国の技術教育高官と日系企業のマッチングイベントでの集合写真
9か国の技術教育高官と日系企業のマッチングイベントでの集合写真
「人材育成と聞くとどうしても、『高校を出てすぐに働ける現場作業員を育てること』だとイメージされがちです。しかし自動制御技術普及プロジェクトは、ものごとの仕組み全体を理解したり、自分で仮説検証をしながら考えたりできるような人材、つまり『高度産業人材』の輩出を目指した取り組みでもありました。実際、企業や工場などを訪問して産業調査を実施したときには、現場から『マネジメント能力や課題解決力、知識を実際の現場で応用して使うことができるような人材が不足している』という声を直接聞くこともあり、高度産業人材のニーズが高まっていることを実感しています。トルコにとって高度産業人材の育成は、今後の重要な課題の一つになってくるのではないでしょうか」
高度産業人材の活躍が期待される、再生可能エネルギーの分野
今後のトルコで高度産業人材が特に求められる分野として、伊藤氏は、トルコや中近東でトレンドになっている「再生可能エネルギー分野」を例に挙げました。現在イズミールでは、風力発電の設備が多く見られ、新たなベンチャー企業もどんどん誕生しています。また、トルコはもともと自動車産業が盛んな国。長年EUへの加盟を目指しているトルコでは、ヨーロッパの市場を特に意識していることもあり、現在は電気自動車やバイブリッドカーなどの開発にも積極的です。伊藤氏は「トルコの大学では、授業の中で電気自動車をつくらせるところも出てきていますし、中学校においても風力発電のしくみを教えています」と語ります。
 イズミール郊外の村の電力を補う風力発電の風車
イズミール郊外の村の電力を補う風力発電の風車
再生可能エネルギーは世界各国が取り組みを進めている、まだ発展途上の分野。そのため、新しい発想や考える力、さらにはチームで仕事をする力が求められます。
「まだ答えが見つかっていないからこそ、課題を見つけたり、分析をしたり、仮説検証を繰り返したりする能力が必要。さらに複数人でアイデアを出し合って新しいものをつくるなど、チームで取り組むことも求められるはずです。個性豊かで個人プレーが得意なトルコ人にとって、『チームビルディングをして仕事をする』こと自体も大事なチャレンジだと思っています」
子どもたち、そして教員たちへの教育も不可欠
高度産業人材の育成には、小中学生の頃から「自分で考える力」を養っていくことが大切。そのために重要な役割を果たすのが、STEAM教育です。「自分たちで課題を見つけて解決しながら、付加価値をつけることができるよう、プロジェクトワークや課題解決型学習を取り入れていく必要があります」と伊藤氏。さらに「子どもたちの教育だけでなく、教員たちの教育も大切」だと語ります。
「私が感じるのは、トルコの教育にはとても進んでいるところがある一方で、極端に遅れている面もあるということ。例えば私が以前プロジェクトで携わっていた高校は、EUや日本の民間企業の支援によって、立派なラボを持っていました。このように学びの環境は整っているのですが、まだまだ課題もあります。
その一つが『評価』に対する認識。トルコの現在の教育の特徴として、ほとんどの高校教員たちが、卒業後の生徒たちの進路を全く知らないということが挙げられます。卒業後のことではなく『卒業すること』がゴールだと考えられていて、授業の質や評価よりも『卒業できるようテストで点数を取らせること』に終始しがち。そのため教員たちの『授業を良くしよう』『授業後の評価をきちんと行おう』という意識が低いように感じます。また、暗記暗唱型の授業が多いことも課題。教員たちが一方的に講義をして、子どもたちがその内容を覚えるというような授業スタイルがまだ多いのが現状です。現在、トルコでも科学実験の教材やプログラミングが学べる教材などが出回ってはいるのですが、教員たちからは、教材の使い方や子どもたちへの教え方がわからないと言われることも。子どもたちの教育と同時に、教員たちへの研修なども同時並行で行っていく必要があると感じています。
教育に限らず、トルコではEUなどから最新の技術や新しい情報が数多く入ってきます。しかしトルコの人々には、まだそれらを扱うだけの能力が伴っていないという側面もあるのです。そのため、トルコにすでにあるリソースをつないだり、情報を整理したり、使い方を教えることも、この国にとっての助けになると私は考えています」
現在進行中のSTEAM教育事業 授業のデモンストレーションもスタート
現在、トルコSTEAM教育事業の立ち上げに向けて準備を行っている伊藤氏。その事業の内容と今後の展望について聞きました。
「小学校から大学までを縦軸で考え、STEAM教育を土台にしながら高度産業人材を育成していこうというのが今回の事業。政府や行政も巻き込みながら、民間のビジネスとして展開できればと考えています。その中で構想しているアイデアの一つが、STEAMに関するプラットフォームづくりです。これは、ユーザーがプラットフォームにアクセスすることで、STEAM関連の教育サービスが受けられたり、コミュニティに参加できたり、資金・資格を取得できたりするようなもの。さらに企業とも提携して、教材の販売を行ったり、インターンシップやジョブマッチングのようなサービスを提供したりすることも想定しています。日本の企業は、トルコを含めて中央アジアや中近東に進出するのが難しい現状があり、日本企業にとって、このプラットフォームがトルコ進出のための一つの突破口になればとも考えています。
現在は、現地での事業立ち上げに関わる情報を集めたり、パートナー候補企業との協議をしたりして、着々と準備を進めています。最近ではトルコの学校で、私たちが日本で展開しているSTEAM教育の講座『科学実験教室』『もののしくみ研究室』を紹介したり、デモンストレーションを行ったりもしました。小学生の子どもたちに対して科学実験教室を実施し、空気砲や静電気の実験をしたときには、みんな興味津々。楽しみながら学ぶ様子を見て、手ごたえを感じています。同時に教員たちには、この講座をトルコの学校のカリキュラムにどう落とし込むか、どう評価するか、などを考える研修も実施しました。今後も実現に向けて歩みを進めていきます」
 21年10月に行われた「科学実験教室」デモンストレーションの様子
21年10月に行われた「科学実験教室」デモンストレーションの様子
「トルコのような新興国では、どうしても経済が優先され、教育は後回しにされてしまいます。しかし幼少期からSTEAM教育などを行って自分で考える力を養うことで、広く活躍できる高度産業人材が育ち、結果的には経済の成長や国の発展にもつながるのではないでしょうか」と伊藤氏。トルコの教育分野に、今後ますます注目が集まりそうです。