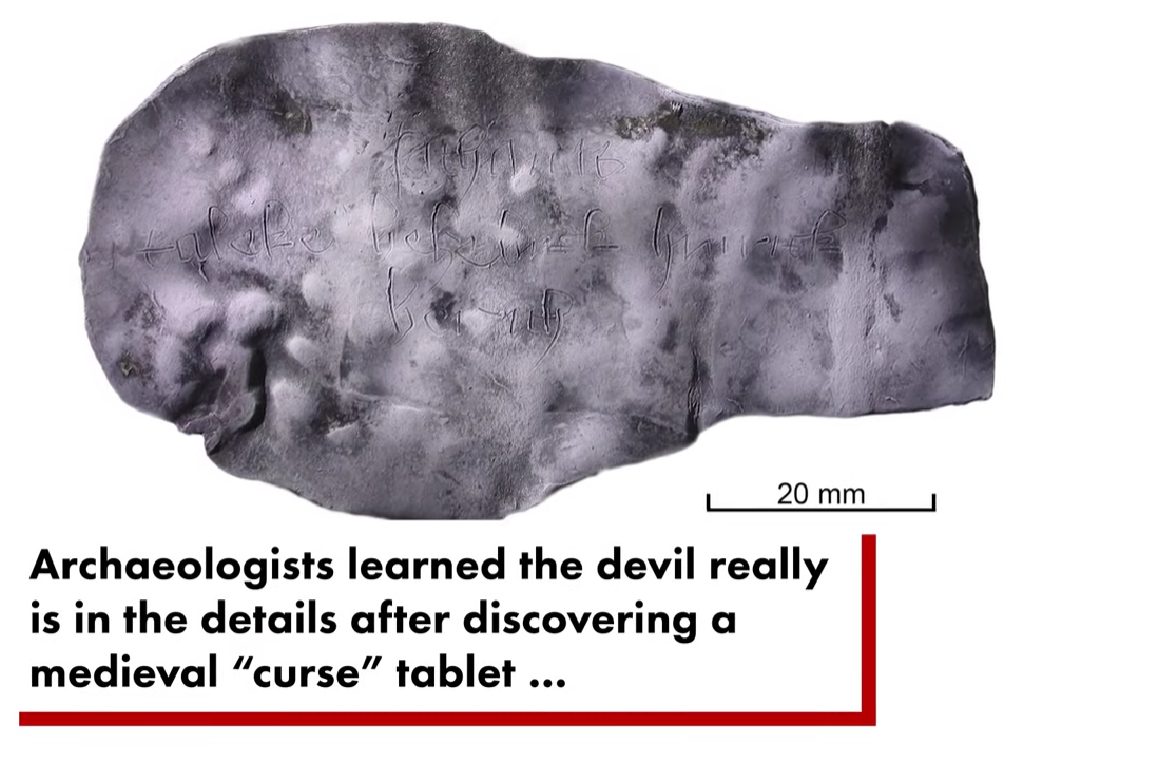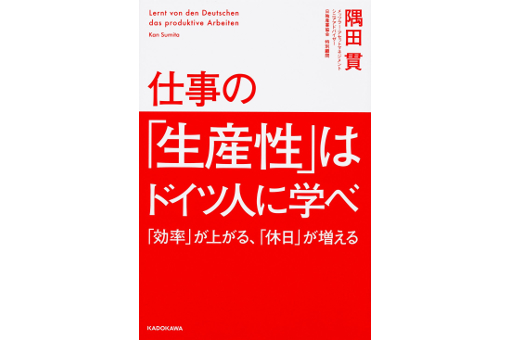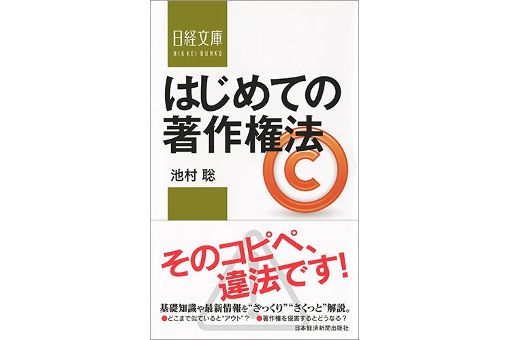世間で注目を集めている商品が一目でわかるAmazon「人気度ランキング」。さまざまなカテゴリの注目商品がわかる同ランキングだが、商品数の多さゆえに動向を追いかけられていない人も少なくないだろう。そこで本稿では、そんなAmazon「人気度ランキング」の中から注目の1カテゴリを厳選。今回は「本」のランキング(集計日:1月19日、昼)を紹介していこう。
効率良く働いて残業をなくそう!
●1位『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149(2) SPECIAL EDITION(サイコミ)』(廾之・著/バンダイナムコエンターテインメント・原著/講談社・刊/2268円)
●2位『最上もが2nd写真集「MOGAMI」』(最上もが・著/桑島智輝・写真/集英社・刊/2376円)
●3位『Stagefan Vol.1(メディアボーイMOOK)』(メディアボーイ・刊/880円)
●4位『三省堂国語辞典 第七版 阪神タイガース仕様』(見坊豪紀、市川孝、飛田良文、山崎誠、飯間浩明、塩田雄大・編集/三省堂・刊/3240円)
●5位『仕事の「生産性」はドイツ人に学べ 「効率」が上がる、「休日」が増える』(隅田貫・著/KADOKAWA・刊/1512円)
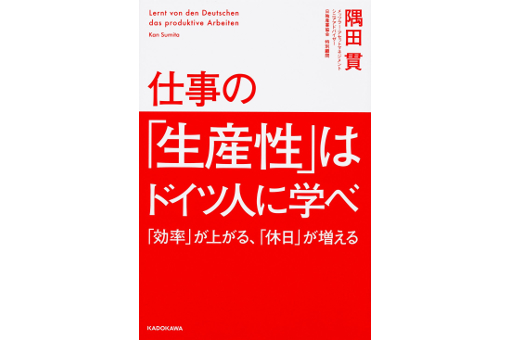 出典画像:Amazonより
出典画像:Amazonより
他の先進国と比較して労働時間が多いのが日本。対してドイツの仕事時間は日本よりも年間300時間少ないが、生産性は日本の1.5倍だという。同書はドイツのビジネス業界に20年身を置いた著者が、一流ビジネスパーソンの生産性の秘密を公開。
SNSやネット上では日本の残業問題や会社の改善すべき点を多くの人が指摘しており、核心を突いた発言が拡散されて注目を浴びることも多い。現在は、情報メディアのアカウントが1月18日に呟いた「残業しても幸せにはなれない。幸福感をストレスが上回ってしまう」というツイートが話題を集めている。
小さい球状の「幸福感」を手にした人が、幸福感より遥かに大きい「ストレス」の球に押し潰されているイラストも合わせてアップ。残業から生まれるストレスの大きさに比べれば、残業代で得られる幸福感は遥かに小さいと説明する内容に多くのユーザーが共感した。「お金だけで幸せにはなれない、辛いだけです」「仕事に目的が見出せない人は尚更だよなあ…」という声が続出。
刺激を受けたユーザーが自身の働き方を改めようと、購入に駆けつけたのかもしれない。
大人気のゆるキャラが著作権問題の渦中に!?
●6位『はじめての著作権法(日経文庫)』(池村聡・著/日本経済新聞出版社・刊/972円)
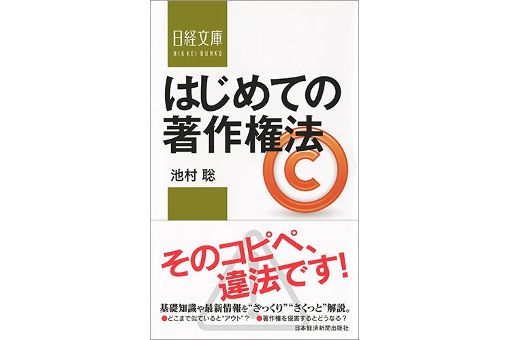 出典画像:Amazonより
出典画像:Amazonより
著作権法の基礎知識を身につけるための、入門書に最適な1冊がランクイン。著者は著作権法に精通した弁護士で、文化庁で著作権調査官として働いた実績も。著作権といえば、今注目を集めているのはゆるキャラのくまモン。
熊本県は今年から、くまモンのイラストの利用を海外企業にも解禁した。くまモンの知名度を世界に広めたいといった狙いからの試みだが、地元の企業からは非難の声が続出。自分たちでくまモンの公式グッズを作れるようになった海外企業から、取引キャンセルが相次いでいるという。
くまモンの非公式グッズはこれまでに海外でも多く作られている。そのため、1月17日放送の「モーニングショー」ではコメンテーターの玉川徹が「中国で偽物作る企業が著作権料払いますかね?」と苦言を呈する場面も。ネット上でも「著作権料きちんと徴収できるのか疑問」「ちゃんと著作権とか対策立てないと、悪用される未来が見える」と話題になった。
●7位『haru*hana(ハルハナ)VOL.46』(東京ニュース通信社・刊/980円)
●8位『田園発 港行き自転車 上(集英社文庫 み 32-8)』(宮本輝・著/集英社・刊/799円)
●9位『田園発 港行き自転車 下(集英社文庫 み 32-9)』(宮本輝・著/集英社・刊/799円)
●10位『できる課長は「これ」をやらない!』(安藤広大・著/すばる舎・刊/1620円)
生産性や著作権法に関する本が上位に揃った今回のランキング。果たして次はどんな結果になるのだろうか。