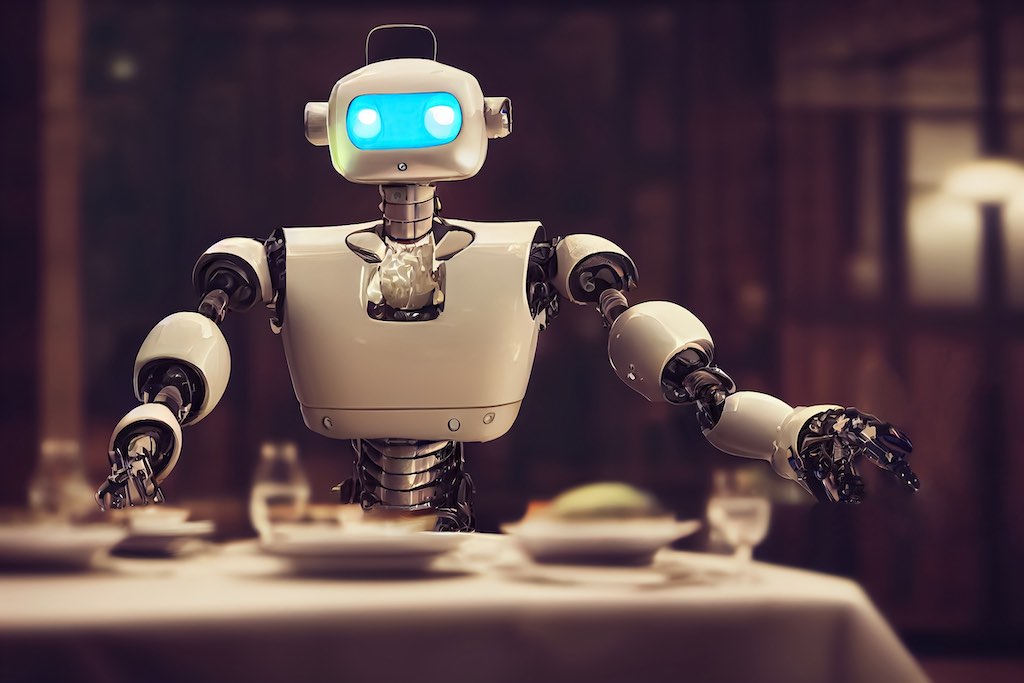空港の滑走路が一時閉鎖されるとき、その原因には、鳥と飛行機が衝突するバードストライクなど、鳥が関係していることが少なくないでしょう。でも、ニュージーランドの空港で先日起きたハプニングは、もっとカワイイ鳥によるものでした。

ニュージーランドの首都ウェリントンにあるウェリントン国際空港で1月12日、小さな動物が滑走路にいることが見つかりました。それは、なんと小さなペンギン。ちょうど離陸しようとしていたエア・チャタムのパイロットがその存在に気づき、一時、飛行機の離着陸が中断されることとなったのです。
空港職員が滑走路に向かうと、滑走路を横断していたペンギンを発見。すぐに捕獲されたそうです。

この空港は、岩らだけの海岸沿いにあり、このペンギンは滑走路の周囲にあるフェンスの下に入り込んだものと見られています。とはいえ、ペンギンが空港に入りこんだのは、おそらく初めてのことで、とても珍しいハプニングだそう。
捕獲されたペンギンは生後6週間ほどで、少し痩せており、お腹が空いていた様子だったとのこと。職員に捕獲された後はタオルにくるまれて、おとなしくしていたようで、同空港のインスタグラムでそのときの写真が紹介されました。現在ニュージーランドは真夏で、ペンギンも暑さに疲れていたため、ウェリントン動物園に運ばれました。
よちよち歩きのペンギンが現れたのは、ほっこりするハプニング。でも、ひとつ間違えば惨事につながりかねません。空港側は同じようなことが起きないように、滑走路のまわりにあるフェンスについて見直しを行うことを発表しています。
この投稿をInstagramで見る
【主な参考記事】
New York Post. Penguin on runway causes delays at New Zealand airport: ‘A very unusual occurrence’. January 24 2024