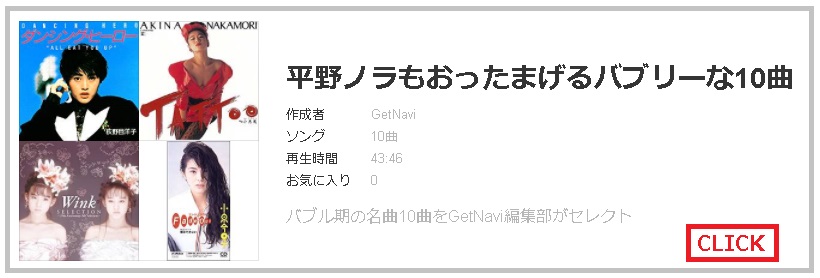大黒PAは神奈川県横浜市鶴見区の首都高速道路神奈川5号大黒線上にある高速道路上の休憩施設である。筆者は大黒PA&横浜ベイブリッジが1989年9月27日にオープンしてからこれまでクルマ雑誌の取材を含め、数えきれないくらい大黒パーキングに通って来た。オープンから28年経過し、大黒PAは今や、日本のサブカル系クルマ文化の発信地となり、多くのクルマ好きが集まる「聖地」となった。英国国営放送BBCの人気車番組「トップギア」が取材に訪れるほど、世界的にもメジャーな場所となっている。
■なぜ大黒PAはクルマ好きの聖地になったのか?
そもそも、大黒PAにクルマ好きが集まるようになったのか? それは簡単。以下の地図を見ればわかる通り、東京方面からも神奈川方面からも集合しやすいのである。

上下線で集合しやすいといえば、東京湾アクアラインの「海ほたる」も人気があるが、こちらは千葉方面からと川崎方面からではパーキングの階が異なるので、千葉方面からの参加者が多い場合は少々面倒かも?また、駐車場はほとんどが建物の中になるため開放感がいまいちだ。その点、大黒PAはどこからでも利用しやすく、広々とした平面駐車場で、コンビニやレストラン、軽食コーナーも利用しやすい位置に配置されているのもイイ感じだ。
◇1989年~1999年
今思えばオープンして2年位は週末の大混雑が続いていた。時はまさにバブル真っ盛りな頃。週末の夜はBMWやメルセデス、フェラーリなどのバブリーなデートカーが続々と大黒に集まっていた。開通して2~3年はベイブリッジの路肩に停車して写真を撮る車も多かったのだ(危険極まりない!)。当時は「24時間闘えますか」の時代で、週休二日制が徹底しておらず、混雑は土曜日に集中していた。東京方面からベイブリッジを渡って大黒パーキングに入り、そこから再び首都高に乗って新山下あたりで降りて、山下公園に行く……というのがお決まりのドライブデートコースだったのだ。

クルマ好きがたくさん集まり始めたのは90年代終わりの頃である。大黒PAが便利な場所という認識が広まったことも理由だが、もっと大きな理由はインターネットの普及にある。パソコン通信利用者には懐かしいニフティサーブには様々なクルマコミュニティができて、いわゆる「オフ会」という催しが盛んに開催されるようになった。その場所として大黒PAはクルマ系オフの会場やツーリングの発着地点として人気となったのである。夜、大黒PAに集まる車が増えてきたのも90年代末頃からである。当時は警察の陣容もこぢんまりとしていたこともあり、無法地帯となり治安がかなり悪かった時期もあった。
◇2000~2010年
2000年に入ると週末の大黒PAには多くのクルマ好きが集まるようになった。いわゆる音響系の車やローライダーのクルマたちがどっと増えたのもこの時期。北関東在住の音響系の車に乗る若者が「大黒デビュー」を夢見てクルマを作る(=オーディオ類を組み込む)姿を取材したことも何度かある。あまりお行儀のよくない車も増え、無許可で屋台を出すものや爆音で駐車場内を走り回るクルマ、対立するグループ同士のけんかも週末の夜には頻繁にあった。
一般利用者からのクレームも増え、(音がうるさい、威圧感があって怖い、利用しにくいなど)2000年代半ばから週末の夜には大黒PAがたびたび閉鎖されるようになった。閉鎖されるということは、一般利用者も使えなくなるということ。不便極まりない。しかし、この措置のおかげで「音響系」やアブナイ系の車はぐっと減ったのも確かだ。それに代わって?増えてきたのがいわゆる「痛車」である。2000年代後半から大黒PAにも痛車の姿が増えて来た。
◇2010年~現在
2010年代に入ると大黒PAに集まるクルマの中心は痛車やスポコン車、ロータリー車(マツダRX7やRX8など)となった。音響系やローライダー、ハイドロなどの車が規制の関係でめっきり減ってしまったことにより、週末の大黒PAに集まる車はおとなしくなってきたように思う。

駐車場もすみわけができていて、痛車エリア、スポコン(ヴィッツ、シビック、インプレッサなどが中心)、ローライダー、メーカー別、車種別などで分かれており、グループ同士の対立やケンカなどもほとんどなくなり、治安のよい状態が保たれている。大黒PAも大幅にリニューアルして駐車スペースも増え、トイレやコンビニも新設され利用しやすくなった。

世界で「大黒PA」の名前が知られるようになったのも2010年前後からである。実は先日、クルマ好き高校生息子の車情報ネットワークで「大黒PAでトップギアが撮影している!」という情報を得た。日曜日の夜10時を過ぎていたが、行ってみることに。そしたら本当に撮影をしていた!しかもクルーの数がものすごく、最初はギャラリーが集まっているのかと思ったが近くに行くと全員外国人で、数にして100人近く?いたるところにクルーがいた。取材されている車は、GT-RやRX-7(FD)、シビック(EK)など。スポコン系、チューニング系が中心だったが、実はトップギアの取材はこの日だけではなく、10日以上日本に滞在し、日本各地の「クルマ好きの聖地」で撮影を行っていたようである。

日本のサブカル系クルマ文化の最前線に触れたい人は、迷わず大黒PAに行くべし!
【著者プロフィール】
自動車生活ジャーナリスト 加藤久美子
山口県生まれ 学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。一般誌、女性誌、ウェブ媒体、育児雑誌などへの寄稿のほか、テレビやラジオの情報番組などにも出演多数。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。愛車は新車から19年&24万キロ超乗っているアルファスパイダー。