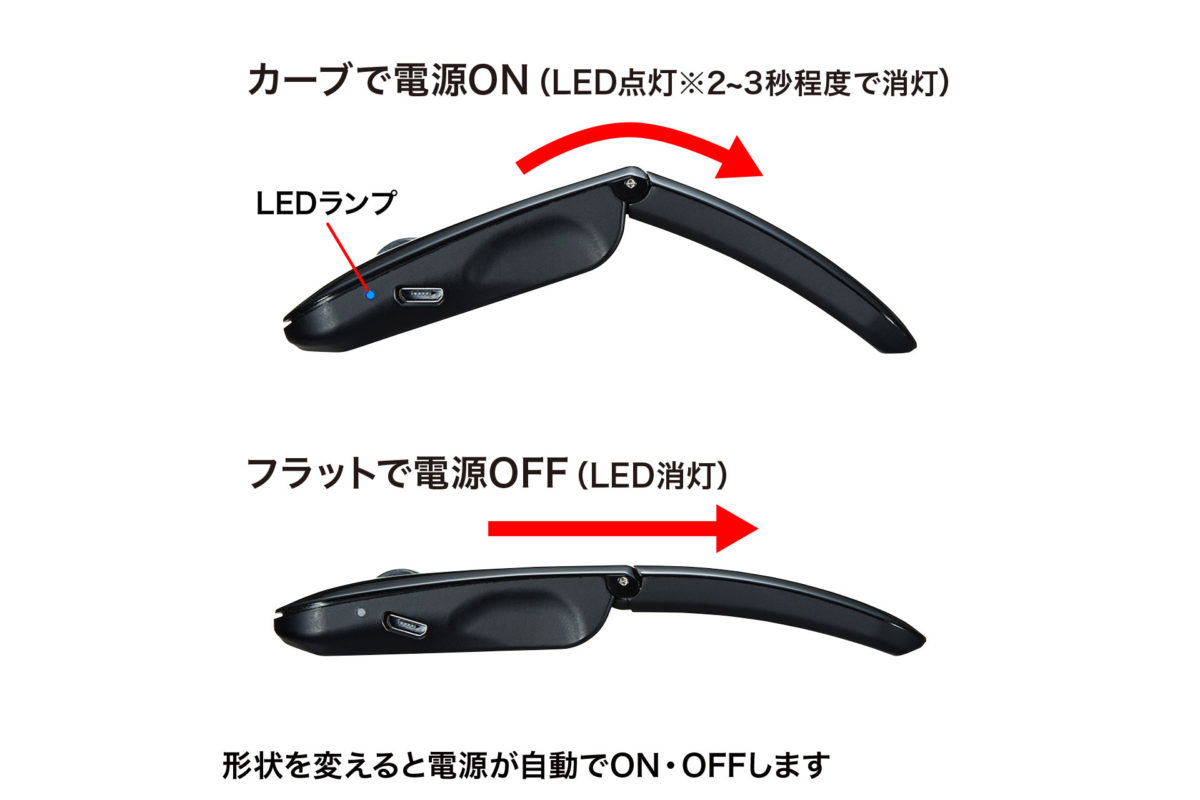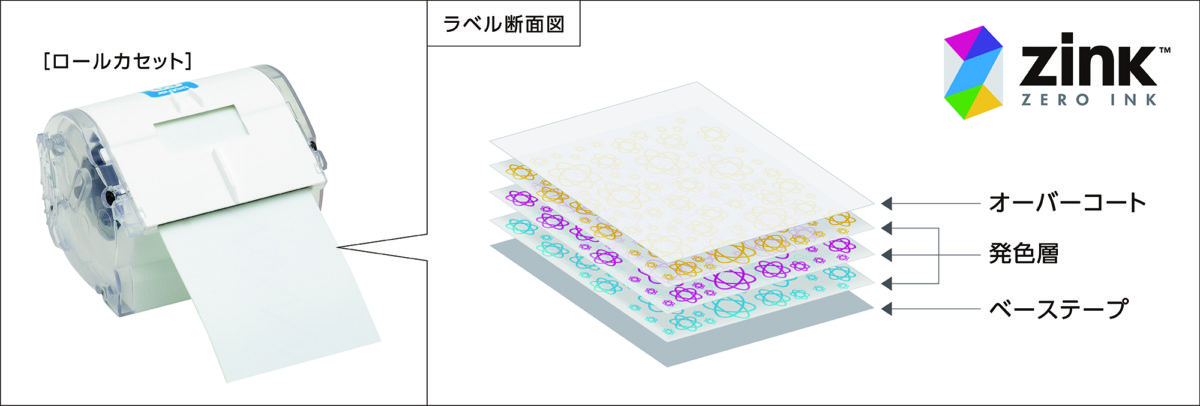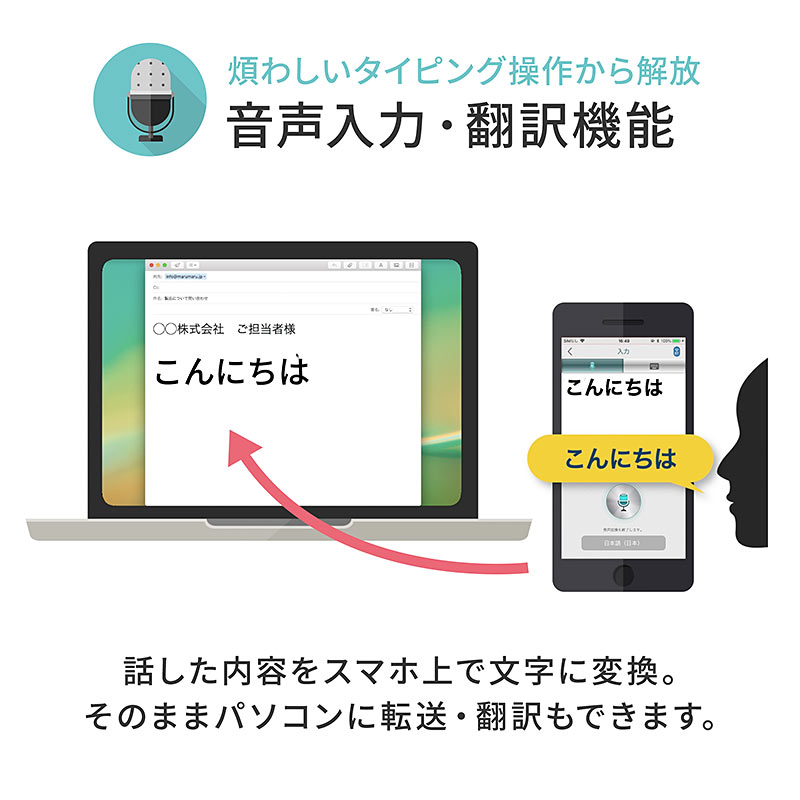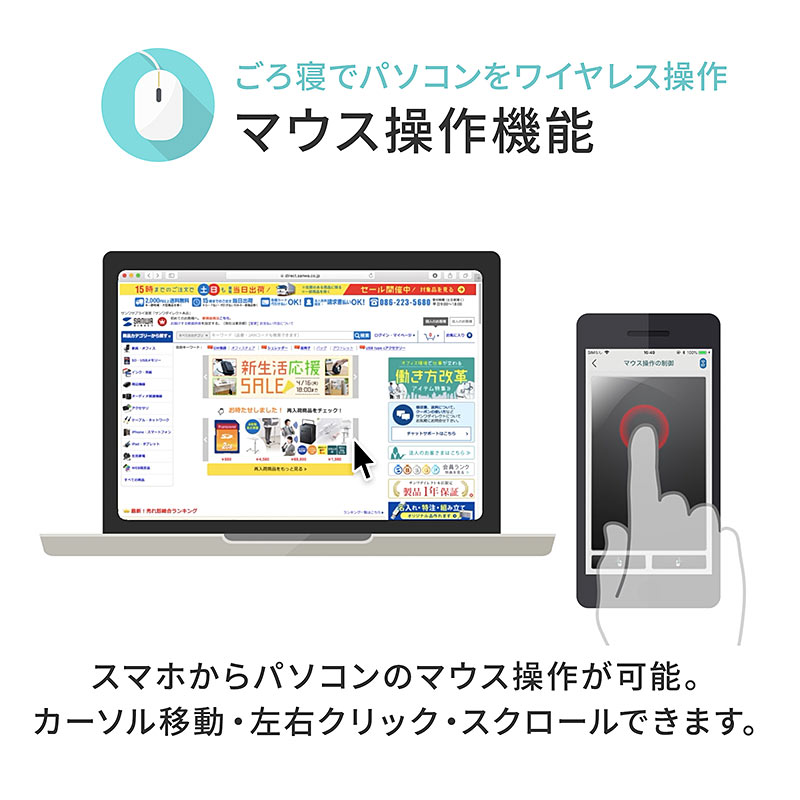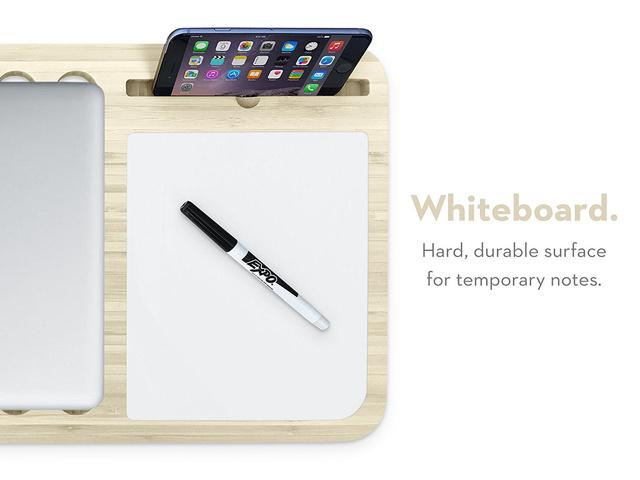海外だけでなく国内でも盛り上がりを見せ始めているe-Sports市場。前回紹介したゲーミングPCに引き続き、今回はゲーミングモニターをライターの岡安 学さんにセレクトして頂きました。

ゲーミングモニターは“速度”が命
「ゲーミングPCよりもある意味重要なのが、ゲーミングモニターです。応答速度が重要なゲームにとって、遅延が大きかったりリフレッシュレートが低かったりするモニターはストレスに直結します」と語る岡安さん。
「ゲーミングモニターを選ぶ上で重要なポイントは、1.応答速度、2.リフレッシュレート、3.画面サイズの3点です。応答速度はPCから出力したゲーム映像が画面に表示されるまでの速度。これが短いほど、時間のロスが少なく速く反応できるわけです。リフレッシュレートは1秒間に何回画面を書き換えられるかの数値。この数値が高いと残像感がなく、解像感が高く感じられます。またサイズですが、通常モニターはテレビを含め、大型サイズが推奨されますが、あまり大きすぎると、画面の情報を一気に見られなくなってしまい、視線が大きく動き、ゲームをするにはロスになることもあります。なので、近距離でも視野に入れやすい24インチくらいがオススメです。またテレビでは広視野角のIPSパネルが重用されていますが、応答速度が最優先のゲーミングモニターではTNパネルの方がベストです」(岡安さん)
初心者にオススメのゲーミングモニターはコレ
1.お手ごろ価格のエントリーモデル
ASUS
VG245H
実売価格2万2840円
VG245Hは24型フルHD液晶モニター。応答速度は1msでリフレッシュレートは75Hzと、フルHD60fpsのゲームであれば問題なく使えます。画面ちらつきを防ぐフリッカーフリー技術も搭載しており、画面が見やすく、疲れにくい仕様。手頃な価格ということもあり、初めてのゲーミングモニターとしては最適です。
2.高機能なハイスペック機
Acer
XF250Qbmidprx
実売価格4万2984円
XF250は24.5型フルHD液晶モニター。1msの応答速度と240Hzのリフレッシュレートで、動き速いのゲームにも対応したハイスペック機。その分、価格も高めですが、240Hzのリフレッシュレートのモデルのなかでは比較的お手ごろ。ディスプレイ回転機能のほか、専用メガネが必要となりますが3Dの表示もできます。2画面表示ができるPiP/PBPやブルーライトカット機能も搭載。
3.バランスの取れたスタンダードモデル
アイ・オー・データ機器
GigaCrysta EX-LDGC241HTB
実売価格3万55円
ゲーミングモニターの基本となる1msと144Hzのリフレッシュレートはしっかりと押さえた24型のフルHDモニター。HDMI端子が3つ用意されており、ゲーミングPC以外にもコンソールゲーム機やHDDレコーダーなどの同時接続をすることもできます。フリッカーレスやブルーライトを低減させるブルーリダクションも搭載。
4.ゲームに合わせた画面調整が可能
iiyama
GB2488HSU-B3
実売価格3万7560円
1ms、144Hzの24型フルHDゲーミングモニター。HDMI RGBレンジ調節や黒レベル調整で、暗い場所の色つぶれなどを軽減します。オリジナルのi-Style Color機能により、スポーツゲームやシューティングゲーム、シミュレーションゲームなどゲームの種類に合わせた画面調整を選択可能。ゲーム以外にも標準やテキストなどのモードも用意されています。モニターが90度回転するので、縦シューティングもフルサイズで楽しめます。
エントリー機からハイスペック機まで幅広いモデルを選んで頂きましたが、ぜひお手持ちのゲーミングPCと組み合わせてe-Sportsを楽しんで下さい!