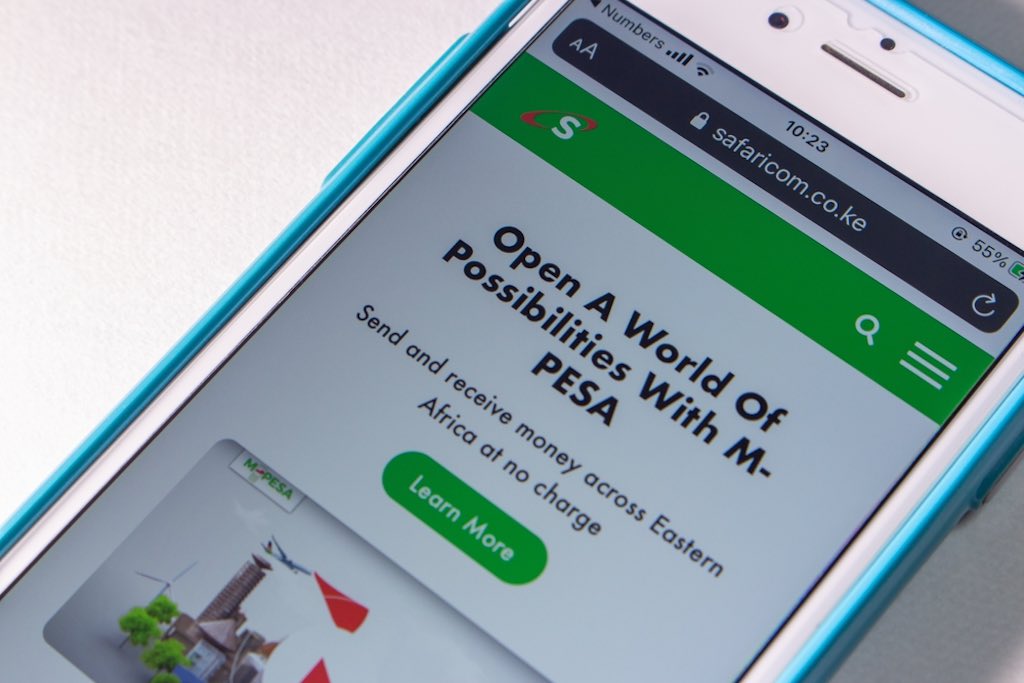インドで大きなシェアを占める小口決済インフラ「UPI(United Payments Interface)」が、Visa(ビザ)やMastercard(マスターカード)にも開放する準備が進められていると、現地紙のThe Morning Contextが伝えています。UPIの国際クレジットカードブランドへの開放は、同国の決済市場にどのようなインパクトを与えることになるのでしょうか。
インドで急成長する巨大決済ネットワーク
2016年4月にスタートしたUPIは、スマートフォンを利用し、24時間365日、リアルタイムで銀行口座間の送金を行う決済システム。利用者の決済手数料は少額であれば基本的に無料。手数料が発生した場合でも従来より少額で済むのが特徴、インドではショッピングモールから道端の屋台にまで、約2億3千万個のUPIのQRコードが設置され、さまざまな送金手段として利用されています。2022年12月には、約13兆ルピー(約1600億円)の決済を処理しました。うち個人間の送金が約10兆ルピー、残り約3兆ルピーが商店での買い物などQRコードを利用した決済となっています。
UPIの普及を後押ししているのが、インドにおけるフィンテックのパイオニアであるPaytmです。商店などは、月額2ドルでレンタルできるハードウェア「Soundbox」を使うことで、手軽にUPIでの決済が可能になりました。
UPIへの国際カードブランド参入を後押しする現地銀行
ただ、銀行預金から即時決済するシステムであるUPIは、少額であれば利用者の手数料が不要なため、預金口座からATMで現金を引き出しているのと変わりません。一方で銀行は口座保有者に預金額の金利を支払う必要があります。しかしこれらの一部をクレジット決済に移行できれば、加盟店舗から得られる決済手数料を銀行とUPI、カード発行会社と分け合うことができるのです。
The Morning Contextによれば、インド準備銀行(RBI)はVisaとMastercardに、UPIのオンライン決済プロトコルへのアクセスを認めることを計画しているそうです。これにより消費者は物理的なカードを利用することなく、クレジットの限度額まで買い物が楽しめるようになります。同国で発行されるクレジットカードはVisaとMastercardが9割を占めるなど、寡占状態が問題視されていることもあり、UPIの国際クレジットカードブランドへの開放は、現地のカード会社など既存業者からの反発も予想されていますが、上記の理由で現地銀行がこれを後押ししていると報じられています。
巨大な決済市場を国際カードブランドへと開放しようとしているインド。同国の決済シーンは、今後大きな変革期を向かえることになりそうです。
読者の皆様、新興国での事業展開をお考えの皆様へ
『NEXT BUSINESS INSIGHTS』を運営するアイ・シー・ネット株式会社(学研グループ)は、150カ国以上で活動し開発途上国や新興国での支援に様々なアプローチで取り組んでいます。事業支援も、その取り組みの一環です。国際事業を検討されている皆様向けに各国のデータや、ビジネスにおける機会・要因、ニーズレポートなど豊富な資料もご用意しています。
なお、当メディアへのご意見・ご感想は、NEXT BUSINESS INSIGHTS編集部の問い合わせアドレス(nbi_info@icnet.co.jp)や公式ソーシャルメディア(Twitter・Instagram・Facebook)にて受け付けています。『NEXT BUSINESS INSIGHTS』の記事を読んで海外事情に興味を持った方は、是非ご連絡ください。