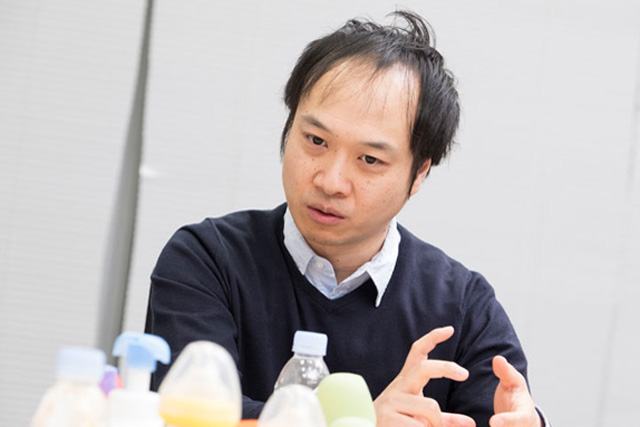赤ちゃんや小さな子どもが乗るベビーカー。ひと昔前まで日本では、歩行がおぼつかない子どもを乗せるための移動手段として主に使われていましたが、最近では4歳まで乗れるように設計されているものもあります。しかし、海外に目を向けると、デザインや大きさ、機能に至るまで、まったく発想が異なっている様子。今回は下記の4点をテーマにイギリス、アメリカ、チリ、中国、ドバイ(UAE)の5か国を取り上げて、各国のベビーカー事情を垣間見てみます。

1:どんなベビーカーが主流? タイヤはシングル、ダブルタイヤ?
2:ベビーカーを取り巻く周辺事情、道路や環境などにまつわる状況
3:国によって異なるベビーカー購入時のポイント
4:日本との共通点と相違点
[イギリス]

イギリスでは10キロ以上あるトラベルシステム(ベビーカー、チャイルドシート、ベビーキャリーを一台に集約した機能)が定番です。今年、特に人気があるのはイギリス製シルバークロスの「Wayfarer」 やiCandyの「Peach」。日本でもお馴染みのバガブーやストッケなどにも根強いファンがいます。
トラベルシステムは、大きめのシングルタイヤ4個のもの(前輪と後輪で大きさが違うタイプも多い)が主流。まずこれを1台目として購入、1歳前後からダブルタイヤ(計8個)の小さめなB型へと移行することが一般的です。

石畳が多いイギリスでは、がっちりしたタイヤがマスト。また電車やバスなどでも、ベビーカー優先や専用置き場があるうえ、イギリス人は赤ちゃん連れに寛容なので大きなベビーカーが主流です。購買層の中心である中流階級のイギリス人はおしゃれなママが多く、デザインやメーカー名を重視。日本との共通点として、人気ブランドのベビーカーを持つことは一種のステータスであること、相違点としては、日本のような利便性や軽量さはさほど求められない点が挙げられます。
[アメリカ]

アメリカにおけるベビーカーの特徴は、クルマ生活に合わせた仕様であること、そしてライフスタイルに合わせた選択肢が豊富であることの2点です。クルマ社会のアメリカでは、ベビーカーのシートがそのままチャイルドシートになる「3 in 1」タイプが多く、寝ている赤ちゃんを起こすことなく、クルマからベビーカーへの移動が容易になっています。
日本に比べ道も家も広く、ベビーカーがコンパクトである必要はありません。そのため、タイヤが大きく操作性の良い重量型が主流。荷物入れのスペースも大きく、ドリンクホルダーも4つあるなど高い機能性を備えています。

さらに、運動好きのママがジョギングをしながらベビーカーを押す「ストローラーラン」も一般的で、「Baby Jogger」社などの3輪タイプが人気(写真上)。そのほか、ベビーカーを好きになるために、クルマの形にデザインされた幼児向けの「Step2」社も人気を集めており(写真下)、公園や図書館では必ず見かけるほど。旅行用に、簡易な傘くらいに折りたためる20ドル程度のベビーカーを2台目として持つ人もいます。

購入するときに重視するポイントは、ベビーカーのシートをクルマへ移動する際の設置しやすさや折りたたみやすさなど、クルマにまつわる機能性です。クルマのトランクサイズに合わせてベビーカーを購入するのはもちろん、ベビーカーが入れやすいクルマを買う人までいるほど。
しかし、アメリカのベビーカーを日本で使うとなると、駅の改札を通れない、電車内で身動きが取れない、階段での持ち運びに重いなどかなり不便です。
[チリ]

南米チリではダブルタイヤのシンプルなB型ベビーカー(生後7か月ころから使えるタイプ)が一般的。そのほかにもシングルタイヤ、対面式のベビーカーなどにも人気がありますが、日本でよく見かけるベビーカーが主流です。
チリの首都サンティアゴではきちんと舗装されていますが、郊外や地方になると舗装されていないところもあり、ベビーカーで出かけるには辛い場所もあったりします。

チリ人がベビーカーを購入する際に最も重視するのは、「価格が手ごろであるか?」という点です。というのも、チリ人の最低月給は約4万円ほどだから。そのため、一般的には5000~1万円程度のべビーカーを購入する人が多いようです。
チリのベビーカーは日本のものとまったく一緒で、他国のブランドにあるようなバギータイプなどはあまり見かけません。日本との相違点をあえて言うなら、使用環境の違いと言えるかもしれません。ベビーカーに関しては寛容で、バスなどで周囲が上げ下ろしを手伝うのはごく当たり前の風景となっています。
[中国]

中国の街中でよく見かけるのは日本でいうA型(生後1か月から使用可)で、赤ちゃんとの距離が近くなれるハイシートタイプも人気を集め、タイヤの形態もシングルとダブルのどちらも見かけます。また、石畳の歩道が多いので振動を受けやすくなっています。そのため、タイヤが大きめなもの、重量がそこそこあるものは抗振動性が高いと認識されています。

購入ポイントとしては、まず赤ちゃんが安全で快適に乗れるかどうか。次に操作性へ重点が置かれます。中国にも安全基準はありますが、EU基準での欧州系ベビーカーはより評価が高く、好まれる理由の1つです。中国では共働き世帯が多く、祖父母やお手伝いさんにお世話をお願いすることになるので、その人たちが操作しやすいこともポイント。タイプの異なるものを2台購入し、状況に応じて使い分ける人も少なくありません。

日本との共通点は、中国で販売されているベビーカーは日本とラインナップが同じということ。ただし、中国では、日本人が重視する押しさすさや畳みやすさはそれほど重要視されていません。
[ドバイ]

ドバイは人口の8割以上が外国人。特に西洋人がストローラーを使うため、アメリカやヨーロッパのブランド(Uppa babyやStokkeやCiccoやBagabooなど)が主流で、シングルタイヤのものは多くのベビー用品店でも大きく展示されています。ローカルのアラブ人向けには、ゴールドカラーや高級車とコラボした約50万円もするストローラーも販売されている一方(写真下)、インド人やパキスタン人が多く住む「オールドドバイ」とよばれる地域では、ダブルタイヤや小型で軽量のベビーカーを見ることもあります。

1年間の最低気温が20度、夏は50度まで上がるドバイでは、外でベビーカーを押す姿はあまり見かけません。ベビーカーはショッピングモールやレストラン、カフェで見かけることが多く、特にモールやメトロも広いスペースなので、大型ベビーカーを押す人が多いです。たまに駅の改札を通れる日本製ベビーカーを見かけることもありますが、とても小さく見えます。クルマ社会なので、アメリカのように直接取り付け可能なシートも人気。

身長が高い西洋人はなるべく赤ちゃんと距離が近くなるようハイシートを重視。「Uppa bab」や「Stokke」などの使用率が高いのが特徴です。その一方、現地のアラブ人は一夫多妻制なので、子どもを4~5人連れた大家族もよく見かけ、双子用やステップのついたもの、荷物がたくさん入るものなど、利便性を重視する傾向です。ドバイは物価が高いので、ストローラーやベビー用品などは年に数回ある大きなセールでまとめ買いをします。

日本との共通点は、ポケットの多さやカップホルダーなどオプションの豊富さと利便性です。ドバイでは欧米系ブランドが多いので、サイズと身長の高さが圧倒的に違います。大きくて安定感はあるものの、折りたたんでもかなり幅をとるうえ、重さも10kg以上あるため、小柄な女性には取り扱いが困難。ただし、ドバイの人たちは妊婦や子どもに優しく、男性トイレにもベビールームが完備されるほど徹底されているので、著者は大きくても困ったことはありません。
では、日本は?

日本でも、最近では芸能人などのセレブたちがおしゃれな海外製を使うシーンがSNSなどで拡散されており、海外ブランドの人気が上昇中。それと同時に、ベビー用品店のオリジナルブランドも増加の一途をたどっています。
また、海外でも見られるように、安全性とともに、カーキャリア、ベビーキャリアなどに使える「~Way」式のベビーカーや、海外デザインを追従したスタイリッシュなものやカラーバリエーションも増えている傾向にあります。
狭い国土や道路、駅の改札、階段の上り下り、体型などの背景から、使用時や折りたたみ時のコンパクトさ、小回りのよさに重点が置かれているところは日本独特と言ってもよいでしょう。そして、女性一人が操作することを念頭にいれた軽量さや高い機能性を兼ね備えた設計もこの国の特徴。やはり大きさに関しては日本と海外、特に欧米系との決定的な相違点と言えますが、日本ならではの利便性や安全性などの細かい配慮も文化的な相違点かもしれません。
海外では振動抑制にはタイヤの大きさでカバーすることが多いですが、日本では小回りの良さをキープするため、タイヤ以外の機能、サスペンションやエアクッションなどで振動を抑える傾向も特徴的かもしれません。タイヤについてもダブルタイヤが多いですが、近年ではピジョンのRunfee(ランフィ)の登場でシングルタイヤのベビーカーも多く出回るようになりました。

海外と比較すると、残念ながら日本はベビーカーに対して寛容とは言いがたく、コンパクトなベビーカーでも電車やバスのなかでは広げたままかたたむべきかの論争が常々されている状況。背景には、日本は国土が狭いうえ、赤ちゃんが泣いたりぐずったりした際、親がすぐに抱っこして、あやすという行動や「他人に迷惑をかけない」という価値観があります。しかし、混雑時の公共の交通機関では子連れ側が自重するだけでなく、周囲の乗客も、ベビーカーを押している親に手を差し伸べるというチリやドバイの人たちの良いところを見習いたいですね。