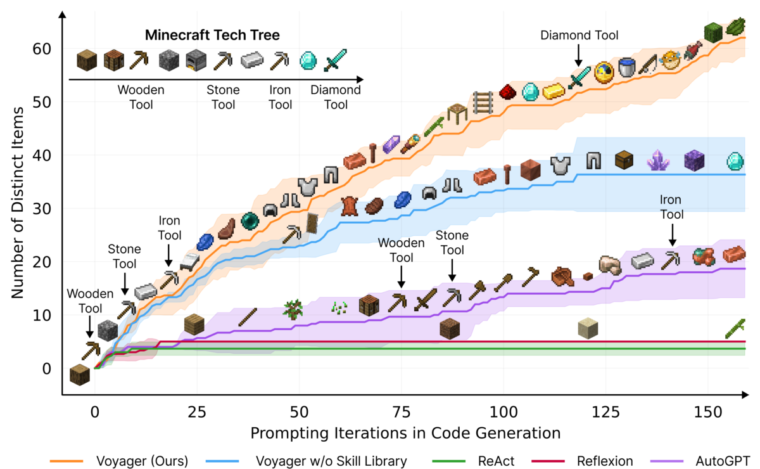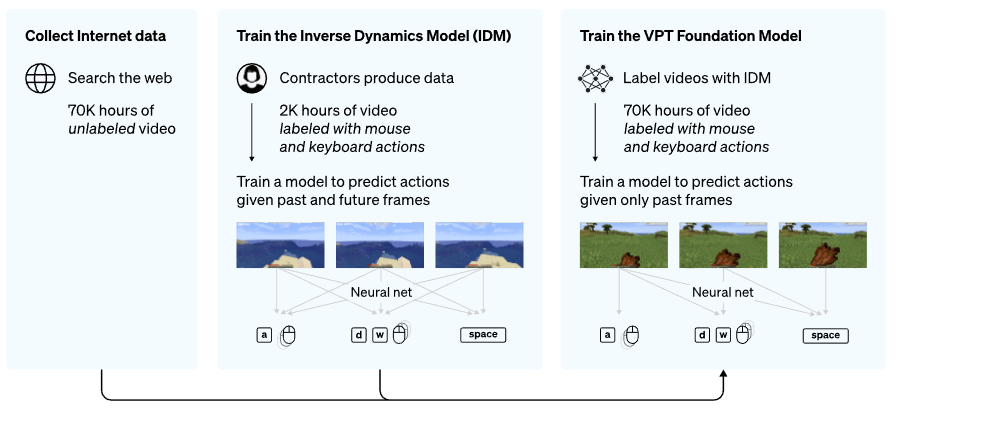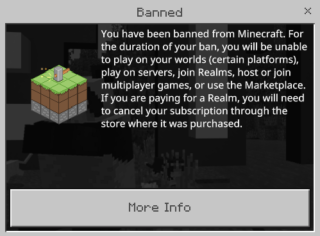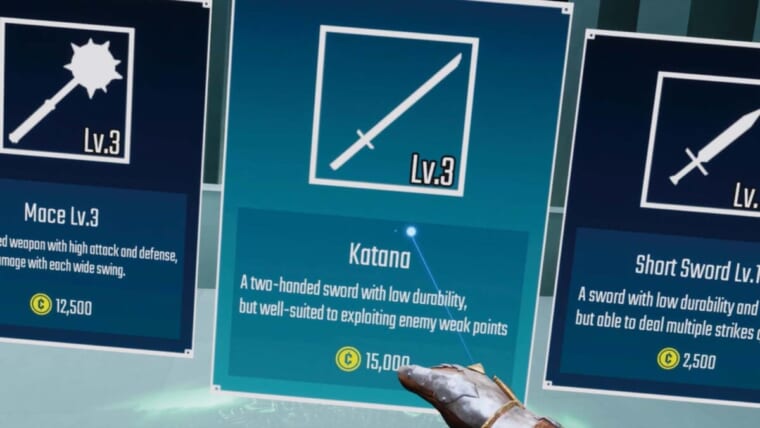2020年プログラミング教育必修化まであと2年。始めるなら今年から! ということで、手軽かつ子どもが楽しみながら学べる。Gakken Tech Program の小・中学生向けのプログラミング1DAYキャンプ(短期集中講座)を紹介します。
◆プログラミングが、子どもに習わせたい習い事ランキング上位に!
2020年の必修化に向けて、プログラミング教育に注目が集まっています。「子どもに習わせたい習い事」を調べた各所のランキングではのきなみ上位にランクイン。プログラミング教育の必修化がはじまる2020年まであと2年となり、ますます注目を集めていることがうかがえます。
一方で、「プログラミングをやらせてみたい」と思っても、何から教えればよいのかわからないという親御さんもいらっしゃるのではないでしょうか? Gakken Tech Programの1DAYキャンプは、プログラミングの基礎からプレゼンテーションまで、1日で体験できる充実のカリキュラムです。
◆1DAYキャンプのカリキュラムを写真で解説!
最初に、1日かけて学習する内容を詳しく説明し、子どもたちに目的意識を持ってもらいます。緑色のポロシャツのお兄さん・お姉さんはプログラミングを教えてくれる講師。
授業で使用するテキストには、たくさんの参考書を作ってきた学研の編集ノウハウが詰まっています。ただキーボードを打つだけでなく、書き込み式のテキストを使用することで、物事を筋道立てて考える論理的思考力や問題解決力が身につくようになっています。
いくつかある学習コースで、特に人気なのが「プログラミング基礎 マインクラフトコース」。プログラミングと聞くと難しそうなイメージがありますが、子どもたちに大人気のマインクラフトを使った学習からスタートすれば、楽しみながら親しめます。好評につき、マインクラフトコースの「VOL.02」も新設しました。
パソコンやプログラミングの経験がなくても大丈夫。2~4人の子どもに対して1人以上の講師がつく少人数制で実施します。万全のサポートで子どもたちの成長をフォロー。
昼食は、同じグループの子どもたちと講師と一緒にとります。保護者の方がいなくても大丈夫。お子様を1日安心して預けていただくことができます。
最後は1日の学習の成果を発表するプレゼンテーションタイム。プログラミングでつくった作品について子どもたち自身が、工夫したところ、どこが大変だったかなどを発表します。
実際の1DAYキャンプの様子はこちらの動画でチェック!
VIDEO
こんな作品を子どもたちが作り上げます!
これまでの1DAYキャンプで、子どもたちが作った作品の一部をご紹介します。
「プログラミング入門 スクラッチでゲームを作ろう」コースで完成したゲーム。使用テキストに掲載されている「ブロックくずし」ゲームをもとに作りました。ドラゴンが星に当たると音を出して消えます。ドラゴンは子どもがスクラッチ上で描いたものです。
「プログラミング基礎 マインクラフトコースVOL.01」では、マインクラフトの敵キャラ「クリーパー」の顔をプログラミングで作ることが目標です。
「プログラミング基礎 マインクラフトコースVOL.02」では、プログラミングで家を作ります。家具の配置や壁の色など、子どもたちがこだわって作った家が完成します。
「プログラミング実践 ホームページとWebアプリを作ろう」では、タイピングゲームを作ります。難易度は高めですが、オリジナルのゲームが完成したときの喜びはプログラミングへの自信となります。
これまでの1DAYキャンプに参加くださった保護者のアンケートでは、ほとんどの方が「とても満足」や「満足」と回答。学校やご家庭では身につけられないプログラミングスキルを学習できる貴重な機会とご評価いただいています。
★参加者へのインタビューはこちらの動画でチェック!
VIDEO
《好きやレベルで選べる4つの学習コース》
◇プログラミング入門1DAY スクラッチでゲームを作ろう
◇プログラミング基礎1DAY マインクラフトコースVOL.01
◇プログラミング基礎1DAY マインクラフトコースVOL.02
◇プログラミング実践1DAY ホームページとWebアプリを作ろう
《お申し込み》http://gakken-tech.jp/camp/?utm_source=prtimes171226-01
《プログラミング1DAYキャンプ開催概要》