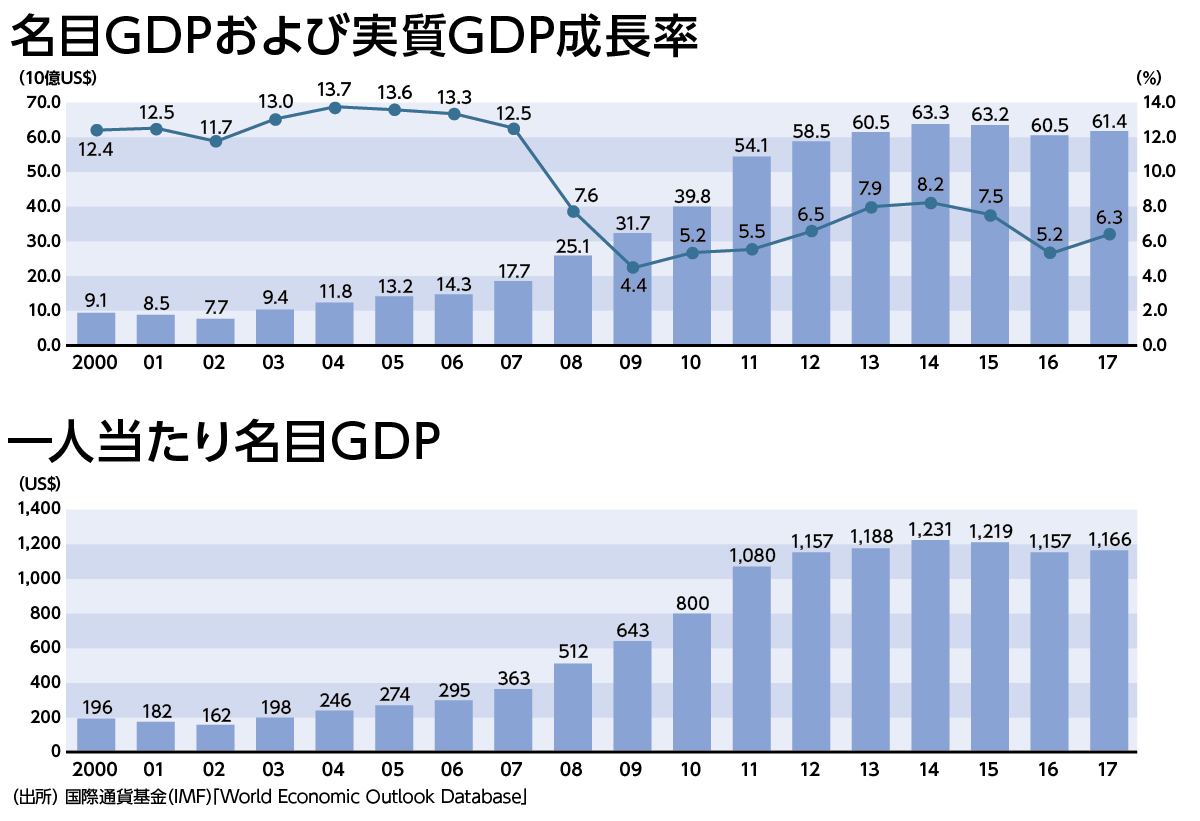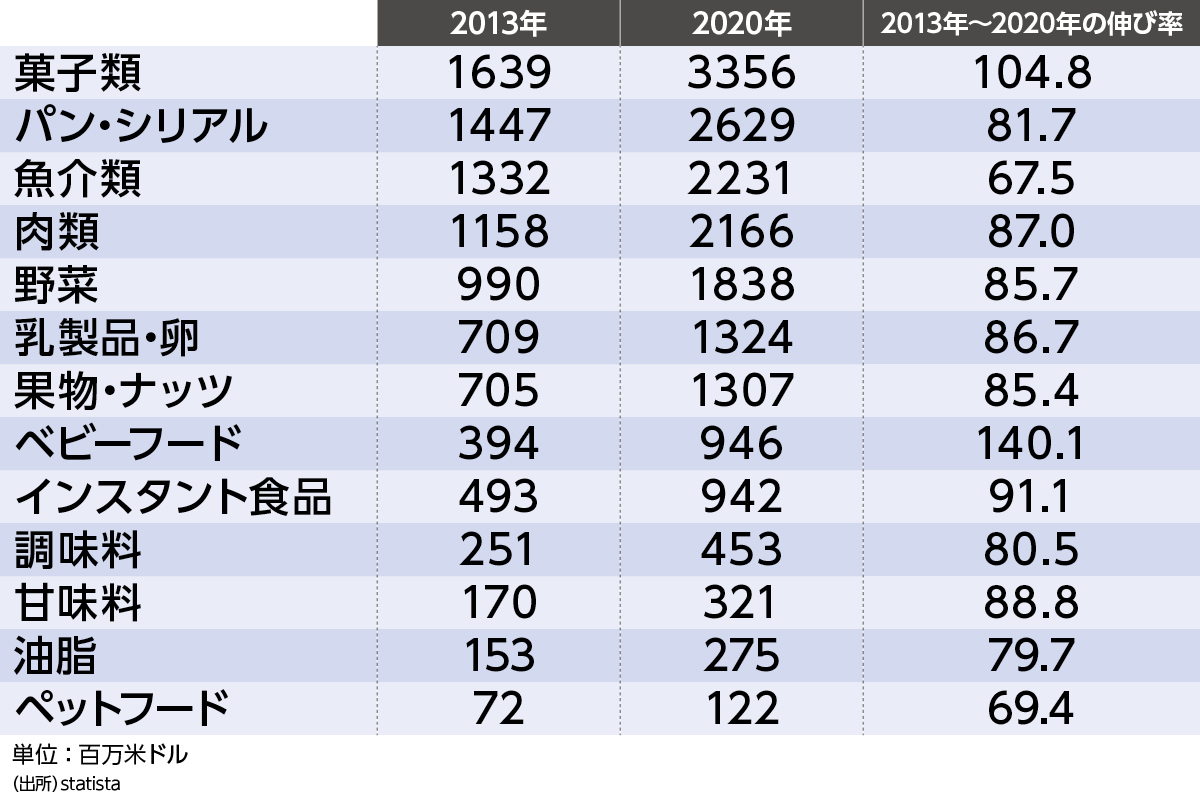2021年2月のクーデターによる軍事政権の復活、大規模民主化運動、民族・宗教紛争と政治的な混乱が続くミャンマー。日本の岸田文雄首相は東アジアサミットに出席した際、同国の情勢について深刻な憂慮を表明しましたが、ミャンマーの経済はどうなっているのでしょうか? 2022年10月中旬に同国を視察し、異様な景色を目の当たりにした、ミャンマーに詳しいシニアコンサルタントの小山敦史氏(株式会社アイ・シー・ネット)がレポートします。
著者紹介

ミャンマーの首都・ヤンゴンの市民生活は、驚くほど静かに営まれていました。実際、街頭での市民の抗議行動や軍の鎮圧活動といったような「騒乱」めいた動きには1週間(10月10日〜16日)の滞在中、一つも遭遇しなかったほど。日中行き交うクルマの数はかつてより減り、夕暮れ時のダウンタウンの街の灯も寂しくなっていましたが、ASEAN(東南アジア諸国連合)でも有数の景色を誇るヤンゴンの緑は、よく手入れされており、美しさを保っています。バス乗り場には、雨季(4月〜10月)の終わりのにわか雨をよけようとするバス待ちの人々が、停留所の小さな屋根の下で身を寄せ合って佇む一方、外資駐在員御用達の高級スーパーの品揃えも意外なほど豊富です。
しかし、街のところどころに、ただならぬ事態が起きていました。建設途中の高層ビルが、完全に作業が止まったまま、足場やクレーンもそのままに、いくつも放置されているのです。「輸入建設資材が入ってこなくなって、にっちもさっちもいかないらしいですよ」と現地の人が解説してくれました。これで何人の建設労働者が職を失ったことでしょう。
平穏に見えるヤンゴンの人々ですが、実は台所は火の車。軍事政権の信用失墜にドル高が加わり、ミャンマーの通貨チャットは下落。同国政府は1ドル2100チャット(約138円※)を公定レートとしましたが、市中価格は1ドル2800 チャット(約184円)以上でした。また、ヤンゴン市民によると、米や野菜などの生活物資の価格は、騒乱による作付不能や不作が重なったこともあり、以前に比べて2 倍以上になっているとのこと。
1チャット=約0.066円で換算(2022年11月15日現在)
外貨は流出傾向にあります。JETRO ヤンゴン事務所の専門家は、観光収入と出稼ぎ収入が落ち込み、外国直接投資(FDI)や援助も厳しい状況が続いているため、ミャンマーの外貨準備高は相当減少しているはずと見ています。
同政府は外貨流出を防ぐために、輸入を露骨に規制し始めました。例えば、原材料を輸入に依存している外資系食品メーカーA社は、これまで経験したことのない「難癖」を当局からつけられ、原材料の輸入が認められなかったと言います。前述の建設途中の高層ビルにまつわる輸入建材の話も同じ文脈で理解できるでしょう。国の台所も火の車なのです。
一方、ミャンマー企業の多くはドル高のデメリットに苦しんでいるようでした。ミャンマーの場合、チャット安で輸入コストが上昇しますが、A社の場合、仮に原材料を輸入できたとしても、支払いはドル決済を迫られる一方、製品の売り上げは国内市場のみ。つまり、稼いだお金は100%チャットです。チャットはドルに転換すると目減りしますが、その分を売価にきっちり転嫁したら、国内での売り上げを大きく減らすことになります。「国産原料に置き換えられないか、真剣に検討を始めました」と同社の社長は話します。3年前にA 社を訪問したとき、国産原材料の可能性は話題にもなりませんでした。
このように、ミャンマー経済は苦境に立たされており、一般市民の生活への影響が心配されます。国民の軍事政権への信頼は低いようで、「反国軍の市民感覚はいまだに強いと思う」と、ある日本人駐在員は語っていました。軍の弾圧によって2000人以上の人々が犠牲になっているのだから、それは当然かもしれません。しかし、経済が悪化する中で時間が経てば経つほど、ますます生活が苦しくなるのは、武力も資力もない一般市民にほかなりません。
五里霧中の企業

民間企業に勝機はあるのでしょうか? A社とは逆に、食品メーカーのB社は全て国産の原材料を使い、作った製品の一部を欧州に輸出しています。訪問時、社長はパリの国際展示会に出張中で、部長が対応してくれましたが、業績はそこそこ伸びているとのこと。チャット安の効果(製品を海外に売りやすい)があると思われます。
ただし、ミャンマー全体で見た場合、B社のようなビジネスをできる企業は多くはないでしょう。少なくとも3つの問題が挙げられます。まず、一定以上の品質の原材料が適切な価格で国内供給できるか? 次に、それを欧米などの市場で売れる品質の製品に加工できる技術と資金があるか? さらに、国際市場にマーケティングしていけるだけのノウハウや資金があるか? このような問題を自力で解決できるミャンマーの地場企業はまだ限られており、だからこそ、政変前はFDI が一定の役割を果たしていました。しかし、「果たしていました」と過去形で書かざるを得なくなりつつある現状こそが、ミャンマーにとって最も苦しい所です。
政変前に訪問した数多くの現地企業では、20 代や30代の若い経営者に何人も出会いました。 彼らは自分たちの夢を早口の英語で語っていましたが、いまはこの難局をどう切り開こうとしているのだろうか——。ミャンマー経済は今まで以上に、日本を含めた外国からの支援が必要なのかもしれません。
読者の皆様、新興国での事業展開をお考えの皆様へ
『NEXT BUSINESS INSIGHTS』を運営するアイ・シー・ネット株式会社(学研グループ)は、150カ国以上で活動し開発途上国や新興国での支援に様々なアプローチで取り組んでいます。事業支援も、その取り組みの一環です。国際事業を検討されている皆様向けに各国のデータや、ビジネスにおける機会・要因、ニーズレポートなど豊富な資料もご用意しています。
なお、当メディアへのご意見・ご感想は、NEXT BUSINESS INSIGHTS編集部の問い合わせアドレス(nbi_info@icnet.co.jp)や公式ソーシャルメディア(Twitter・Instagram・Facebook)にて受け付けています。『NEXT BUSINESS INSIGHTS』の記事を読んで海外事情に興味を持った方は、是非ご連絡ください。