ラーメン店でお酒を楽しむ、通称「ラ飲み」。本稿は、お酒をより深く楽しむための情報サイト「酒噺」 (さかばなし)とコラボし、この「ラ飲み」にスポットを当てた企画である。案内人は、GetNavi本誌でラーメン連載を持つミュージシャン、サニーデイ・サービスの田中 貴さん。本稿では「ラ飲み」でオススメの店を行脚しつつ、「ラ飲み」の楽しみ方や珠玉のラーメンを紹介していただく。今回は、全6回となる連載の第4弾をお届け。
コチラ
【プロフィール】
田中 貴(たなか・たかし)
サニーデイ・サービスのベーシスト。日本全国を食べ歩くラーメン好きとしても知られ、TVや雑誌などでそのマニアぶりを発揮することも多い。2019年にはグルメ誌「食楽」で表紙を飾った。
バンドは3月13日に通算13作目となるニューアルバム「いいね!」をリリース。エレキギター・ベース・ドラムという最小限のバンドアンサンブルに立ち帰り、自身たちのルーツたる音楽性を詰め込んだ傑作が誕生した。ライブはドライブイン形式のイベントとして「山中湖交流プラザ きらら」で開催される、「DRIVE IN LIVE “PARKED”」の初日、9月26日に出演が決定。また、カーネーション、岸田繁(くるり)とのライブ音源集「お~い えんけん!ちゃんとやってるよ!2020セッション」が10月21日にCDとLP盤でリリースされる。
街中華は何人かで飲みに行くときの有力な選択肢のひとつ
今回訪問したのは、新宿駅の東南口からすぐの場所にある「石の家」(いしのいえ)。昨今注目が集まっている街中華(町中華)カテゴリーのお店だ。田中さんはラーメン専門店だけではなく街中華にも詳しい。そんな田中さんが、数ある名店のなかから「石の家」を選んだ理由は、名物メニューがあり、多くの人が足を運べる立地だからだという。また、「麺や 七彩」の阪田博昭さんをはじめ、田中さんと仲のいい有名ラーメン店主のなかにも「石の家」のファンは多いのだとか。
↑「石の家」の入口。裏路地に入ってすぐの、地下のネオンが目印だ
入店して料理を待つ間、田中さんにとって、街中華とはどんな存在なのか、街中華でラ飲みを楽しむ魅力などについて教えてもらった。
「街の中華屋さんと聞いて一般的にイメージされるのは、日本風にアレンジされた中華料理を出すお店ですよね。オムライスやカレーなどの洋食からカツ丼などの食堂メニューまで出す、住宅地の駅近くに必ずあるタイプの店。それらとは違うタイプで、中国の方が厨房にいらっしゃる、本場の味を出すお店というのもあります。格式高い本格的な中国料理店とは違い、庶民的なスタイルで古くから続く店が、都心にはまだいくつか残っています。どちらのタイプの店にもいえるのは、安くてボリュームがあるということ。数人で、何品も頼んでワイワイやるのが楽しいですね。もちろん、麺料理も豊富にあるので、一軒でシメのラーメンまでいけちゃいます」(田中さん)
「いい街中華」は「おっちゃん世代が集まる店」であることが多い
ただ、最近人気が出てきたとはいえ、街中華は公開されている情報量がラーメン店に比べて多くはない。いい店は、どうやって探せばいいのだろうか。
「まず、長く続いている店は間違いないですよ。新宿とか渋谷とか、若者が多くてお店の移り変わりも激しいなかにも、オッチャンがたむろしている古くからの店はあるものです。そういう店は、まあ安くてウマい店ですね。オッチャンたち全てが食にこだわっている人ばかりではないですが、人生経験を積んだ先輩たちが選ぶ店には、何かしら意味があります。あとは、オリジナリティ溢れる名物料理があること。『いい店』と『名店』の違いは、これがあるかないかに尽きます」(田中さん)
↑近所の年配のご夫婦が営む深夜営業の中華の「いい店」が突然閉店し、途方に暮れていると語る田中さん
田中さんがお話しした条件の通り、「石の家」もこの界隈屈指の老舗であり、近くの「ウインズ新宿」に通うベテラン勝負師たちが足しげく訪れるお店。ファンであることを公言している著名人も多いのだという。
「酔貝」をはじめ、酒が進む「間違いのない前菜」が登場 やがて、一品目の「酔貝(すいがい)」が到着。街中華としてはやや珍しい本格派で、しかも台湾料理である。カンタンに言えばシジミのニンニク醤油老酒漬けで、絶妙な火加減でレアな食感に仕上げたシジミを、自家製のタレで約2時間漬け込んだ人気の前菜だ。
「ニンニクと紹興酒が効いた味付け。ガツンときますね! シジミの身が大きめなのは珍しい。肝臓にもいいような気がして酒が進みます(笑)」(田中さん)
↑「酔貝 ハーフ」400円(通常サイズは750円) ※お酒の画像はイメージ。店舗でも取り扱いなし(以下同)
ちなみに、ふだん料理をオーダーする流れについて田中さんに聞いてみると、「『石の家』の場合、まず飲み物と一緒に、このシジミとか腸詰といった前菜を頼みますね。台湾系の料理があるのも、ここの魅力です。そのあとは、酒に合う炒め物や揚げ物や、流れにまかせて……といった感じですね」と教えてくれた。そうこうするうちに、「焼餃子」と「腸詰」が到着。
「焼餃子が庶民的な料理として一般に普及したのは戦後からですが、ここはそのころから珉珉などと並んで有名だったそうで、古川緑波(ふるかわ・ろっぱ)の随筆にも『石の家』の名が出てきます。ロッパも食べた餃子を、建物は変われど同じ場所で食べていると思うとロマンを感じますね。僕が上京したころは、この新宿駅の南側も闇市の名残ある街並みでしたが、ずいぶん変わりました。さかさクラゲと呼ばれた連れ込み旅館や、生コン工場なんてのも数年前まであって、ゴチャゴチャした感じが魅力的だったんですが……」(田中さん)
↑手前は、「酔貝」と並ぶ人気の台湾料理「腸詰」700円。「焼餃子(6個)」400円は、キャベツ、白菜、ニラを豚ひき肉と合わせ、にんにくとしょうがを効かせた間違いのないおいしさ
「石の家」の名は、創業者が採石建材店と懇意にしていたことに由来
ここで、店の由来について二代目オーナーの金井由美子さんに話を聞いてみた。創業は昭和29(1954)年。当初は現在のように地下ではなく、2階に座敷を備えた建物だったそう。店名は、創業者が近隣の採石建材店と懇意にしていたことに由来。その後昭和59(1984)年に改築され、現在は金井さんの娘さんが三代目として同店を営んでいる。
↑二代目オーナーの金井由美子さんと。新宿周辺の昔話に花が咲く
いまでこそ新宿駅の東南口は整備されて都会的な雰囲気に変わったが、昭和のころは「新宿西口思い出横丁」のような、ディープな雰囲気だったとか。駅前に並ぶ屋台のなかには台湾料理店があり、その店主が「石の家」の常連だったことからレシピを教わり、同店でも台湾料理を提供するようになったという。
おかずにもつまみにもなる炒め物&揚げ物が到着
続いて、ご飯のおかずにもつまみにもなる炒め物と揚げ物をオーダー。街中華の定番である「木須肉(ムースーロー=キクラゲ、卵、豚肉炒め)」は、濃い味付けに仕上げた同店伝統の一皿だ。一方、「イカとセロリ炒め」は、セロリの上品な香りとコリっとした食感が絶妙。豚肉とピーマンの天ぷらを盛り合わせた「肉の天ぷら」は、山椒や八角をほんのり効かせてスパイシーに仕上げているのが特徴だ。
↑「木須肉(ムースーロー)」850円(手前)、「イカとセロリ炒め」900円(左奥)、「肉の天ぷら」850円(右奥)
「このムースーローは、ジャズピアニスト・山下洋輔さんのエッセイにちょいちょい出てくるもんだから、上京前から憧れの一品でした(笑)。イカとセロリの炒め物も、こういう中華屋さんの定番ですね。酒にもよく合います。肉天って関西ではポピュラーで、僕も子どものころから好物なんです。東京ではほとんど見かけないので、ここに来たら必ず注文しますね」(田中さん)
名物の「やきそば」は、焼きうどんのような太麺が醍醐味
そして、いよいよ麺料理へ。オーナーの金井さんによると、創業時のメニューは餃子と焼きそばとタンメンの3つだけだったそう。これらは、メニューが増えたいまでも同店を代表する人気料理だ。そのなかから、まずは開店当初50円だったという「やきそば」から頼んでみよう。
↑創業当時の味を伝える「やきそば(太麺・しょうゆ味)」550円。細麺ではなく太麺で、ソース味ではなくしょうゆ味だ。しょうゆ、塩、うまみ調味料などで味付け、ゴマ油が効いているのがポイント
「この焼きそばが『石の家』の名物なんです。うどんのような太麺が、ブヨンブヨンの食感でたまらない。量も多いので、数人でつまむのにもってこい。この焼きそばは、ファストフード店が普及する前には、安くてウマくて腹一杯になると学生に大人気だったそう。何年か前に、『石の家』で数十年働いてた方とこの近くの飲み屋で出会いまして、当時の話をいろいろうかがいました(笑)」(田中さん)
焼きそばの麺の量は、200gとボリューム満点。麺類は昔からずっと同じ製麺所に特注しているという。ちなみに、餃子はかつて皮が自家製だったが、いまはこの製麺所に作ってもらっているとのこと。
↑紹興酒も一緒に飲み始めた田中さん。焼きそばや炒め物をつまみにお酒が進みます
タンメンは野菜の旨みがしっかり効いていて深みのある味
そして最後はタンメンを注文。同店には通常のタンメンと、昔ながらの太麺タイプの2種があり、今回はやはり後者をチョイス。味の軸となるのは、鶏と豚のガラを中心に前日から約8時間炊いたスープで、タンメンの場合はこれに野菜などの甘味が加わる。
↑「太麺タンメン」750円。スープが白濁していないあっさり系だが、奥深いふくよかなうまみがあって飲み干したくなるウマさ
「中華屋さんでは、ベーシックなラーメンよりもタンメンなどを頼む
↑つるりとした太麺と野菜の旨みが溶け込んだスープの相性はバツグン!
前菜からシメまで、お酒の進む絶品料理が良心的な価格で楽しめる。おまけに立地は抜群で、昼夜通しで営業していて、定休日もないという使い勝手のよさ。多くの人に時代を超えて愛されるというのも納得だ。こうした素晴らしい店が時代に飲み込まれずに残っていること自体、もはや奇跡と言っていいだろう。新宿は数々の老舗や名酒場が存在する街だが、東南口の「石の家」も、必ず覚えておくべき名店といえる。
撮影/黒飛光樹(TK.c)
【SHOP DATA】
石の家
住所:東京都新宿区新宿3-35-4 ユーコービル中地下
アクセス:JRほか「新宿駅」東南口徒歩3分
営業時間:月~土11:30~23:50(L.O.23:00)、日祝11:30~22:50(L.O.22:00)
※営業時間は変更の可能性があります
定休日:なし
人に話したくなるお酒のお役立ち情報やうんちくを知りたい方は、酒噺 へ!
撮影/黒飛光樹(TK.c)
【フォトギャラリー(画像をタップすると閲覧できます)】



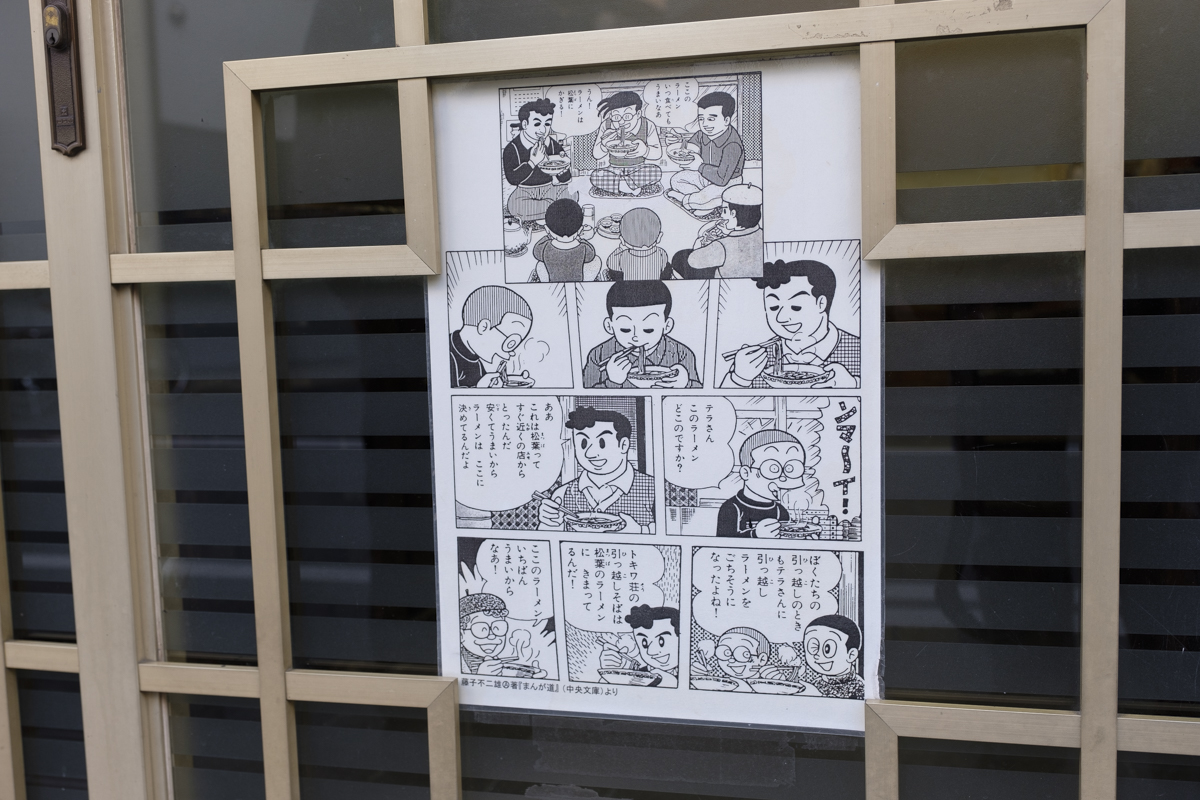














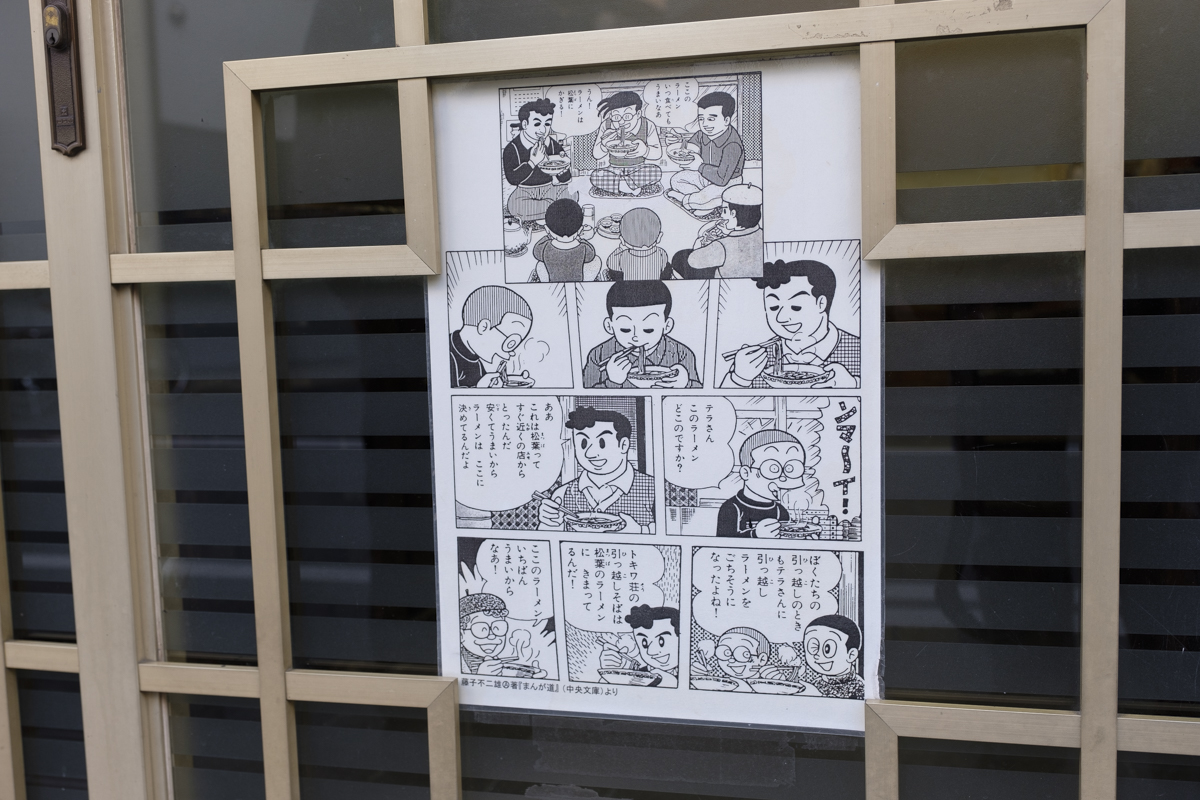











 「ラ飲みの名店」連載一覧は
「ラ飲みの名店」連載一覧は










