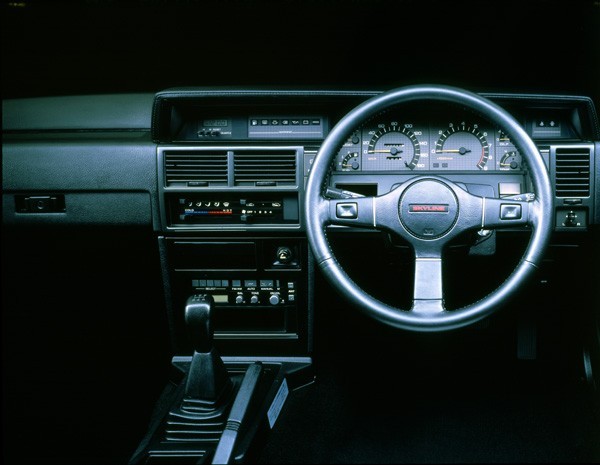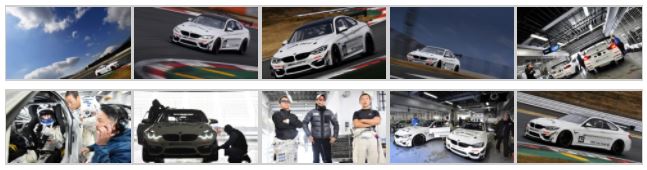3月17日(土曜日)にJR各社のダイヤ改正が行われる。この春は新路線の開通といった華々しい話題はないものの、各社の変更点を見ていくと、時代の変化を感じざるをえない。旅客各社のダイヤ改正で目立った変更ポイントをチェックした。
【JR北海道】国鉄型キハ183系が走る路線がわずかに
まずはJR北海道のダイヤ改正で目立つポイントから。
長年、函館駅と札幌駅を結んできた特急「北斗」が消え、すべての列車が特急「スーパー北斗」となる。車両がキハ183系から、すべてキハ281系とキハ261系に変更されるのだ。この車両変更によって、若干の所要時間の短縮(既存列車から0〜9分の短縮)と乗り心地の改善が図られる。
この改正以降、キハ183系は道南から撤退、定期運用される列車は、石北本線を走る特急「オホーツク」と特急「大雪」のみとなる。特急「北斗」にはキハ183系のなかでも唯一のハイデッカー仕様のグリーン車が連結されていたが、この車両も消えることになりそうだ。長年、北海道の特急運用を支えてきたキハ183系の撤退だけに、一抹の寂しさを覚える。


さらにこの3月には、スラントノーズの名で親しまれてきたキハ183系の初期型車両が消えていく。車体に動物のイラスト、車内に動物をテーマにした遊び場が設けられていたキハ183系「旭山動物園号」。3月25日にラストランを迎える。

【JR東日本】中央本線の特急と臨時列車に大きな変化が
JR東日本の管内で、より変化が大きいのが中央本線だ。
特急「スーパーあずさ」に使われるすべての車両が新型のE353系に変更される。これまで使われてきたE351系は、廃車となる予定。JR東日本の車両形式として「E」を初めて付けたE351系だが、登場して25年という期間での消滅となる。E351系はJR東日本で唯一の制御付き自然振子装置を備えた車両だった。整備の手間がかかるということで嫌われたのかもしれない。


昨年の暮れ、JR東日本がダイヤ改正を発表した際には明らかにされなかったが、長年、中央本線の臨時列車として使われてきた国鉄形特急電車189系の2編成(M51・M52編成)も4月末までに引退することになった。
残る189系は長野支社に配属されるN102編成のみで、こちらもあと数年で引退となりそうだ。国鉄形特急電車の姿を色濃く残した車両だけに、鉄道ファンから引退を惜しむ声があがっている。

【JR東海】「あさぎり」という特急名が「ふじさん」に
小田急電鉄の車両が当時の国鉄御殿場線に乗り入れることで始まった列車名の「あさぎり」。愛称は富士山麓の朝霧高原にちなんで名付けられた。
60年近くにわたり走り続けてきた小田急本線から御殿場線への乗り入れ列車だったが、この春から「ふじさん」という特急名に変更される。世界文化遺産に登録された富士山は、海外の人たちへもその名が知れ渡る。この名称変更も、やはり時代の波なのかもしれない。

JR東海では、ほかに注目されるのが特急「(ワイドビュー)ひだ」の名古屋駅の発車時間。午後の名古屋駅発の下り列車は、ほぼ2時間間隔となり、最終は20時18分と遅い発車となる。東京駅発18時30分の「のぞみ」に乗車すれば、乗り継げる時間に設定。このあたり、飛騨高山の人気と、海外からの利用者が多いことへの調整と思われる。
【JR西日本】国鉄形通勤電車の運用を最新タイプに変更
JR西日本では上り特急「こうのとり」を1時間間隔で運行、また18時台に新大阪駅発の和歌山駅行き、下り特急「くろしお」を増発させるといったビジネス利用を考慮したダイヤ変更を行っている。
一方で、鉄道好きには気になる車両の動きも。阪和線では、ごく一部に通勤形電車205系が使われてきたが、こちらが消える予定。さらに阪和線の支線、羽衣線の103系も車両変更される予定だ。
国鉄形車両の宝庫であったJR西日本も、徐々にJRになってから生まれた車両が多くなりつつある。阪和線を走っていた205系は奈良線などに移る見込みで、103系は残念ながら廃車ということになりそうだ。



JR西日本の路線のうち話題を呼んだのが三江線(さんこうせん)。ダイヤ改正後の3月31日に廃線となり、43年にわたる歴史を閉じる。利用者の減少という地方のローカル線が抱える問題が如実に現れた三江線の廃止。第2、第3の三江線が出ないことを祈りたい。
ちなみに現在、発売中の「時刻表」誌3月号には、三江線の時刻が掲載されている。三江線のダイヤが掲載された最後の「時刻表」誌となるのかもしれない。

【JR四国】新型車両を利用した特急が増える一方で――
新型車両の導入が順調に進められているJR四国。ダイヤ改正で、特急用の電車8600系で運転される特急「しおかぜ」「いしづち」と、特急用の気道車2600系で運転される特急「うずしお」が増えることとなった。2車両ともJR四国の社内デザイナーがデザインした新造車両で、評判もなかなか。人気デザイナーに頼らず、独自の新型車を生み出す姿勢が目を引く。


新造車が増える一方で消えていく車両も。JR四国の2000系は、気道車としては世界初の制御付き振り子式車両として開発された。1989(平成元)年に製造されたTSE2000形が、鉄道史に名を残す2000系最初の車両となった。この試作車両の編成3両がダイヤ改正とともに姿を消すことになった。

【JR九州】減便が多く見られる厳しい現状
JR九州は、JR東日本やJR西日本に次ぐJRグループの“優等生”となりつつあった。鉄道事業以外に、多角経営に乗り出し、新規事業それぞれが順調に推移していた。
しかし、ベースとなる鉄道事業が、度重なる大規模災害や、利用者減少の荒波を受け、厳しさを増しているように見える。熊本地震による豊肥本線の寸断、さらに昨年の大水害による久大本線や日田彦山線の長期不通など、鉄道事業を揺るがす大きな負担となっている。そのため、一部の優等列車の減便や、閑散路線の運行本数を減らすなど、今回のダイヤ改正でもマイナス要素が目立ってしまっている。

在来線の特急列車の本数や、運転区間の見直しが多くなっている。なかでも減便の割合が大きいのが特急「有明」。ダイヤ改正時までは博多駅〜長洲駅(ながすえき)間に上り2本、下り3本の運行で、長洲駅着が深夜1時20分と帰宅する利用者に重宝がられる列車も運行されていた。
それがダイヤ改正以降は、大牟田駅発の博多駅行きとなり、上り大牟田駅発6時43分のみになってしまう。区間短縮、さらに上り片道1本のみとは、なんとも思い切ったものだ。
ほかにもこうした例が見られる。

鹿児島中央駅と肥薩線の吉松駅を結ぶ特急「はやとの風」。錦江湾越しの桜島を眺めや、嘉例川駅や、大隅横川駅(おおすみよこがわえき)といった、明治生まれの駅舎が残る駅に停車するなど鉄道好きに親しまれてきた観光特急だ。
この「はやとの風」の運行日が毎日から、週末や長期休みの期間のみに限定されることになった。
同列車の終着駅・吉松駅からの北側区間は、さらに状況が厳しい。肥薩線では「山線」と呼ばれる吉松駅〜人吉駅間。スイッチバック駅の大畑駅(おこばえき)や真幸駅(まさきえき)がある険しい線区だが、この区間は走る列車がこれまでの5往復から、1日わずか3往復に減る。珍しいスイッチバックがあり、また日本三大車窓が楽しめた風光明媚な路線の旅が、かなり不便になりそうだ。
厳しい現実を見せつけられたJR九州のダイヤ改正の内容。一筋の光明を見いだすとしたら特急「あそぼーい!」の復活だろうか。

「あそぼーい!」は熊本地震が起こる前までは、豊肥本線の熊本駅〜宮地駅(みやじえき)を結ぶ人気のD&S(デザイン&ストーリー)列車だった。熊本地震以降には、臨時列車として、各地で運行されていたが、3月17日以降は、大分県の別府駅と肥薩線の阿蘇駅間を走ることになる。
週末や長期休み期間のみの運行となるが、パノラマシートから見る前面展望の楽しみが復活するわけだ。期待したい。