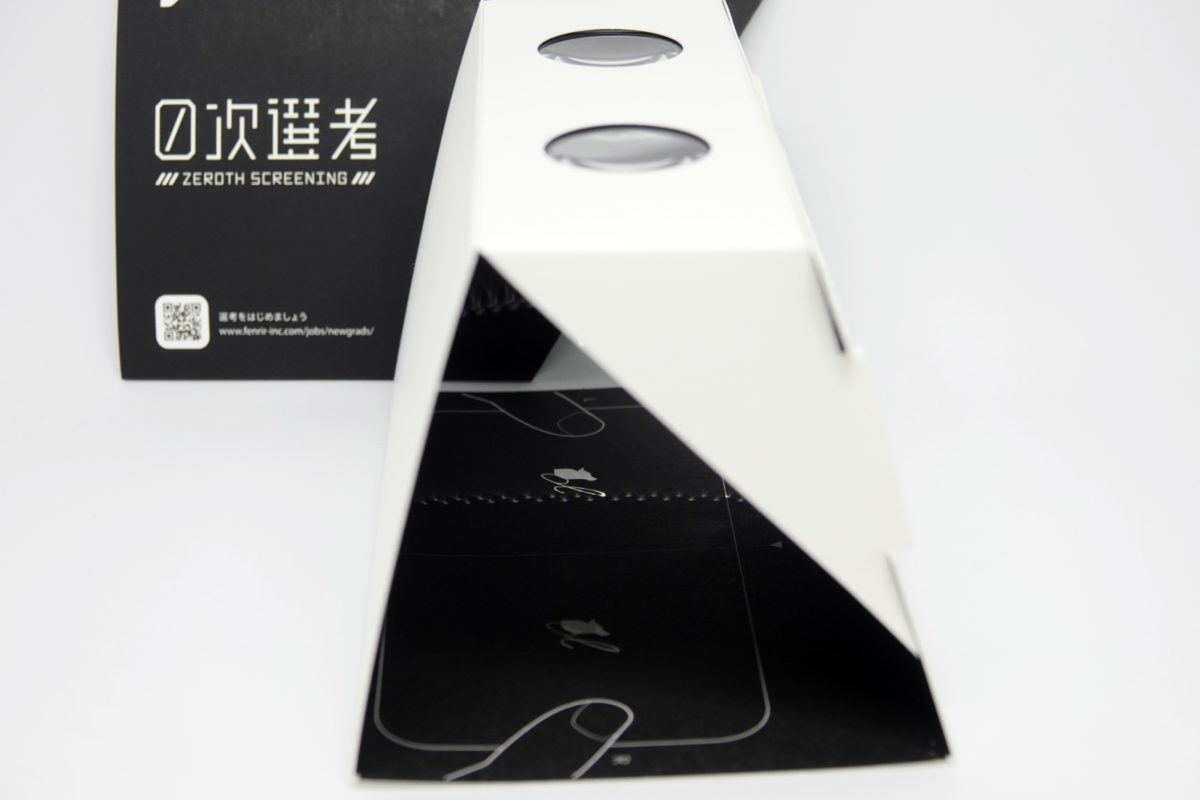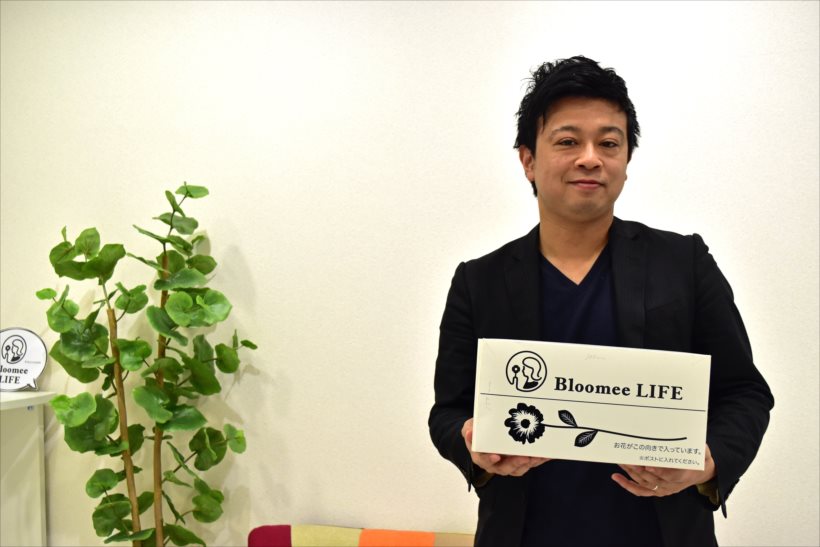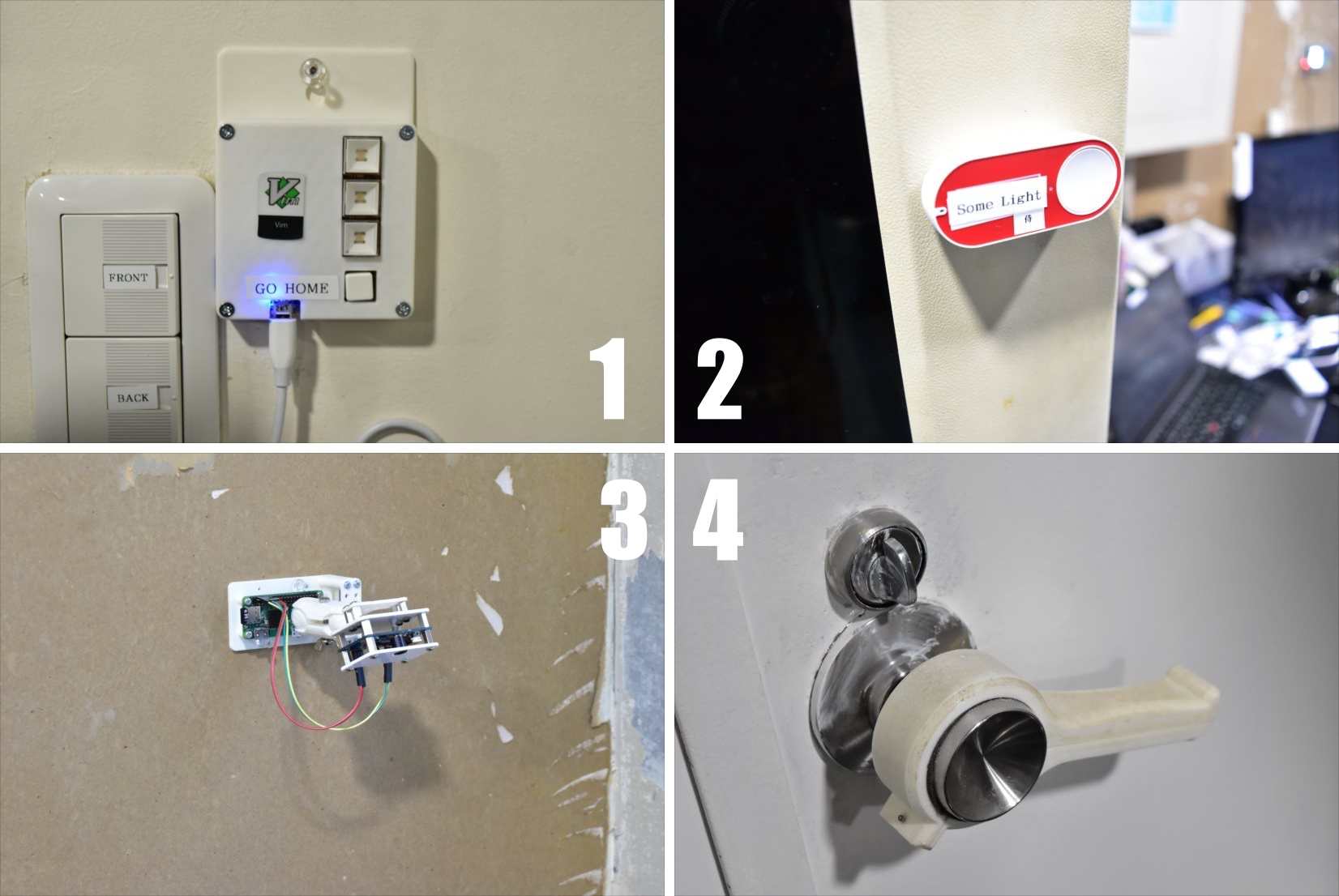2869万人――これは2017年に日本を訪れた外国人観光客の数だ。1人あたり平均15万円以上を国内で消費し、また7~8割は“日本の食事”を観光目的にしているという。そのため、訪日観光客が国内で飲食に費やす額は1兆円近い。飲食業は日本の観光資源とも言えるわけだ。とはいえ、その飲食業界では人材不足が続いている。せっかく入店しても辞めてしまうことも多く、離職率は28%にのぼるという。
そのような飲食業界の課題を解決すべく、飲食に特化した人材サービスを提供しているスタートアップ企業がある。大阪に本社を構えるクックビズだ。同社は大阪のほか、国内4か所にオフィスを持つ。そのうちのひとつが五反田だ。

五反田スタートアップ第12回は、クックビズ代表取締役社長CEO 藪ノ賢次氏に、同社が提供するサービス「クックビズ(cook+biz)」と飲食業界を取り巻く課題について話をうかがった。
人気のある日本の食事を提供している飲食業そのものを、人気の職種にしていきたい
――:まずは、どのようなサービスを提供しているのか教えてください。
クックビズ代表取締役社長CEO 藪ノ賢次氏(以下 藪ノ):主に飲食に特化した人材サービスを提供しています。大きく3つの柱があり、有料の職業紹介事業、求人サイト運営事業、研修事業です。
人材紹介サービス事業では、飲食業界に特化した転職支援を行っています。相談に来られた転職希望者にカウンセリングを行い、お仕事を3つ~4つほど紹介。転職に成功すれば、転職先企業から報酬をいただく、という形です。
求人広告サービスについては、人材紹介サービスを使うのはハードルが高いと感じている人、あるいは仕事場所や分野など希望する転職先のイメージが具体的にできあがっている人向け。コンサルを受けるほどでもない、という転職希望者が自分で求人サイトを見て応募できるようになっています。また、自分のレジュメを登録しておいて、名前など個人を特定できる情報以外を企業向けに公開し、それを見た企業からのスカウトを受ける、というスカウトサービスも展開しています。
最後に研修事業ですが、こちらはスタッフへの教育がなかなかできず、せっかく優秀な人が入ってきても定着しない、という課題を解決するためのサービスとなっています。

――:人材サービスのなかでも、なぜ飲食業界に特化することにしたのですか?
藪ノ:いろいろ理由はあるのですが、はじまりは食関連の専門学校とタイアップした「アルバイトマッチング」だったんです。講義が終わった午後6時ぐらいから飲食店で働くことで、いわば実地で学ぶことができる。そういうサービスでした。
そうやって飲食店と関わっていくなかで、飲食業界が慢性的に人不足に陥っていること、離職率が高いこと、人手が足りないから教育も行き届かないことなどの課題が見えてきました。しかも、そもそもの給与があまり高くないから採用が成功した際の報酬も低く、人材サービスに関しては誰も手を付けていない。それならば自分がやってみようか、と。
訪日外国人の76%が日本の食事を目当てにしている。日本のおいしい食事を食べたい、と思ってやってくる。インバウンドを引きつける力になっているんです。なのに、人手が足りない。人気がないからですよね。人気のある日本の食事を提供している飲食業そのものを、人気の高い職種にしていきたい、と考えているんです。
離職率の高さは特有の“ミスマッチ”が大きな要因
――:1/3近い人が辞めてしまうそうですが、なぜそれほどまでに離職率が高いのでしょうか?
藪ノ:飲食業の7~8割は中小企業。10店舗未満の個人店なんです。そうなると、人が少なく、余裕がないから新しいスタッフを教えている時間がありません。いわゆるOJTが成り立っていない。でも、お客さまは待ってくれませんし、粗相があれば即クレームに結びつきます。
そうすると、新しいスタッフは心が折れてしまいます。それが続けば辞めてしまう。そういった状況を変えるべく、接客マナーや組織として働くことの心構えなどを学べる「クックビズフードカレッジ」という事業をスタートしました。
クックビズフードカレッジでは、お店で働くスタッフだけでなく、店長向けの研修プログラムも用意しています。お店によって、あるいは店長によってルールが違うと、スタッフは戸惑ってしまい、それもまた辞める原因になってしまいますから。このようにお店のルール共通化を学べるほか、面接の仕方や損益の見方なども研修を通して習得していただき、店舗運営に強い人材を目指します。それがひいては組織の強化・発展につながっていくと考えています。

――:アルバイトスタッフだけでなく、正社員として転職した場合でも辞めてしまう人が多いのはどういうことが原因なんでしょうか?
藪ノ:総合的な転職サイトや雑誌にある情報では足りない、ということが主な原因ですね。飲食業で転職したいという人は、「将来自分の店を持ちたい」という志を持っている人が多い。その準備としてお金を稼ぐ……というために転職しているわけではなく、仕入れや経営、メニュー作りなど、将来独立するときに役立つ情報を学びたいからそのお店に入るんです。
でも、一般的な求人情報にあるのは「給与」「仕事時間」「福利厚生」といったありきたりの情報だけ。もちろんそれらも必要ですが、それは最低限の情報ですよね。求められているのは、どんな仕事がそこでできるか、どんなスキルが身につくかといった、数字だけでは見えてこないものなんです。決められた仕事時間内で学べないことは、定時後にお店にとどまってでも学びたい、そういう職人の世界なわけです。
このように、少ない情報だけで転職を決めざるを得ないから、ミスマッチが生じ、辞めてしまう、というのが実情です。そこで、わたしたちは「cook+biz」というサービスを通じて飲食業界内での転職におけるミスマッチをなくし、楽しく目標を持って働く人たちを増やしていきたいと考えています。
――:飲食業界ならではの難しさはありますか?
藪ノ:ビジネスで、経営資源といえば「ヒト・モノ・カネ」。インバウンドによる底上げもあって、「カネ」の部分はだいぶ回っていますし、いままで聞いたこともないようなジャンルの食を扱うお店も出てきていることから、コンテンツも豊富になっていることがわかります。これは「モノ」の部分ですね。
でも、「ヒト」に関しては、“人材剰余”時代の印象が雇用者側に根強くて、働き手が少なくなっているという現状に気づいていないお店が多い。4店舗で求人を出しても、採用できるのは1店舗のみということが当たり前に起こりうる状況があまり理解されていません。
そういう職人気質というかクリエイティブな方に危機感をもっていただく、というのがなかなか難しいと感じています。
――:御社では「クックビズ総研」という食のキュレーションサイトも運営されていますが、時代に合った認識を持っていただくためにも情報発信し続ける必要がある、ということなんですね。
ところで、この事業を展開していて良かったな、と感じた場面はありますか?
藪ノ:採用のお手伝いをした会社の店舗数が増えていったり、人が定着したりするのを見るのはやっぱりうれしいですね。企業の成長には、人の成長が欠かせない、その最初の部分に人材サービスとして関わっている、というのを実感できますし、なんといっても成長が止まっているといわれる国内産業のなかでもまだ伸びしろがあるんだ、ということが手応えとして得られる。飲食業界を元気にすることで、この閉塞感を打ち破っていければと思っています。
【五反田編】さまざまな「食」が一堂に会する場所
――:それでは、次は五反田にまつわるお話をうかがいたいと思います。御社は大阪に本社があり、名古屋、福岡、そして東京には新橋と五反田にオフィスを持っていらっしゃいますが、五反田に拠点を構えたのはどういう理由があるのでしょうか?
藪ノ:そもそも拠点を数か所持っているのは、転職希望者が相談に来られるように、というのが理由です。直にお会いして、コンサルティングさせていただいているんです。東京の拠点のなかでも、新橋はそのための場所になります。
一方、五反田は面接のための場所ではなく、求人広告事業の事務所として使っています。築浅のきれいなオフィスが格安で借りられる。しかもアクセスがいい。横浜の案件も増えているのですが、五反田は山手線の西側だからその点でも便利です。
あと、五反田って飲食業が盛んなイメージありますよね。いろんなジャンルの食を楽しめる、そういう意味でもこの場所はいいかなと感じています。
――:特にお気に入りのお店はありますか?
藪ノ:祐天寺や中目黒にもあるようですが、「もつ焼き ばん」が東京に来てからのお気に入りです。夜は居酒屋の「てけてけ」が安くていいですね。肉料理では「なるとキッチン」。ザンギがうまいです(笑)。また、スタッフはよく「酒田屋」を利用しています。
――:五反田にあるスタートアップ企業の中でコラボしたいと思われるところはありますか?
藪ノ:食関連でいえば、トレタさんでしょうか。先ほどお話したとおり、飲食で働きたい人は目的を持っている人が多い。決して予約の電話に振り回されるためにそこにいるわけじゃないんですよね。従業員目線で何かしらできたらいいなと思います。
――:最後に、今後のビジョンについて教えてもらえますか?
藪ノ:そうですね……日本の飲食業界の未来は実は明るいんです。
というのも、日本はアメリカやフランスに並ぶ食の先進国。そして今後、全世界的に経済が成長しGDP比率が増えてくるのはアジア地区。経済的な豊かになったアジアの人たちに最も近い食の先進国が日本、というわけです。つまり、日本は飲食という観点でいえば地の利がある、ということになります。
ますます元気になっていく国内の飲食業界をもっと盛り上げていくには、人材が必要です。いまは国内でのみ転職マッチングをしていますが、将来的には国境を超えたマッチングも手がけていきたい。自分のウデと包丁1本で渡り歩いていける業界ですし、国境は関係ないですしね。
わたしたちがいままでの「日本人」という枠から「アジア人」の一員というアイデンティティを確立するようになったときに、飲食業界内で価値を提供できるような、そんな企業になっていたいですね。