1月7日の朝に食べる七草粥(ななくさがゆ)は、一年の願いを込めていただく食事。そもそもおかゆとは、胃腸がまだ発達していない子どもの離乳食にもなるほど消化によく、胃腸に負担がかかりにくいので、行事食以外でも積極的に作りたいところです。
管理栄養士の鈴木あすなさんに、七草粥の正しい作り方やゆえんに加え、おかゆのおいしい作り方を教えていただきました。おかゆ作りは、生米から炊くおかゆから、炊き上がったごはんから作る簡単な方法までを紹介していきます。
七草粥とは“無病息災”を祈る食べ物
セリやナズナなど、7種類の野菜“春の七草”を入れて炊く「七草粥」は、“人日の節句”(じんじつのせっく=)に無病息災を祈っていただくもの。
「古くは中国から伝わった願掛けであるとも言われています。節句に節目としていただくのはもちろん、そもそも現代人は常に食べすぎていると指摘されているので、胃腸を休めるため、疲れたときにおかゆを作っていただくのもいいでしょう。七草粥には、脂質やタンパク質が豊富に入っているわけではないので、これだけで栄養バランスが整うわけではありませんが、ミネラルやビタミン、食物繊維は七草から摂れ、デトックスにもいいんですよ」(管理栄養士・鈴木あすなさん、以下同)
※じんじつのせっく。五節句のひとつに数えられる。五節句とは、1月7日の人日にはじまり、3月3日(上巳)、5月5日(端午)、7月7日(七夕)、9月9日(重陽)をいう。
“春の七草”とは?

・セリ……奈良時代から食用とされていたことが古事記や万葉集にも残っているセリ科の植物。香りがよく、料理では三つ葉のようにも使われる。
・ナズナ……アブラナ科の植物。ペンペン草とも呼ばれ、河原や草原でも自生している。
・ゴギョウ……キク科の植物。ハハコグサとも呼ばれ、昔はよもぎではなくゴギョウで草餅を作ったそう。
・ハコベラ……ハコベともいう。野原でよく見かけるナデシコ科の植物。白くて小さいきれいな花が咲く。
・ホトケノザ……コオニタビラコのことで、キク科のもの。図鑑などで見るホトケノザとは別の植物。
・スズナ……アブラナ科の植物。蕪(かぶ)は別名スズナといい、春の七草でもその呼び名が使われる。
・スズシロ……アブラナ科の植物。大根の葉の部分のこと。
七草粥の炊き方

七草粥は、その見た目から苦味やえぐみが強いのでは? と敬遠されがちですが、実はどの葉にも味に強いクセはなく、あっさりとしていてとても食べやすいものです。
「七草粥の作り方は、通常おかゆを炊く場合とさほど変わりません。おかゆの炊き方はこのあと解説しますね。
ただし、葉をはじめから入れてお米と一緒に炊いてしまうと、葉に火が入りすぎてしまい、見た目も食感も悪くなってしまうので、お粥を炊き上げてから、別でさっと茹で、刻んでおいた七草を入れていただきます。葉の歯応えや香りが残り、おいしくいただけますよ」
ここからは、おかゆの基本と、作り方を教えていただきましょう。
全粥、五分粥……おかゆの種類には何がある?

“おかゆ”とひと口に言っても実は、いくつかの種類があります。それぞれどのようなものか、鈴木あすなさんに解説していただきました。
「まず間違えがちなのは、“おかゆ”と“おじや”です。どちらも炊いたごはんから作れるのですが、おかゆの場合は炊いたごはんを一度洗ってから煮ていきます。洗うことでデンプンの粘りをなくし、ごはんがさらさらした状態になるんですね。一方、おじやは、炊いたごはんを洗わずにおかゆ状にしたもの。汁が白く濁り、粘り気のある仕上がりになります」
・お粥(おかゆ)・全粥……お米1に対して水5で炊く5倍粥のこと。一般的に、おかゆというと、この炊き方のことを指す。
・五分粥……10倍粥ともいい、お米1に対して水を10倍にして炊く。全粥よりとろみがあり、糖質も少ないのでダイエット食にも用いられる。
・重湯(おもゆ)……炊いたおかゆをざるで漉し、お米を取り除いた汁だけのもの。離乳食はここからはじまるので、ファスティング後の回復食にもよい。
・おじや……ごはん(炊いたお米)を洗わずにおかゆとして炊いたもの。お鍋の後にごはんを入れるものを示すこともある。
土鍋で生米から炊くおかゆの作り方
はじめに、生米から土鍋でおかゆを炊く方法を確認しましょう。今回使うのは、ごはん炊き用の土鍋ですが、片手鍋や鋳物の鍋などでも同じように炊けます。

「土鍋で炊いたおかゆは、とろみがありながら粘りは少なく、さらりとした食感です。そのままでももちろんおいしくいただけますが、ねぎや梅干し、海苔などをトッピングしても楽しめます」
【材料(2人分)】

・生米…100g
・水…500ml
【作り方】
1. 生米は洗ってざるにあげ水気を切る

「ざるにあげたら、最低でも10分はこのまま水切りしておきましょう。急いでいないときは30分ほどあげておき、次に進みます。洗ったあとにこうして水をきちんと切らないと、分量よりも水分量が多くなってしまい、仕上がりが変わってきてしまうんです」
2. 土鍋に米と水を入れて強火にかける

「沸騰するまでは強火にかけましょう。蓋を少しずらしておき、中が見えるようにして火をつけると、吹きこぼれの心配がありません」
3. 沸騰したら、弱火で20〜30分炊く

「弱火にしてからも、吹きこぼれないよう蓋は少しだけ開けておきます。ただし、たくさん開けてしまうと水分が飛びすぎてしまうので、あくまでも吹きこぼれないように少しだけにしてください。20〜30分炊いたら固さを見て、好みの固さになるまで炊きましょう」
4. 炊き上がったら、全体を混ぜて盛りつける

「炊き上がったばかりのおかゆは、水分とお米とにちょうどよく分かれています。ここから時間が経つごとにお米が水分を吸ってしまい、水気のないおかゆになっていってしまうので、炊いたら早めにいただきましょう」
炊いたごはんから簡単におかゆを作る方法

続いて、炊いたごはんからおかゆを作ってみましょう。
「お米から炊くよりも時間が短縮でき、手軽なので、急いでいるときやすぐに食べたいときには便利です。ただ、炊いたお米から作ると、お米が潰れたり溶けたりしやすく、水の色が白色に濁り、粒が感じにくいおかゆができます。おかゆ用に炊くことを考えるなら、少し硬めに炊いておくのもいいでしょう。離乳食やファスティング後の回復食として食べるなら、あえて粒感がないよう、ごはんから作ると手軽でいいかもしれませんね」
【材料(2人分)】
・炊いたごはん…200g
・水…500ml
【作り方】
1. 炊いたごはんを洗う

「炊いたごはんをざるに入れたら、上から水をかけて手でさっと洗います。ここであまり時間をかけてしまうと、ごはんが水を吸ってしまうので、あくまでもさっと表面を流す程度にしましょう」

「ごはんの周りにあった粘り気が取れ、パラパラとした感触になったら炊きはじめましょう」
2. 分量の水を入れて火にかけて炊く

「はじめは強火にかけ、沸騰したら弱火にして10分ほど煮ていきましょう。このときも蓋を少しだけずらした状態で上に乗せておきます」

「炊けたおかゆに溶き卵を流し入れ、うすくち醤油で味をつけました。たまごの甘みが加わるとさらにおいしく、タンパク質も取れますよ」
消化にいいものを摂って胃腸を休めることが、翌日からのパフォーマンスにもつながります。とくに、いつも以上にご馳走を食べる機会が多いハレの日が続く年末年始の後には、体を軽くするためにも、おかゆを食事に取り入れたいもの。七草粥に限らず、おかゆでデトックスする生活をしてみてはいかがでしょうか。
【プロフィール】

管理栄養士・料理研究家 / 鈴木あすな
愛知県名古屋市出身。大学卒業と同時に「管理栄養士」を取得し、世界中にたくさんの素敵な食卓=TABLEを作りたいという想いから、株式会社Table forを立ち上げる。現在はテレビ・ラジオ・雑誌のレギュラーを持ち、メディアを通じた情報発信を行う他、料理教室「Table for」の運営や企業とのレシピ開発、商品プロデュース、地域貢献など、より豊かな食卓が増えるよう幅広い活動をしている。著書に『美人をつくる! まいにちの簡単スムージー123』(学研プラス)などがある。
Table for https://table-for.co.jp/










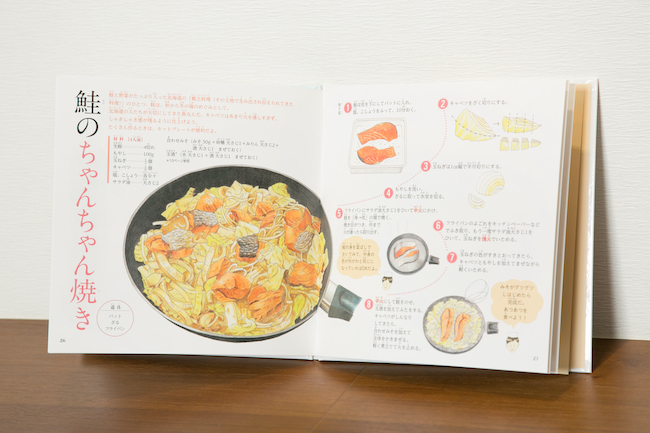


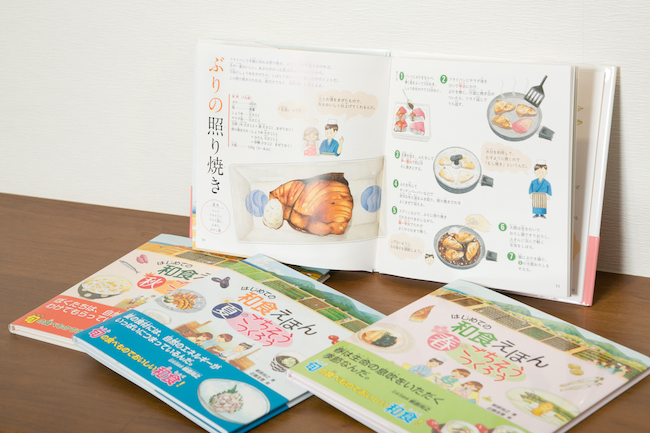

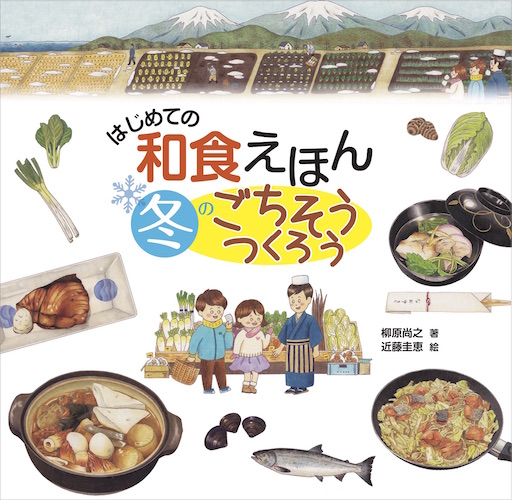









 関西の月見団子
関西の月見団子










 まだまだ続きますので、どうぞお楽しみに
まだまだ続きますので、どうぞお楽しみに