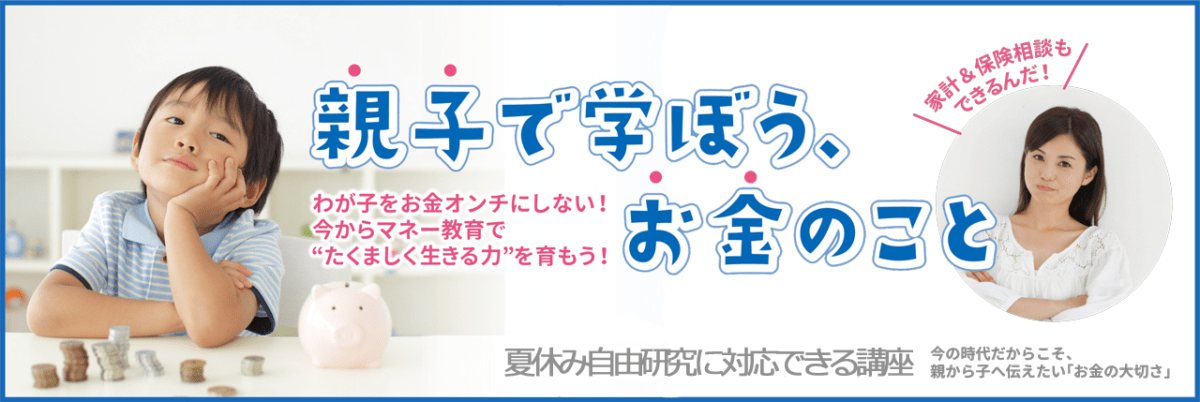自転車保険への加入を義務化する自治体が増えています。すでに兵庫県、大阪府、滋賀県で義務化されていますが、10月から名古屋市で義務化、京都府でも段階的に義務化が始まります。なぜいま、この動きが進んでいるのでしょうか。ベリーベスト法律事務所の弁護士が説明します。

■小学生の起こした自転車事故で1億円近い賠償を命じる判決
2013年、神戸地方裁判所で下された、ある自転車事故に関する判決。その事故は、坂道をマウンテンバイクに乗って時速20〜30kmで下っていた小学5年生の少年が60歳代の女性に正面衝突したもので、女性は自転車に突き飛ばされるかたちで転倒し頭部を強打して意識不明に陥りました。
事故から5年近く経った判決時点で、女性の意識はいまだ戻っていませんでした。裁判では、少年の母親が監督責任を果たしていなかったとして、少年の母親に、被害女性及び被害女性に人傷保険金を支払った保険会社に対して、介護費用、逸失利益、慰謝料、医療費等、総額で9521万円の損賠賠償を命じる判決が下りました。
この賠償額は自転車事故に起因するものとしては最高額です。これほどの賠償額でなくとも、自転車事故に起因する高額賠償判決は各地で下されています。
■加害者が破産すると賠償を受けられない可能性がある
賠償額が高額になると、加害者や加害者の親などの監督者が弁済することができず、破産して賠償が免責されることがあります。
加害者が意図的に事故を起こした場合や、飲酒運転やスマートフォンを操作しながら猛スピードを出していたなどの重大な過失がある場合は、破産しても免責されない場合もありますが、一般的なケースですと、加害者が破産すると免責されてしまいます。
そうすると、被害者が救済されない事態に陥ってしまいます。被害者は、自身が加入している保険から補償を受けられることもありますが、そのような保険に加入しておらず、被害者がまったく救済されないケースも起こりえます。こうした背景を受けて、各自治体で自転車保険が義務化されるようになったのです。
■自動車保険と比べて自転車保険の加入率は低いのはなぜ?
自動車の場合は、自賠責保険(または自賠責共済)への加入が全国で義務化されていますし、任意保険(対人賠償)の加入率も74.1%と高水準です。一方で自転車保険の加入率は25%ほどに留まっています。
2010年に実施された自転車保険未加入者を対象とした未加入理由調査の結果は、次のとおりです。
自転車保険自体の存在を知らなかったから 45.7%
どのような保険があるかわからないから 32.4%
自分が加害者になると思っていないから 14.0%
自転車事故で多額の賠償金が発生するとは思えないから 11.9%
その他 5.8%
この2010年の段階では「自転車保険自体の存在を知らなかったから」が45.7%でトップですが、この7年で自治体の自転車保険義務化が進むなど、認知度が著しく向上していることは想像に難くありません。
自転車保険サービスを提供するKDDIが今年おこなった調査では、自転車保険の認知率は、78.3%でした。この調査は未加入者だけでなく、加入者も含む調査なので、純粋な比較はできませんが、認知度が向上していることは間違いなさそうです。
認知率の問題は改善しつつあります。次に未加入理由として挙げた人が多かった「どのような保険があるかわからないから」についても具体的な課題は想像できます。自動車保険に比べて自転車保険は市場が小さいため、使える広告費が限られています。テレビCMを頻繁に打つことも難しく、保険の名称や内容まで消費者に認識されていないことが考えられます。
■自転車保険を強制介入の制度にしては?
また、各自治体が独自に義務化するのではなく、自動車の自賠責保険のように強制加入の保険制度を作ればよいのではないかという議論もあります。
この点、前述の2010年の調査では、次のような結果となりました。
必要 62%
不必要 15%
どちらでもない 23%
「必要」と回答した人は、およそ6割に留まりました。
ここで、改めて考えてほしいことがあります。自動車の自賠責保険のおもな目的は、無資産の加害者から賠償を受けられない被害者の救済です。また、加害者にとっても、自分の行為による結果による責任を果たす助けとなるものです。
自転車は気軽に乗れるため、子どもから大人まで利用する人すべてが加害者になりえます。そのような危険性があっても、自転車の利便性は多くの人々の生活に欠かせないものです。だからこそ、皆が安心して利用できるべきなのです。自転車保険はひとつの手段。今回、名古屋での義務化が決定したことを契機に、さらなる仕組みの整備に向けた議論が進むことを望みます。
監修:リーガルモール by 弁護士法人ベリーベスト法律事務所
【著者プロフィール】
熊谷直樹
弁護士。法科大学院卒業後、弁護士法人ベリーベスト法律事務所に入所。「日進月歩」を職務信条とし、依頼者の望みを最大限尊重しつつ、法的にも妥当性が認められるような最善の主張を依頼者との丁寧な対話により見つけていくことに定評がある。趣味は睡眠。
弁護士法人ベリーベスト法律事務所:https://www.vbest.jp/