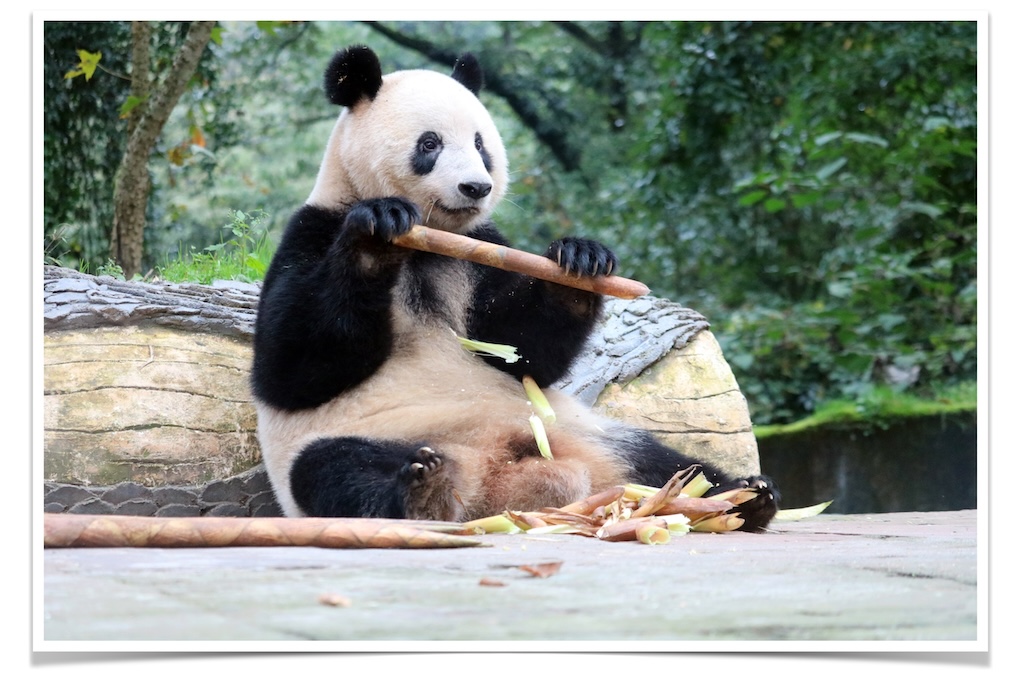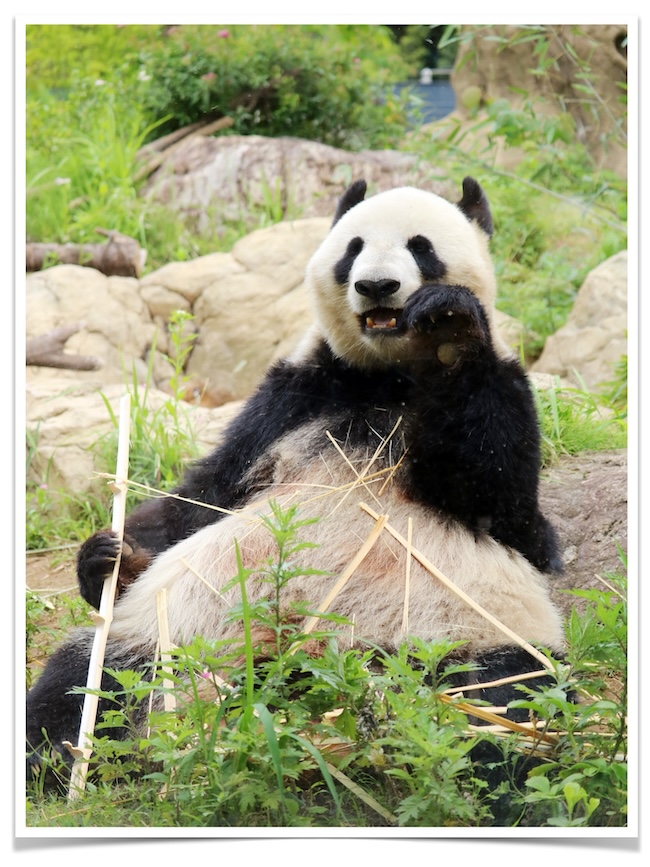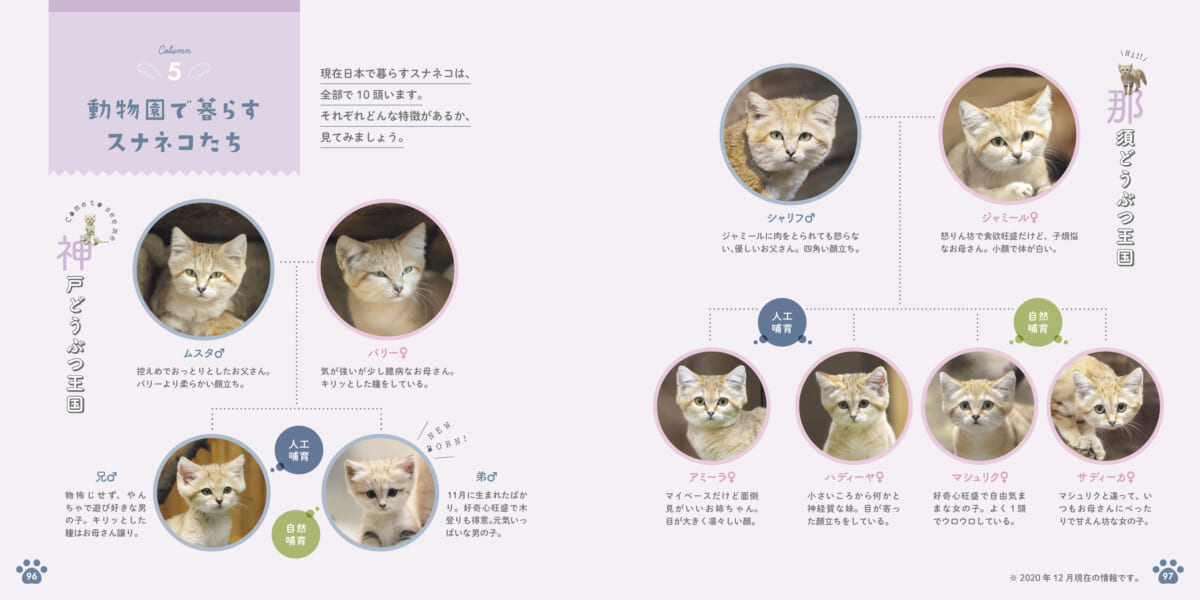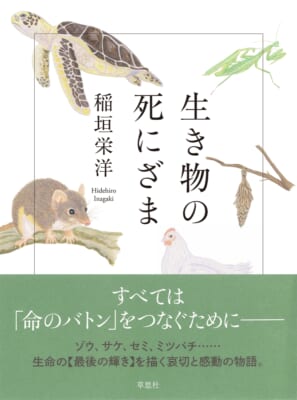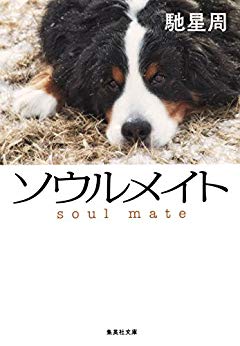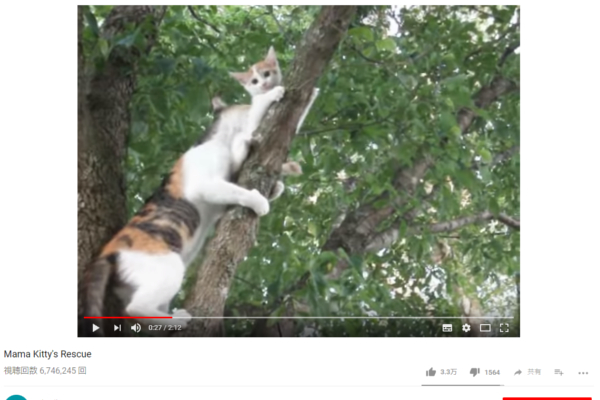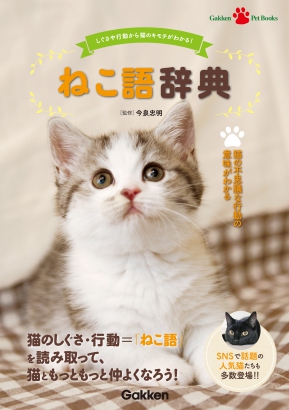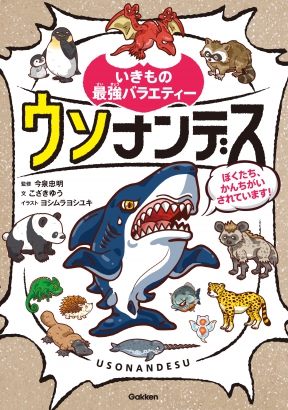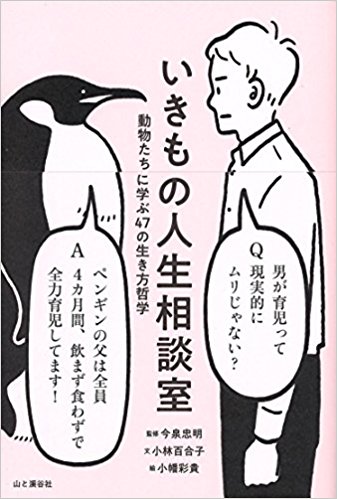近年、性別や年齢問わず幅広い層から人気を集める競馬。G1と呼ばれる大きなレースで活躍する競走馬に脚光が当たる一方で、怪我をしてしまったり、結果を出せなかったりして、引退する競走馬もいます。そうした引退競走馬たちのセカンドキャリアを支えるためには、費用面や活用機会の創出などの課題も存在しています。そこで、引退競走馬の保護・支援事業を幅広く展開する、株式会社TCC Japan 代表取締役の山本 高之さんに、引退競走馬を取り巻く状況や、私たちにできる支援の形についてお話を伺いました。
毎年約5000頭の競走馬が引退する現実

日本各地の競馬場で年間を通して競馬が行われていることもあり、毎年多くの競走馬が誕生しています。日本中央競馬会によると、2023年度の生産頭数実績は7796頭と公表されています。その中でも、レースで活躍できる競走馬はごくわずかで、その多くは結果を残せずに引退してしまうと言います。実際、毎年どれくらいの競走馬が引退していくのでしょうか?
「毎年変動はあるものの、引退する競走馬の頭数としては、日本中央競馬会に在籍する競走馬だけでも約5000頭にもなると言われています。
引退の理由は競走馬によってさまざまです。大きなレースで優勝するような牡馬(ぼば、オスの競走馬のこと)は、価値のある血統を後世に残すべく、父親として繁殖入りするために引退するケースがあります。そして、牝馬(ひんば、メスの競走馬のこと)も母親として繁殖入りするために引退する場合があります。しかし、繁殖入りが引退理由となる馬はほんの一握りです。
多くの馬は、レースでなかなか勝利できない、加齢によって能力が衰える、怪我や病気で次のレースに出走するのが困難であるといった理由で引退する場合が多いのです」(株式会社TCC Japan 代表取締役 山本 高之さん、以下同)
毎年多くの競走馬が引退していく中で、気になるのは引退した競走馬たちのセカンドキャリアです。引退した競走馬たちはどのような形でセカンドキャリアを送ることになるのでしょうか?
「上記でお話したとおり、優秀な成績を持つ牡馬は父親として、牝馬は母親として繁殖入りするといった進路があげられます。
繁殖入りしなかった引退競走馬の進路としては、乗馬になることが考えられます。一般の方を安全に乗せられるようになるまで、乗馬用のリトレーニングを受けてから乗馬として再出発することになります」

繁殖や乗馬といったセカンドキャリアが用意された引退競走馬がいる一方で、そうした進路を迎えられない引退競走馬も現実に存在しています。
「競走馬時代の馬主が引退後も馬を所有し続けるケースはあまりありません。そのため、引退後に新たな引き取り手が見つかれば、繁殖や乗馬としてセカンドキャリアを歩むことができるでしょう。
その一方で、引き取り手がなかった引退競走馬は、屠畜(とちく)されてペットフードなどになる場合があります。また、引退した理由が怪我や病気だった場合、手の施しようがないほど重篤な症状で、馬が非常に苦しがっているようであれば、獣医の判断により安楽死の措置が取られることもあります」
生涯飼育に掛かる費用は数千万円…
引退競走馬支援で向き合う課題
繁殖や乗馬といった形でセカンドキャリアを歩める馬もいる中で、すべての馬がそのようにすごせるわけではないことは、現実として受け止めなければなりません。とはいえ、できるかぎり多くの引退競走馬たちに、よりよいセカンドキャリアを用意してあげたいもの。そのためには、向き合わなければならない課題も存在しています。
「引退競走馬のセカンドキャリアを考えるうえで課題となるのは、まずは費用面です。馬を牧場や乗馬クラブに預けるとなると、飼育する場所代や餌代、世話をするスタッフの人件費などとして預託料というものが発生します。預託料は受け入れ場所により価格は異なりますが、毎月大体10万円~15万円が相場になります。寿命が30年くらいになる馬もいますので、寿命が来るまで預託料を払い続けると数千万円という費用が掛かります」

「次に馬が活躍できる場所が少ないことです。繁殖や乗馬以外にも、セラピーホースとして福祉に役立てる、放牧されている馬を鑑賞・撮影するといった観光資源として活用する方法も考えられます。しかし、なかなか活用の幅が広がらず、そういった活用自体も進まない現状です。引退競走馬たちの活躍の場を多く用意してあげるためにも、活用機会について、認知拡大を図ることが大切です」

上記に挙げた要点以外にも、「馬を十分に飼育できるだけの場所や、馬を世話するための人材確保にも課題はある」と山本さん。引退競走馬たちのより良い支援の形を探るためには、現実的な問題にも目を向ける必要があります。
私たちでもできる引退競走馬の支援方法

引退競走馬を生涯にわたって飼育するための諸課題を解決しようとしても、個人の力でできることには限りがあります。それでも、私たちが支援するとしたらどのようなことができるのか、山本さんにお尋ねしました。
「費用面での支援であれば、引退競走馬の支援団体を通して寄付をするといった方法があります。毎月定額で寄付ができるタイプと、その都度寄付ができるものがあり、寄付金は馬の預託料や支援団体の運営費用などに充てられます。
団体によって寄付額の設定はさまざまですが、その都度寄付の場合は一口あたり1000円程度を目安に、毎月寄付の場合は1500~2000円程度を目安に寄付ができます。支援したい引退競走馬がいたら、まずは寄付という形で支援するのはいかがでしょうか」
費用としてではなく、牧草や馬が喜ぶおやつなどの差し入れで寄付をする形もあるようです。また、競馬場によっては飲料を買うことで寄付ができる自動販売機が設置されているところも。自分が無理なくできる寄付の形を選んで支援するのもよいですね。
「寄付という形でなくても、引退競走馬の現状や社会課題、支援の在り方を知ってもらうことも、支援の一つになると考えています。
その方法としては、引退競走馬と触れ合うイベントや、引退競走馬の支援者同士の交流会などに参加といった方法があります。このような形で、支援者同士が交流できる機会を作り、情報共有することで、支援の輪を広げていくことも大切だと考えています。
引退競走馬について学びを深めたい方向けの勉強会が開催されていることもあります。興味があれば、そうした機会を活用して、知見を広げてみることもおすすめしています」
支援団体によっては、ボランティア活動という形で引退競走馬を直接お世話する方法もあるのだとか。寄付、学び、支援者同士の交流、直接的な支援など、引退競走馬たちを支援する方法は、私たちにできる範囲でも数多く存在しています。
「引退競走馬たちのセカンドキャリアについて語ることを、センシティブな問題として捉える方もいると思います。だからといって、『馬がかわいそうだから』という思いで支援するのは少し違うと感じています。
引退競走馬を支援するのなら、乗馬や触れ合いイベントなどで引退競走馬と関わることで、馬自体を好きになってほしいのです。『好きだから応援したい』という思いで支援したほうが、自分自身も楽しみながら、継続して引退競走馬たちのセカンドキャリアを応援できるのではないでしょうか」
好きという気持ちがあってこそ、引退競走馬たちの幸せな余生やセカンドキャリアについてポジティブに向き合えるのかもしれません。まずは馬の魅力を知るところから始めて、「馬が好き」という前向きな思いで引退競走馬たちを支援してみませんか。
Profile

株式会社TCC Japan 代表取締役 / 山本 高之
2006年1月にITベンチャーを起業。東日本大震災をきっかけに地域の重要性を感じ、生まれ育った滋賀県栗東市へと戻ることを決意。馬のまちならではの地域資源として馬を活用し、「引退競走馬の支援活動」と「馬をパートナーとした社会活動」を通じて、人馬のソーシャルイノベーションに取り組む。「TCC Therapy Park(滋賀県栗東市)」を活動拠点に、引退競走馬の支援活動を行う「TCC 引退競走馬ファンクラブ」の運営や、ホースセラピーなどの社会福祉事業を行う。そのほか、馬糞を堆肥にして育てた野菜を活用した「BafunYasai TCC CAFE(東京都渋谷区)」や、引退競走馬を観光資源として活用する養老牧場「TCC メタセコイアと馬の森(2024年11月正式オープン予定)」を運営する。
TCC Japan
TCC 引退競走馬ファンクラブ
※「ホースシェルター」は株式会社TCC Japanの登録商標です。