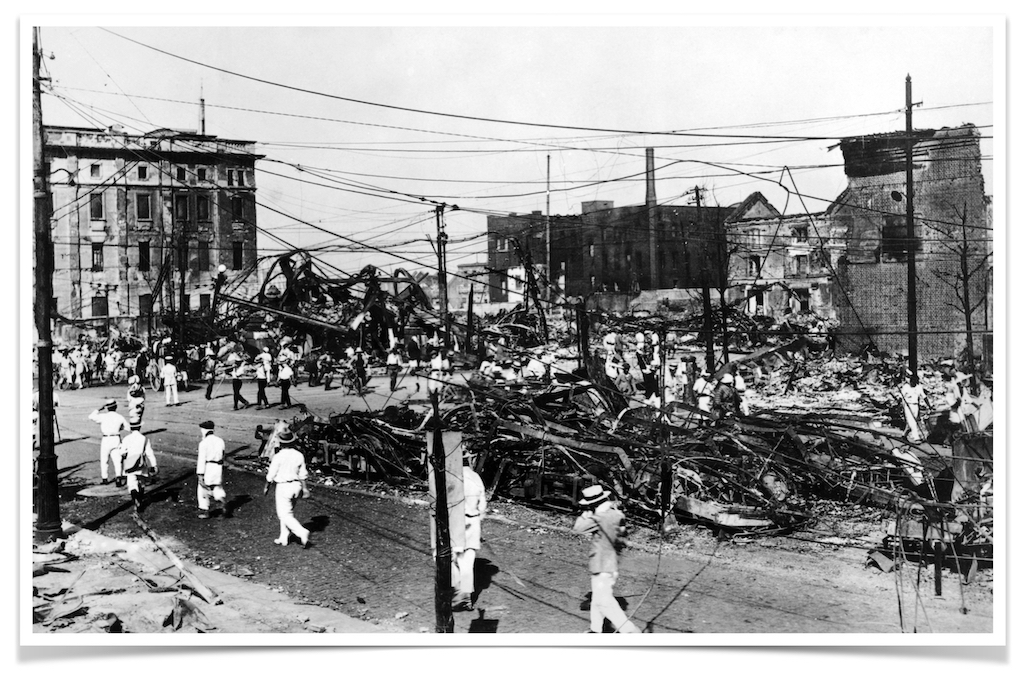近年、日本各地で台風や豪雨による大規模被害が発生しています。2019年に発生した台風19号では各地で電気設備が被害にあい、ピーク時には約52万戸が停電。多くの人々がパニック状態に陥りました。とはいえ、地震と異なり、台風はある程度予見することができます。私たちは、大規模な台風発生に備えてどのような対策を取ったらよいのでしょうか?
今回はマンション暮らしの場合の台風対策を紹介します。解説してくださるのは、拓殖大学地方政治行政研究所特任教授・防災教育研究センター長の濱口和久さんです。
復旧に1週間も!?
停電時はエレベーター・トイレが使用不可

マンション暮らしでは、どのような台風被害が考えられるのでしょうか? 濱口さんに3つの被害を想定していただきました。
1.強風による被害
「強風もしくは、強風による飛来物により窓ガラスが割れ、台風が室内に吹き込みます。割れたガラスの破片も風とともに室内に散らばり大変危険です」(防災教育研究センター長・濱口和久さん、以下同)
2.停電による被害
「停電になると、まず明かりがつきません。エレベーターが止まり、トイレも使えなくなる構造のマンションが多いです。当たり前ですが、電化製品全般も使用できなくなります。また、停電による断水で水道が使えないマンションもあります」
3.浸水による被害
「水があふれ、周辺が水浸しになると1階部分や玄関が浸水します。1階や地下に駐車場や配電盤があるマンションも多く、車が水没し、停電が発生します」

浸水による停電で、電気の復旧に1週間
水道の復旧に2週間かかったことも
「たとえば、関東地方では2019年に発生した台風19号を思い出す方も多いかもしれません。多摩川が氾濫するのではないかと言われるほどの雨が降り、神奈川県川崎市では一部の地域で降雨量が排水処理能力を超え“内水氾濫”が起きて、局地的な冠水状態が発生しました。東急東横線の武蔵小杉駅付近のタワーマンションでは、地下に配置された電気設備が浸水したため、電気が使用できなくなりました。電気の復旧に約1週間、水道の復旧に約2週間を要したそうです。
このような内水氾濫は、川が近くにある地域でしか起きないと思われているようですが、大量の雨量を伴う台風の場合、街の排水機能を上回り、どんな場所でも同様の浸水が起こる可能性があります」
マンションの台風対策はいつから?
「居住マンションの基礎知識」と「事前の準備」が大切
台風は、地震と異なり予測ができると濱口さんは言います。
「台風に備えるためには、まず自宅マンションの基礎知識を身につけ、普段の生活に絡めた備えをすることが第一です。台風が発生してから上陸するまでには、2〜3日かかるため、その間に備蓄やベランダのチェックなど確認する時間を確保できます」

「まずは以下のチェックポイントの項目を確認しましょう」
マンション防災のチェックポイント
□ マンション周辺のリスク
「ハザードマップで洪水、土砂災害、津波などの危険度を確認することで、避難のタイミングや備えておくべきことがわかります。指定されている避難所までの経路を普段から歩いて自分の目で危険な箇所などがないかを確認しておきましょう」
□ 電気設備(配電盤)の設置場所
「停電の復旧は数時間〜3日程度で回復する場合が多いですが、先の川崎市のタワーマンションの停電の復旧には1週間かかりました。これは配電盤が地下にあり、浸水してしまったことが原因です。マンションの配電盤がどこにあるかを知っておくと、その後の被害の予測ができます」
□ 備蓄
「マンションの管理組合によっては備蓄を行っているところがあります。高層階のマンションでは物資の引き取りの負担を軽減するために、5階おきに備蓄を設置している場合もあります」
□ 止水板の設置の有無
「マンションの1階や地下に、駐車場や電気設備が置かれている場合もあるため、浸水を防ぐことが大切です。そのために有効なのが止水版です。土のうに比べて設置が楽で、女性でも扱えるというメリットがあります。水害に備えてそのような設備があるか確認しておきましょう」
台風接近3日前(72時間前)から着手すべき
マンション住まいの事前の準備
続いて、台風接近前から行う事前の準備についてうかがいました。
■ 台風接近72時間前
1.窓ガラスの飛散対策を施す
→飛散防止フィルム、もしくは厚手のカーテンをかける
「窓ガラスが割れるのを防ぐためには雨戸が一番ですが、雨戸が設置されていないマンションも少なくありません。マンションでは高層階になればなるほど、風は強くなり、遮るものがないため強風を受けやすくなります。万が一、飛来物が飛んできて窓ガラスが割れたときの対策としては、室内に破片が入り込むのを抑える飛散防止フィルムを貼るのが一番です。その時間がない場合は、厚手のカーテンを準備しておくことをおすすめします。マンションの高層階になると、レースカーテンのみで暮らしている方が多くいらっしゃいます。厚手のカーテンをしっかり閉めておけば、窓ガラスが割れたとしても、カーテンがガードしてくれるので、ガラスの破片が室内に飛び散るのを防ぐことができます」

「また、養生テープ等を“米”の字に貼って飛散を防止する方法があります。養生テープは台風が通過した後、窓ガラスから剥がす際に、テープの跡が残ったりする場合もあるので、事前に剥がしたときの状態を確認しておきましょう」
2.停電に備えた対策
→自動点灯するライトを手元に置く

「夜間に停電が発生した場合、まず初めに必要となるのが明かりです。そこで、自動点灯するライトを廊下や寝室に差し込んでおきましょう。また、停電が長時間になると、明かりがないことはストレスになるので、長時間使用可能な充電タイプのランタンなども準備しておくとよいでしょう」
ポータブル電源は必要?
近年は、さまざまな自然災害に備え、ポータブル電源を購入する人が年々増加しています。「最低限の暮らしと重要な情報源を守るために、ポータブル電源は非常に役立ちますが、どれも10万円以上と決して安い買い物ではありません。ひとり暮らしの女性であれば、スマホを使用するためのモバイルバッテリーを備えておけばOK。ポータブル電源は高価なうえにかさばるものなので、停電がしばらく続くようであれば、wi-fi環境が整ったホテルに避難する方がよいでしょう」
3.水とトイレの準備を行う
→1週間分の水と非常用トイレを準備

「台風の被害は、その後の停電や浸水状況によって異なりますが、一般的には1日、長くても2日程度であり、台風が過ぎ去れば、外出し買い物に行くことができます。このため、食料の備蓄は3日間程度あればよいでしょう。一方で、停電して水が出ない、トイレがしばらく使えないことを想定して、水と非常用トイレの備蓄は1週間分を用意しましょう」
水の備蓄方法
「ウォーターサーバーを普段から利用していると、備蓄にもなります。台風ではありませんが、2018年9月北海道胆振東部でマグニチュード6.7の地震が発生し、北海道全域でブラックアウト(大規模停電)が起きました。復旧に1週間ほどかかり、しばらく水が使えない状況に陥りました。その後、アンケート調査を行ったところ、水の備蓄でウォーターサーバーがとても役立ったと言う声が多くありました。ペットボトルなどで水を確保しておく手もありますが、ウォーターサーバーであれば、スペア用に大容量の水を普段から確保することが可能です。停電するとお湯は使用できまんが、水は停電しても使用できます。北海道胆振東部地震が起きた9月は暑く水をよく使う時期でもありました。台風が多いシーズンとも重なります」
非常用トイレを選ぶときのポイント
「非常用トイレで心配なのが、使用後の凝固剤の機能性と消臭の持続性です。非常用トイレは用を済ませた直後に固まりますが、物によっては時間が経つと、固まった汚物が解け出すことがあります。融解すると、消臭が持続できず汚臭が発生する、袋から汚物が滲む、袋が破れてしまったときに中身が飛び散ってしまうなどの問題が発生してしまう場合があります。非常用トイレを購入する際には、商品の特性をよく確認してから購入しましょう」
■ 台風接近48時間前
4.二次被害を防ぐ!
→ベランダの植木鉢や物干しなどをしまう

「風速15m/秒以上で看板や植木鉢が飛び、風速20m/秒以上で子どもや体重の軽い人は飛ばされそうになるといわれています。鉢植えはもちろんですが、自転車等大きなものを置いている場合も飛ばされる危険性があります。物が落下して、人にぶつかったり、他人の窓を壊したりすると大変危険です。二次被害を作らないためにも、飛ぶ危険性のあるものを確認し、いったん室内へ。ベランダには何もない状態にしましょう」
5.台風の規模を確認
→ホテル避難も検討する

「内閣府が出している避難情報に関するガイドラインでは、住民は『自らの命は自らが守る』意識を持ち、自らの判断で避難行動をとるとの方針が示され、5段階の警戒レベルを明記して防災情報が提供されることになっています。ひとり暮らしの女性の場合、自治体から警戒レベル4の避難指示が発令された場合には速やかに避難しましょう。避難というと自治体が用意した避難所を思い浮かべますが、プライベートが守られ、Wi-Fi環境が整い、清潔な空間であるビジネスホテルもひとつの選択肢です。台風自体は長くても2日ほどで過ぎ去るので、台風が通過したあとに自宅に戻り、そのまま自宅に戻ることが可能か停電はしていないかなどの状況を把握し、その後の身の振り方を考えてもよいでしょう。台風時、会社勤めの人の中には、電車が止まってしまうことを見越して、会社近くのホテルに宿泊される方も多くいらっしゃいます」
住まいは何階?
「停電が起こりエレベーターを使えない場合は、何階に住んでいるかが避難をする上で判断材料になります。マンションが5 階以上であれば、上り下りは思った以上に大変であることを念頭におきましょう。1〜2日程度であれば問題ありませんが、1週間以上停電が続く場合、重い水や荷物を運びながらの階段の上り下りはとても大変です。不安があるのであれば、友人宅や親戚の家、ホテルなどに避難しましょう」
避難する時の持ち物は?
「マンションは強度があるため、倒壊することはほとんどないでしょう。台風が過ぎればいったん自宅に戻れるので、多くの荷物は必要ありません。1泊2日程度の着替えやタオルなどがあればよいでしょう。急に環境が代わり体調が崩れることもあるため、生理用品や常備薬なども準備しておくと安心です。」
マンションの台風被害で心配なのは、停電と断水。集合住宅ではさまざまなインフラを電気で制御していることが多いので、生活に多くの影響が出ます。あらかじめ「今住んでいるマンションで停電が起きたら?」「断水が起きたら?」と、シミュレーションしておきましょう。日頃の備えがあれば、実際に被害にあったときに慌てず行動に移せるはずです。
Profile

拓殖大学地方政治行政研究所特任教授・防災教育研究センター長 / 濱口和久
防衛大学校材料物性工学科卒、名古屋大学大学院環境学研究科博士課程単位取得満期退学。防衛庁陸上自衛隊、元首相秘書、日本政策研究センター研究員、栃木市首席政策監(防災・危機管理担当兼務)などを経て、現在、拓殖大学地方政治行政研究所特任教授・防災教育研究センター長、一般財団法人防災教育推進協会理事長などを務めながら、防災に関する知識向上を務める活動を行っている。安全保障、領土問題、日本の城郭史にも詳しく、執筆活動や講演を全国で行っている。令和6年5月には日本危機管理学会「学術貢献賞」を受賞。