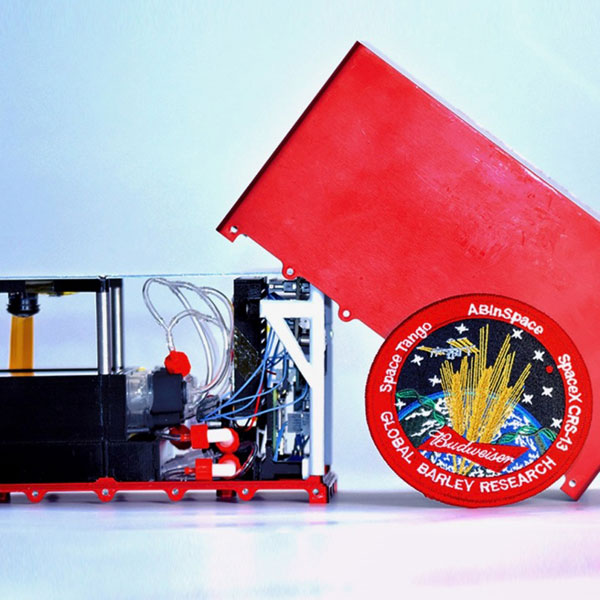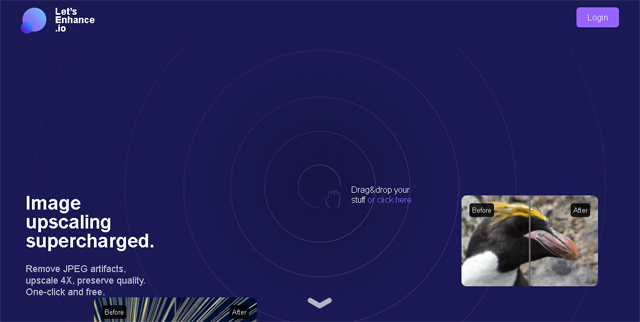Google、Facebook、Amazonとアメリカの大手テック企業が経済ニュースに登場しない日はないですよね。日本からもスマートニュースやメルカリといったスタートアップ企業がアメリカに進出していますし、アメリカのテック企業で働く日本人エンジニアを見かけることはニューヨークでも珍しくなくなってきました。これは西海岸でも同じようです。
日本で働いている人も実はアメリカ進出に興味がある方は多いはず。「あの同僚もLinkedInに英語のプロフィールを作ってる!」と驚いて触発された方もいるでしょう。

じゃあ「アメリカのどこ?」と聞かれると、カリフォルニア州シリコンバレー以外になかなか評判が聞こえてこないのも事実です。でもアメリカのテクノロジー経済は東西南北に広がっているってご存知でしたか? それを如実に示している「ニュー・エコノミー指標 2017」を今日は紹介したいと思います。
世界有数の非営利シンクタンク・ITIF(インフォメーション・テクノロジー・アンド・イノベーティブ・ファンデーション)が約20年間にわたって調査している「ニュー・エコノミー指標」は、ITイノベーションによる経済成長がどの州で起きているのかをランキング形式で発表しています。
エリートな州が競うトップ5

1位:マサチューセッツ(スコア96.6/100)
2位:カリフォルニア(84.7)
3位:ワシントン州(84.5)
4位:ヴァージニア(81.7)
5位:デラウェア(80.4)
ワースト5は、下から順番にミシシッピ(37.9)、アーカンソー(42.8)、ウェスト・ヴァージニア(44.1)、ワイオミング(47.1)、ルイジアナ(47.6)となっています。
西海岸と東海岸に偏っているかと思いきや、コロラド(7位)、ユタ(9位)、ミネソタ(12位)、テキサス(17位)、ジョージア(18位)と中西部や南部にもテクノロジー経済は点在しているようです。ニューヨークは11位となっています。
エンジニアだけじゃない、テック業界が欲しがる人材

ニューヨークに住む私の周りでも、テック企業へ転職を希望している知人が増えています。エンジニアはもちろん、マーケティングや人事部の仕事をしている人でもGoogleやAmazonといった大手テック企業やスタートアップに移ろうと狙っている人は多くなっています。
その理由は、経済が大きく成長しているこの分野では人材確保の競争も激しく、企業も給料や勤務体系といった面で高待遇を提示しているところが多いから。この業界での経歴を身につけることでその後のキャリアも広がります。
Amazonは第2本社を建設する都市を選別中ということで、全米の都市が「ウチに来てください!」とラブコールを送っています。そんな中のこのニュー・エコノミー指標の発表を受けて、Amazonの本社があるシアトルの新聞シアトル・タイムズは「Amazon第2本社を誘致したい州はこのランキングの上位に入ってないとまずいだろう」と述べています。
「州の経済が栄えるかどうかは、究極的にはモノやサービスをグローバル市場へ輸出し、厳しい競争に勝ち残っている企業が存在しているかどうかによる」とITIFのプレジデントでレポートの共著者であるロバート・D・アトキンソン氏は述べています。
アメリカでは、テック企業によって地域の経済が成長し、そこから新しい世代のスタートアップも生まれるということが起きています。アメリカで働きたいなら、どこにするか? 選択肢は1つではありません。
評価基準

ニュー・エコノミー指標は、評価項目が大きく5つに分かれています。1つ目は「知識ベースの仕事の割合」。マネージャーや技術者といった職業の割合、知識ベースの職業に就く海外からの労働者の流入などがこの項目では調査されています。各州にどれくらいテクノロジーやイノベーションのための労働力が存在しているかということですね。
2つ目はモノやサービスの輸出先がグローバルであるかどうかといった「グローバリゼーション」。3つ目の「経済的なダイナミズム」ではスタートアップがどれくらい生まれているか、急速に成長している企業はいくつ存在しているか、特許はいくつ取得されたかなどが評価されます。
面白いのは4つ目の「デジタル経済」。ここではブロードバンドの速度、州政府が情報を伝達するときにITをどれくらい活用できているか、医療分野ではどうか、そして農業においてインターネットとコンピューターがどれくらい活用されているかが評価されています。農業におけるデジタル技術の普及具合も見られるなんて驚きですよね。
最後は「イノベーション・キャパシティ」。電子機器製造やテレコミュニケーション、バイオ医療といったハイテク産業の仕事の数や研究開発に注がれる投資金額などが評価されています。
ただ単にイノベーション関連の仕事が集まっているだけではなく、デジタル環境が良い地域かどうか、州や国境を越えた労働力を受け入れる土壌があるかなども分かるわけですね。
1999年からずっと1位のマサチューセッツの場合、ソフトウェアやハードウェアにおける大企業が集まっているほか、MITやハーバード大学からの支援を受けるバイオテック企業も多く存在していることが理由として挙げられています。
逆に投資を集めているという点で飛び抜けているのは、やはりシリコンバレーを持つカリフォルニア。なんとアメリカのベンチャー・インベストメントの55%はカリフォルニアに注がれているとのことです。