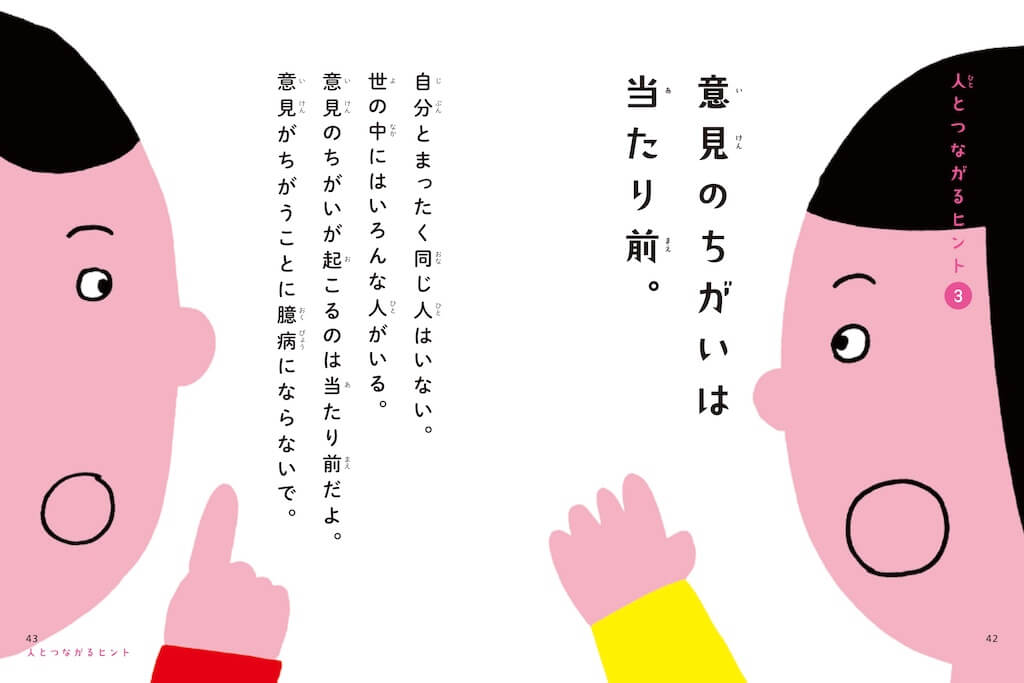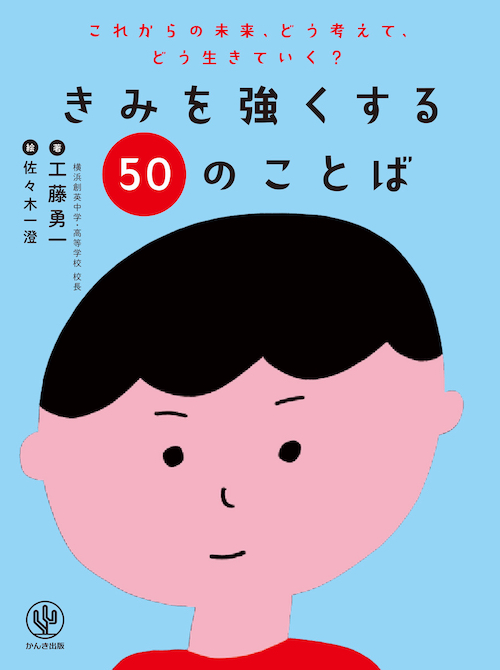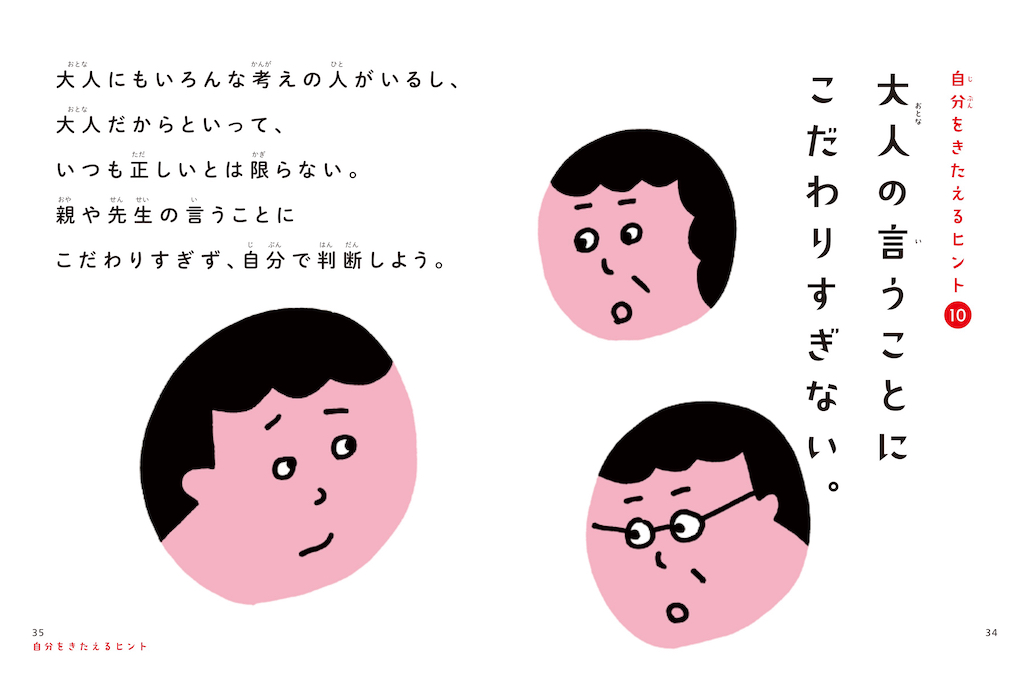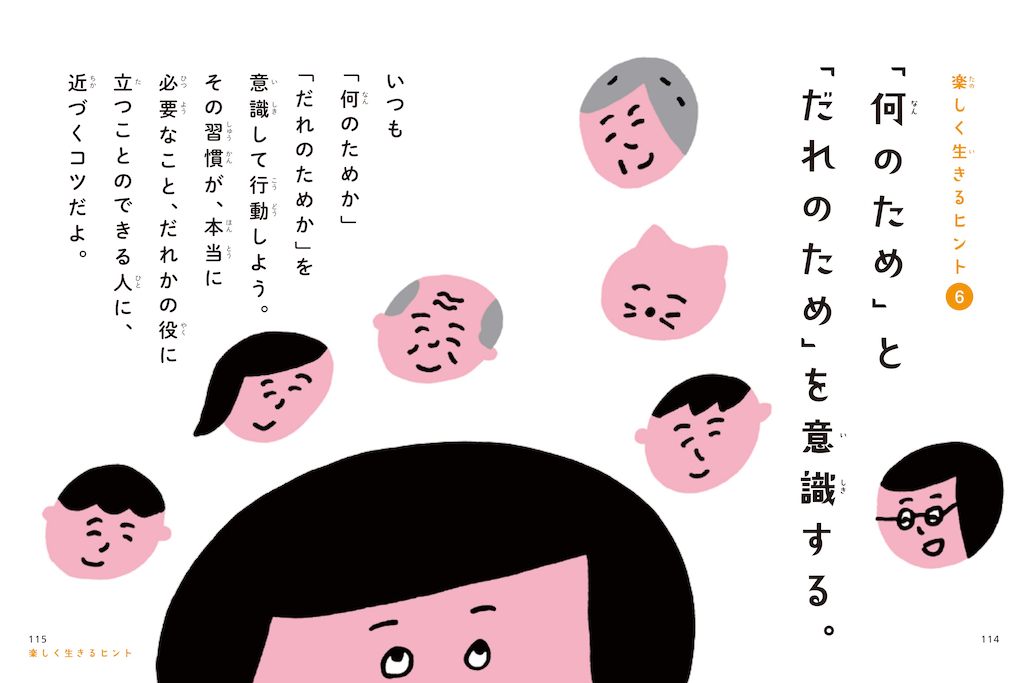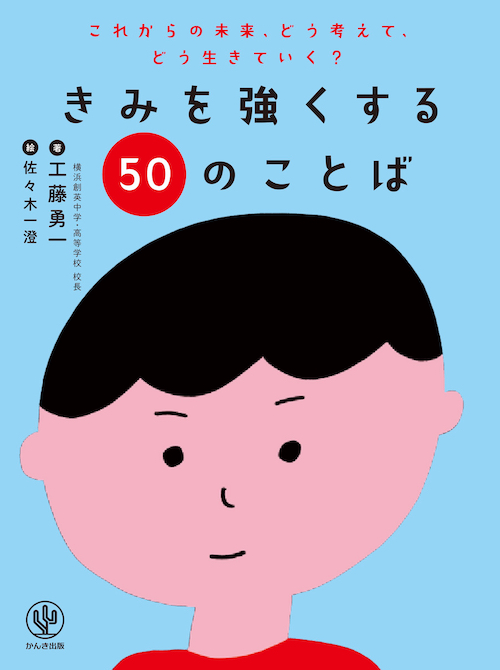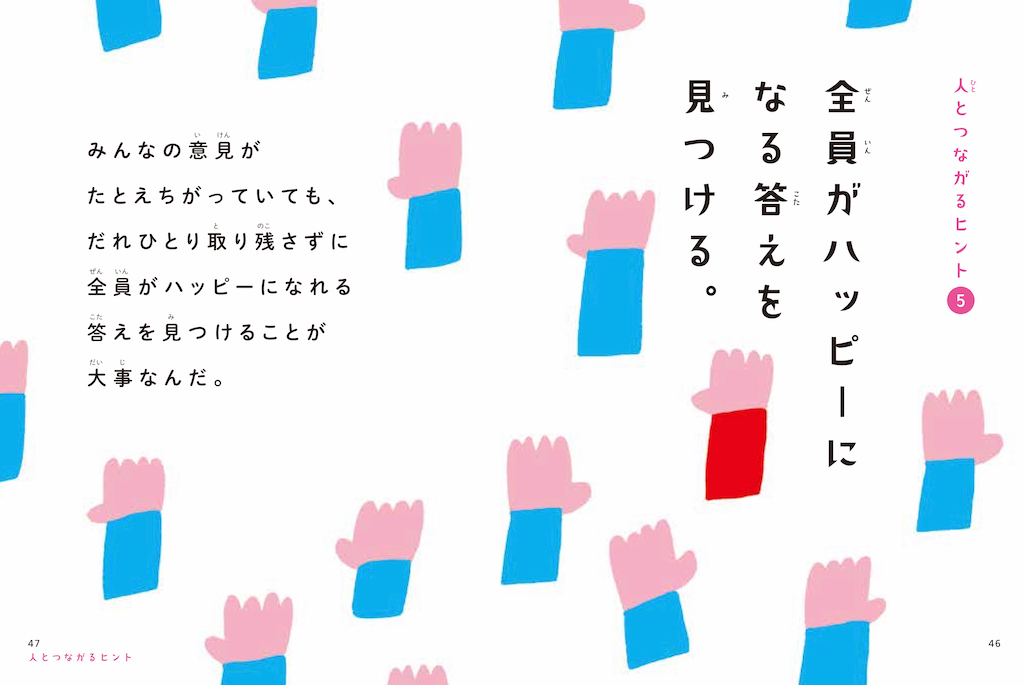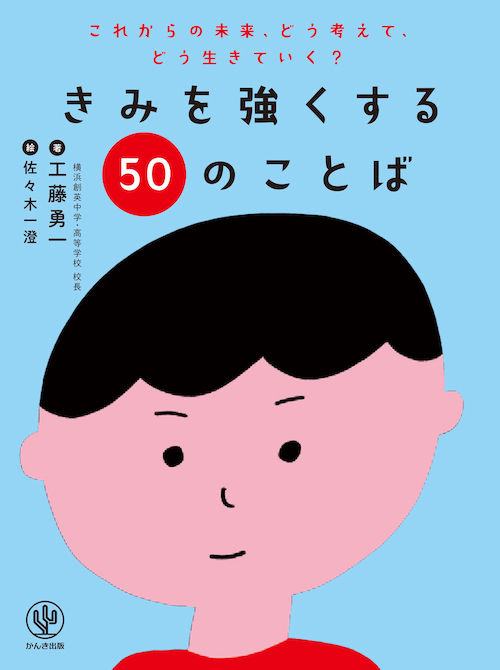「みんな一緒」に経済成長できる時代は終わり、多様な文化を認めながら自身で考えて答えを導く、いわば「自律」の力が求められる時代。自分はいったい何がしたいのか、どう生きていくのか? 子どもも大人も、当事者意識を持つことが求められるようになったのです。
学校にはびこる“当たり前”を撤廃し、自律型教育を進める横浜創英中学・高等学校校長の工藤勇一先生。著書『きみを強くする50のことば』(かんき出版)には、子どもも大人も知っておきたい自律のヒントがたくさん詰まっています。これからの時代に必ず役立つ、工藤先生のことばをお届けします。
全員ちがってオーケー。
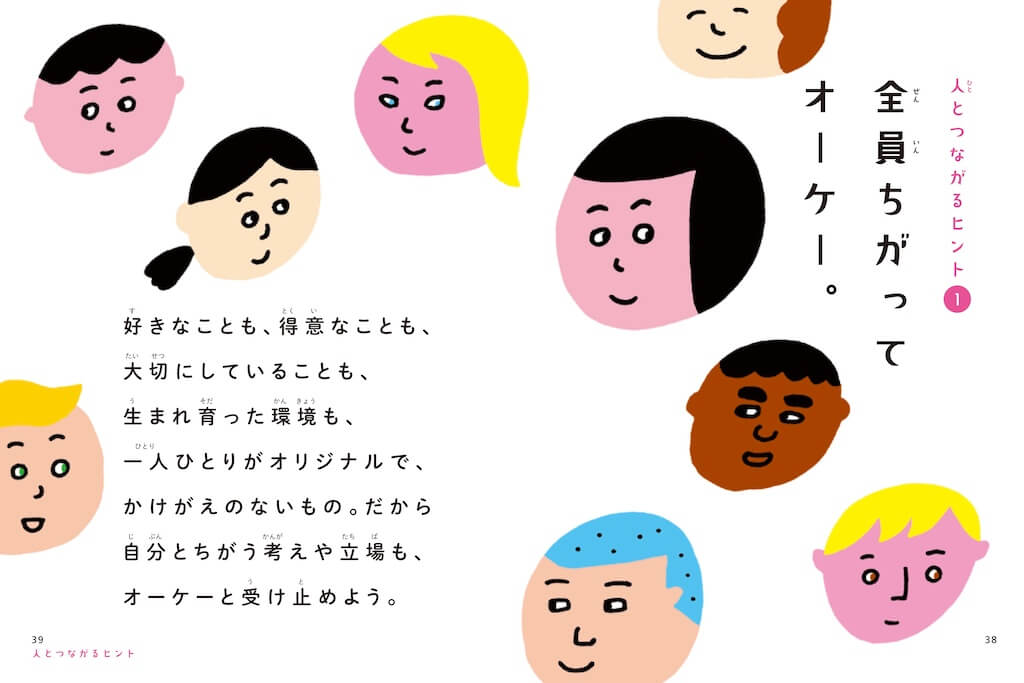
学校でのいじめの多くは「みんなと違う」という排除から始まります。私たちは小さい頃から、「みんなで仲良くしようね」「友達はたくさん作ろうね」と言われて育ってきました。そのため、仲良くできない人は排除する、突出して優れた才能は叩いて揃えようとします。
また多数決も、マイノリティを切り捨て、排除する仕組みです。多数決で決められたことは、数が多い意見が正義となり、少数だった人の意見を「みんなで決めたことだから」と切り捨て、平気で全体主義化してしまうのです。これは学校だけでなく、企業や政治など、社会のあらゆる場面で起こっていることですよね。
私たちは対立を起こさないよう、手軽な多数決で解決しようとします。しかし『意見のちがいは当たり前。』でもお話したように、そもそも同じ人間はいません。好きなことも、得意なことも、生まれ育った環境も、大切にしている価値観も異なります。今、目の前にある課題は、本当に多数決で決めて良いことなのでしょうか?
まずは異なるものを排除してしまうのではなく、経験しながら「全員ちがっていいよね」と認めていく。いろいろな経験を重ねることで、わかるようになる時がやってきます。大人になれば、どうしても仲良くできない人もいるし、それが普通だって認められますからね。
髪の色が違う、スカートの丈が違う、得意な教科が違う、家族が違う、趣味が違う、そんなことは当たり前。日頃から心の中で「全員ちがってオーケー」と唱えて、訓練してみましょう。
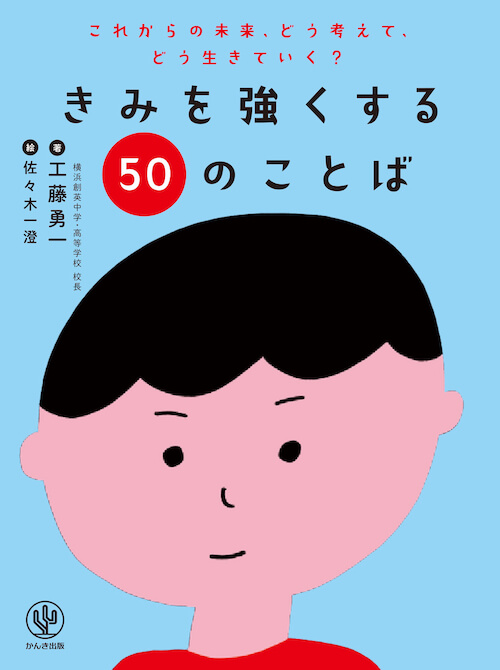
『きみを強くする50のことば』(かんき出版)
「どうしたら、すてきな大人になれるだろう?」___やさしい絵と、心に響く50の言葉が並ぶ本書は、絵本のようでいて、大人でもハッとするような人生のヒントが満載。「自分をきたえるヒント」「人とつながるヒント」「学ぶときのヒント」「挑戦するためのヒント」「楽しく生きるヒント」の5つの切り口から紹介されている。
Profile

横浜創英中学・高等学校校長 / 工藤勇一
1960年山形県生まれ。山形県と東京都の公立中学校の教員を務め、東京都や目黒区、新宿区の教育委員会へ。2014年から千代田区立麹町中学校の校長になり、宿題なし・テストなしなど「学校の当たり前」を見直し、子どもたちの「自律」を育んでいくことに注力。これらの取り組みはさまざまなメディアでも紹介されている。2020年4月より横浜創英中学・高等学校校長に就任し、さらなる教育改革に取り組んでいる。
Twitter