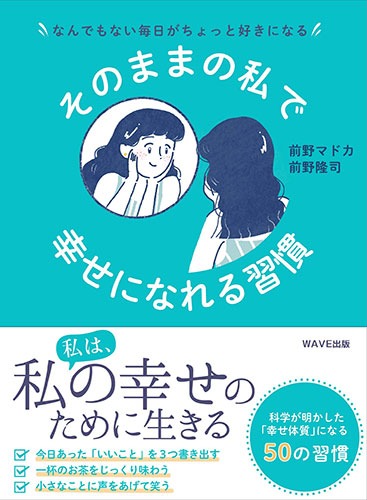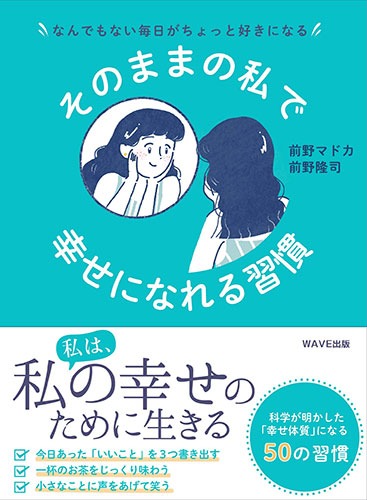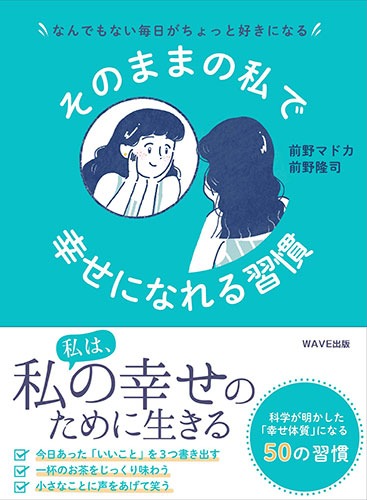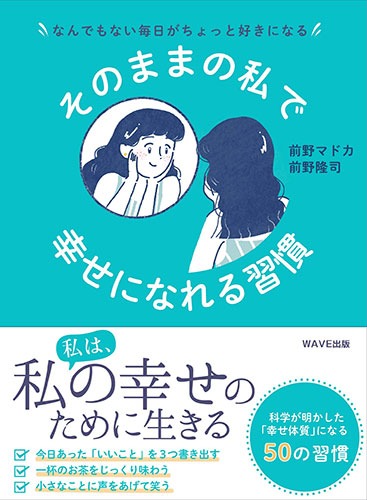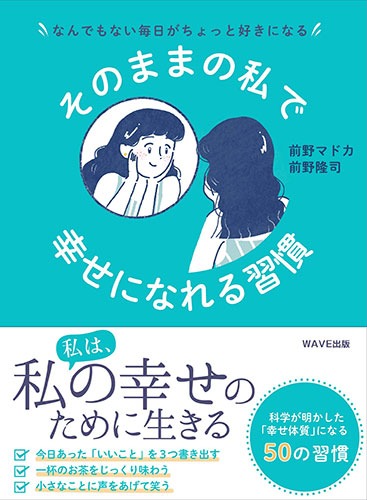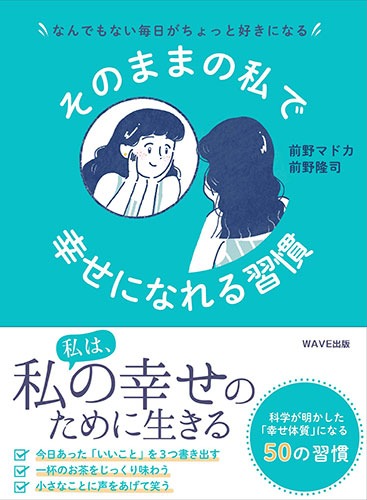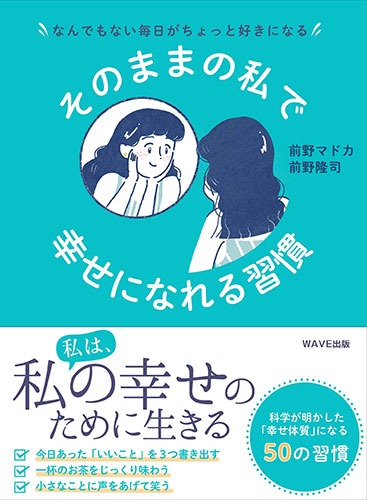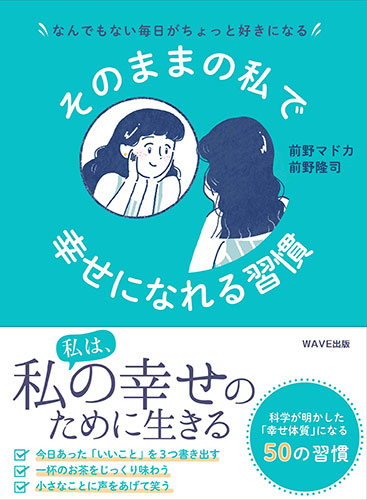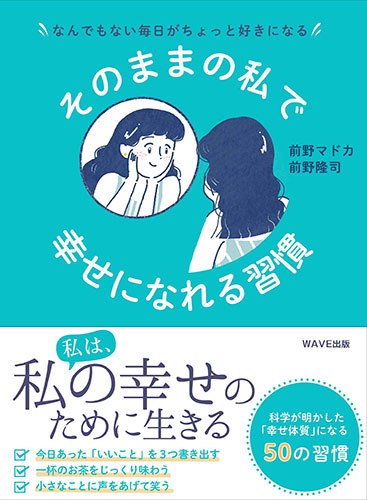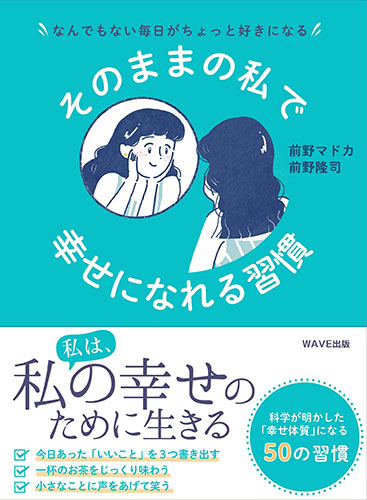いま誰もが、忙しい日々に追われ周囲の視線を気にして、自分を見失っているのではないでしょうか? 毎日がもっと楽しくて、幸せに感じられるものならいいのに——。落ち込む時代の空気に反比例するように“ウェルビーイング”が重視されるなか、幸せを科学的に研究・実証する「幸福学」が注目されています。
幸福学とは、心理学を基礎として、統計的にどういう人が幸せなのかを明らかにしていく学問のこと。この連載では、幸福学を研究する前野マドカさんに、さまざまな視点から幸せを感じる習慣や思考法など、「幸せになる方法」を教えていただきます。第6回のテーマは、大人が自己肯定感を育むためにできること。
自分で自分をねぎらう習慣
———今回のテーマは「自己肯定感」。よく耳にする言葉になりましたが、あらためてどういったものなのか、教えてください。
「自己肯定感とは、文字の通りで “ありのままの自分を肯定し認めてあげること” を言います。自己肯定感には、自分の存在そのものを認める『絶対的自己肯定感』と、他者評価や成功体験によって育まれる『社会的自己肯定感』の2種類があるんです。最近よく言われている “自己肯定感が低い”“高い”という話は、絶対的自己肯定感のこと。絶対的自己肯定感の高い人は、自分のいいところもダメなところも含めて、自分を肯定できている人といえます」

———その絶対的自己肯定感は、どうやって育まれるのでしょうか?
「絶対的自己肯定感は、主に幼少期に育まれるものです。テストでいい点を採ったから、試合で活躍したからではなく、“存在しているだけで素晴らしい” と感じられる体験をどれだけしてきたかが影響します」
———そんな体験をしてこれたかどうか、自信がない……という大人は多そうです。
「もし幼少期に絶対的自己肯定感を育めなかったと思う人でも、不安にならないでくださいね。大人になってからでも高めることができます」
———安心しました。今からでもできる、自己肯定感の高め方を教えてください。
「今日からでも、すぐに始められますよ。道具は必要ありません。毎日シャワーを浴びる時、ポジティブな言葉のシャワーも一緒に浴びる “ホメホメシャワー” を試してみてください」
———“ホメホメシャワー” ですか?
「これは、実際に毎日大きなプレッシャーやストレスに直面している海外のハリウッドスターが実践していることです。『俺はできる』とか『私は最高!』なんて前向きな言葉を、シャワーと一緒に浴びるもの。“シャワーを浴びたら、自分を褒める” と習慣化するのがおすすめです。
寝る前に『私は今日も一日よくがんばった』と、自分に対して言ってから眠るだけでもいいんです。自分で自分をねぎらってあげることが、絶対的自己肯定感を育むことにつながります」
———頭のなかで唱えるのではなく、声に出して言ったほうがいいんでしょうか?
「できれば声に出して言うことをおすすめします。自分で再度聞くことになりますから、より効果的ですよ」
誰かの自己肯定感を高めるためにできること

———自分で自分を褒めることが大切なんですね。逆に、他者の自己肯定感を高めるためにできることはありますか? 同僚や友人、パートナーや子どものためにできることがあれば知りたいのですが。
「ただ『すごい』や『えらい』とポジティブな言葉を伝えるだけでなく、何がすごいのか理由を一緒に伝えてあげましょう。すでにできていることやいいところの理由と一緒に伝えることで、自分の存在を認められるようになります」
———大人になると、褒めても「いやいや、私なんて」と謙遜する人も多いですよね?
「謙虚ですよね。とくに日本人は、照れ隠しで『いや』とか『そんなことない』とまず否定してしまう人も多いと思います。褒められたら最初に『ありがとう』と受け入れてみましょう。自己肯定感が高いアメリカの友人には、『その服かわいいね』と言うと『I know!』と返されます(笑)。自己肯定感が高い人の言葉を真似て、自分の自己肯定感を高めてみましょう」
———本当にちょっとした心がけで、自己肯定感を育んでいけるのですね。
「自分で自分をいたわる。誰かに褒められたら、受け止める。『ありがとう』が承認になるので、褒めた相手も心地よくなれますよね。これは家族、同僚、友人、恋人、すべての人間関係に共通します。
先日、女子大学生向けのフォーラムに参加したのですが、『自分のことを好きな人』はたった2割程度だったんです。普通が6割、それ以外が2割。ところが、それが小学生低学年だと、ほとんどの人が『自分のことを好き』と手を挙げてくれます。年齢を重ねていくうちに人と比べる機会が増えるので、自分を好きだと認められなくなるんですよね」
———幸せな人は人と自分を比べない、幸福度は主体性と大きく相関があるというのは前回のお話にもありましたね。
「そうですね。幸せになるためには、主体性が大切。まずは自分が幸せになることで、自然と自己肯定感も高くなっていくでしょう。
もしどうしたら幸せになれるの? と迷ったら『幸せの4つの因子』を思い出し、自分はどんな時に幸せを感じるのか? 自分に足りないところはどこなのか? 照らし合わせてみるのがおすすめです」
幸せの4つの因子
■「やってみよう!」因子
・主体的にやりたいことに取り組んでいる人
・得意なことがあり、それを伸ばそうと努力をして強みをさらに高める人
・好きなことがあり、それを突き詰めようと打ち込んでいる人
■「ありがとう!」因子
・人の喜ぶ顔を見たいと思う人
・困っている人を支援したいと思う人
・他者とのあたたかい付き合いに感謝している人
■「なんとかなる!」因子
・考えすぎず物事を決断できる人
・失敗しても気持ちを切り替え立ち直るのが早い人
・自己受容できている人
■「ありのままに!」因子
・地位財形型の競争を好まない人
・自己像が明確な人
・他者への許容度が広い人
「小さなことからコツコツと幸せを積み重ねていきながら、幸福度、さらには自己肯定感を育んでいきましょう」
幸せになる思考習慣……「ホメホメシャワーで自己肯定感を高める」
・自己肯定感には、絶対的自己肯定感と社会的自己肯定感の2種類がある
・大人になってからでも自分を労ることで絶対的自己肯定感を高められる
・褒められたら、謙遜や否定をせず「ありがとう」と受け止める
「自己肯定感が低いな」と感じた人は、今夜からホメホメシャワーを実践してみませんか? まずは試してみる、これは幸福度の「やってみよう!」因子ともつながります。自分ができるところから行動し、暮らしの中の幸福度を高めていきましょう。
Profile

慶應義塾大学大学院研究員 / 前野マドカ
EVOL株式会社代表取締役CEO、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科附属システムデザイン・マネジメント研究所研究員、一般社団法人ウェルビーイングデザイン理事、国際ポジティブ心理学協会会員。サンフランシスコ大学、アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)などを経て現職。著書に『月曜日が楽しくなる幸せスイッチ』(ヴォイス)、『家族の幸福度を上げる7つのピース』(青春出版社)などがある。