【ムー的オリンピック秘話】聖火でなく矛!戦勝祈願の1万人リレー「1938年の聖矛継走」(1)
【ムー的オリンピック秘話】幻の東京五輪を悼む神事だった!?「1938年の聖矛継走」(2)
神聖リレーの秘された目的地とは
矛を掲げて走ることは、「神事」として特別な意味を帯びてくる。前回はその仮定のもとに聖矛継走の意味を推測してみたが、そのルートについてもまた「神事」と仮定して再確認してみたい。
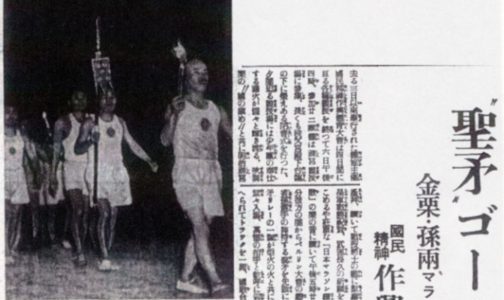 聖矛継走を報じる「東京日日新聞」(国会図書館デジタルアーカイブより)
聖矛継走を報じる「東京日日新聞」(国会図書館デジタルアーカイブより)
伊勢を出発した聖矛は熱田神宮を中継し、ひたすら東海道を下る。そして江戸時代には江戸四宿のひとつとして栄えた玄関口・品川から東京に入っている。
東海道から最終目的地の明治神宮を目指すには、距離だけを考えれば、品川駅のやや手前から左に折れ、山手線と並走するように五反田、渋谷方面を通って原宿に至るのが最短のルートになるだろう。あるいは神宮外苑を目指すのならば、六本木を抜けて青山に向かう方法もある。
しかし実際の継走コースは、日比谷から二重橋前に向かい、神田を経由して靖国神社へと向かっている。そして半蔵門から赤坂の日枝神社を通過して外苑方面に折れていくのである。ずいぶんな遠回り、寄り道をしながら進んでいるといった印象だ。
そしてそのコースを眺めると、まるでぐるりと皇居を囲い込むような線を描いているのである。
聖矛継走は、明治神宮を最終目的地と宣言しながら、実は皇居(宮城)を隠れた目的地としていたのではないだろうか。
つまり、聖矛継走は、八咫の鏡を奉斎する伊勢神宮、草薙御剣をもつ熱田神宮、そして天皇と八尺瓊の勾玉の鎮まる宮城の三点、三種の神器が鎮座する三つの聖地をすべて結びつけ、明治天皇の御霊が眠る明治神宮へと収束していくのである。
聖矛継走とは、伊勢、熱田、皇居の三聖地を結びつける、巨大な結界を張るための神事だったのではないか――。
キリスト教が「7」を聖数とするように、古来神道では「8」という数字が重んじられてきた。また、矛は本来神前に二本一対で並べ立てるものであり、奇数では座りが悪いところがあるのだ。
聖矛継走が、隠された目的地「宮城」を含め、8箇所の神域を結ぶ神事だったのだとしたら。諸々がうまく説明できるようにも思うのだ。
「支那事変」勃発の昭和12年以降、日本軍はなし崩しに戦線を拡大させ、収拾のつかない戦争に足を踏み込んでいく。そして昭和16年12月8日の真珠湾攻撃をもって、米英に対する全面戦争にまで突入していく。
昭和13年当時、中国大陸での戦争に国力を集中させていた日本で、対米戦を想定していた人間などほぼ皆無だっただろう。
しかし、聖矛が描いた軌跡を眺めていると、それはまるで、太平洋側からもたらされる「なにか」を防ぐための、総延長500キロにもわたる巨大な結界――のようにも見えてならないのである。
聖矛継走が空前の巨大結界だったとして、それは効力を発揮したのだろうか。結果は、歴史が示す通りである。
聖矛が奉納された神社の、その後の歴史を見てみよう。2番目の奉納神社となった結城神社は、昭和20年7月の津市大空襲において灰燼に帰してしまう。
これに先立つ1ヶ月前、6月9日に名古屋市熱田区域を襲った大空襲によって、第3の奉納社、熱田神宮も焼失している。
継走の最終目的地だった明治神宮、そして宮城も、無事ではすまなかった。昭和20年5月25日夜、帝都東京は3月10日に次ぐ二度目の大規模空襲に襲われる。
このなかで明治神宮は社殿を完全に焼失。そして同日未明、天皇の住まいであり、憲法発布式など大日本帝国の歴史を見守ってきた文字通りの国家の中枢・明治宮殿も跡形もなく焼き尽くされてしまったのである。
伊勢神宮、三島大社、鶴岡八幡宮、そして奇跡的に焼失を免れた靖国神社と4つの神社が残されたが、聖矛により結ばれた結界は、無残に寸断されてしまったといえるだろう(伊勢神宮も空襲を受けているのだが、ここも奇跡的に燃えなかったのだ)。
日本の敗北が決定し占領軍の上陸が始まるのは、明治神宮および宮殿が焼滅した3ヶ月後のことだった。もちろん、首都をなす術なく空襲されている時点で、すでに敗北は必至だったとはいえるのだが。

最後に、聖矛継走がその後に与えた影響についてもみてみたい。
昭和13年の聖矛継走はおおむね大成功として捉えられ、継走というスタイルを今後も続けるべきだという論調が新聞などにも展開された。
こうした空気を受けてのものか、翌14年、後醍醐天皇崩御600年を記念して催行された後醍醐天皇六百年祭では、南朝ゆかりの15の神社が参加した「建武中興神旗継走大会」が挙行されている。
後醍醐天皇を祭神とする吉野神宮に向けて、14の神社からそれぞれの神紋が染め抜かれた神旗を奉じた一団が継走するというもので、北は福島県の霊山神社、南は熊本県の八代宮からも神旗継走団が送られている。聖矛が奉納された結城神社は、この神旗継走の参加社にも名を連ねていた。
そして昭和15年。この年は「紀元二千六百年」を奉祝するイベントとして、各地で多くの神社巡拝継走が行われたのである。
九州では、霧島神宮の神火を捧げて九州全県を走破する「御神火九州継走」が、長野県では、橿原神宮の神火を諏訪大社にいただき、その分火をもって県下各地を疾走する「橿原神宮聖火継走」が行われた。
横須賀市で開催された「建国祭記念神社参拝継走大会」は、現在の同市市民駅伝の前身になるものだという。
最も規模の大きなものでは、軍用保護馬の鍛錬と愛馬思想の普及をはかる、との名目で挙行された「全日本軍用保護馬継走大騎乗」がある。
馬を使っただけに走行距離はぐんと伸び、継走も2班に分けて行われている。
南下班は北海道旭川市の護国神社から奈良県の橿原神宮へ、北上班は宮崎神宮から明治神宮へと、馬上神旗を捧げながら走破。紀元二千六百年にちなみ、両班の走行距離はそれぞれ2600キロになるよう計画されたとのこと。
そして、平和であればこの年に行われたはずの東京オリンピック、そして聖火リレーもまた、紀元二千六百年を祝祭するものとなるはずだったのである。
戦時中に行われたこれら多くの神社巡拝継走は、戦勝祈願、あるいは国威・皇威発揚を大義とし、自治体や官庁もコミットする半官半民の準公的行事として開催されていた。
そこからは、神社と国家が、また神道と国策が一体化するように結びついた、「オカルト国家・日本」というかつてのこの国の姿が浮かび上がってくるようでもある。
文=鹿角崇彦
「ムーPLUS」のコラム・レポートはコチラ
