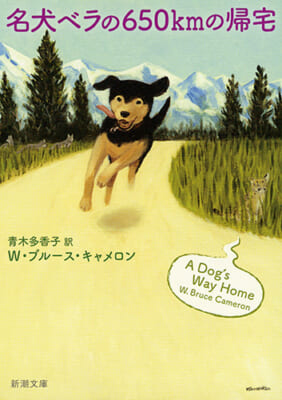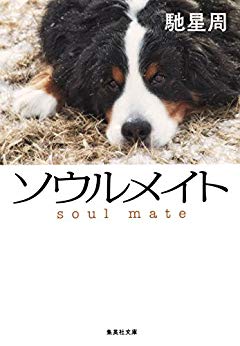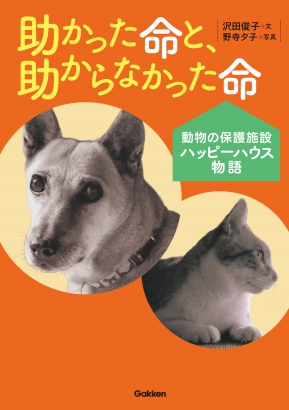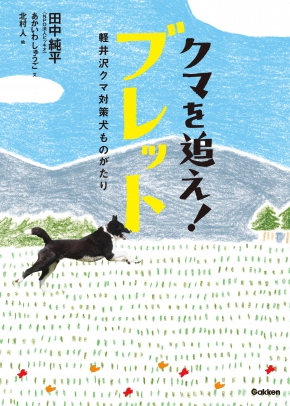ペットとの暮らしは、いつでもわたしたちの心を癒し、支えてくれます。ペットがいると自宅で過ごすのが楽しくなり、休日のお出かけや散歩を通して世界が広がったり、心を満たされたりする方は多いでしょう。空前のペットブームである今、特に都心の住宅事情から、犬も猫も室内で飼うことが一般的となり、ペットが室内で快適に過ごせるようなマンションや設備やアイテムが充実しています。

今回は、ペットの住宅事情にくわしいペットホームウェブの有瀧さんと中根さんに、室内でのペットの飼い方やおすすめのペットグッズ、ペット可賃貸の選び方など、ペットと家にまつわるあれこれを伺いました。室内で飼えるペットと言ってもさまざまですが、ここでは室内で飼える小型犬と猫に焦点を当てています。
犬を室内で飼うときに大切にしたい3つのポイント

1.室内犬を飼うときは床への対策が必須!
犬を新たに迎えるときに、サークルやベッド、食器などを揃えるのはもちろんのことですが、室内で飼うときに必ず考えてほしいことがあります。
「もっとも必要なのは、フローリングへの対策です。犬の足先は爪で地面をグリップする構造のため、どうしても床を傷つけてしまいます。とくに、小型犬は遺伝的に股関節や膝蓋骨が弱いため、ラグやタイルカーペット、クッションフロア、コルクマットなどを敷き、滑りや衝撃から守ってあげる必要があります。お部屋全体でなくてもいいので、犬が遊んだりくつろぐ場所、通り道に敷いてください。階下などへの騒音防止にもつながります」(ペットホームウェブ・有瀧さん)
【対策】ペット用のタイルカーペットを使う
「フローリングのペット可賃貸に入居された方におすすめなのは、裏に吸着加工がされたペット用タイルカーペットです。必要な部分に置くだけで固定でき、ペットが汚したところだけ外して洗えます。さまざまな色があるのでインテリアに合わせてみては? 2色使いなども楽しいですよ」(ペットホームウェブ・中根さん)
【おすすめアイテム】

東リファブリックフロア
「アタック270 キャンバスファイン」
6500円/㎡ 1040円/枚 全14色 40cm角
「スクエア2400 ソワレ」
8000円/㎡ 2000円/枚 全9色50cm角
東リ(広報企画部)Tel:06-6494-6605
https://www.toli.co.jp
2.きちんとしつけをする
どんな犬にもしつけのトレーニングは欠かせませんが、マンションなどの集合住宅で暮らす室内犬には、室外犬に比べてより多くのトレーニングが必要となります。
「マンションなどで暮らす犬には、トイレのしつけや無駄吠えさせないトレーニングが必要です。これはご近所と良好なおつきあいをするための、必須事項といえます。また、廊下やエレベーターでほかの住人に吠えたり、飛びつくといったトラブルを避けるためにも、どんなときでも犬をコントロールできるように、犬との信頼関係を築きあげておくことが重要です。日ごろから犬としっかりコミュニケーションをとって、犬に信頼される飼い主になってください」(ペットホームウェブ・中根さん)
【対策】用途別に部屋を3つに分ける
「自由奔放に広い家の中を駆けずりまわることが幸せのように考えがちですが、安心して寝る場所(クレート)、トイレをする場所(サークル)、遊ぶ場所(サークルや部屋の一部)という3つに分けておくのが、犬の安心につながります。クレートもサークルもつい大きいものを買ってあげたくなりますが、必ずしもそうではなく、くるくる回って丸くなって寝る、あるいは、トイレをするのにちょうどよいサイズか、少し狭いぐらいのほうが落ち着くのです」(ペットホームウェブ・有瀧さん)
【おすすめアイテム】
・ペットが安心して眠れるキャリーバッグタイプのクレート

リッチェル「キャンピングキャリー」3サイズ展開
4320円〜8640円
https://www.richell.co.jp/shop/pet/detail/58381/58391

「室内でも、車移動にも使えるので、犬も安心して眠れます。洗いやすいのがポイントです」(ペットホームウェブ・有瀧さん)
・お掃除しやすいサークル

リッチェル「ペット用 お掃除簡単サークル」3サイズ展開
1万800円〜2万7000円
https://www.richell.co.jp/shop/pet/detail/89201

「柵が床になる受け皿よりも外側なので、柵が傷みにくく、お掃除もラクでおすすめです。受け皿が木枠で柵が受け皿の中に入る商品は、トイレのはみ出しで木枠が傷んで匂いを消すことが難しくなりますので、注意しましょう」(ペットホームウェブ・有瀧さん)
3.肥満させないように管理する
最近、獣医師の間でとても問題になっているのが、犬の肥満だとペットホームウェブの有瀧さんは言います。肥満の原因の多くは、飼い主による食事やおやつの与えすぎによるもので、犬も人と同じように肥満から生活習慣病が引き起こされてしまいます。当たり前のことですが、飼い主がきちんと良質なフードを選び、適正な分量を与えて飼育することが、飼い主の義務と言えるでしょう。
【対策】規則正しい生活リズムをつくる
「室内で飼育する小型犬にも、きちんと食事の管理をしてあげることが大切になってきます。人間の食べる塩分の強いものを与えたり、かわいいからと言っておやつを頻繁にあげたりすれば、当然肥満や病気の原因につながります。また、人と同じで毎日のリズムをつくって過ごすことも、ペットにとって必要です。食事の時間、散歩の時間、と時間割を決めて習慣化することでストレスを軽減できます。なるべく毎日同じ時間に同じことをするスケジュールを決めてあげましょう」(ペットホームウェブ・有瀧さん)
以上、ここでは犬を飼うときのポイントをまとめましたが、続いて、目下大ブームの猫。
猫を飼うときに大切にしたい3つのポイント

1.爪とぎは猫にとって本能であると理解する
猫に自由に爪とぎをさせると、壁のクロスが破れ、床や柱が傷つき、部屋中がボロボロになってしまいます。また、爪とぎの音が近隣の方との騒音トラブルの原因になる場合も。とは言え、爪とぎは猫の本能ですからやめさせることはできません。
【対策】爪とぎできる場所を用意する
「賃貸物件で猫を飼う場合は爪とぎへの対策が重要です。猫がきちんと爪とぎできるよう、好みに合った爪とぎを用意してあげたり、爪とぎをしてほしくない場所を爪とぎ防止シートなどでガードしたりして、猫がストレスなく室内で過ごせるように工夫してあげましょう」(ペットホームウェブ・中根さん)
2.責任を持ってにおい対策を行う
「猫は肉食動物なので、排泄物の臭いが強いのが特徴です。そのため、猫トイレの臭い対策は猫の飼い主の必須事項となります。基本はこまめに掃除をしてあげ、消臭効果の高い猫砂やシステムトイレを使いますが、必要に応じて空気清浄機や脱臭機、消臭ビーズ、消臭スプレーなどを使いましょう。使用済みの猫砂やうんちは防臭袋に入れて、におい漏れにご注意ください」(ペットホームウェブ・中根さん)
※お住まいの市区町村やトイレのタイプによっては、うんちをトイレに流せない場合もあるのできちんと調べておきましょう。
【対策】におい専用のグッズを用意する
・においをシャットアウトするエチケット袋

「うんちが臭わない袋BOSペット用」(Sサイズ15枚入り)170円
「うんちが臭わない袋BOSネコ用」(Mサイズ90枚入り)1000円
https://bos-bos.com/
「犬用、猫用、ペット用と、用途・サイズ展開も豊富な防臭袋です。犬のお散歩用から、室内のゴミ箱用の大きなサイズまで揃っています」(ペットホームウェブ・中根さん)
・消臭効果だけじゃないペット用に開発されたスプレー

ハーパーベンソン「ミラクリーンP 500ml」4860円
http://harper-benson.com/item/mira/how/pet
「舐めても安心の消臭抗菌スプレーです。消臭だけでなく、ダニやカビなどからもペットを守ることができ、無臭なのでとても使いやすいです」(ペットホームウェブ・有瀧さん)
3.猫の飼育にも床対策を
猫は犬と違って爪を出し入れできるのですが、フローリングの床対策は必要です。「歩いているときや軽く走るだけのときは爪を引っ込めていますが、走ったり飛び上がったり、急に止まるとき床に爪を立てます」(ペットホームウェブ・中根さん)
【対策】ぺット用タイルカーペットなどを用意する
「犬の床対策と同じように、ペット用タイルカーペットやクッションフロアを猫の通り道や遊び場に敷いてください」(ペットホームウェブ・中根さん)
犬・猫の室内飼いの注意点や家づくりのコツに続き、最後に物件探しについても教えてもらいました。
「ペット可」の賃貸物件を探すときの注意点
1.そもそも「ペット可」でない物件ではペットを飼育できない
室内でペットを飼いたい、と思っても、賃貸物件はペットが飼える物件でなければ、もちろん飼うことができません。ペット可でない物件でペットを飼った場合、ペットを手放すか、貸主から提示された期日までに退去しなければならなくなりますし、場合によっては違約金を請求されることもあります。ペットを飼うときには、その物件が「ペット可」であることが必須です。
2.「ペット可」の注釈をよく確認する
インターネットでペット可賃貸を検索していると、「ペット可」とだけ記載された物件と、詳細欄などにペットの条件が書いてある物件があります。《小型犬一匹まで、小型犬二匹まで》などの記載がある物件は、そのほかの中型犬や大型犬、そして猫は飼ってはいけない、という意味です。「ペット可」とだけ記載された物件は、あえて詳細を記載していないことも考えられます。
「じつは少し前の時代は、賃貸物件でペット可というと、小型犬1匹だけ、という認識でした。猫は爪とぎの習性と強烈なオシッコのにおいから、賃貸物件のオーナーさんにいやがられる存在だったのです。しかし、猫砂が改良され、猫の爪とぎを防止する方法や飼育マナーが広まると、猫へのイメージを改める賃貸オーナーさんが増えてきました。猫OKのペット可賃貸は増えつつあります。猫と暮らせるペット可賃貸をお探しの方は、詳細欄に猫可や猫1匹まで、などの記載がある物件をチョイスしてください」(ペットホームウェブ中根さん)
3.ペットが住みやすいお部屋はペット目線で探す
・犬や猫が落ち着けるエリアであること。車が多い道沿いや繁華街はNG!
・カーペットやクッションフロアの物件で探すのもおすすめ
・家の中でペットが落ち着いて眠れ、排泄できる場所を確保できる間取りであること
・ペットがほとんどの時間を家で過ごすこと、留守番させることを考えたお部屋探しをする→風通しを考えた立地と間取り、夏の暑さを想定してマンション最上階や南向きは要注意
・周囲に安全で快適に散歩できる大きな公園や川沿いなどのスポット、コースがある
・若い猫を飼う場合は、上下運動ができるロフト付きやメゾネットの物件もおすすめ
「ペット可」の賃貸物件で暮らすときの注意点
1.「ペット可」であってもマナーは守る
「ペット可」のマンション、ペット可住宅にはペットと暮らしていない人も入居しており、なかにはペットが苦手だったり好きでない人が住んでいる場合もあります。そのため、どうしてもトラブルが起こりがちです。その点、ペット共生型の集合住宅は、ペットと暮らす人だけが入居しているのでトラブルは少なく、安心してペット暮らせる物件といえます。また、ペット可物件であっても、フローリングの床をペットの爪から保護しないで使っていたり、壁紙が猫の爪とぎでボロボロだったり、においが染みついてしまったりしていると、床材や壁紙の張替えとなり、原状回復費が高額になってしまうので、きちんと対策をしながらマナーを守って住みましょう。
・「ペット共生型物件」という選択
ペットと住める物件のなかには、「ペット共生型」と呼ばれるペットのための施設や設備の整えられた物件があります。ペットと居住者のことを考えて作られており、そのほとんどがペット用カーペットやペット用クッションフロア仕様になっています。
一般的なペット可賃貸では、猫用の設備がある物件はほとんどありませんが、猫専用賃貸にはキャットステップ、キャットウォーク、猫トイレ置き場、くぐり戸、猫の脱走を防止する二重扉や窓柵、猫の爪がひっかからない腰壁などの設置された共生型の物件もありますから、ペットが気持ちよく過ごせる部屋を探してみましょう。
・戸建への住み替えを機にペットとの暮らしをスタート!
ペットと一緒に長く住むことを考えると、戸建て住宅への引っ越しを考える方も多いでしょう。大和ハウスからは、賃貸住宅の管理運営を行う関連会社、大和リビング「D-room」の入居者向けに、ドッグハウスやドッグランを備えた分譲住宅が販売をスタートしています。
 ↑プロダクトデザインを手掛けるクオリクスと大和リビングが共同開発した、オリジナルドッグハウスとミニドッグランを標準搭載
↑プロダクトデザインを手掛けるクオリクスと大和リビングが共同開発した、オリジナルドッグハウスとミニドッグランを標準搭載
犬小屋付き賃貸併用分譲住宅「SEJOUR DD-1」http://www.daiwahouse.com/about/release/house/20180308095332.html
2.騒音には特に注意する
室内で一緒に過ごしている間は無駄吠えがなくても、外出して、犬だけでお留守番のときが課題となるケースも多くあります。
「たとえばFurbo(下部参照)という、スマホで遠隔操作をしておやつをポーンと出す機器などは、外出の多い方におすすめです。カメラつきで音声のやり取りもできるので、コミュニケーションを図りながら、おやつをあげることができるので人気です。また、慣れるまでは遠隔カメラを活用して、お留守番がちゃんとできているか確認してみることをおすすめします。インターフォンの音が無駄吠えのきっかけになるケースも多いので、普段から音に慣れるようなトレーニングもしておきたいものです。騒音問題は、ペットに限ったことではなく、集合住宅の大きな課題です。犬だから吠えるのが当然と考えるのではなく、できることをしましょう」(ペットホームウェブ・有瀧さん)
【おすすめアイテム】
・遠隔操作でおやつが出せるコミュニケーションツール

Furbo「ドッグカメラ」2万7000円
https://shopjp.furbo.com/
問い合わせ先 hello.jp@furbo.com

「お留守番中のペットを見ることができるカメラですが、ペットが吠えたり寝起きしたりすると、スマホにアラートが出て確認できたり、遠隔操作でおやつをあげることができます」
ペットとの生活は楽しいことや癒されることもたくさんありますが、飼い主がすべきことも多くあります。お部屋に一番長くいるのはペットですから、ペットが快適にストレスなく過ごせるように考えて飼いましょう。
※価格はすべて税抜です
【プロフィール】

ペットホームウェブ https://www.pethomeweb.com
「ペットを飼っているみなさんが、引越し先を探すのに苦労している現状を変えたい!」という思いからはじまった、ペットと住まいの総合情報サイト。ペット可物件の検索では、業界最大掲載数の全国約27万件のペット可賃貸から、大型犬・中型犬・小型犬・猫からの絞り込みができます。
監修=ペットホームウェブ 取材・文=吉川愛歩 構成=Neem Tree
何気ない日常を、大切な毎日に変えるウェブメディア「@Living(アットリビング)」