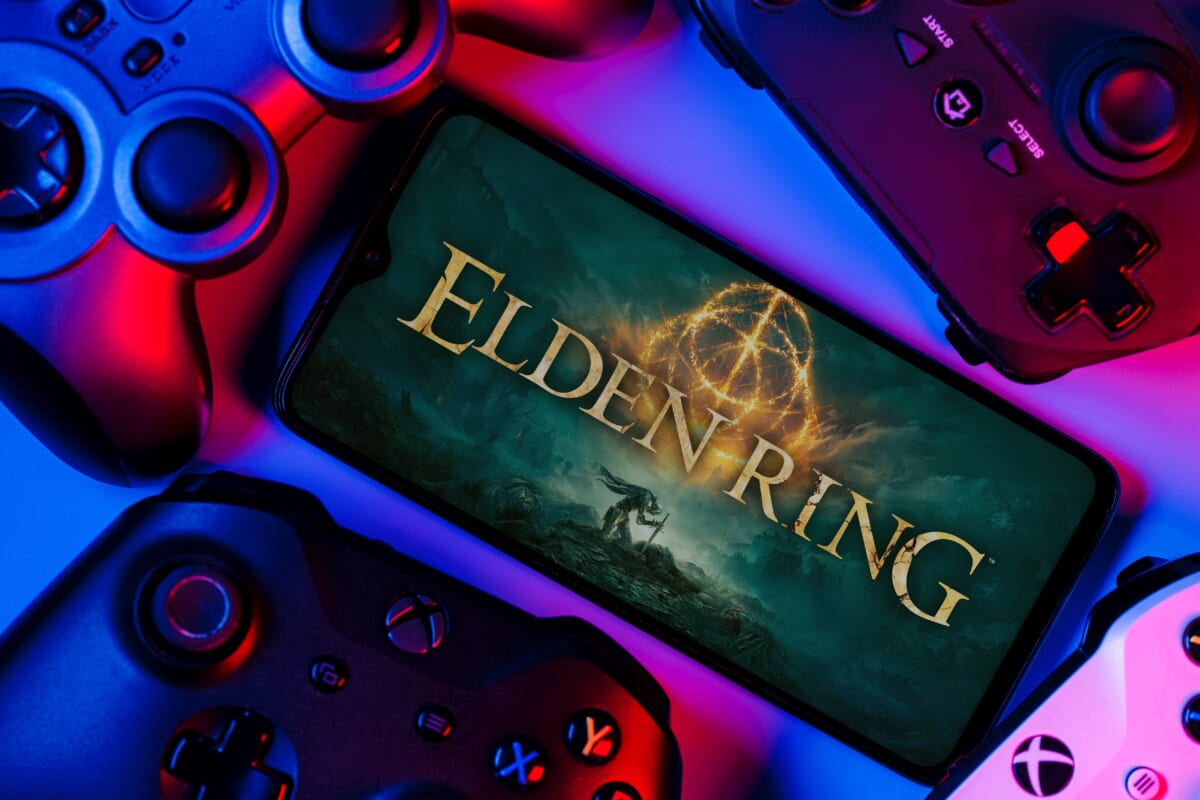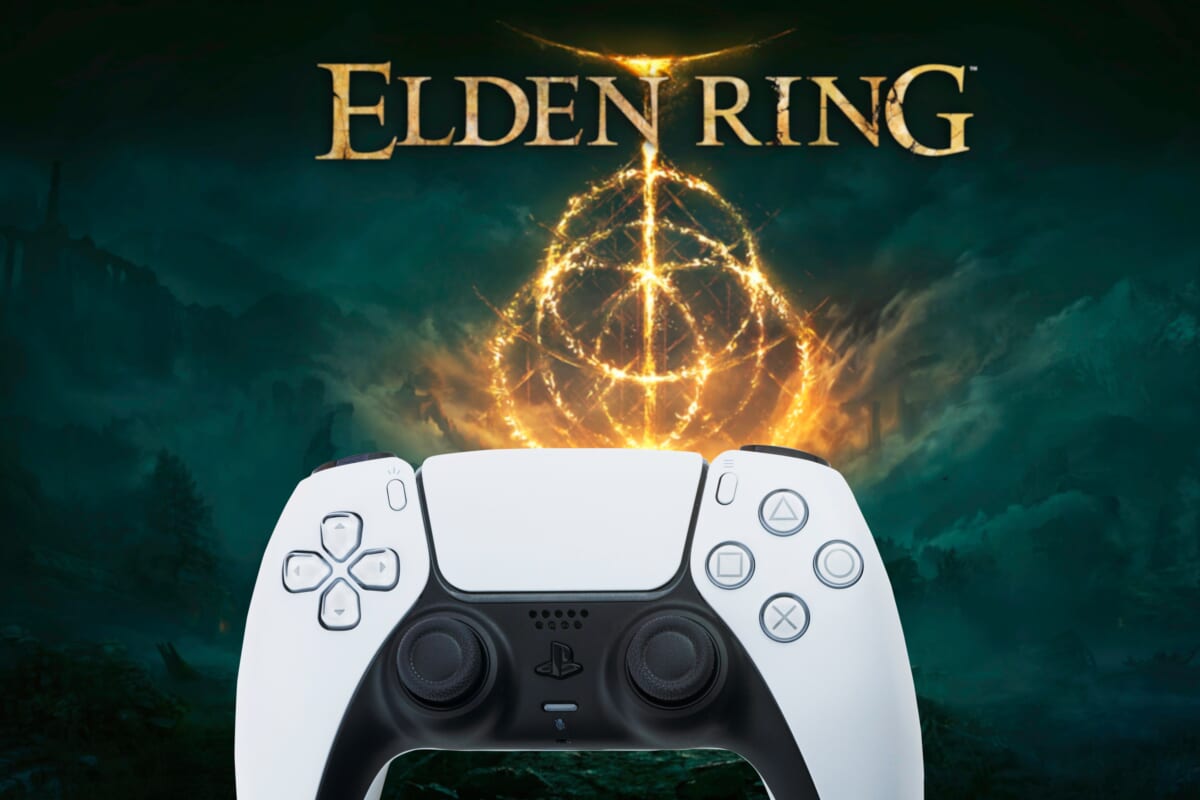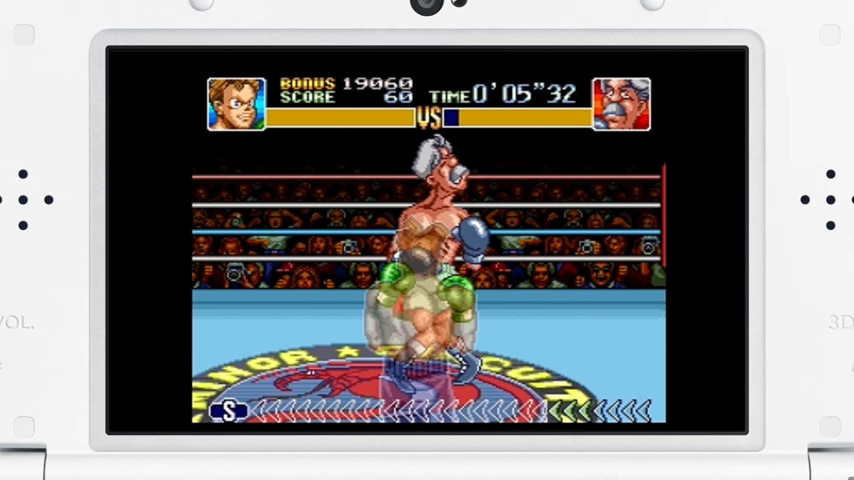かつて『ポケットモンスター』のテレビアニメが初めて放送された当時、子供たちには劇中さながらのオモチャ「ポケモン図鑑」が大人気でした。赤い電子手帳型であり、十字ボタンや各種ボタンが付いており、ポケモンのデータを見ることができました。

それから20年以上が経過したいま、あるYouTuberがポケモン図鑑を自力で作成し、ChatGPTを入れてフィギュアやオンライン画像のポケモンを識別できるようにしました。
元GoogleのエンジニアであるAbe Haskins氏は、実際に動くポケモン図鑑(英語では「Pokedex」)を自作する作業を紹介した動画をYouTubeに公開しています。
Haskins氏は、アニメや漫画、SFに登場するアイテム実生活で再現する製品の大ファンではあるものの、それらは見かけが似ているだけで、ほとんど役に立たないと指摘。そこで、実際に機能するポケモン図鑑を作ろうと思いついたと語っています。
このプロジェクトの目標は3つ。アニメに出てくるポケモン図鑑と同じ見た目にすること、ほとんどの場合にポケモンを認識できるようにすること、そしてアニメに出てくるのと同じ機械音声にすること。その計画の簡単なスケッチを描いてから、すぐHaskins氏は作業に取り掛かりました。
まず、ボディとなる長方形の赤いケースを3Dプリント。このケースに、ポケモンを視覚的に捉えるカメラや機械音声用のスピーカー、バッテリーや基板などを収納しています。
そしてポケモンの識別は、ChatGPT-4が担当。OpenAIのツールを使ってカメラが撮影した映像を分析し、ポケモンのデータを取得できるPokeAPIと照合。さらに米国版でポケモン図鑑の声を担当した俳優Nick Stellate氏の声を、AI音声生成ツールPlayHTにより再現し、ポケモンの説明を読み上げさせています。
この自作ポケモン図鑑を開発している途中、表示が文字化けを起こしたり、音声がおかしかったり様々な不具合に出くわしていますが、最終的には満足のいく仕上がりとなっています。ポケモンのぬいぐるみを上手く識別できていませんが、アクションフィギュアやオンライン画像を認識することはできました。
Haskins氏は、これは信じられないほど難しいプロジェクト遭ったと振り返っています。YouTubeのコメント欄でも多くの称賛が寄せられており、その中には「販売する予定はないの?」という声もあり。
が、ご本人の答えはノーです。「私が目指すことは、人々が自分のプロジェクトに取り組むよう励ますことです。単に、私が作ったものを買うことではありません。それは楽しくない」とコメントしています。
ポケモン関連、しかも実在したオモチャ再現したものを販売するのは、権利的にも問題があるはず。ひとまず、Haskins氏の頑張りに拍手を送りたいところです。
Source:abe’s projects(YouTube)
via:Kotaku
※Pokedexの1つ目のeは、アキュートアクセント付きが正式な表記です




 (@lipilipsi)
(@lipilipsi) 
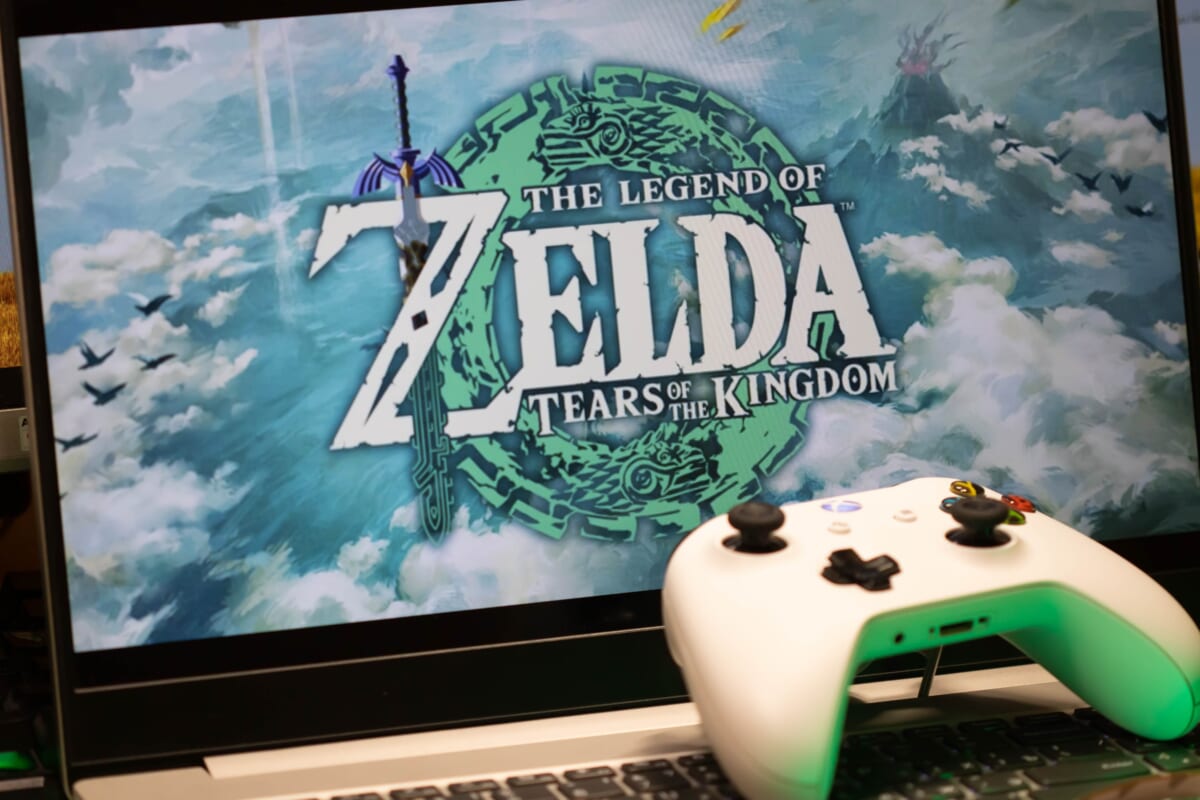
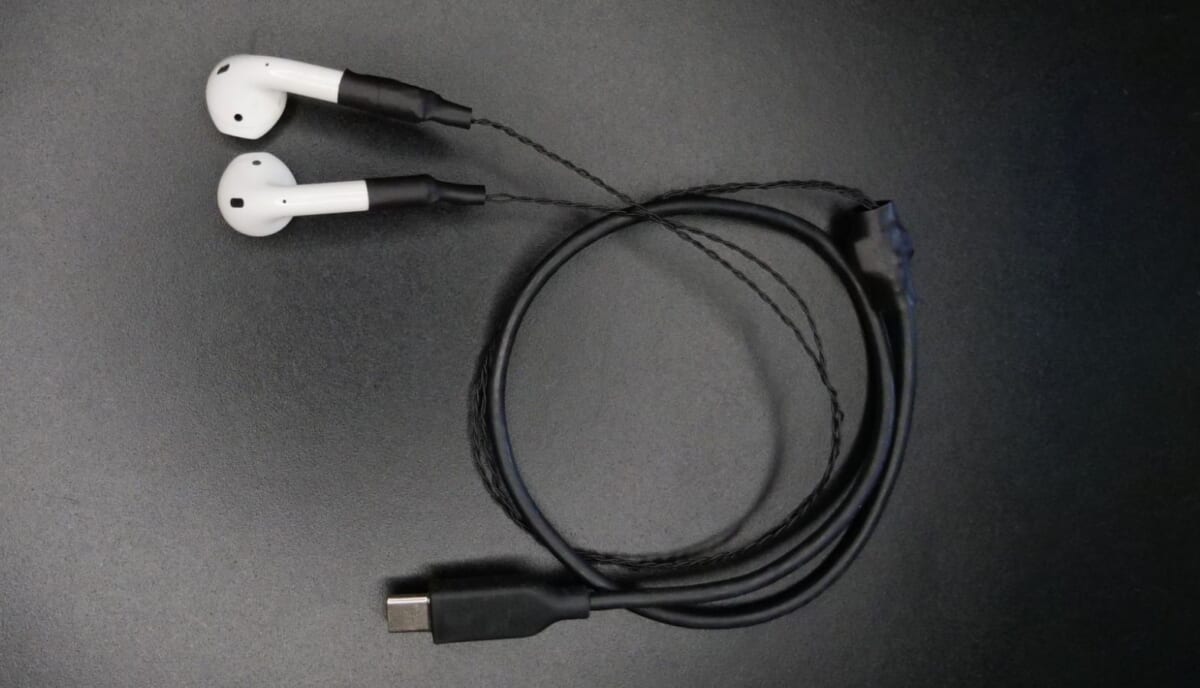








 (@lipilipsi)
(@lipilipsi) 

 (@czr_drums)
(@czr_drums)