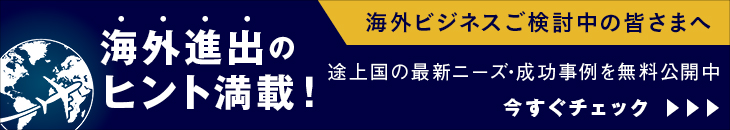経済成長の目覚ましい国として注目されるバングラデシュ。2021〜2022年度の実質GDP成長率が6.4%、2023年度も6.1%と、安定的に成長しています。しかし、そんな同国で現在、大気汚染が悪化中。人々の健康や経済成長にまで悪影響を及ぼしつつあるのです。

世界銀行は先日、バングラデシュにおける大気汚染に関する報告書(※)を発表しました。その内容によると、大規模な建設が行われ、交通量の多い首都ダッカ市内で最も大気汚染が進んでおり、微小粒子状物質(PM2.5)はWHOのガイドラインを平均で150%も上回っているとのこと。これだけ大気が汚染されている状態は、毎日1.7本のたばこを吸うのに相当するそうです。大気汚染は同国全土に広がり、全ての地域でWHOのガイドラインの推奨レベルを超えるPM2.5が観測され、バングラデシュ国内で最も空気がきれいと言われるシレット管区でさえもガイドラインを80%上回るPM2.5が観測されています。
大気汚染によって最も懸念されるのが健康被害。同報告書によると、大気汚染は、ぜんそく、肺炎、肺機能の低下といった下気道感染症の原因になるとされています。PM2.5の量がWHOのガイドラインのレベルを1%上回ると、呼吸困難を感じる割合が12.8%、湿った咳(痰の出る咳)が出る割合は12.5%、下気道感染症にかかるリスクは8.1%高くなるとのこと。また、交通渋滞が頻繁に起きたり大規模な建築工事が行われたりする場所では、住民の精神衛生にも悪影響が及び、鬱になる可能性が20%高くなると指摘されています。
実際、バングラデシュにおける死亡と障がいの原因で2番目に多いのが大気汚染。2019年には大気汚染が原因で8万人前後が亡くなったと言われています。また、バングラデシュの大気汚染がひどい地域に暮らす子どもたちの間で、下気道感染症の発症率が著しく高くなっていることが明らかとなりました。
世界銀行の報告書をまとめたWameq Azfar Raza氏は、「バングラデシュの都市化と気候変動によって、大気汚染はさらに悪化する」と指摘。大気汚染と気候変動による健康への被害に対処しなければならないと述べ、大気汚染状況の監視システムや、公衆衛生の各種サービスの充実・改善など、早急な対応を勧めています。
その一方、大気汚染は経済成長にも影を落としかねません。2019年のバングラデシュの国内総生産(GDP)は、公害によって3.9~4.4%下がったと世界銀行の報告書ではまとめられています。世界銀行のバングラデシュ・ブータン担当のDandan Chen氏が「大気汚染は子どもから高齢者まで、あらゆる人を危険にさらす」と述べているように、すべての世代の健康状態を悪化させ、それによって労働人口が減るなど経済成長にも影響を及ぼしていく可能性があるでしょう。
「バングラデシュの持続可能で環境にやさしい経済の成長と発展のためには、大気汚染への対応が非常に重要」と、Chen氏は述べています。
高度経済成長期(1955〜1970年代初め)に各地で公害が発生した日本を含めて、先進国は経済の生産性が大きく向上していく過程で大気汚染のような公害を起こしてきました。日本では住民の声を背景に自治体が努力して、公害の原因とされる企業と公害防止協定を結んだと言われていますが、そのような経験をバングラデシュにも生かすときかもしれません。
※【出典】Raza,Wameq Azfar; Mahmud,Iffat; Rabie,Tamer Samah. Breathing Heavy : New Evidence on Air Pollution and Health in Bangladesh (English). International Development In Focus Washington, D.C. : World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/099440011162223258/P16890102a72ac03b0bcb00ad18c4acbb10
読者の皆様、新興国での事業展開をお考えの皆様へ
『NEXT BUSINESS INSIGHTS』を運営するアイ・シー・ネット株式会社(学研グループ)は、150カ国以上で活動し開発途上国や新興国での支援に様々なアプローチで取り組んでいます。事業支援も、その取り組みの一環です。国際事業を検討されている皆様向けに各国のデータや、ビジネスにおける機会・要因、ニーズレポートなど豊富な資料もご用意しています。
なお、当メディアへのご意見・ご感想は、NEXT BUSINESS INSIGHTS編集部の問い合わせアドレス(nbi_info@icnet.co.jp)や公式ソーシャルメディア(Twitter・Instagram・Facebook)にて受け付けています。『NEXT BUSINESS INSIGHTS』の記事を読んで海外事情に興味を持った方は、是非ご連絡ください。