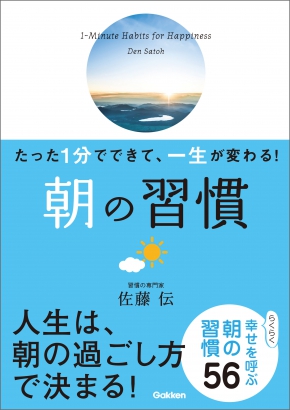天才といえば、破天荒な人生や不規則な生活というイメージがあります。どれだけ才能があるからといって、乱れた生活を送っている人が、はたして偉業を成し遂げることができるのでしょうか?
『天才たちの日課』(メイソン・カリー・著、金原瑞人・翻訳、石田文子・翻訳/フィルムアート社・刊)という本を読むと、じつは天才たちには規則正しいマジメ人間が多いことがわかります。

大文豪トルストイの金言
「私は毎日書かなければならない。それは成果をあげるためではなく、習慣を失わないためだ」
レフ・トルストイ(小説家)
(『天才たちの日課』から引用)
トルストイは、19世紀を代表するロシア文学者です。前述のフレーズは、代表作のひとつ『戦争と平和』を執筆していた当時の日記に書かれていました。
1日のスケジュールは……朝9時すぎに朝食をとったあと、トルストイは紅茶をもって書斎にこもってひたすら執筆。夕方には仕事を終えて、深夜一時に眠りにつくまでは、家族との時間を過ごしていたそうです。
偉業は一夜にして成らず。成果として認められるかどうかは気にせずに、やめないこと、ひたすら続けることが成功の秘訣です。
詩人のイェーツは悪魔に○○○を与えた
「人は生きるために おのれの一部を悪魔に与えなければならない」
W・B・イェーツ(詩人)
(『天才たちの日課』から引用)
イェーツは、20世紀を代表するアイルランド生まれの詩人です。のちにノーベル文学賞を受賞するほどの偉大な芸術家ですが、詩を書くだけでは生計を立てられませんでした。
じつは、前述のフレーズには「私は批評文を与える」という言葉が続きます。イェーツは、詩作のかたわらに文芸批評を寄稿して生活費を稼いでいたからです。
詩人といえば夢見がちと思われがちですが、じつは現実主義者が少なくありません。たとえば、ノーベル賞受賞者である詩人のT・S・エリオットは、銀行員としての生活を「退屈だが気楽でいい」と述べていました。おなじく20世紀を代表するアメリカ詩人のウォレス・スティーヴンズは、保険会社の社内弁護士として定年まで勤めました。
天才といえば「変人」と思われがちですが、意外なことに「まともな人」が多いです。あえて「変わったところ」を探すならば、それは食生活に見出すことができます。
偉大な映画監督は○○○でハイになる
ここ七年間、食事はビッグボーイでとっている。行くのは二時半ごろ。昼の混雑が一段落したあとだ。チョコレートシェイクを一杯と、コーヒーを四杯か五杯か六杯か七杯──砂糖をたっぷり入れて飲む。チョコレートシェイクにも砂糖がたっぷり入っている。
(中略)
大量の砂糖でハイになると、アイデアが次々に湧いてくるんだ。
デイヴィッド・リンチ(映画監督)
(『天才たちの日課』から引用)
リンチ監督に負けないほどの甘党といえば、哲学者のキルケゴールです。コーヒーを飲むときには、カップのなかに砂糖を山盛りに積み上げて、その頂上から濃いコーヒーを注いだものを好みました。キルケゴールの嗜好は、まさに『死に至る病』です。
作曲家のベートーヴェンは、仕事をするときに飲むコーヒーをいれるため、1杯につき「60粒のコーヒー豆」を数えていた時期があったそうです。インスピレーションを得るために必要だったのでしょう。
習慣の奴隷になろう!
私がとくに注目したのは、人々の”ルーティン”すなわち日常的な習慣だ。
“ルーティン”という言葉には、「平凡さ」や「思考の欠如」といったニュアンスがある。習慣に従うことは惰性で動くことだ。しかし個人の毎日の習慣は、ひとつの選択、または一連の選択の結果でもある。
(『天才たちの日課』から引用)
本書『天才たちの日課』には、変人にまつわるエピソードも収録されています。しかし、その変人たちですらルーティン、つまり規則正しい生活を繰り返しています。天才や革新者のイメージに反して、早朝に起きて仕事をはじめる「朝型人間』が過半数を占めています。
ほとんどの天才たちは、きちんと仕事を終えてからお酒を飲みます。なるべく愛する人や家族と過ごすようにしていました。推理作家のアガサ・クリスティは、家事をおろそかにせず、スキマ時間をつかって数々の名作ミステリを書き上げています。
本書『天才たちの日課』は、100名以上の天才たちの伝記やインタビューにみられる「習慣」をまとめたものです。読み進めるほどに、無秩序や破天荒だと言われていた天才たちが、じつは「習慣の奴隷」であったことを思い知らされます。お試しください。
【書籍紹介】
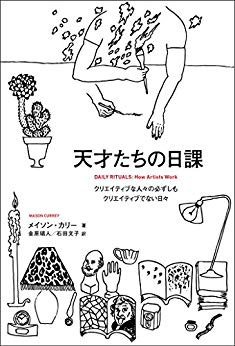
天才たちの日課
著者: メイソン・カリー
発行:フィルムアート社
偉人たちも、いや偉人たちこそ、最高の仕事をするために、毎日どう時間をやりくりし、どう過ごせば創造性や生産性を高められるかを悩んでいました。彼らはどう解決していたのでしょうか。そのヒミツは日常のごく平凡な小さな積み重ねにあったのです! 本書では、古今東西の小説家、詩人、芸術家、哲学者、研究者、作曲家、映画監督など161人の天才たちの、これまで見過ごされてきた「仕事の周辺」に注目。起床時間、就寝時間といった毎日のスケジュール、部屋での様子や生活信条、仕事の際のクセやこだわり、嗜好品をまとめることで見えてきた、知られざる素顔や意外な事実は、驚きとともに、創造的な活動を続けるための秘訣に値する手がかりが満載でした。