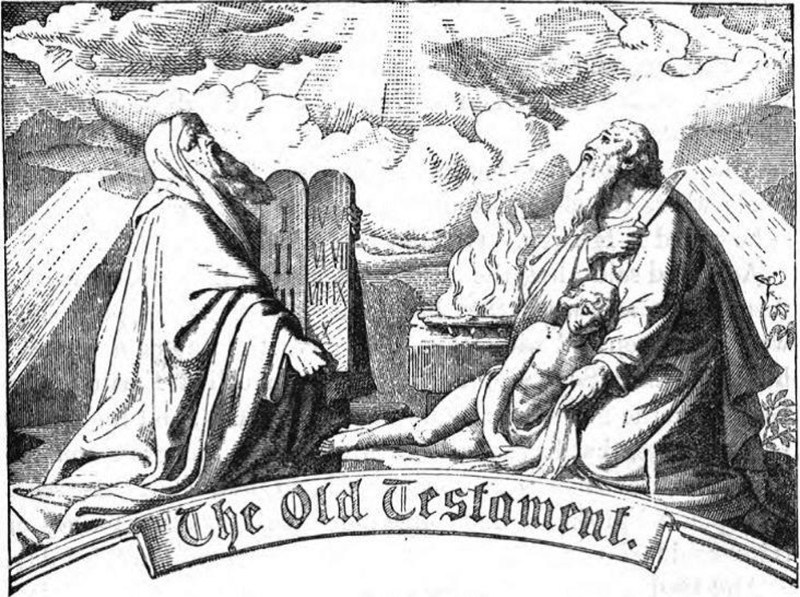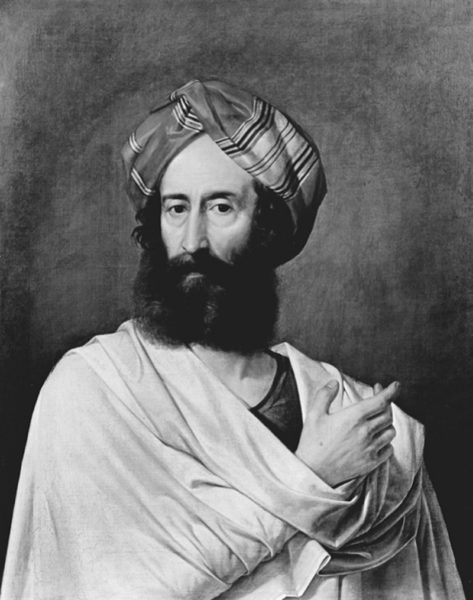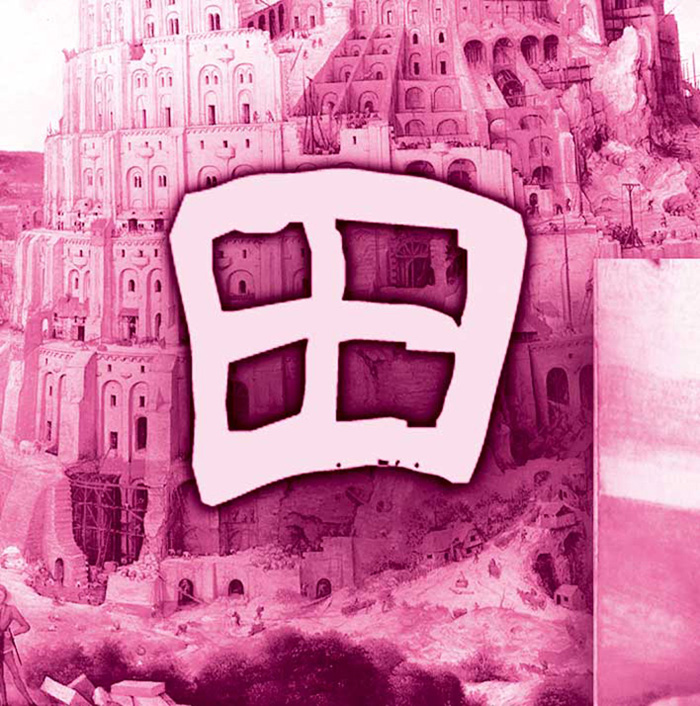筆者は、英米のニューエイジ系作家が書いた文章を訳すことが多い。これまでかかわった作家たちに共通する特徴は意外に数字にこだわること、そして当然のことなのだろうが、聖書からのクォーテーション=引用=がとてもうまいことだ。

読み物としての聖書
本気で聖書を読もうと思ったのは、32歳の時だ。フリーになって半年後、初めて一冊通して訳すというお仕事をいただいた。『天使の辞典』というタイトルで、さまざまな聖書の記述を何回も確かめる必要があった。
最初こそ面倒くさいという気持ちを抑えながらの作業になったが、終わる頃には、聖書の読み物としての面白さに目覚めていた。これはちょっといいな、というお気に入りの言葉もいくつかできた。
東洋思想の専門家が語る聖書
『聖書の名言100』(綾瀬凛太郎・著/学研プラス・刊)の著者、綾瀬凛太郎さんの専門分野は原始仏教、密教、禅、チベット仏教などだ。まえがきで“専門外”の聖書について論じる姿勢を次のように記している。
聖書というのは、ある意味、人がどう生きるべきかを、膨大な言葉の積み重ねによって明らかにしようとした書物だと思う。
今回、門外漢にもかかわらず、無謀にもその解読に乗り出したわけだが、門外漢だからこそ見える側面もあるかもしれない。『聖書の名言100』より引用
東洋思想の専門家が語る聖書の言葉。アプローチとして非常に興味がある。聖書の専門家の口からは出ないだろう言葉の数々を期待できそうだ。
「わたしをおいてほかに神があってはならない」
『出エジプト記』:20章3節に記されている言葉だ。エジプトを出たモーセがシナイ山で神から授かる十戒の最初の項目でもある。一神教であるキリスト教を象徴するような言葉に対し、綾瀬さんは次のように語る。
さて、聖書を読めば読むほど、聖書の神が一神である理由がわからない。わからないが、とにかく神がほかにあってはならないというのだ。しかも、これに続けて、「いかなる像も造ってはならない」という。いわゆる偶像崇拝の禁止だ。
『聖書の名言100』より引用
キリスト教の神こそが唯一無二の存在であり、ほかの宗教に対する排他的な響きも感じられる。
偶像崇拝を否定したのは、おそらく神を限定的に、誤ってとらえてしまうことを危惧したからだろうが、それにしても徹底してきびしい突きつけ方である。
『聖書の名言100』より引用
はっとした。キリスト教特有の――と少なくとも筆者は思っていた――排他的な姿勢を示すだけに感じられた言葉の裏側に、「神を限定的に、誤ってとらえてしまうことへの危惧」が介在している可能性は考えてもみなかったからだ。
「地上に富を積んではならない」
『マタイによる福音書』:6章19節、『ルカによる福音書』:12章33節に出てくる言葉。地上的な価値観にとらわれないという意味で、さまざまな宗教で命題とされている言葉だが、綾瀬さんによれば「これほど簡単でこれほど難しいこと」はないという。
一般に、キリスト教では清貧を尊ぶと思われているし、実際イエスの言葉にもそうした傾向がある。が、たんに貧乏なほうがいいというのではなく、ここでは富に執着するなといっているのだろう。
『聖書の名言100』より引用
まえがきに書かれている「門外漢だからこそ見える側面」という言い方のニュアンスがよく出た文章だと思う。歴史に名を残すような宗教家なら清貧も不可欠な要素かもしれない。でも、一般人にまでそれを求めるのは酷だ。あまりに貧しければ、心まで貧しくなってしまうかもしれない。
貧しさをよしとすることと、富に執着しないということはまったく別である。筆者はこれまで、自分勝手な想像の中で、キリスト教のありもしない極端な特質を創り上げていたようだ。
「常に喜びなさい」
『フィリピの信徒への手紙』:4章4節に出てくる言葉。口角が下がりきっている人。決してそういうつもりではないのだろうけれど、にらみつけるような視線を送ってくる人。こういう人は、電車の中でもスーパーのレジ待ちの列でも見る。綾瀬さんは言う。
不況もある。大気汚染もある。町には失業者があふれ、安心して食物も食べられない。どこをみても不安と疑惑、あきらめや憎悪が渦巻いている。こんな環境でいったいどう喜べばいいというのか。いやこんな環境だからこそ、喜びが求められているのだ。そしてそれは、きわめて有効な手段なのである。
『聖書の名言100』より引用
日々の生活の中でこそ生きる聖書の言葉
日常に落とし込んで、聖書の言葉の意味を説明していく。まえがきのとおり、聖書が「人がどう生きるべきかを膨大な言葉の積み重ねによって明らかにしようとした書物」であることを具体的に示してくれる。
筆者は、聖書の読み物としての面白さを改めて感じることができた。この本を手に取る人たちの多くが、同じように思ってくれるだろう。最後に、筆者が一番好きな聖書の言葉を紹介しておきたい。
「旅人をもてなすことを忘れてはならない。このようにして、ある人々は、気づかないで御使(みつかい=天使)たちをもてなした」(『へブル人への手紙』:13章2節)
みなさんも、自分だけのお気に入りの言葉を見つけてみませんか?
【著書紹介】

聖書の名言100
著者:綾瀬凛太郎
出版社:学研プラス
「なんじの敵を愛せ」「心の貧しき人は幸いなり」「人はパンのみに生きるにあらず」「求めよ、さらば与えられん」……など、旧約聖書・新約聖書から心をうつ100の名言を厳選紹介。ユダヤ、キリスト教3000年の知恵による、生き方のヒントを学ぶ本!
Kindleストアで詳しく見る
楽天Koboで詳しく見る
iBokksで詳しく見る
BookBeyondで詳しく見る