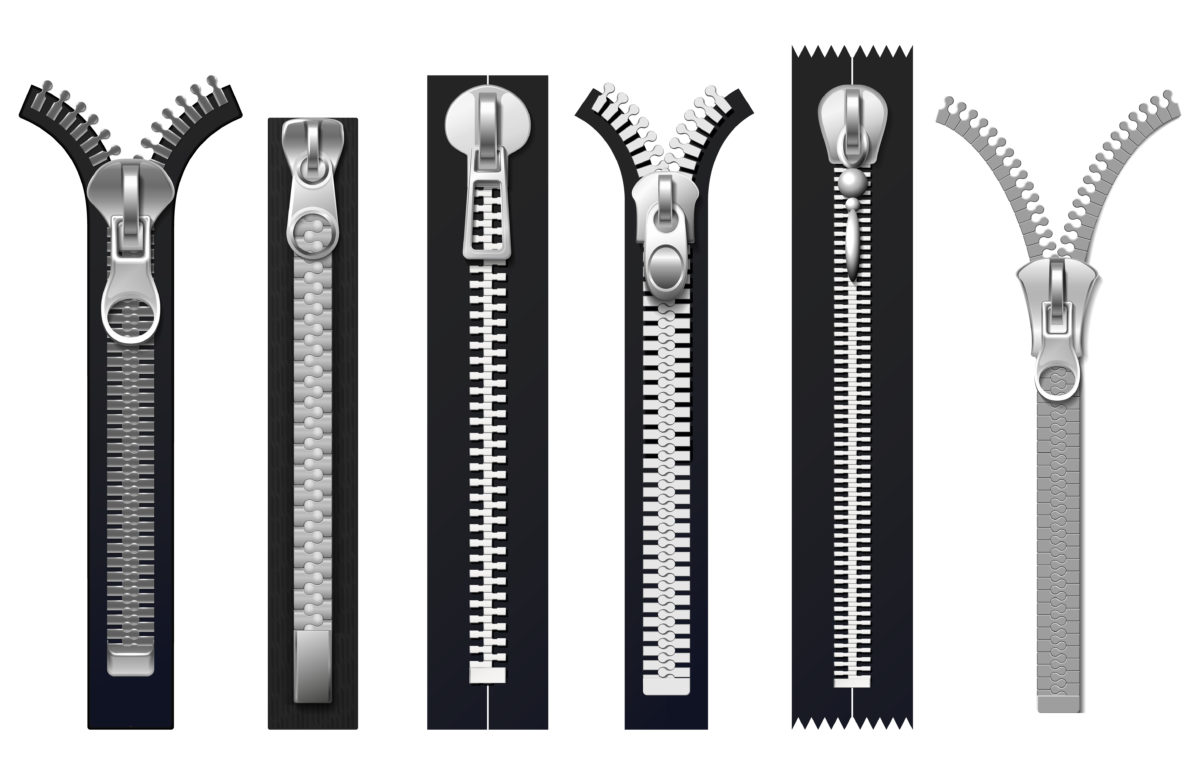学研プラスの「まんがでよくわかる ひみつシリーズ」。食品や工業製品に職業、果ては自治体まで、様々な「ひみつ」についてまんがでわかりやすく解説したこのシリーズ、じつはインターネットがあれば無料で読めることを知っていますか? 2学期開始直前、まだ自由研究に手がついていないという方々のために、いくつか紹介していきましょう。
トンネルのひみつ

<日本のトンネル技術は世界一ィィィ! あなたの知らないトンネルの世界――『トンネルのひみつ』>では「トンネルのひみつ」の中から、世界のトップレベルにある日本のシールド工法について紹介しています。
トンネルには大きく分けると、地中に掘るトンネルと、山の中に穴を開けるトンネルがある。日本は、地盤が柔らかいために地中のトンネルを掘るのが難しく、大きな事故も起きている。
しかし、現在の日本のトンネルの技術は世界でもトップレベルと言われている。特に、地中トンネルを掘るための「シールド工法」は、海外でも採用され、世界一の長さを誇る海底トンネル「英仏海峡トンネル」にも、日本のシールド工法およびシールドマシンが用いられている。
そのほかにも、いろいろな工法の紹介など「トンネルのひみつ」を読めば、いままで気になっていたトンネルについての疑問が解決するはずです。
「トンネルのひみつ」 https://bpub.jp/bookbeyond/item/000405916936/
お化粧のひみつ

そもそも人間はなぜ化粧をするようになったのでしょうか?
古代エジプト人は目のまわりに黒いふちを描いていましたが、これには2つの意味があったといいます。1つ目は太陽の光の反射を少しでも防ぐためで、現在、スポーツ選手が目のしたに“アイブラック”を入れているのと同じ。
そして、もうひとつの理由は信仰のため。古代エジプト人は「太陽は神さまのシンボル」と考えていて、その太陽が人の体の中では「目」にあたり、目には神さまが宿っていると信じていたのです。だから目を大切にし、まわりを黒くぬっていたようです。
<ビジネスシーンでは男性も化粧が不可欠? 歴史からひも解くメイクの意味>で紹介した「お化粧のひみつ」ではこのような歴史から、化粧品はどうやって作られるのか? メイクアップ・アーティストの仕事とは? そして、どうしたらメーキャップアップアーティストになれるのか? まで興味深い内容が満載です。
「お化粧のひみつ」https://bpub.jp/bookbeyond/item/000405914958/
歯ブラシづくりのひみつ

歯ブラシは決まったものを使っているよ! という方も多いかもしれませんが、選ぶ基準は人それぞれ。では、「やわらかめ」「ふつう」「かため」は、どういう基準で決められているかってご存知ですか? <歯ブラシが一番売れるのは12月! あなたの歯ブラシは、かため? ふつう? やわらかめ?>で紹介した「歯ブラシづくりのひみつ」によると
歯ブラシのヘッド部分の穴の大きさは「かため」も「やわらかめ」も同じ。毛のかたさは、穴に植える毛の太さを変えて調節しています。小さな力でも曲がりやすい細い毛を植えるとやわらかめに、曲がりにくい太い毛を植えると「かため」になるとのこと。
知っているようで知らない歯ブラシについて「歯ブラシづくりのひみつ」を読んで調べてみてはどうでしょう。
「歯ブラシづくりのひみつ」https://bpub.jp/bookbeyond/item/000405915805/
いなり寿司のひみつ

なぜ「いなり」が、油揚げのことを指すのでしょうか? いなり寿司の語源は、稲荷信仰に関わりがあると言われています。稲荷神社は、日本全国の神社のうち3割以上を占めており、まつられているのは「五穀豊穣の神さま」です。その使いであるキツネの好きなものが「油揚げ」だと信じられているから……という説があります。
<いなり寿司がすぐできる! キミは「味付けいなり揚げ」の存在を知っているか?――『いなり寿司のひみつ』>で紹介している「いなり寿司のひみつ」には、いなり寿司の由来から、地方ごとのいなり寿司の形や具材の違いなども解説されています。
たとえば、酢飯の味付け。関東は「白い酢飯」ですが、関西は「五目ちらし酢飯」を詰めます。東北地方の青森県では、紅しょうがで味付けした飯を詰める「ピンクいなり寿司」が有名です。地域によっては、米飯を詰めるとは限りません。代わりに「おから」を詰めるところもあれば、お蕎麦やソーメンを詰めるところもあります。
歴史や地方ごとの特色を調べつつ、自分で作ってみると幅の広い研究になるかもしれません。
「いなり寿司のひみつ」https://bpub.jp/bookbeyond/item/000405916999/