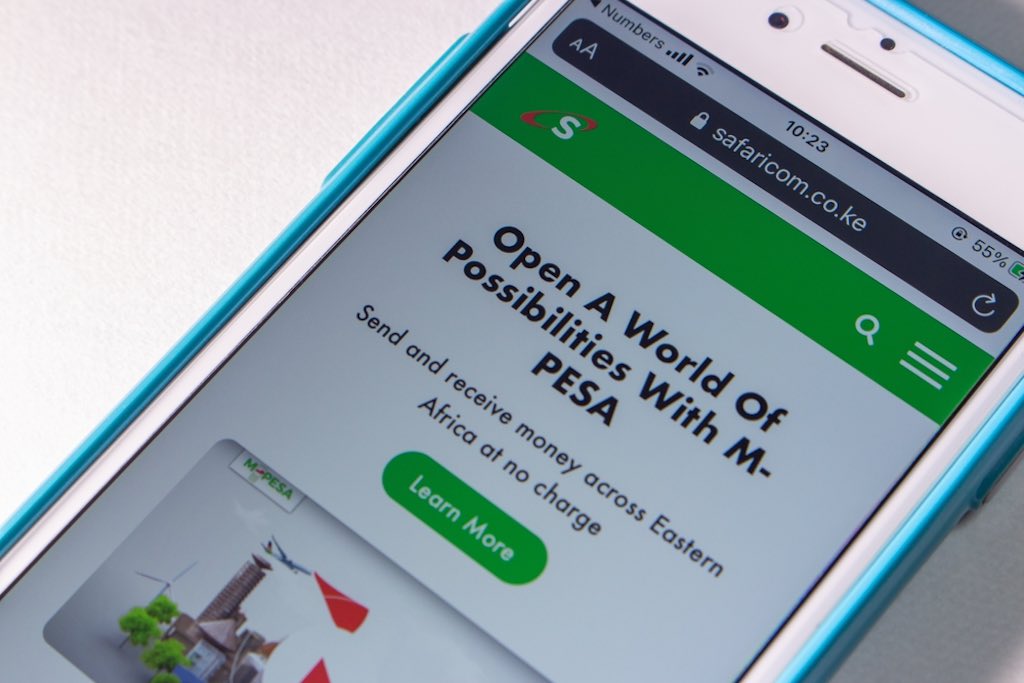現在、アフリカでは史上最悪の食料危機が起きており、多くの人たちが飢饉に苦しんでいます。専門家の間ではアフリカの農業をもっと発展させなければならないという危機感が募るとともに、国際的な支援の重要性もますます高まっています。日本企業がアフリカの農業に目を向けるべき理由はどこにあるのでしょうか? 大きく4つの可能性が考えられます。

1: 衰えない農業の市場規模
一つ目の理由は、アフリカにおける農業の市場規模が高いまま維持されているから。アフリカで農業がGDP(国内総生産)に占める割合は約35%で、世界銀行によると、この割合は数十年間変化がありません。他の新興国に目を向けてみると、農業の規模は縮小している所が多くあります。例えば、1970年の東南アジア諸国では農業がGDPの30~35%程度を占めていましたが、2019年には10~15%までに低下しました。アフリカでは今後も農業の市場規模が維持されていくと見られており、日本の企業が参入できる可能性は大きいと言えそうです。
2: 工業化に転じない可能性
経済は、農業のような一次産業から工業や製造業といった二次産業に発展することが一般的ですが、アフリカは必ずしもそれに当てはまりません。国際ビジネスを専門とするニューヨーク市立大学バルーク校のライラック・ナフーム教授は農業がアフリカ経済を牽引すると主張しており、その理由の一つとして「製造業を中心とした成長にはインフラが必要だが、アフリカのインフラは整っていない」と指摘しています。実際、エチオピアやモロッコなどの一部の例外を除いて、アフリカの多くの国で製造業を確立することが実現できていないので、他の新興国が辿ってきた発展のプロセスを踏む可能性は低いと考えられます。それゆえに、アフリカは持続可能な農業の形を模索することができるのかもしれません。
3: 栽培に適した広大な土地
アフリカには豊かな土地があることも、日本企業がアフリカ進出を検討すべき理由の一つに挙げられます。アフリカの国土は、中国、インド、アメリカ、ヨーロッパなどの国々の合計よりも広く、その半分以上は耕作が可能な土地と言われています。そこで栽培されたカカオやコーヒー、紅茶などはアフリカを代表する作物であり、最高級品質のものが世界中の市場に輸出されています。
近年、アフリカでは気候変動によって水不足や洪水などが起きることが多くなり、農業への影響が懸念されるようになりました。農業を守るためには、例えば、水が不足する時期の灌漑用水の確保や、効率的な栽培技術の発展などの技術革新が必要でしょう。また、きび、ひえ、あわなどの雑穀は、比較的過酷な環境下でも栽培しやすく栄養価も高いことから、国連を中心に注目が高まっています。作物を育てるのに適した気候と十分な土地があるアフリカに適しているかもしれません。
4: 求められる生産性の改善
アフリカの農業は、使用している機械の量が世界で最も少なく、生産性が世界最低のレベルであると指摘されています。その一因は、アフリカの農家の大半が、自分や家族が生活する分だけの作物を栽培する小規模農家であること。国際農業開発基金によれば、サハラ以南のアフリカの平均農地面積は1.3ヘクタールで、中米の22ヘクタール、南米の51ヘクタール、北米の186ヘクタールと比べると数十倍から百倍以上の差があります。また、小規模農家の多くは貧しく、機械を購入できるほどの資金がないことも生産性が低い原因と考えられますが、経済的な自立を支援していくためには、生産性を上げることが欠かせないでしょう。だからこそ、人口の半数以上が農業に従事しているとされるアフリカでは、日本のように人手不足を補う効率化ではなく、農業の作業を効率化して生産性を上げる技術やサービスが求められると考えられます。
国連食糧農業機関(FAO)が2021年に発表したデータによると、アフリカでは5人に1人にあたる2億7800万人が飢餓に直面していたとのこと。アフリカの農業はカカオやコーヒーといった作物を他国に輸出している反面、多くの国が輸入に依存しており、食料自給率が低いことも課題となっています。従来の「自分たちが食べる作物だけを育てる」という小規模農業から、生産性の高い農業にシフトすることは、このような状況を改善し、より多くの人々の利益につながっていくことが期待されます。しかし、この変化を起こすためには、日本などの政府による支援と、技術や知見を持った企業の関わりが必要不可欠でしょう。
読者の皆様、新興国での事業展開をお考えの皆様へ
『NEXT BUSINESS INSIGHTS』を運営するアイ・シー・ネット株式会社(学研グループ)は、150カ国以上で活動し開発途上国や新興国での支援に様々なアプローチで取り組んでいます。事業支援も、その取り組みの一環です。国際事業を検討されている皆様向けに各国のデータや、ビジネスにおける機会・要因、ニーズレポートなど豊富な資料もご用意しています。
なお、当メディアへのご意見・ご感想は、NEXT BUSINESS INSIGHTS編集部の問い合わせアドレス(nbi_info@icnet.co.jp)や公式ソーシャルメディア(Twitter・Instagram・Facebook)にて受け付けています。『NEXT BUSINESS INSIGHTS』の記事を読んで海外事情に興味を持った方は、是非ご連絡ください。