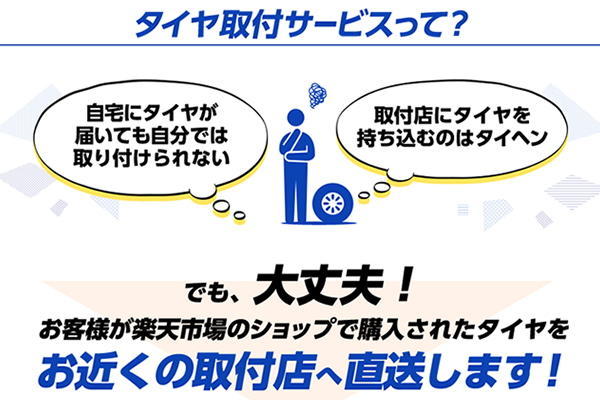2018年型のF1マシンを見て「あれ何?」と思った人がいることだろう。「あれ」の正体は頭部保護装置のHaloだ。日本では「ハロ」の呼称が一般的になりつつある。英語圏の人は「ヘイロー」のように発音し、イタリアの人は「ハロー」と言っている。ここではハロで通す。

ハロは2018年のレギュレーション変更で装着が義務づけられた。ドライバーの頭部を守るためのデバイスだ。ドライバーはすでに頭部を守る目的でヘルメットを被っているが、ダメージを防ぎきれないケースがある。
2009年には当時フェラーリをドライブしていたフェリペ・マッサのヘルメットに、前方の車両から外れたコイルスプリングがぶつかる事故が発生した。ぶつかった場所がヘルメット開口部の縁だったこともあって衝撃を防ぎきれず、マッサは頭蓋骨骨折の重症を負った。この特異なケースに対処するため、11年からはヘルメットのバイザーに強化パネルを接着することが義務づけられた。
もっと大きな部品が飛んできたらどうなるだろう。例えばタイヤとか……。2009年のF2選手権ブランズハッチ戦のレース2では、バリアに衝突した弾みで外れたタイヤが後方を走っていたヘンリー・サーティース(F1チャンピオン、ジョン・サーティースの息子)の頭部を直撃。将来ある若手ドライバーの命を奪った。
2015年のインディカー・シリーズ第15戦ポコノでは、ウォールにクラッシュしたマシンから飛散した大物パーツが、後ろを走るジャスティン・ウィルソンの頭部にあたった。やはり、ドライバーの生命を絶つ結果になってしまった。
■アフリカ象が2頭載っても大丈夫!?

時速200キロを超えるスピードで走っているときに、中身がいっぱい詰まったスーツケースが頭にあたった際の衝撃を想像してほしい。いかにヘルメットを被っていようと、致命的なダメージを防ぐことができないことは、容易に想像できるだろう。ハロは、そうした事故からドライバーを守るために考案され、導入が決まった。
ハロはF1を統括するFIA(国際自動車連盟)が指定する3社が製作し、チームに供給する。チタン合金製で重さは約7kgだ。ハロの装着を見込んで、車両の最低重量は2017年の728kgから、2018年は733kgに引き上げられた。ん? 計算が合わない。車両の他の領域で軽量化を図らないと、車重を最低重量未満に抑えることはできないのだ。
さらに悩ましいのは、ハロは既存の車体骨格にボルトで留めるだけでおしまいではない点だ。例えて言うと、225km/hで走っているときにフルサイズのスーツケースがぶつかっても、びくともしない強度を確保しなければならない。もう少し具体的に説明すると、上方から約12tの荷重を5秒間かけた際に、サバイバルセル(カーボン繊維強化プラスチックでアルミハニカム材を挟んで作った車体骨格)や取り付け部が壊れてはいけない。
言い換えれば、アフリカ象を2頭載せても、ハロ本体のみならず、車体骨格やその取り付け部が壊れてはいけないのだ。そのためには、車体骨格を強化する必要がある。強化すれば重くなってしまうが、そうならないように工夫する必要があるというわけだ。
悩みはまだある。7kgもの重たい部品が車両の高い位置に搭載されることになるので、重心位置が高くなってしまう。低重心化はF1のみならずレーシングカーの生命線だ。どこか1チームではなく全車が平等に負ったハンデとはいえ、設計者にとっては頭の痛い課題だったに違いない。
空力(エアロダイナミクス)にも影響を与えた。ハロはリヤに向かう空気の流れを邪魔することになるので、できるだけ空力的にニュートラルになるよう、開発は行われた。ハロ本体はチタン合金がむき出しになった状態だが、シュラウドで覆ったうえ、ごくわずかな範囲で空力的な処理を施すことが認められている。その細かな処理に、チームの独創性が現れている。

Yの字をしたハロは3点で車体骨格に締結される。ちょうどドライバーの目の前に柱が立つことになるが、視界の妨げにはならないようで、ドライバーにはおおむね好意的に受け止められている。ただ、雨が降り出したときなどはハロが邪魔をしてバイザーにあたりにくくなるため、「わかりにくい」というコメントもあるよう。外からは、ドライバーのヘルメットは見えづらいという指摘がある。
ドライバーの頭部を保護する新しい安全デバイスのハロは、2018年シーズンから、F1に加え、直下のF2にも導入される。日産が参戦することで話題のフォーミュラEは2018年冬から始まるシーズン5から新型マシンにスイッチするが、「Gen2」と呼ぶ新世代マシンもハロを装着することが決まっている。

見慣れないデバイスなので最初は違和感を覚えるかもしれないが、数年経ってハロの付いていないF1を見たときに、「あぁ、昔はこんな危ない状態でレースしていたんだ」と思うに違いない。ヘルメットを被らないでレースすることが考えられないように。
【著者プロフィール】
世良耕太
モータリングライター&エディター。出版社勤務後、独立。F1世界選手権やWEC(世界耐久選手権)を中心としたモータースポーツ、および量産車の技術面を中心に取材・編集・執筆活動を行う。近編著に『F1機械工学大全』『モータースポーツのテクノロジー2016-2017』(ともに三栄書房)、『図解自動車エンジンの技術』(ナツメ社)など