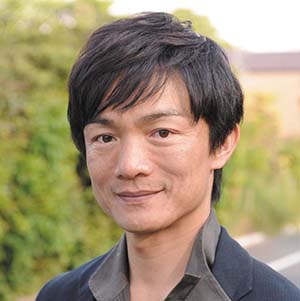ダイハツ「ムーヴ」といえば、スズキ「ワゴンR」と並んで、軽乗用車ハイトワゴンの代表格として知られます。そのムーヴが2025年6月5日、実に10年半ぶりに7代目としてフルモデルチェンジを果たしました。今回は10年にもおよんだその進化のポイントを、試乗レポートを含めてお届けします。

◾️今回紹介するクルマ
ダイハツ/ムーヴ
135万8500円〜(税込)
※試乗グレード:RS、X
全車にスライドドア採用。カスタム仕様はオプションで対応
7代目となったムーヴが、内外装の一新と共に最大のウリとしたのが、全車にスライドドアを採用したことです。これまでハイトワゴンはヒンジドアを採用することがほとんどでした。しかし、ムーヴの姉妹車種である「ムーヴ キャンバス」にスライドドアが採用されると、狭い駐車場で乗り降りしやすい、開口幅の広さなどの理由から大好評。ダイハツによれば、今では軽自動車を求める人の多くがスライドドアを要望するそうです。新型ムーヴがスライドドアを採用したのは、こうした市場の声に応えたものということでした。
プラットフォームはタントなどと同様、最新の「DNGA」を採用し、これが車体の軽量化と共に剛性を高めることにつながり、走行性能を大幅にアップさせています。グレード構成は自然吸気(NA)エンジンモデルに装備を違えた「L」「X」「G」の3種類と、ターボエンジンモデル「RS」の1種類の全4グレード構成。それぞれ駆動方式で2WDと4WDが選ぶことができます。


ただし、ムーヴが初代からラインナップしていた「カスタム」は廃止され、代わりに外観や装備を好みに応じてカスタマイズできるオプション品を充実させた、「アナザースタイル」と呼ばれるパッケージが2タイプ用意されました。一つはブラックを基調としたエンブレムやエアロパーツなどが装備される「DANDYSPORT STYLE」、もう一つは、カッパー色のパーツをアクセントに取り入れて上品な雰囲気に仕立てられた「NOBLE CHIC STYLE」です。カスタム系を好むなら前車の「DANDYSPORT STYLE」がオススメとなるでしょう。
端正なフォルムとAピラーの傾斜で“躍動感”ある新デザインに刷新
ボディサイズは、2WD車が全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mm(4WD車は1670mm)で、ホイールベースは2460mm。全モデルに比べて全高が若干アップしましたが、プラットフォームが同じこともあり、そのサイズはキャンバスにかなり近いといえます。
しかし、前車のデザインの違いは明らか。キャンバスが丸みを帯びた可愛らしさをアピールする一方で、ムーヴはシャープさを伴った“端正で凜々しい”デザインとしています。ムーヴとキャンバスが共にスライドドアを採用したことで、棲み分けが難しいのではないか?との疑問にダイハツは、キャンバスは若い女性ユーザーをターゲットとする一方で、新型ムーヴは子育てを終えてモノを知り尽くした中高年世代を狙っているとの違いを強調しました。
それだけに、新型ムーヴでは少しAピラーを寝かせ、リアのショルダーラインをキュッと持ち上げることで、躍動感を感じさせるデザインとしていることがわかります。フロントフェイスは左右のヘッドライトをグリルでつないで中央部にボディと同色パネルを組み込む新デザインとする一方で、リアは縦型コンビランプを採用してムーヴらしさを継承しています。ボディカラーは全10色。さらにルーフ部のツートーンカラー3色も設定しました。



視認性と質感を両立した内装。グレードごとのカラー&装備差にも注目
インテリアは操作系と視認系をきっちりと上下に分けて使いやすさを感じさせるもので、同時に広い前方視界の確保にもつなげています。シートは全車ファブリックとなるものの、上位グレードとなるGとRSにはシルバーステッチを加えたネイビー色を、XとLには明るいグレージュ色を採用。また、上位グレードとなるGとRSにはダッシュボードの各部にシルバー加飾を与えることでスポーティさを演出しており、この辺りからは従来のカスタム系の名残を感じさせますね。






運転支援も充実。電動スライド・ACC・スマアシの実力を検証
注目のスライドドアについては最上位のRSにのみ両側電動式を採用。GとXは左側のみを電動式とし、右側はメーカーオプションで装備できます。特に電動式では、スライドドアが閉じるのを待たずにドアロックができる「タッチ&ゴーロック機能」が備わります。また、両側電動式装備車になると「ウェルカムオープン機能」が装備され、これは車内の予約設定ボタンを押しておくことで、戻ってきたときに自動的にスライドドアが開くというもの。使ってみるとこの機能は使い勝手が良く、多くの場面で重宝しそうな印象を受けました。なお、最廉価グレードのLにはオプションでも電動式の設定はありません。


パーキングブレーキもグレードによって仕様が違っています。オートホールド機能付き電動パーキングブレーキを採用したのはRSとGで、このグレードにはLEDヘッドランプのオートレベリング機能やアダプティブドライビングビーム(自動配光制御)も装備。LEDヘッドランプは全車に標準装備となり、降車後、一定時間ヘッドランプが点灯し続ける「ヘッドランプ点灯延長機能」もこれと合わせて装備されます。
先進運転支援システム(ADAS)は、従来採用されていたステレオカメラ方式の「スマートアシスト」を採用しました。衝突警報機能や衝突回避支援ブレーキ機能は、夜間の歩行者や二輪車にも対応し、全車速対応型のアダプティブクルーズコントロールと車線維持支援機能をRSに標準装備(Gにのみオプションで追加可能)。さらに自車の斜め後方にいる車両を検知する「ブラインドスポットモニター(BSM)」を全車にディーラーオプションで用意したほか、アクセルペダル踏み間違え時に急加速を抑制する「つくつく防止」はL以外の全グレードにディーラーオプションで追加装備できます。


【試乗①】RS(ターボ)は“パワーと快適性”のバランスが秀逸
最初に試乗したのはRSでした。パワーユニットは「KF」型の0.66リッター直列3気筒で、ここにターボチャージャーが備わって最大出力64PS、最大トルク100N・mのパワーを発揮。特にRSには遊星歯車機構を組み合わせたステップシフト機能付きの「D-CVT」が組み合わされ、スロットル特性の改良も加わって、ターボラグをほとんど感じさせないスムーズな走り出しを体感することができました。

高速域でもそのパワーはいかんなく発揮され、中間速度域からの加速も力強く、高速道路本線への流入もストレスをまったく感じさせません。なかでも感心したのが、都市高速で多く見られる路面の継ぎ目を乗り越えたときのショックのいなし方で、快適に乗り心地を得ることができました。操安性も高く、キツメのコーナリングでもスムーズに通過し、足回りの追従性が飛躍的に向上していることがはっきりと実感できました。これなら長距離移動でも快適にドライブできるでしょう。

【試乗②】X(NA)は市街地に最適。静粛性・乗り心地にも好印象
次の試乗はダイハツが最量販グレードと想定するXで、パワーユニットはノンターボとなる「KF」型の0.66リッター直列3気筒エンジンとなります。こちらも走り出しはとてもスムーズです。信号待ちからのスタートでもクルマの流れに無理なく乗ることができ、しかも路面の荒れに対しても不快なショックはほとんど伝えてきません。これは高速域でも代わらず、この点ではホイール径が大きいRSよりも上であることは間違いありません。
ただ、高速域に入るとノンターボであるが故のパワー不足は否めません。本線への流入でもやや強めにアクセルを踏む必要があり、しかもエンジン音の高まりに車速がついてこないために、ついアクセルを踏む足に力が入ってしまいます。これは高速域での上り勾配でも同様の傾向となりました。それでも60km/hぐらいまでならトルク感もあって、運転していてストレスを感じることはほとんどありません。やはりノンターボモデルはシティユースで乗りこなすことがメインになりそうです。
【総括】スライドドア×走りの進化で中高年層に刺さる!人気の理由を考察
後部ドアをスライドドアとすることで、使い勝手を大幅に向上させると共にハイレベルな操安性を兼ね備えたこと。これが10年半ぶりのフルモデルチェンジに集約された7代目ムーヴの進化点ということができると思います。特にスタイリッシュである上に走りも満足できるのは、ハイト系ワゴンであるからこそ可能になったこと。すでに発売1か月で受注台数は3万台に達する好調な滑り出し。まさに7代台目ムーヴはダイハツが狙う“モノを知り尽くした中高年世代”に響く格好の一台となるのかもしれません。
SPEC【ムーヴ(X)】●全長×全幅×全高:3395×1475×1655mm●車両重量:860kg●パワーユニット:0.66リッター直3 DOHC 12バルブ●最高出力:52PS/6900rpm●最大トルク:60N・m/3600rpm●燃費(WLTCモード):22.6km/リッター
SPEC【ムーヴ(RS)】●全長×全幅×全高:3395×1475×1655mm●車両重量:890kg●パワーユニット:0.66リッター直3 DOHC 12バルブ ターボ●最高出力:64PS/6400rpm●最大トルク:100N・m/3600rpm●燃費(WLTCモード):21.5km/リッター
【フォトギャラリー(画像をタップすると閲覧できます)】
撮影/宮越孝政
The post 【試乗】新型ムーヴ(2025)がスライドドア化! 走りと安全性が進化した7代目を徹底解説 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.